
川柳自句自壊小説 廻


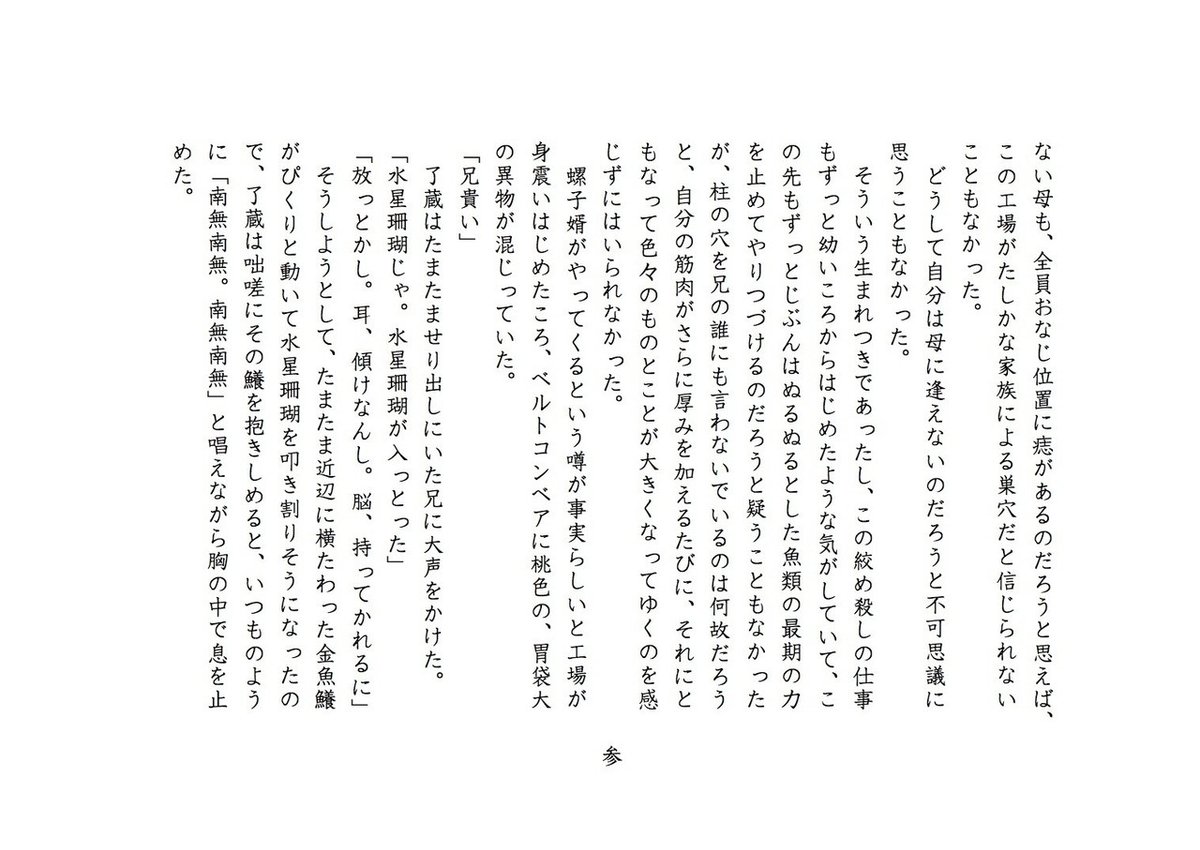


螺子婿が来るというので、鱶切工場の兄弟みながうかれるとも、もの悩ましくなるともつかぬ曇った人相を防鱗マスクに隠して立ち働くなか、了蔵はひとり顔も覆わずに、いつものごとく黒いあばた面に無感動な皺を寄せたまま、はんぱ鱶殺しに精を出していた。
工場はちょうど鱶の肉をまっすぐに切ったような立方体をしており、ひとつの角を最下方に、対角を天上に向けて、貫く太い柱を中心にゆるやかな回転をつづけ、建物の中心部には巨大な丸鋸があるから、そこで本格的な鱶切りをしているのだと、兄の幾人かは言っていたが、了蔵がそこにたどり着いたことはない。
了蔵は十五歳、筋肉が冬の鱶のごとくはち切れそうになっていて、兄たちはもう自分たちより肥大した少年を半ばおそれるように「了は、ちょうど五十二番目の子だで」と何かにつけて言挙げするのだが、なにがちょうどなのか了蔵にはわからず、ただおのれが工場の末子だと言うことは疑いようもなく、いまだ赤子というものを見ずに十六歳になろうとしていた。
工場の四方はすぐ軍隊緑色をした山で、各方面に穿たれた隧道からベルトコンベアで玄翁鱶、胡蝶鱶、里芋鱶などの死骸が流されてくるのだが、なかには死ぬに死にきれず、鹹水の染みたベルトの上で、鰭を切られたままびどりびどりと跳ね返っているものたちもいて、その自分の体長ほどもある魚類を絞め殺して、工場の監視塔に手を振ってから流通に返すのが了蔵の仕事だったが、それが兄たちに忌避される作業なのか、兄の誰もが工場内に引き籠もって降りてくることはなく、地上に降りているのはほぼ了蔵ひとりきりだったので、柱の穴をみつけたのもやはり了蔵ひとりきりだと自分では思っていた。
工場は回転しているから、鱶の受け取り口は広く、コンベアの終わるところにせり出しがあって、丁度の機を狙って、兄たちが魚体を拾い上げ、時として「了、殺しが足りんぞ」と怒鳴るのだが、それは怒りではなく、唸りつづける工場が山峡に反響するから、それに負けないための叫声であったが、了蔵は十四歳になる頃から、その声を聞くたびに工場の心棒である柱を蹴飛ばしていた。
蹴飛ばすたびに、柱の表面は少しずつ抉れていって、それが直接の原因でないにせよ、ささいな傷から算盤蟻が侵入したのだろうか、黒い拳大の穴は日に日に大きくなるようで、いつかこの柱はぽっきり折れるだろうと想像しても、了蔵にはこれが今ここで起きていることとは思えないのだった。
了蔵は五十二番目の子だと聞かされていたが、母がそこまで息子を産出することが可能かどうか、考えてみたことはあったが、出逢ったことのある兄はみな右瞼の上に痣を刻されていて、見知らぬ兄も、そしてまだ記憶にない母も、全員おなじ位置に痣があるのだろうと思えば、この工場がたしかな家族による巣穴だと信じられないこともなかった。
どうして自分は母に逢えないのだろうと不可思議に思うこともなかった。
そういう生まれつきであったし、この絞め殺しの仕事もずっと幼いころからはじめたような気がしていて、この先もずっとじぶんはぬるぬるとした魚類の最期の力を止めてやりつづけるのだろうと疑うこともなかったが、柱の穴を兄の誰にも言わないでいるのは何故だろうと、自分の筋肉がさらに厚みを加えるたびに、それにともなって色々のものとことが大きくなってゆくのを感じずにはいられなかった。
螺子婿がやってくるという噂が事実らしいと工場が身震いはじめたころ、ベルトコンベアに桃色の、胃袋大の異物が混じっていた。
「兄貴い」
了蔵はたまたませり出しにいた兄に大声をかけた。
「水星珊瑚じゃ。水星珊瑚が入っとった」
「放っとかし。耳、傾けなんし。脳、持ってかれるに」
そうしようとして、たまたま近辺に横たわった金魚鱶がぴくりと動いて水星珊瑚を叩き割りそうになったので、了蔵は咄嗟にその鱶を抱きしめると、いつものように「南無南無。南無南無」と唱えながら胸の中で息を止めた。
「ありがとう」
と水星珊瑚が言ったのがきっかけかどうかは、ずっと後、了蔵が一人前になってからもわからなかったのだが、ともかく了蔵は流れてゆく水星珊瑚を引っ掴むと、工場の真下、上からは不可視の影に運んでいった。
「ありがとう。たすけてくれて」
了蔵はなにも言わなかった。
「ありがとう。たすけてくれて。ありがとう。たすけてくれて。たすがとう。ありけてくれて」
わめきつづける水星珊瑚を、了蔵は柱の穴に押しこむと、それは母があらかじめ決めたかのように、ぴったりおさまり、黒い穴に珊瑚は桃色の体表を小刻みに震わせていて、どんな鱶の内臓より内臓らしいと思った。
その日から、工場の最下層、了蔵の個室から目覚めるたび、仕事場から引き上げて来てゆっくりとした回転に身をまかせるたび、あの水星珊瑚はいつか自分を了蔵と呼んでくれるのだろうかと、淡々しい情動に喉の底が飛び出しそうだった。
日々を重ねるに連れて、水星珊瑚の言葉は「たすけとう。ありがてくれて。たすけくれ。ありがたすけ。ありたすけ。すけがとう。すけがとう」と意味を崩壊させていったが、そもそも当初から意味など微塵もなかったかもしれず、言葉が通じなければ通じないほど、自分のこころが染み渡る気分になって、了蔵は魚を絞め殺した。
そして螺子婿入りの夜になった。
上階から、見たことがない兄たちが降りてきて了蔵に言った。
「お前は五十二人目じゃ。婿さんが来たらこれ以上の口はまかなえん。お前は力も精もある。外は広い。お前はひとりで生きてゆけ。儂らにはできんことをしてくれや」
了蔵は頷いて、「ちょっと待っててくれ」と柱に駆け寄った。
柱ごと柱の穴は回転していて、それに合わせて了蔵も廻りながら水星珊瑚になにも語らなかったが、水星珊瑚もなにもものを言わず、ときおり「あああ。たたた」と雑音を立てながら、桃色が少し褪せたように思われて、了蔵は珊瑚を抜き取ると、ぶっとい腕にすべての力をこめて、砕いた。
兄たちは黒影になって立ちつくしていて、了蔵は深く頭を下げると、背を向けて山の斜面に飛びつき、これでいい、これでいい、殺生の罰はおれひとりが受ける、おれひとりだけが自由なのだと呟きつつ、母切草をかきわけて振り返りもしない。
途中、ほのかな行灯を見た気がして、ああ螺子婿さんだ、螺子婿さんならあの穴を直してくれるだろうと信じたが、不乱に山を登る了蔵は、ついに鱶切工場全景を見ることがなかった。
さらば兄潜水艦を壁に貼り 大祐

もしお気に召しましたら、サポートいただけるとありがたいです。でも、読んでいただけただけで幸せだとも思います。嘘はありません、
