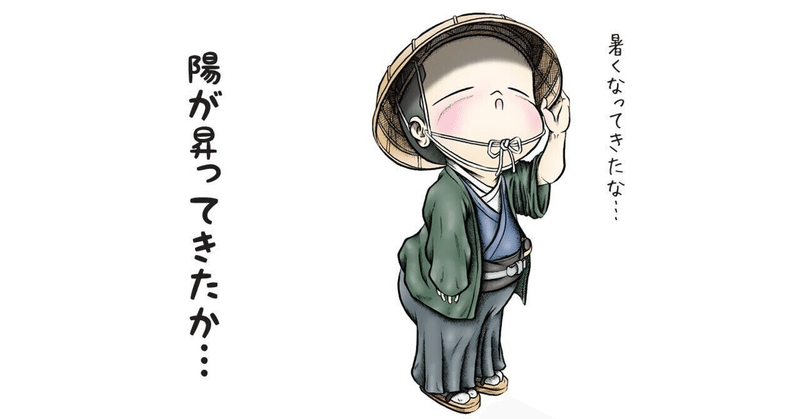
【株】7/25〜7/29振り返りと来週の展望
今週の注目決済指標
・米国 06月 中古住宅販売成約指数
米6月中古住宅販売成約指数、パンデミック経済封鎖直後の低水準、ドル伸び悩み、全米不動産協会(NAR)が発表した6月中古住宅販売成約指数は前月比‐8.6%と、5月+0.4%からマイナスに落ち込みパンデミックにより経済封鎖開始直後の20年4月来で最小となった。
・米国 07月 FRB政策金利
米国連邦準備制度理事会(FRB)は7月26、27日に連邦公開市場委員会(FOMC)を開催し、政策金利であるフェデラル・ファンド(FF)金利の現状の誘導目標1.5~1.75%から0.75ポイント引き上げ、2.25~2.5%とすることを決定した。6月の消費者物価指数(CPI)上昇率は前年同月比9.1%とこれまでに続き高い伸びだったことから、前回会合で実質的に予告していた0.5~0.75ポイントの金利引き上げを上回る、1ポイントの引き上げを予想する声もあったが、結果的には予告どおりの引き上げ幅となった。なお、今回の決定は参加者12人の全会一致だった。
・米国 第2四半期 GDP
米商務省が28日発表した第2・四半期の実質国内総生産(GDP)速報値は年率換算で前期比0.9%減と、2四半期連続で縮小した。米連邦準備理事会(FRB)が40年ぶりの物価高に対応するため積極的な利上げを進める中、米経済がすでに景気後退入りした恐れがあるとの懸念をあおる可能性がある。市場予想は0.5%増だったが、2.1%減から2%増まで幅があった。第1・四半期のGDPは1.6%減だった。2四半期連続のマイナス成長は景気後退(リセッション)と見なされる。
原油価格の動向
・結果
今週は、週通して小幅な値動きが続きました。しかし週末は25日移動平均線に届くと、大きな下ヒゲ陽線となった。前回高値をブレイクせずに反落しそうな様子です。週間で約4ドルの上昇。
・テクニカル
200日移動平均線は割らずに価格をキープ。直近の高値と安値の間でヨコヨコするレンジ相場突入か。

・気になった原油関連記事
[ブリュッセル/ロンドン/ケープタウン 22日 ロイター] - アフリカの石油・天然ガス資源は、気候変動懸念やコストがネックとなり、敬遠される存在だった。しかし欧州でロシア産からの代替需要が高まり、エネルギー業界で開発意欲が再燃しつつある。上場・非上場企業の推計に基づくロイターの試算によると、エネルギー企業がアフリカ大陸で検討中の開発プロジェクトは総額1000億ドルに上る。現在は石油・ガスをほとんど産出していないアフリカ諸国のうち、ナミビア、南アフリカ、ウガンダ、ケニア、モザンビーク、タンザニアなどで今後数年間に数十億ドルの開発投資が行われる可能性がある。
[メルボルン 29日 ロイター] - アジア時間の原油先物は供給懸念やドル安を背景に約1ドル高で推移している。市場では石油輸出国機構(OPEC)と非加盟産油国でつくる「OPECプラス」が来週開く会合が注目されている。CMCマーケッツのアナリスト、ティナ・テン氏は「ドル安と供給逼迫という背景から原油価格が大幅に下落する可能性はほぼない」と語った。関係筋によると、OPECプラスは8月3日の会合で、米国から供給増の要望が出ているにもかかわらず、9月の生産水準を現状維持とする方向で検討する。小幅の増産も議論はされそうだという。
米国債10年利回りの動向
・結果
週間で約1.3%の下落。2.65%で大引けしました。米連邦公開市場委員会(FOMC)が予想通り2会合連続の0.75ポイント大幅利上げを決定した後、米国債市場で広く注目されるイールドカーブの逆転がさらに広がった。
・テクニカル
前回安値の2.7%抵抗線をブレイクし、下落する形となった。
75日移動平均線と25日移動平均線のデッドクロスも確認。

・気になった金利関連記事
米連邦公開市場委員会(FOMC)が予想通り2会合連続の0.75ポイント大幅利上げを決定した後、米国債市場で広く注目されるイールドカーブの逆転がさらに広がった。米国の10年国債利回りはFOMCの発表を受けて低下し、2年債利回りが10年債利回りを一時32ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回った。こうした逆イールド(長短金利差逆転)は、リセッション(景気後退)リスクを示唆するとしばしば受け止められる。FOMCは声明で「インフレ率を目標の2%に戻すことに強くコミットしている」と表明した。KPMGのチーフエコノミストのダイアン・スウォンク氏はブルームバーグテレビジョンで、「米連邦準備制度はインフレに真っ正面から集中している。それは需要を直撃し、国内総生産(GDP)ははるかに低い水準になりそうだ」と指摘した。
米ドルの為替動向
今週のドル円相場(USDJPY)は、週初136.07で寄り付いた後、①米FOMCを控えたポジション調整(100bpのサプライズ利上げに対する警戒感)や、②株式市場の堅調推移(リスク回避ムード後退)、③米金利上昇に伴うドル買い圧力、④対ユーロでのドル買い圧力、⑤スポ末仲値のドル買いフロー、⑥米FOMCの75bp利上げ実施(全会一致)、⑦パウエルFRB議長による「インフレ抑制を強くコミット」「労働市場は非常にタイトでインフレは高すぎる」「インフレを低下させることが不可欠」との発言などが支援材料となり、週央にかけて、週間高値137.48まで急伸しました。しかし、買い一巡後に伸び悩むと、⑧パウエルFRB議長による「ある時点で利上げ速度を緩めることが適切となるだろう」との慎重な発言(利上げペース鈍化の可能性を示唆する発言)や、⑨米4ー6月GDP速報値(結果▲0.9%、予想+0.5%)の冴えない結果(2四半期連続のマイナス成長→テクニカルリセッション入り)、⑩上記⑧⑨を背景とした米長期金利の急低下(米10年債利回りは4/7以来となる2.62%へ急低下→日米金利差縮小に伴うドル売り・円買い)、⑪雨宮日銀副総裁による「出口戦略について全く考えていないという事ではない」「出口の具体的議論は時期尚早だが方法は常に考える必要がある」とのタカ派的な発言が重石となり、週末にかけて、週間安値132.51(6/17以来、約1ヵ月半ぶり安値圏)まで急落しました。もっとも、売り一巡後に下げ渋ると、⑫米6月PCEデフレータ(結果6.8%、予想6.8%、前回6.3%)の伸び率加速や、⑬米6月PCEコアデフレータ(結果4.8%、予想4.7%、前回4.7%)の伸び率加速、⑭米主要株価指数の堅調推移(リスク選好の円売り圧力)が支援材料となり、本稿執筆時点(日本時間7/30午前3時00分現在)では、133.35前後まで持ち直す動きとなっております。

ドル円は7/14に記録した約23年10ヵ月ぶり高値139.40(1998年9月以来)をトップに反落に転じると、今週はパウエルFRB議長による利上げペース鈍化を示唆する発言や、米経済のテクニカルリセッション突入懸念、米長期金利の急低下が重石となり、週末にかけて、6/17以来となる132.51まで急落しました。この間、一目均衡表転換線や基準線、21日移動平均線やボリンジャーミッドバンドを下抜けした他、強い買いシグナルを示唆する三役好転も消失するなど、テクニカル的に見て、地合いの悪化を印象付けるチャート形状となりつつあります。但し、ダウンサイドには一目均衡表の雲が控えているため、ここからの更なる下落は容易では無いと考えられます(事実、週末にかけての急落時においても、一目均衡表雲上限がサポートとして機能)。ファンダメンタルズ的に見ても、今週はパウエルFRB議長による「ある時点で利上げ速度を緩めることが適切であるだろう」との発言や、米GDPの 2四半期連続マイナス成長に市場が過剰反応し、「米長期金利低下→ドル円急落」の流れを引き起こしましたが、前者については、同氏はこの発言の前段階で「米景気よりインフレ抑制を重視する構え」を見せており、また後者についても、イエレン米財務長官やバイデン米大統領は「米雇用情勢が強いことからリセッションには当たらない」と発言しているため、今週の下落要因である上記2つの賞味期限切れは相応に近いのではないかと考えられます。そうなると、残る要素として、①米FRBによる金融引き締めの長期化観測(一部で燻っていた100bp利上げには至らなかったものの、6月・7月で計150bpの利上げを行うなどタカ派姿勢が鮮明)や、②日銀による金融緩和の長期化方針(日銀は先週開催した金融政策決定会合で金融緩和の長期化方針を再強調)、③上記①②を背景とした日米金融政策の方向性の違い(日米名目金利差拡大に伴うドル買い・円売り)、④米政府・当局によるドル高容認姿勢(米国はインフレ抑制に繋がるドル高を容認する構え)、⑤日本とその他各国との金融政策格差(対ドルに対してだけでなく、対主要通貨全般で円売りが進みやすい構造)が再浮上するため、結果としてドル円相場には上昇圧力が加わるシナリオが想定されます。
以上を踏まえ、当方では引き続き、ドル高・円安トレンドの継続をメインシナリオとして予想いたします(ポジション調整一巡後の反発リスクに要警戒)。
NYダウの動向
・結果
27日から3日連続で実体の大きな陽線で価格上昇する形に。週間で約800ドルの上昇に。GDPのマイナス成長による金利低下は好材料に価格が上昇。
・テクニカル
直近高値だった31800円台の抵抗線もブレイク。次回は33000円台の抵抗線をブレイクできるか要注目。

日経平均の動向
・結果
週間では約100円の上昇。米国のFOMC議事発表までの様子見姿勢と、それを受けたドル円の円高反応が重しとなり、低調な価格推移を見せた模様です。来週からの決算発表に伴い個別銘柄に注目が集まります。
・テクニカル
25日移動平均線と75日移動平均線のゴールデンクロスを確認。節目の28000円台が大きな抵抗線となっている模様です。

業種別株価変化率の動向
今週の最も上げた業種は鉱業で、最も下げた業種は輸送用機器となった。
原油の価格上昇に伴い、石油石炭関連事業の業績好影響が示唆され、逆に運用コストがかさんでしまう輸送用機器は売られる展開となった。

来週の注目決済指標
・米国 07月 ISM製造業景気指数
・米国 7月 ADP雇用者数
・米国 07月 ISM非製造業景気指数
・米国 07月 失業率
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
