
Netflix等で出会った英語表現集 (随時更新します〜)
基本的にはNetflixで見かけた「生きた英語」をまとめていきたいと思ってます。
雑なまとめ方なので、便宜上各シーンの私の好きなセリフをタイトルにしていますが、他のセリフの言い回しや単語も非常に勉強になると思いますので適宜解説等を入れておきますね。
勝手な解釈での解説もあるかもですので間違ってたら指摘していただけると嬉しいです〜。
・Not that there's nothing to discuss. [かと言って別に話すこともないけどね。]
「ユニークライフ(原題:Atypical)」S1-E1 より


Not that SV [(だからと言って/かと言って) SVということではない]
例えば、
He gave her a present. Not that he likes her.
彼は彼女にプレゼントをあげた。(だからといって)彼は彼女が好きだというわけではない。
・It must be hilarious being you. [あなた"で"いるのは楽しそう]
「ユニークライフ(原題:Atypical)」S2-E1より



it = being you という構造で、it is 形容詞 〜ing の文。「あなたでいるのは面白そうだね」という意味ですので、"You're hilarious". の上手な言い換えといった感じです。ここでは「面白い視点ね」と上手く訳されています。
・You're always going to have her back. [いつも君が彼女の味方さ]
「ユニークライフ(原題:Atypical)」S2-E10より

※"every now and then" = sometimes のよりネイティブっぽい表現

最終回で主人公のサムが名付け親になったペンギンちゃんの元に行った際にお父さんが行ったセリフですね。
"Even if they're hard on her every now and then, you're always going to have her back."
※"have sb's back" = 〜を支える/〜の味方になる
時制的な話をすれば、『"Even if 〜"という仮定の話が起こる度に、いつも味方になる』という仮定の中での決まった事柄の話をしているので、"You're always going to〜"となります。
・That's just asking for trouble. [それは論外]
「ユニークライフ(原題:Atypical)」S2-E8


"ask for trouble" は直訳すると「災いを求める」なので、そこから転じて「災いを招く/面倒なことになる」という意味の口語表現になります。
ここでは"just"が付くことで意味を強調しており、「それは論外/問題外だ」という意味で使われていますね。
ちなみに言い換えると"That's out of the question." となります。
・I really need to knock their socks off. [向こうの度肝を抜かないと]
「ユニークライフ(原題:Atypical)」S2-E8


"knock sb's socks off" はここでサムが言うように「慣用句--phrase」の一種で「〜を仰天させる/〜の度肝を抜く」と言う意味になります。
一単語で言い換えると"surprise", "astonish", "astound" といったところでしょうか。
・I could use the support. [助けが欲しいの]
「ユニークライフ(原題:Atypical)」S4

" I could use 〜" は、一見すると肯定文ですが、実は『丁寧な依頼』の表現です。
ただし、" Can/Could I use 〜?" と疑問文で使うのは不自然な表現だそうで、注意が必要ですね。
"I could use the support."はニュアンス的にこの場面では "Could you come with me?" のような意味です。他によく聞くのは、"I could (really) use your help." [君の助けが必要なんだ。] ですね。
また補足として、"I could use 〇〇" は、
"I could use 〇〇" = "Could you get me 〇〇"
[〇〇を取ってくれませんか?]
という意味でも使われます。

コアイメージはどちらの用法でも共通して、「〇〇に該当するものを相手に求める丁寧な依頼」の表現です。
・Am I right in assuming this isn't your first rodeo. [今回が初めてではない?]
「Daredevil」S1-E3 より

※injurious consequences [傷害結果]
主に傷害罪が適応される対象の事象に対して用いられる法律用語(legal vocabulary) ですね。

※have quite the legal vocabulary [法律用語に詳しい]
"vocabulary"というのは「語群」の感覚なので、集合名詞的な扱いですね。

"Am I right in〜" [〜において私は合ってますか?]
※ 別の表現では "Am I correct in 〜" もあります。
ですので、"Am I right in assuming 〜" で 「〜と思ってよろしいですね?/〜で合ってますね?」という自分の仮定や推論を確認するフレーズです。
そしてもう一つの表現は、
"This isn't one’s first rodeo." [以前にも経験がある / 今回が初めてじゃない]
・For a while, they went hand-in-hand. [前はどっちも両立してた。]
Daredevil S2 より

・Are you taking about〜 or you talking about 〜?
or 以降の文章も疑問内容に含まれるので、
"Are you talking about〜 or are you talking about〜?"
ではなく、文頭の Are に包括させる!

go hand-in-hand [ (with〜と) 協力する / 手を取り合って進む / 密接に関連している ]
コアイメージは「"2つのもの"がバランス良く両立している感じ」
"They went hand-in-hand." についてですが、まず "They" は "our firm" と "our friendship" のことです。つまり、「事務所と僕たちの友情は前は(=for a while)バランスを取れてた / 両立していた。」
ちなみに "for a while" を「前は」と訳すのは個人的には初めてみましたが、考えてみれば「しばらくは〇〇だった。」と「前は〇〇だった。」というのはほぼ同じ意味ですので、この訳し方も意外と良いかもしれませんね。
・I've crossed paths with / Needless to say
Daredevil S2


I've crossed paths with your attorneys before. Needless to say, I'm not a huge fan. [君の弁護士とは以前に関わりがある。言うまでもないが、気に入らない。]
・cross paths with sb [〜と偶然出会す / 〜と偶然関わる]
・needless to say, 〜. [言うまでもなく、〜だ。]
・be a huge/big fan [ (of〜が) 好きだ / 気に入っている]
上記3つの表現は非常によく耳にしますし、洋書や記事でもよく見かけます。是非使えるようにしておきたいですね。
特に "I'm a big fan of 〇〇." [〇〇が好きなんだよね。] は会話でも頻繁に使う便利なフレーズです。
また補足ですが、"attorney" という単語も法律関係の作品では頻出ですが、同じく「弁護士」を意味する "layer" との違いもちゃんとあります。
layer : 法律上の手続き全般の助言や支援を行う者
attorney:訴訟の際に依頼人の弁護を代わって行う者
・I must have left it in my car. [きっと車に忘れてきたんだ。]
Daredevil S3-E3

助動詞 + have p.p. の表現です。
解説したいのは、ここでの must have p.p. は厳密には「must の過去形ではない」という点です。
今回の場合は、「それ(=it)を車に忘れてきた」というのは「過去形のニュアンス」ではなくあくまでも「現在完了のニュアンス」で語っています。つまり"今現在もまだ"車に置きっぱなしということです。
つまり、今回の "must have p.p." における "must" は「現在完了形の文章に「〜してきたはずだ」のニュアンスを付与している。」ということになります。
ただもちろん通例通り "must have p.p." を「過去の断定的な推測」として用いることもできます。
Ex: She must have been busy yesterday. [彼女は昨日、忙しかったに違いない。] ※現在完了のニュアンスなら"yesterday" のような明確な過去の表現は使えません。
・It would be inappropriate "of"/"for" me to tell you that 〜 [君に話すのは不適切だが、〜]
Daredevil S3-E4 より



※ launch an internal investigation [into〜についての内部調査を始める]
まず、ここでの"would" は、仮定法の意味などではなく、単純な「推測」の意味「〜だろう」です。
本題は、捜査官の言う"It would be inappropriate of me to tell you that 〜"の部分です。興味深いことに、このシーンのすぐ後に相手側の捜査官がこのように返します。

こっちでは"It would be inappropriate for you〜"となっているのです。
"形容詞 of you to do" と "形容詞 for you to do" の違いは実にシンプルで、[forが使われている場合は "to〜以降の事柄"に対する評価]、[ofが使われている場合は"人"に対する評価]になっています。
・it would be inappropriate "of me" to tell you that〜
=I would be inappropriate to tell you that〜
(inappropriateなのは "me")
・it would be inappropriate for me to tell you〜
=It would be inappropriate that I tell you that〜
(inappropriateなのは "I tell you that〜")
このようにどの箇所にその形容詞の意味がかかっているかによってofなのかforなのかを区別していますね。
・throw sb under the bus [〜を見捨てる]
Daredevil S3-E5 より

"throw sb under the bus" は、「〜に(罪や責任をなすりつけて)見放す / 陥れる」という意味です。
このシーンでは、男性の捜査官がFBIに任務失敗の責任を押し付けられてスケープゴートにされたことを知るシーンですので、ぴったりな表現です。
・Consider it p.p. [任せてください etc.]
Daredevil S3-E10 より

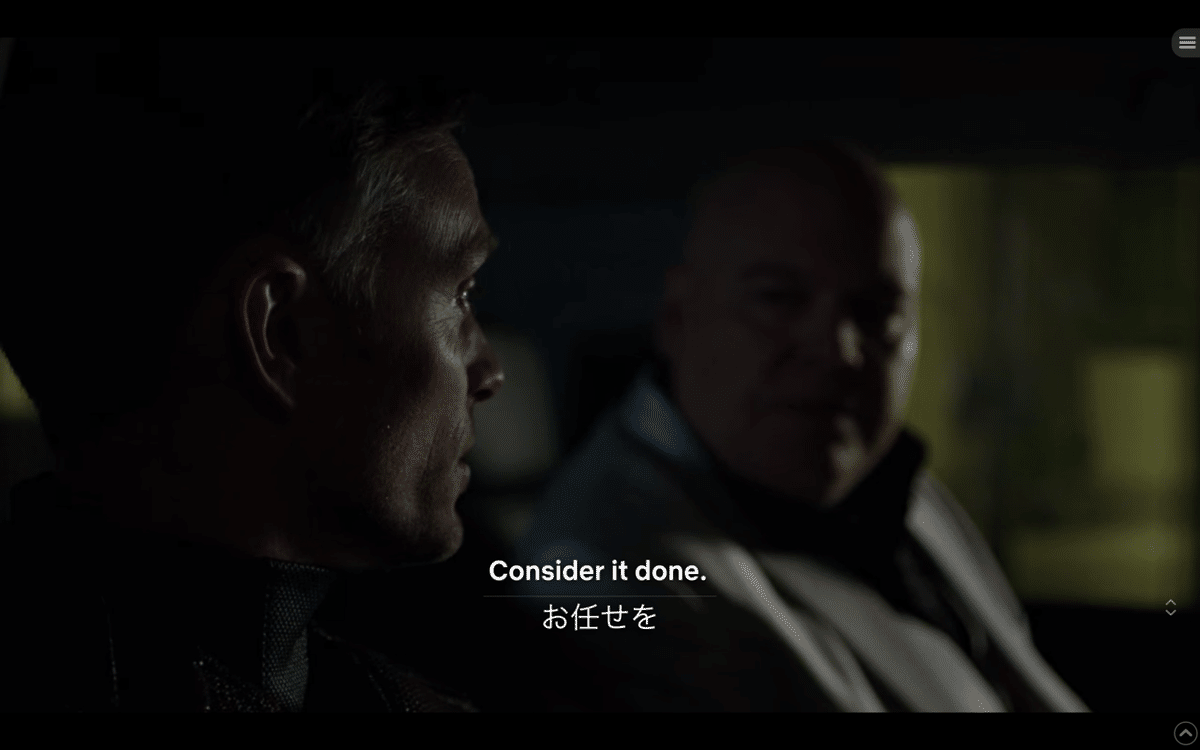
"Consider it done"「かしこまりました/了解しました」
※「それ(=it) はもう完了したと思ってください」
このパターンは実はいくつかあり、他にも。。。

これは私の大好きなドラマ "Brooklyn 99"のS5-E13からの抜粋です!
"Consider it gifted" = それはもう贈ったと思っておいてくれ=了解した
このように"Consider it p.p."のp.p.を状況に応じて帰ることで様々な言い換えができるようですね。
・You had me at "no paperwork." [「書類仕事無し」ってのが効いたよ!]
Brooklyn Nine-Nine S1-E3

"You had me at 〜" というフレーズはあまり聴き慣れないとは思うのですが、注意して探してみると意外とよく遭遇します。
"You had me at 〜" [〜で(オファーに対して)前向きになった / 〜であなたに興味を持った / 〜で心が決まった・確信した]
"You had me at hello." [出会った時(helloと挨拶した時点)から好きだった。] などがあります。
・As much as I want to hear those thoughts, [その感想を聞きたいのはやまやまなのですが、]
Brooklyn Nine-Nine



全文書き起こすと、
" As much as I want to hear those thoughts, and it is so, so much, I think we should probably let Amy speak. "
[その感想もすっごく、本当にすごく聞きたいんですけど、今はエイミーの話す番です。]
文頭の" As much as SV, "ですが、これは実は" Even though SV, "と同じ意味で使われているケースです!
「〜なのはやまやまなのですが、」というような「譲歩」の意味ですね。
そして、“ 〜, and it is so, so much,〜 ” は挿入句で、「本当にすごく聞きたいんですけど、」ということを注釈しています。
it = I want to hear those thoughts という構造だと思います。
・That should do it. [それで良い / それで行こう]
Brooklyn Nine-Nine

イディオムを勉強されている方なら "That will do" [それで大丈夫です etc.]という表現を聞いたことがあるのではないでしょうか。
"That should do it." は「それでオッケー/それでいこう」といった意味で、 "That will do." 又は "That should be enough." の言い換え表現です。ただし、 ”That should do it.” の ”it” を抜かさないように注意してくださいね。
また、この表現の構造としては、
・That = 話者の間で”直前に”起った事または話した事
・do = 〜がOに対して十分であること
・it = 提案内容が用いられる「状況」のこと
このように考えておくと良いでしょう!
・I like your company. [一緒にいると落ち着く]
Brooklyn Nine-Nine S1-E1 より

one's company で、「〜と一緒にいること/一緒に過ごす時間」のことです。日本語には無い感覚ですね。
他には、I enjoy one's company. [〜といるのを楽しむ] という言い換えもでき、I enjoyed your company. [ご一緒できて良かったです。] というビジネス表現として使います。
・Every time I think I understand how bad it is, it's just way worse than I imagined. [知ったような気になってもいつも現実は想像以上にずっと酷い。]
Brooklyn Nine-Nine S6-E8
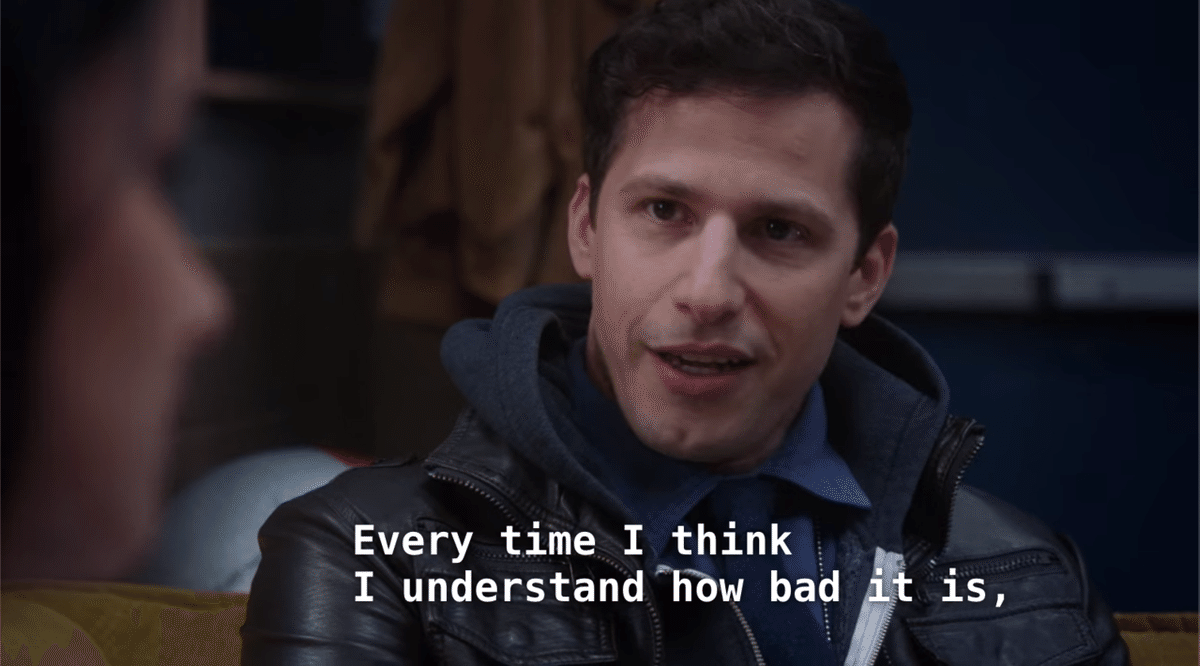

これは私が最も好きな台詞の一つです。エイミーが過去に受けたセクハラ被害を告白したシーンで夫であるジェイクが嘆くシーンです。
Every time I think I understand how bad it is, it's just way worse than I imagined. (知ったような気になってもいつも現実は想像以上にずっと酷い。)
※ way 比較級 [(〜より)ずっと〇〇]
このエピソードはブルックリンナインナインの中でも特にシリアスで非常に大切な回ですので、機会があれば是非とも見てみてください。
・Vis-a-vis [〜に相対して / 〜に面と向かって etc. ]
Brooklyn Nine-Nine より



What did you think of the thesis, vis-a-vis modern slavery and its undeniable role in economy?(現代の奴隷制とその否定し難い経済的役割に相対するあの主張について君はどう思った?)
※ thesis =主張 etc.
つまり、the thesis は「反奴隷制の記事」ということが推測できる。
"vis-a-vis" という前置詞は、フォーマル目な表現です。“face-to-face” を意味するフランス語から由来しており、18世紀頃から使われ始めたそうです。
主に 「〜と相対して/〜に面と向かって・〜に対して/〜に関して」のような意味で使われます。
他の実例も見てみましょう。


I have never once insulted you in my life, especially vis-a-vis your appearance. (一度だってあなたをバカにしたことないわよ。特にあなたの見た目に対しては。)
ここに関しては訳が非常に悩ましいです。添付している画像の日本語字幕では、「面と向かって」と訳されていますが、"your appearance" についての言及をオミットした訳のように思えます。
加えてこのシチュエーションが、同僚のハロウィーンのコスチュームに対しての会話ですので、「見た目に対しては特に」とする方が個人的には納得できます。
"vis-a-vis" は記事や論文では「相対して」というよりかは「直接的に(面と向かって)〜に対して」のニュアンスで用いられることが多いのですが、それぞれ文脈に応じて解釈した方が良さそうです。
・I could talk about that for hours. [そのことなら何時間でも話せる]
Brooklyn Nine-Nine より

「実際はそんな何時間も語れないけれども、気持ち的には/主観的には何時間でも話せる」というニュアンスがあるため、仮定法的な could という助動詞を用いています。
仮定法とはあくまでも、「現実とは異なること」あるいは「話し手の主観的な仮定の話」ですので、自分の気持ち的に「何時間でも話せる!」というのであれば、このように仮定法を使うんですね。
他にもこんな使い方があります。

I could eat this every day.
[実際は毎日なんて無理だけど、気持ち的には毎日食べれる!]
・〜 and whatnot [〜とかいろいろ]
Master of None S2 より

meetings and whatnot [ミーティングとか色々]
"〜and whatnot" はあるものをあげた後に他にも色々あることを示す表現です。他には "and so on" などがありますが、"and whatnot" はライティングなどには適さないかなりカジュアルな口語表現です。
・倍数表現とマイノリティであること
Master of None S2-E8 より


Minority is a group of people who have to work twice as hard in life to get half as far.
"as 〜 as ..." で、いわゆる「同等」を表します。
そのかたまりの頭に "half" や、今回のように "twice" や "third"、あるいは "one third"(3分の1) のような数字表現をつけることで、「倍数表現」になります。
今回の場合ですと、"twice as hard 〜 as far" ですので、「それまでの2倍ハードに」という意味です。
"far" というのは「これまで辿った過程」のことを意味しますので、"twice as hard in life to get half as far" は、「半分の収入を得るために、"それまでの人生の2倍" 働かなければいけない」という太字部分の意味で "far" を使っています。
この後の表現も興味深いので見てみましょう。

disenfranchised [(公民権を)剥奪された]
公民権がない=自分たちの声が届かない という構造的差別にさらされる人々のことを指します。
・pull out all the stops [最大限努力する/誠心誠意行う]
Master of None S2 E9 より


How did he propose? Did he pull out all the stops?(彼はどんなプロポーズをしたの?ちゃんと誠心誠意でプロポーズしてた?)
主人公のデフはこの左の子に好意を寄せているのですが、実は彼女には婚約者がおり、その彼との馴れ初めを聞いているシーンです。
"pull out all the stops" はビジネスやニュース等でもよく耳にする表現です。
Ex: We need to pull out all the stops to get more clients.(顧客獲得のために全力を尽くさなきゃ。)
・puck a mean punch / when it counts etc.
The Defenders より

"be off" で「変な / イカれてる」を意味します。現実から少し外れてる(=off) というイメージです。

"he packs a mean right hook" [こいつの右フックは強烈だ/ヤバい]
これは "pack a hard punch" という表現が元になっています。意味は "have a very strong impression" といった感じで、要は「〜は強烈だ。〜は凄い」といった口語表現になります。
また、ここで "mean" となっているのは、米俗語で「ヤバい」のような意味があるため、強調として "hard" よりも "mean" が選ばれているのでしょう。
そして "when it counts" は「いざというときには / 肝心な時には」という意味です。
・This is not yours to fix alone. [あなた一人で解決できることじゃない]
Stranger Things S1-E7

"This is not yours to fix alone" = "This is something that you cannot fix alone"
これと似た言い回しが、かの有名なドリス・デイの "Que Sera Sera" の歌詞にもあります。
The future is not ours to see.
[未来は私たちが見通せるものじゃない / 未来はどうなるかはわからない]
・I'd have left you too. [私でもあなたを置いて出て行ったはず]
Girlboss S1-E11 より


※"No wonder S V." [どおりでSはVするわけだ / SがVするのも当然だ]
そして、"I'd have left you, too." これは仮定法(3rd Conditional)の文章で、"If I were her," が省略された文章です。会話でよく見られるパターンですね。
ちなみにですが、「私が彼女である」ことは現在でも過去でもあり得ないことなので、"If I had been her," という表現は不適当になります。
ですのでどんな場合でも ”If I were you,”としておきましょう。
・A(名詞) or lack thereof [Aの有無]
The End of the F***ing World より

"The sex or lack thereof is not why you're here."
[セックスの有無であなたをここに呼んだんじゃない。]
※ A or lack thereof = Aの有無
ちなみに、"The sex" に "The" が付いている理由は、この男性がこのシーンの直前に性交渉を行なっていないことを説明するのですが、そのことについて語っているので "The sex" (="その"セックスの件) ということです。
・so〜that構文を使って「死ぬほど〜」
SSSS.GRIDMAN E12 より


(There are) so much (that) I could die!
「ありすぎて死んでしまう」=「死ぬほどある!」という英訳です。
また、実際には死んでしまうわけではないので、あくまで主観的に or 仮定的に「死んでしまう」ということを言っているので、"could die" となります。
・I don't think it was until 〜 that S V [多分SがVしたのは〜からだと思う]
Melissa Fumero のインタビュー動画より
動画の 3:36 あたりから抜粋
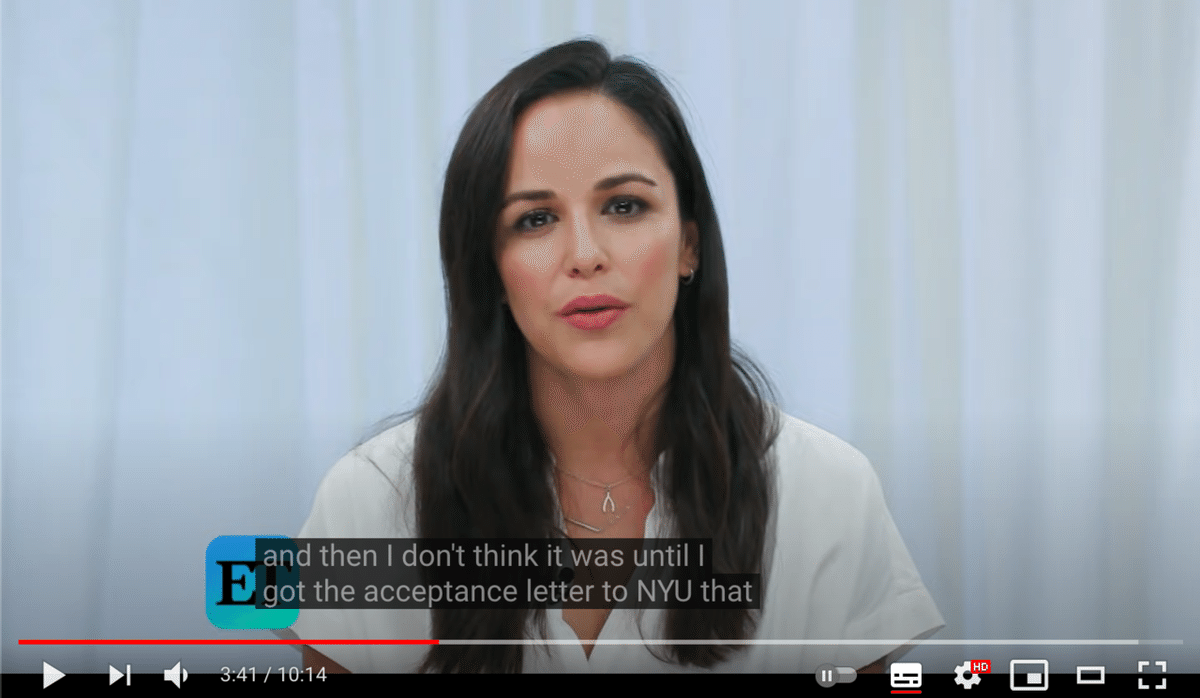

YouTubeの自動字幕では間違いがいくつか出てきてしまうので書き起こしてみます。
And then I don’t think it was until I got the acceptance letter to NYU that my parents were like... maybe... maybe she's really good? maybe she can do this?
[多分あれは、私がニューヨーク大学に合格してからだったと思います。両親が、「この子はもしかしたら上手くいくんじゃないか?」と思ってくれたのは。] ※口語的に訳しています。
まず確認するべき表現は "It was not until 〜 that SV" でしょう。
It was not until 〜 that S V. [ 〜して初めてSはVする ]
※ 強調構文の一種です
この表現がここでは "I don't think it was until 〜" となっており、元の表現でも強調されている "not" を "I don't think 〜" で先に伝えていますね。
この構文は形式的に覚えても会話でぱっと使うのは難しいと思いますので、先程の書き起こしの口語的な翻訳部分のような意識で文章を組み立ててみるとスムーズに会話でも使えると思います!
・own up to it [白状して]
23号室の小悪魔 NG集(Gag Reel) より
動画の 4:11 あたりから抜粋

Someone's phone's ringing. Own up to it. Turn it off. Just do it. (誰か携帯鳴ってるわ。白状して。今すぐ切ってね。)
※ own up to [〜を認める/〜を白状する] = admit
Ex: He finally owned up to having broken the computer.
[彼はようやくPCを壊したことを認めた/白状した。]
命令形+Just do it. (今すぐ〜してね。) もすごく自然な言い回しで、非常に会話でよく聞きます。命令形にただ "now" を付けるよりも少し柔和で、「よろしく〜」のようなニュアンスが加わります。
ちなみにこの Krysten Ritterという女優さん。非常に可愛らしくて私も大好きなのですが、ものすごく早口で喋る印象です笑。ここでも正確に聞き取るのが少し難しいですが、何回も聞いてみると自然な英語の聞き取りの練習になると思います。
・That's gonna bleed into Black Friday! [それじゃブラックフライデーに間に合わないじゃない!]
23号室の小悪魔 より
こちらは私が一番大好きなコメディドラマ「23号室の小悪魔 (原題:Don't Trust the b---- in Apartment 23)」のワンシーンからです!
動画の0:20秒あたりから抜粋

黒髪のCholeちゃんに誘われて感謝祭のパーティーに来たJuneですが、どうやら相当に長ったらしい食事会らしく、翌日のブラックフライデーに間に合わないことを嘆いてるシーンです。セリフを確認してみましょう。
Chloe: We're just gonna go in for a quick five course meal. We'll be done in 9 hours max.
(ちょっと5コース分の食事を食べるだけだし、長くても9時間で帰れるわ。)
June: 9 hours? That is gonna bleed into Black Friday.
(9時間?それじゃブラックフライデーに間に合わないじゃない!)
Chloe: June, you can have sex with black men any day of the week.
(ジューン、黒人の人とはいつでも寝られるわ。)
解説しがいのある表現がたくさんありますが、まずはChloeちゃんのセリフにある "in 9 hours max."。直訳すると「最大で9時間後に」となります。数字の最後に副詞である "max" あるいは略さずに "maximum" をつけるだけで、「最大で〇〇」となるので便利です。
次に June のセリフにある "bleed into〜" ですが、ここの意味の汲み取りは非常に厄介です。というのも、"bleed into〜" は元々「〜に出血する」という意味ですので、ネットで調べても基本その意味しか出てきませんし、翻訳にかけてもそのように訳されます。
ですがここでの "bleed into〜" は「〜に影響する etc.」といった意味で使われています。
・bleed into〜 = something is going to extend into, overlap with, or affect the second thing.
「〜(後続する別のもの)にまで及ぶ/〜まで継続する」、「〜に重複する」、「〜に影響する」
実際に日常会話でも英語の記事でも、上記の意味で用いられることが非常に多いです。例えば、こちらの記事のタイトル部分も
Shortage of Apple's iPad and iPhone (is) to bleed into June quarter following Japan tsunami.
[日本の津波被害を受けて、アップルのiPadとiPhoneの不足が6月の四半期にまで及ぶ/継続する見通し。]
となっています。(英語記事のタイトルではよく be動詞 は省略されます)
そして最後のChloeちゃんのセリフは、"週末にあるBlack Friday"を逃しそうなJuneに向けて、「黒人の人(Black)となら週のいつの日でも(any day of the week)寝られるじゃない。」と皮肉で返してます笑。
"any day of the week" は一般によく使う慣用句で「いつでも=anytime」という意味です。
・仮定法内の関係詞節 / my 形容詞 self
23号室の小悪魔 より
動画の 1:48 あたりから抜粋
主人公の Chloe ちゃんの素晴らしい名言です。ちなみに June というのはルームメイトの子。かっこいいだけでなくユーモアもあり、文法的にも非常に興味深いセリフですので是非覚えてみてくださいね。

If I had time to worry about every person who admired, imitated, or stalked me, I wouldn't have time to be my fabulous self.
(私のことを称賛したり、真似したり、ストーカーする人をいちいち気にしていたら、素敵な自分でいる時間がなくなるじゃない。)
まず解説させていただきたいのが、"If 〜," の部分全体です(以降、if節)。
"If I had time to worry about〜" の太字部分はまず「仮定法(2nd Conditional)」です。
そして、"every person who admired, imitated, or stalked me,〜" の部分は、「(実際にはいない or いるか分からないけど) 〇〇する人全員」というニュアンスなので、ここの関係詞節内(=who〜 以降) の動詞は全て仮定法になっています。
このように、「仮定法がそれ以降の動詞に影響する現象」は、「仮定法の伝播」と呼ばれているそうです。(リンク参照)
ただし、仮定法のニュアンスというのが「実際には起こっていないこと/話者の主観的に可能性が低いこと」ですので、もし「本当に起こったこと」や「客観的事実」なのであれば仮定法を影響させる必要はありません!
[関係詞節も仮定法の場合]
・If I had time to worry about every person who admired, imitated, or stalked me, I wouldn't have time to be my fabulous self.
→ 実際は別に称賛され、真似されたりストーカーされてはいないかも or 自分的にもその可能性は低いと思っている、ということ。
[関係詞節が通常の時制の場合]
・If I had time to worry about every person who admires, imitates or stalks me, I wouldn't have time to be my fabulous self.
→ 実際に称賛され、真似されたりストーカーされたりしている or 自分的にそういう人がいると思ってる、ということ。
そして次に、"my fabulous self" (素敵な自分) という表現方法ですが、意外とよく聞きます。感覚としてはおそらく、「自分の中にある(=my)もう一人の自分(=〇〇 self)」 ということなのでしょう。
これ以外にも、"my true self" (本当の自分) や、"my old self" (以前の私/昔の私) という表現があり、先程の「感覚」を念頭に置かなければパッと意味が取れなさそうな表現ですね。
・when it could be just 〇〇 [ただの〇〇で済むはずなのに、 etc.]
23号室の小悪魔 より
上の動画の続きから抜粋です。


Why do you have to make things so complicated when it could be just sex?
[なんでただのセックスで済むはずのことをそんなに難しく考えるわけ?]
まず "make things (so) complicated" は、「(物事を)難しく考える」という意味で、意外とよく使います。
そして、"when it could be just sex." は、「ただのセックスで済むはずなのに」 というような所謂「譲歩」の意味です。"even though" に近いと思います。
細かく考えていくと、"it" というのは「想定している状況のこと全般」を総称する意味で、英語ではよくある概念です。(Ex: It's raining. etc.)
そして、ここでの "could" は、本来であればただのセックス(just sex) である "はず" が、色々難しく考えてしまうが故に、そうはなっていないことを意味していますので、「仮定的な可能性」を意味します。
"could" 自体は「現在/未来の仮定的な可能性」を示す役割があるので、仮定法だとかは意識せずに自然に用いられます。
・You're shoveling food into your face. [あなた食べ過ぎ]
23号室の小悪魔 より
0:59 あたりから抜粋
June, you're an addict. You're shoveling food into your face, constantly.(ジューン、あなた依存症よ。ずーっと食べてるじゃない。)
※ an addict [ (麻薬などの)中毒者/依存症患者 ]
"You're shoveling food into your face." は、元々別の慣用句として "shovel food into your mouth." [ガツガツ食べる] というのがあり、それを "〜into your face" とすることで めちゃめちゃ食べてる感 をより強めています。
加えて、最後に"constantly" を入れることで ずーっと食べてる感 も加えています。
・My beef isn't with you, Luther. [あなたに文句があるんじゃないのよ]
23号室の小悪魔 より
Chloe: My beef isn't with you, Luther.
(あなたに不満があるんじゃないのよルーサー。)
Luther: Thank you... (結局Chloeちゃんにおもちゃの銃で撃たれる)
"beef" とはご存知の通り「お肉」のことですが、「不満/文句」「喧嘩」というスラングとして使われることもあります。
Ex: I have a beef with you! [お前さんに不満があるんだ!]
・It would be one thing if〜 [〜なら話は別だ。]
TEDx より
12:15 より
〜 And it would be one thing if the photo and the videos and the social sharing were creating happiness, but data is pouring in that proves otherwise.
(写真やビデオといったソーシャルシェアリングが幸福を形成しているのであれば話は別ですが、実際はそれを反証するデータが次々出てきます。)
※ pour in [〜が殺到する/押し寄せる/続々来る]
※ prove otherwise [反証する]
It would be one thing if *SV(, but 〜)
[SがVすれば話は別だが、(実際は)〜だ。]
※ SV は必ず仮定法
この構文は非常に便利でよく使うのですが、不思議なことに所謂英語解説サイト等々でも詳細な解説記事がありませんでした。Twitter等で検索をかけていただければわかると思うのですが、一般的によく使われています。
ほぼ全てのパターンで、後ろに , but〜 を伴って用いられます。最初に if SV で自分の「願望」を言い、but〜で「しかし実際は〜である」と現状を言い表します。
そのため、if SV の部分は必ず仮定法時制で、but〜の部分は通常の時制になります。
仮定法の捉え方が難しい会話
Brooklyn Nine-Nine S1-E13




書き起こし
Jake: If you'd (had) won the bet, were you really gonna destroy my car? [もし賭けに勝ってたら俺の車廃車にしてた?]
Amy: No. I was gonna drive it. So I could learn stick. [いいえ。運転するつもりだったの。そしたら運転の練習になるし。]
※ learn stick [(マニュアル車の)運転の仕方を学ぶ]
"stick shift" で「マニュアル車」という意味。
まず仮定法が使われているのは"If you'd won the bet,〜"というJakeの質問ですね。仮定法は実際に起こらない/起こらなかったことを意味するので、「実際はAmyは賭けに負けた」ということが間接的に伝わりますね。
ではAmyの返答はどうでしょうか。"I was gonna drive it." は一見すると仮定法のように思われますが、もし仮定法なのであれば "I would have driven it." のようになるはずです。つまり、"I was gonna drive it." は仮定法ではなく、「(賭けに勝つか負けるかは関係なくもともと) 運転するつもりだった。」という意味です。
「〜するつもりだった。」というのは元々の「願望」のことですので、「実際には起こらないこと/起こらなかったこと」を表す仮定法には専門外の領域なんですね。
そして "So I could learn stick." の "could" は、直前の "I was gonna drive it." と連動している文です。
I was gonna drive it so (that) I could learn stick. [それで練習ができただろうから、運転するつもりだった。]
ここでの "could" は、「運転するつもりだった」という過去の話を念頭に置いて、「そしたら〜できただろうし。」という意味で使っています。要は「時制の一致」です。so that構文内でも時制の一致のような現象として、このように助動詞をcouldやwouldに変えることがよくあります。
この会話には続きがあるのですが、そこの会話も一見すると混乱してしまうような仮定法が使われています。



書き起こし
Jake: You wouldn't. [まさか(運転なんて)するつもりじゃなかったよね...。]
Amy: I would. Would've been like, ... [その気だったわ。(賭けに勝ってたら)こんな感じの運転だったと思う。ギギギギギィィィィ...(車の音マネ) ]
まずJakeの"You wouldn't."。
これは、Amyが直前に言った "I could learn stick." に対して、"You wouldn't (learn stick)." 「まさかやるつもりなかったよね...。」と言っています。ここでの "would" は、"I was gonna drive it." という過去の時点からの意志の話です。
そしてAmyのセリフですが、まず最初の "I would." はJakeの "You wouldn't." に対する返答ですね。当初の意志の話として「〜するつもりだった」ということです。
そして直後の "Would've been like..." ですが、これはそもそもの会話の起点であるJakeの "If you had won the bet,〜" に対応した仮定法になっています。
つまり、整理するとこのようになっています。
・I would. → "So I could learn stick." に対応した表現で、賭けの勝敗がわかる以前の「当初の意志」の話。「(最初は)〜するつもりだった。」
・Would've been like... → "If you had won the bet,〜" に対応した仮定法 -- 3rd Conditional の表現で、「もし賭けに勝っていていたら、実際こんな風に運転してたと思う。」という意味。
このようにして、前提としている時制が異なるために、それぞれ対応した表現になっています。
仮定法のeven if における evenの省略
Brooklyn Nine-Nine S1-E8
Jimmy Broganという作家が自分の上司を「ホモ野郎」と差別したことに対し怒った主人公はその作家の顔を殴ってしまい、その後に記事で大々的に非難されてしまうのですが、そのことを知った上司が主人公を労った際のセリフがこちらです。


Jimmy Brogan wouldn’t know a legit cop if he punched him in the face.
※ he = a legit cop / him = Jimmy Brogan
※ "legit" はlegitimateの省略形で口語表現。日本語で言うところの「ガチの」や「モノホンの」と言う意味ですので、「本物の」という訳もアリです。
字幕:「ジミーブローガンは殴られて初めて、本物の刑事が分かっただろう」
吹き替え:「本物の刑事に殴られても懲りないようだ」
この文章をパッと見ても翻訳通りの意味に取るのは少し難しと思います。その原因は単純で、実はこの文章では本来 "even if" であるはずが、 "even" が省略されているのです!
"Even if〜" で "even" が省略されるケースは意外とよくあるのですが、慣れていないと即座にそれを見分けることは難しいですし、意味も通らなくなってしまいます。
Jimmy Brogan wouldn’t know a legit cop if he punched him in the face.
if〜と捉えた場合:「もし顔を殴られたら、彼は本物の警官を知らないだろう」(少し意味不明。。。)
even if〜 と捉えた場合:「彼に本物の警官はわからないだろう。たとえその警官に顔を殴られたとしてもな。」
見分けるコツですが、今回の実例のように、
『文の後ろに if〜 がある時は大抵 even が省略されてる「たとえ〜しても」の意味』 と考えておきましょう!
ちなみに、この文章は「仮定法」を使っています(even if he punched him〜 から分かる。)が、この上司はあくまでも主人公がジミーブローガンの顔を殴ったことを知らないフリをしているので、「(実際殴られたのかは知らないが) 殴られても彼に本物の警官はわかるまい。」と、洒落た労い方をしているんですね!
・If節が仮定法過去で、主節が仮定法過去完了に見えるパターン
The Punisher S1-E5

このシーンは、主人公のフランクに車を修理してもらった際に、その家の娘ちゃんがお母さんに言ったセリフです。
興味深いのは、このセリフが以下のような構造になっていることです。
It would have cost 500 bucks if we went to a mechanic.
(もし修理に行ってたら、500ドルはしただろう。)
if we went (If節):仮定法過去 (2nd Conditional)
It would have (主節) : 仮定法過去完了(3rd Conditional)...?
この文自体が仮定法の文であることは間違い無いのですが、実はここの仮定法過去完了に見える「主節」が肝なのです。
実はここの主節は、直説法に戻した時には「過去形」になるものではなく、「完了形」になるものなのです!
仮定法:It would have cost 500 bucks, if we went to a mechanic.
「もし修理に行っていたら、500ドルはしただろう」
直説法:It will have cost 500 bucks if we go to a mechanic.
「修理に出したら、それは500ドルはかかることになるだろう」
つまり、主節の "It would have" は、本来は未来完了と呼ばれる"will have" が、仮定法時制として will → would に変化したものです。
ですので、意味的にも仮定法過去完了(3rd Conditional)ではなく、あくまでも仮定法過去(2nd Conditional)の意味になります。
[if節が仮定法過去で、主節が仮定法過去完了というパターン]
に遭遇したら、その主節は直説法に戻したときに「完了形 (現在完了or未来完了)」のニュアンスであり、その主節自体は仮定法過去(2nd Conditional) の意味であることに注意しましょう!
・more than meets the eye [見かけ以上の] / per sb [〜によって] etc.
デザイナー Christine Wada氏 についての記事より

Loki Costume Designer Tells Us the Secret of Tom Hiddleston’s Magic Pants
たまにはNetflixからではなく一般向けの英語記事からの実例も見ていきたいと思います。
こちらは現在 Disney+ で配信中の『Loki』でコスチュームデザイナーをされているChristine Wada 氏についての記事です。

While these observations are true, I thought interested parties would also like to know that Hiddleston’s suit pants had even more impressive powers than meets the eye.
[これらの考察が本当なのだが、ファンたちはヒドルストンのスーツパンツに隠された見かけ以上のすごい仕掛けを知りたいのではないだろうか。]
※ more 〇〇 than meets the eye [見かけ以上に〇〇な]
ちなみに、本文中にある "interested parties" 。これは本来は「ビジネスの当事者/利害関係者」などを意味しますが、ここではおそらく"interested parties" (関心を持った人々) =「ファンたち」の意味で使っていますね。
もちろんファンたちも作品のビジネスに関わる立派な「当事者」ですので、ダブルミーニングでもあると思います。

It turns out, per Wada, that they "are actually made out of vintage 1950s suiting fabric.”(Wada氏によって、それらが実際に50年代ヴィンテージのスーツ生地で出来ているということが明かされた。)
※ it = that 〜
この "It turnes out, per 〇〇, that SV." は覚えてしまえば英作文などでも使える非常に便利な文章です。"per" という前置詞は「〜毎に」という意味で覚えている方もいるかもしれませんが、実は「〜を通じて/〜によって」という意味でも使われるんですね。

This perfectly gels with the TVA's overall retro-futuristic look.(この工夫はTVAの全体的なレトロフューチャーな見た目にぴったりだ。)
※ gel with 〇〇 [〇〇と上手くやる / 〇〇にぴったりである]
→ ゲルが流れ込んでぴったり合うようなイメージ。
"TVA" というのは Loki に登場する組織の名前で、正式名称は "Time Variance Authority" です。
"retro-futuristic" [レトロフューチャー感のある] という形容詞も、最近の作風のブームを語る上では欠かせない表現です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
