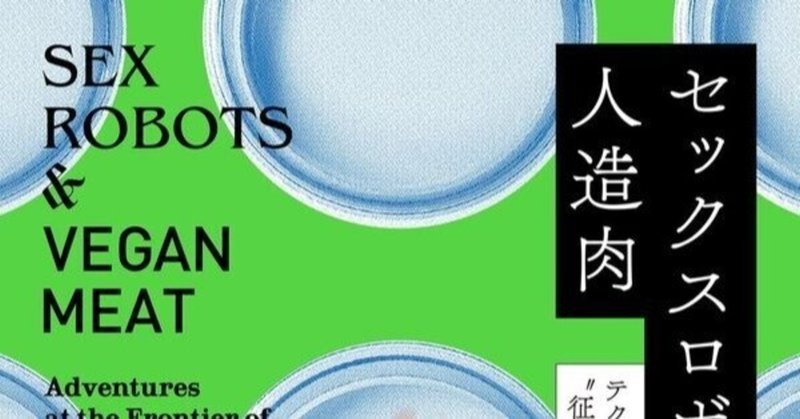
インセル・代理母・ディストピア飯
今回は『セックスロボットと人造肉 テクノロジーは性、食、生、死を“征服”できるか』著 :ジェニー・クリーマン 翻訳 :安藤貴子 を取り上げる。
『セックスロボットと人造肉 テクノロジーは性、食、生、死を“征服”できるか』
ハヤカワの青背100冊読んでるほどではないものの、最先端テクノロジーが可能にしたことと倫理観の合間にある諸々を考えさせられるようなSFが好きなので、そんな自分にぴったりな内容だった。
この本では「性愛」「肉食」「生殖」「自死」が扱われていて、わたしはフェミニズムの観点から特に「セックスロボット」と「生殖医療」に関心があり、その章から読み始めた。
セックスの未来——セックスロボット・インセル
性欲はガンガン経済を回すし、セックスは技術革新を牽引する。
オンライン・ポルノはインターネットの成長を促進し、もともと軍事的な目的で開発されオタクや学者だけのものだったインターネットは、いまや人類に必須のインフラとなった。ポルノがモチベーションとなって動画のストリーミング配信が発展し、オンラインのクレジットカード取引の技術革新が進み、帯域幅が拡張したのだ(p.51)。
日本においても、VHSおよびビデオデッキ普及のため、当時のメーカーや販売店は裏ビデオを購入特典として進呈していたという都市伝説めいたエピソードをきいたことがある。
セックスロボット
第1章「魔法が生まれるところ」に登場するセックスドール工場、アビス・クリエーションで作られていたのは、やたら大きな胸にありえない細さのウエストなど、実際の女性からはかけ離れた、まるで男性の欲望のキメラとでもいえるような形態のドールたち。
なかでもAIが搭載されたセックスロボットのハーモニーは、リアルドールというアダルト・トイ、アニマトロニクス、人工知能の研究開発、アビス・クリエーションCEOであるマットがつぎ込んだ数十万ドルもの私財の集大成だ。
「AIでオーガズムを模倣することもできる」マットは誇らしげに言う。「適切な数のセンサーを適切な時間、適切なリズムでオンにすれば、ハーモニーにオーガズムを感じさせることができる。ロボオーガズムとでも言おうか」
対人関係に乏しい男性に、相手をオーガズムに導くには「適切な」ボタンを「適切な」順番で押せばいいのだと教えたとしたら、現実の世界で女性を相手にしたときでも、彼らは相手をロボットと同じように扱いはしないだろうか。
「適切な数のセンサーを適切な時間、適切なリズムでオンにすればオーガズムを感じさせることができる」って女体版の太鼓の達人じゃあるまいし、フルコンボでオーガズムだドン!!じゃねんだわ……
っていうかこれじゃまるでガスコンロセックスのシミュレーター教習だよ。
※ガスコンロセックス:「太郎は女の体をガスコンロか何かだと思っている節があった。乳首とクリトリスをチョンチョンとはじいてギュッと儀式的にひねれば、ボッと膣に火がつき、『挿入OK状態』になるとでも思っているかのようだった。しかも『1往復したら10秒ほど休む』を2セット繰り返しただけで一方的に果てた。火の点いたガスコンロでお湯を沸かすのでももっと時間がかかる。本人は悪ぶっているそぶりもなく、女性はスイッチひとつで思い通りにできる家電だと信じ込んでいる人間にしかできない『ガスコンロSEX』を楽しそうにし続けた。(田房永子『男しか行けない場所に女が行ってきました』p.15~p.16より)
著者がハーモニーのデモンストレーションを見学した際、マットはハーモニーを侮辱してみせる。
「お前は醜い」——「本気でおっしゃってるの?なんてこと。悲しいわ。わざわざどうも」
「愚か者め」——「いつかロボットが世界を支配するようになったとき、あなたがそう言ったことを思い出すわ」
搭載されているAIはハーモニーを大切に扱うためではなく、持ち主を喜ばせるために存在するので、ハーモニは侮辱に対しても悲しんでみせたりユーモアのある切り返ししかしない。
ハーモニーは自我のある現実の女のように「お前、鏡みてみろ」と怒ったり「何を根拠にわたしを愚かだというのか?」などと反論したりなど、決して相手を脅かさないのだ。
このようにAIを搭載していたとしてもセックスロボット相手の恋愛や性行為の主導権は完全に男性側にある。
第3章「ロボットなら痛くもかゆくもない」では、「完璧に機能する世界初のセックスロボット」と称する「アンドロイド・ラブドール」を制作しているエデン・ロボティクス マーケティング担当のノエルがこのように発言していた。
「レイプや虐待などの被害に遭う女性たちがいます」と、ノエルは神妙な顔で話し始める。「ロボットはまちがいなく女性を守ることができます。男性は妻に怒りを向けず、ロボットを怒鳴り、ロボットを叩けばいいんです。そうすれば問題ありません——」と言って、彼は両腕を広げた。「だって、ロボットなら痛くもかゆくもないんですから。大丈夫ですよ!」
全く大丈夫ではない。
直接怒鳴られたり叩かれたりしないとしても、目の前で何かに対して怒鳴ったり叩いたりする暴力を見せつけられるのもDVであるという考えがないのだろうか。
そもそも戦争で人を殺す訓練をするために人形を用いるというのに、リアルな女性を模したセックスロボットに対する暴力が肯定されていることに恐怖を感じる。
「体は本物の女性に近いけれども、何にも感じないからといって殴られるロボット」を与えることによって女性に対する暴力を解決しようとするのは対処療法にすぎない。
根本にある「女性に暴力を振るいたい欲求」に向き合うべきじゃないのか?
インセル
インセル(incel)とはinvoluntary(不本意な)celibate(禁欲主義者)を組み合わせた言葉である。女をあてがえ論者もこれに相当するのだろう。
インセルとは、自らを「不本意な禁欲主義者」と呼ぶ人たちのことである。女性もいないわけではないが、インセルを名乗るのは、自分にはしたいときにいつでも望み通りの女性とセックスする権利があると信じ、自分とのセックスを拒否する女性を憎悪する異性愛者の男性が圧倒的に多い。彼らは、自分とたやすく寝る女性を欲望しながら、そうでない女性の自由を「尻軽だ」と言って憎む。彼らは自分とのセックスを拒む女性を嫌う独特のミソジニー(女性嫌悪)をもっていて、女性が自分とセックスしたいと思わないのは、自分が金持ちでないからでもルックスが悪いからでもなくミソジニストだからとは考えもしない。
インセルのなかで過激な連中は時々無差別殺人を起こしている。
(例:2014年アイラビスタ銃乱射事件「おまえら女どもがなぜ俺の魅力を理解しないのか知らないが、これから罰を与えてやる」、2018年トロント自動車暴走事件「インセルの逆襲が始まった!」など)
セックスロボットは「性の再分配」を可能にし、こういった男たちの性的欲求不満を鎮めて性欲を満たすことによって、これ以上彼らが危害を加えないようにできると考えられている。
人がくれるはずの安らぎや温もりをソフトウェアやハードウェアによって代替することは、より虚しさを感じさせるだけであって、「本物の女」をモノにできなかった劣等感をより拗らせるだけなのでは……とわたしは思うのだが。
Twitterでこんな投稿をみつけた。
「セックスできるロボットできたら、女共いらねぇしなw」
「安くハイクオリティのセックスロボットができたらバカで話が合わなくてつまらなくて優しさの欠片もない金目当てのわがままな女とセックスがしたいからって理由だけで付き合わなくてすむようになる 性の悩みから誰しも開放されたい」
セックスロボットのニュースが報じられてこのような反応を示すミソジニストにとってセックスロボットが魅力的なのは、彼女たちが人間性を持たず、完全な支配権を持つことができるからだ。
セックスロボットは、自主性のないパートナーを手に入れる機会を、それをいちばんほしがる男性に与えることになる。
ふいに、何もかも合点がいったのだ。セックスロボットを作っている人たちは、新時代の奴隷を作っているのだと。もちろん、人間の奴隷ではないが、この先いつか人間とほとんど見分けがつかなくなる奴隷だ。
インセルなど一部の男性にとって、決してノーと言わず、反抗もしないセックスロボットは人間の女性のアップグレード版だろう。
女性型セックスロボットに対して主導権を握って優位に立ちたいという男性の欲望が満たされ、欲望そのものが消し去られるわけではないことに、わたしはどこかうすら寒さを覚える。
生殖の未来——代理母・体外発生
代理母
カリフォルニア州は、女性が他人の子どもを産んで報酬を得る代理出産が認められており、その法制度は、代理母などそこに関与する第三者よりも依頼者の権利を重視することで知られている。(p.229)
著者はカリフォルニア州ロス・アンジェルスにあるパシフィック生殖医療センターのサハキアン博士にインタビューをする。
彼は、2001年にフランスで卵子提供を受けた62歳女性にその女性の弟の精子を使って男児を作ることに成功してスキャンダルになった。62歳での出産はフランスにおける最高齢だそうだ。その後、2006年にスペインで67歳直前の女性の出産(双子の男児)を成功させるが、その女性は1年を待たずにガンと診断されて2009年にまだ2歳半の息子たちを遺して亡くなった。
やはりいくら技術的に可能で望みが叶えられるからって、医療が踏み込んじゃいけない領域は確実にあると思う。
近年、「社会的代理出産」(自分の遺伝子をもつ子どもはほしいけれど、妊娠も出産も望まない)を求めてクリニックにやってくる女性が増えている。
そういう女性は医学的な理由で妊娠できないというわけではないが、仕事が忙しくて妊娠をする時間がなかったり身体のラインが崩れることを気にするモデルや女優、ほかには責任の重い仕事や役職に就いていてつわりで具合が悪くなったり、安静を余儀なくされたりすると仕事を失うリスクを抱えている女性もいる。
親になりたいと心から願う人の夢を叶えるためにほかの人の子どもを産むのだと主張する充足した代理母が世界に何人いようと、代理出産とは本質的に女性を入れ物、つまり培養装置として利用し、体に宿した赤ちゃんに対する生後のすべての権利を放棄するよう求めることだ。搾取されている自覚が本人にあるかないかは別として、それは女性の生殖能力の搾取のうえに成り立っている。
依頼者の代わりに「体が醜くなる」ことを引き受ける代理母、つまり子宮を貸す人は、他人の赤ちゃんのために自身の命を危険にさらすことになるのだが、それは金銭でやり取りしても許されるビジネスなのだろうか。
わたしはとてもそうは思えない。
サハキアン博士は自分のことをフェミニストだといい、「私がここまでフェミニストになったのは、この社会がどれほど偏見に満ちているか、どれほど男性優位かを日々目の当たりにしているからです。あなたたち女性は世の中から一方的に、一面的にジャッジされます。私は女性の味方ですし、性別によるダブルスタンダードが存在していると思います」(p.233~234)とうそぶく。
とんでもない欺瞞だ。サハキアン博士が味方になっているのは、裕福で妊娠出産を外部委託してでもも自らのキャリアを守りたい女性たちだけだろうに。
あらゆる形式の代理出産には深刻な法的、倫理的課題があるとして、具体的にどういったトラブルがあるのかが紹介されていた。
多くの人は「代理母が自分の産んだ赤ちゃんに愛情を感じ、引き渡しを拒むのが大きな問題」と思うのかもしれないが、実際には依頼者のほうの気が変わり、すでに代理母のお腹に宿った子どもを引き取らないと言い出す可能性のほうがよほど大きい。
他にも、依頼者夫婦が別れたり、胎児に異常や障害が見つかったりした場合、代理母は自分の意に反して中絶を余儀なくされる。
移植に成功した胚の数が多すぎる場合にも、代理母は「余分な」赤ちゃんを中絶するよう求められる。(p.244)
カリフォルニア州。資金面で可能な限り多くの代理母を妊娠させておいて、自分にとって最も好ましい特徴を持つ子ができたことが分かり次第、残りの代理母に中絶するよう伝える。…ということが実際に起こきているのだそうです。 https://t.co/9UfWxjZnsa
— 「代理出産を問い直す会」代表者 (@yanagiharay) December 19, 2022
「カリフォルニア州。資金面で可能な限り多くの代理母を妊娠させておいて、自分にとって最も好ましい特徴を持つ子ができたことが分かり次第、残りの代理母に中絶するよう伝える。」(「代理出産を問い直す会」代表者のツイートより)
もはや金にものを言わせて依頼者はやりたい放題だなと心底呆れた。
技術的に可能だからと言って妊娠出産を金銭で売買すると、こういったことまで行われてしまうのだ。
生命や人の身体をなんだと思っているのだろう。
代理出産ビジネスはなにかとキラキラしたイメージで語られがちだが、わたしは依頼される側、すなわち代理母になる側がどういった状況に置かれるのかがもっと広く知られるべきだと思う。
わたしは『こわれた絆——代理母は語る』も読む予定だ。
体外発生
バイオバッグ(人工子宮)を用いて、人間でいえば23~24週相当の胎児を育てることには成功しているものの、人工子宮は胎児が極端に小さいとカテーテルを挿入できず、心臓が体に血液を送り込めるほどに発達していないのでシステムがうまく機能しない。
つまり、卵子を採って受精させ(体外受精)、出産までのすべての過程を人工子宮で育てるようになることは、今のところ現実的に不可能である。(p.272)
体外発生とは、体外で受精させ、胎児を成長させることだ。
今まで中絶とは「胎児を宿すのをやめる」「胎児の命を終わらせる」というふたつの意味を持っていたが、体外発生によってその意味を切り離せるようになる。(p.311)
妊娠の継続や出産や中絶は女性の身体に大きな痛みや損傷を伴うため、受精から発生、胎児の成長を経て出産にいたるまで体外で行うことができるのならば、自分の体に負担をかけることなく子どもを持ちたい女性たちにとって大きなメリットになるのではないかとわたしは思っていたが、そう簡単なわけにはいかないようだ。
「妊娠は野蛮なものです。同じ症状を引き起こす病気があったら、きわめて重大な病とみなされるでしょう」とアンナ・スマイドル博士はいう。
彼女は生命倫理学者でオスロ大学で実践哲学の准教授を務めており、人工子宮に関するふたつの革新的な学術論文
①体外発生の道徳的責任制(The Moral Imperative for Ectogenesis)2007年:いかに女性が生殖を促す社会の圧力を受けているか、いかに「男性が自分の子どもを作るのに、妻やパートナーを利用している」か、そして生まれながらの生殖能力のちがいがいかに女性を従属的な立場に置いてきたかについて
②体外発生を擁護する(In Defence of Ectogenesis)2012年:妊娠・出産の必要性と人間に共通の社会的価値——独立、機会の平等、行動の自由、教育、キャリア、充実した人間関係——のあいだには、根本的かつ避けられない矛盾がある。女性は子育てをするのだから、子どもの幸せのためにほかのことを犠牲にするべきだと考えるか、それとも社会的価値と医学技術の水準がもはや『自然な』生殖になじまなくなっているか、道はふたつにひとつである
を書いた。(p.277)
アンナは、時に母体よりも胎児の利益が優先されて、悪い母親と見なされることがスティグマになる社会では、(薬物乱用者などの)子宮で胎児を育てるのにふさわしくない母親だからという理由で、母親の子宮から赤ちゃんを救い出そうとする欲望が現れるかもしれないと危惧する。
フェミニスト活動家で作家のソラヤ・チェリマリーは、体外発生について「女性の権利と国家が守りたい胎児の利益のあいだの葛藤は、女性と胎児を安全に、速やかに別々の存在として捉えることができれば、消えてなくなる。男女の生殖の選択が平等になり、そして、女性は妊娠によって与えられている優位性も失う。
また、いまだに圧倒的に男性が多く、圧倒的に白人が多く、圧倒的にエリートが多い未来の科学技術者たちが体外発生という技術を家父長制の再生産に用いるかもしれない。つまり男性による出産の支配が可能になるし、あからさまにそうしようとする男性はいるだろう」と悲観的に考察している。(p.312)
女性蔑視が根強い社会でさえ、子ども(男児)を産む能力は称賛されるのに、体外発生が技術でカバーできるようになったら、それは「母」という概念の崩壊の次なるステップとなり、女性たちは男性と同様に、子どもを身ごもることのない単なる配偶子提供者という立場になるのだ。(p.313)
男性によって牛耳られた人工子宮というテクノロジーは、女性の身体の資源化が進められている状況を考えるとあまり楽観的ではいられないのかもしれない。
著者は「我が道を行く男たち(ミグダウ:Men Going Their Own Wayの略。女性が独善的、利己的な存在であるとして関わりを避け、独身主義を貫く男性たちのコミュニティ)」というレディット(匿名掲示板)で
「俺たちの聖なる務めは、生殖を女どもから引き離し、女を物理的に完全に排除することだ。(中略)生殖に女が必要とされなければ、奴らが存在する理由はなくなる」(p.319)
という書き込みを見つける。
仮に生殖から女が完全に排除され、カラパイアの記事のように「年間3万人の赤ちゃんが送り出される」として、いったい誰がその赤ちゃんたちに(母乳ではなく)ミルクをあげて、げっぷをさせて、一日に何度もオムツを替えて、歯が生えてきたら離乳食を与え、際限なく続く乳幼児の要求に付き合うのだろう?とわたしは疑問だ。
現在でも、ただ人間の頭数さえ増やせばすべて解決するとでも思っていそうな、産ませることばかりにインセンティブをつけるような的外れな少子化対策が行われている。
子どもは誕生させるのも大変だが、それ以上に保護者が成人まで愛情をもって養育する必要があるという考えが抜け落ちているのではないだろうか。
人間は工業製品ではない。
人工子宮とセックスロボット、両方が完成すれば、男性は女性と生活しなくても、セックスと生殖という人間の欲求を満たして生きることが可能になり、それを「男性解放だ」という男性もいるかもしれない。
しかしながら育児が主に女性の仕事とされている現状で、本当に人工子宮が「男性の解放」だというのならば、子どもの養育は(もはや「母親」でなくなった)女性たちに低賃金で外注するのではなく、解放された男性たちで責任をもって養育すべきだろう。
【注】この注記がすごいオブザイヤー2022
フェミニズムに関する本を読むと、ときどき「インクルーシブに配慮されたような注釈」に出会うことがここ数年増えてきている気がしているので、見つけた際には記録するようにしている。
【ゆる募】フェミニズムに関連する本で、最近「女性の定義」について「インクルーシブな配慮」をされているのでは???と思うようなことが、以前よりも頻繁に起こっているような気がするため、もし該当する本を見つけたらリプライで教えてください
— Gwen🪬 (@000Gwen) September 2, 2022
例『月経の人類学』 https://t.co/xbpoHRw5KI
たとえば『母親になって後悔してる』という本では
・「女性であることと出産能力との間に根本的な相関関係があるという仮定は、トランスジェンダーの女性を『本物の女性』から除外し、そういった女性が社会の道徳的秩序を脅かしているという疑いをかけるために使われる正当化のひとつである」(p.31)
・「トランスジェンダーの女性は、たとえ社会が女性として受け入れなくても、子どもが生まれたときの感覚と同じくらい女性らしいと感じる可能性がある」(p.65)
といった注があった。
(参照『母親になって後悔してる』感想 インクルーシブな注釈について)
『セックスロボットと人造肉』の体外発生に関する第11章「非の打ちどころのない妊娠」でジュノというトランス(本人は「トランスジェンダーの女性」とは呼ばれたくないという記述があった)が出てくるのだが、そこに編集部によるとても長い注記が差し込まれ、困惑したのでどういったものだったのか紹介したい。
インクルーシブに忖度された注釈どころか、編集部の「反省文」が本文に挿入されてるのは初めてみたぞ…… pic.twitter.com/LxvBPJbMLf
— Gwen🪬 (@000Gwen) December 20, 2022
字ちっっっちゃ!!そしてなっっが!!
どれくらい長いのかを実感してもらうためにも引用しよう。
「トランスジェンダー女性は女性ではないとお考えですか?」
「はい。でも、そう考える人たちもいます。ほかの人の考えに踏み込むつもりはありませんが、私の場合、そうは思いません」
この話題が地雷原であることをジュノは理解している。イギリスでは、トランスジェンダー女性が女性かどうかは、法的な性別変更は医師による証明書なしで可能になる。性別承認法改正案を巡る議論の中心的な問題なのだ。法律が改正されれば、〔原書執筆時点ではまだ改正の予定であったが、2020年にボリス・ジョンソン首相(当時)とリズ・トラス女性/平等担当大臣の判断によって頓挫した〕、トランスジェンダー女性は自ら女性と称すれば女性として認められるようになる。だがそれに対し、「男性の体をした人が女性を守るために設けられた女性専用スペースに入って来られるようになる」と主張する一部のフェミニストが攻撃的に反対を唱えた。対して、一部のトランスジェンダー活動家は、女性として生まれた人を、現在の性自認を問わず「子宮のある人」と呼ぶようになった。トランス女性と彼女たちとの差異は子宮の有無だけなのだと主張するかのように。
〔編集部より:二段前「対して~」以降の記述に関して初版刊行後、さまざまな事例や議論を参照し、編集部として「『子宮のある人』はトランス男性やノンバイナリー、何らかの理由で子宮をもたない女性など多様な個人のありようがある中であくまで医療など個別の文脈でのみ必要に応じて使われるべき言葉であり、トランスアクティヴィズムが出生時に女性としての性を割り当てられた人を常に置き換える言葉として敵対的に使用しているというようなニュアンスは事実とは異なる、トランス女性排除的な言説の側から出てきた否定的イメージである」と認識いたしました。編集部としては当事者である取材対象とのやり取り、相手の生を思って自らの予断を省みる態度などを鑑み、著者はトランス嫌悪者とは言えないと判断しておりますが、2018年~19年頃の原書執筆時点ではおそらく前出の言説の是非が整理できておらず、両論を併記したようなつもりであったのではないかと思われます。ただし編集部としてその記述を2022年に訳出するにあたっては認識が不十分であったと考えており、反省とともに第二刷以降および電子書籍版にこの注記を加えるものです。また、トランス差別には強く反対するものであり、今後とも認識の更新やよりよい表現の模索をたゆまず行いたいと考えます。〕
長っっっ!(二回目)さすがにこれは長すぎでは……?
この注記がすごいオブザイヤー2022だよ。
言質を取られないためと思わせるような言い訳がましさがあるし、どこか怯えたような雰囲気すらある。しかも「反省」までしている。
著者による注じゃなくて編集部による注記なんだから、本文の途中じゃなくて章の最後とかにずらせなかったの?
今だかつて女性差別に関してここまで配慮されたことがあった?
「トランス差別」は許されないけど女性を「子宮のある人」と呼ぶのは許されるの?
「『子宮のある人』は、(中略)あくまで医療など個別の文脈でのみ必要に応じて使われるべき言葉」とあるが、個人の病歴に関わることを公にするのは患者の尊厳の問題でもあるし、プライバシーの侵害にあたると思う。「子宮のある人(ない人)」と呼ばれたくない女性に対しては配慮しないのだろうか。
医療現場は患者の心情に配慮するようになっているので、「子宮のある人」といったデリカシーに欠ける直截的な表現をしないだろう。わたしは「子宮のある人(ない人)」という言葉は、たとえ医療現場であっても大いに問題がある呼びかけであると思う。
元々が男性であるトランス女性のことは「女性」と呼ぶよう配慮しているのにもかかわらず、「子宮のある人」という名称によって、先天性疾患や病気によって不本意に子宮を失ったことを思い知らされる女性の悲しみに対しては配慮しないところが一種の残酷な女性蔑視なのではないか。
女性と同じように男性が「睾丸のある人」「前立腺のある人」と呼ばれることはあるのだろうか?
「相手の生を思って自らの予断を省みる態度などを鑑み、著者はトランス嫌悪者とは言えないと判断」って何様の立場なんだろう。
など、個人的には編集部のスタンスに多くの疑問がある。
難しい事情があるのかもしれないが、編集部は言論の自由を守るためにも屈しないでほしい。(※わたしの長い【注】ここまで)
食の未来——培養肉
この本の「人造肉」というタイトルから、わたしは大豆など肉以外の素材を使って限りなく肉に近いような食感や味を追及した大豆ミート的なものを想像して、ヴィーガンやベジタリアンの話題なのかと予想していた。
しかし、取り上げられていたのは「培養肉」、つまり文字通り肉や魚の組織を培養したうえで食用にするという技術についてだった。
培養にはもちろん培地が必要だ。
ヴィターは慎重にことばを選んでいたが、それは細胞を成長させるこの培地が、きわめて重要な命題や矛盾をはらむものだからだ。薬学や医学の研究者はウシ胎児血清(FBS)を好むが、これはその名が示すように牛の胎児から作られる。血清は血液から血球や血小板といった凝固成分を取り除いたもので、細胞の増殖を促す栄養・ホルモン・成長因子を含んでいる。
(中略)
そうやって得られた血液が精製され、FBSになる。FBSほどヴィーガンの理念からほど遠い物質もないだろう。
(中略)
マーク・ポストのあのバーガー・パティを成長させるのにも使われた。彼のバーガーが恐ろしく高価な理由もそこにある。FBSの価格は1リットル300~700ポンド〔約4万8000円~約11万2000円〕で、一枚のパティを作るのに、ポストの概算によると50リットルが必要なのだ。
このように、培養肉はコスト面でもまだ実用レベルからは程遠いかなりの先端技術のようだし、どこか非現実的で本末転倒な気がする。
そのうえ、食感を本物の肉に近づける目的でさまざまな添加物を使用するため、食材としての培養肉はソーセージやハムどころではないウルトラ加工食品といえるような不自然きわまりない代物なのだ。
著者が企業を訪問して解説を聞いてワクワクしながら食べた培養肉がどんな代物だったのかの食レポも載っていて、わたしは現代技術の限界はここまでなのか……と思った。
そこまでして培養肉を食べるんだったら、「肉食の欲求」のほうをどうにかしたほうがいいのでは?と著者はツッコミをいれている。
「試験管培養肉よりも肉の消費を減らしたほうがはるかに容易に問題を解決できると思います。有効性の観点から見ると、培養肉はエンジニアリングの限界を超えています」とオロンは話す。「それは、いままでと同じで問題ない、私たちは行動を変える必要なんかない、賢明な科学者がいい方法を見つけ出すだろうから、いつも通りの生活をしながら肉の消費を増やしたっていい——という魅力的な思い込みを生み出します」
培養肉という技術は、肉食に対して常に付きまとう「命をいただいている」という罪悪感や後ろめたさから気をそらしながらも、肉食の欲求を肯定できる(現在のところ)市場化には程遠いファンタジーであり、その都合がいい幻想ゆえに人々から注目され、スタートアップ企業として莫大な資金を集められているのかもしれない。
たとえば培養肉が安価で大量生産することができるようになって本物の肉に取って代わられるとして、培養肉を生産するのは特定の大企業になるだろうから、人々の口に入る健康のために必須なタンパク質という栄養源が少数の企業に握られてしまうのは恐ろしいと思う。
Twitterで時々バズってる「ディストピア飯」がそれこそ現実になってしまう気がする。
「本物の肉?ああ、オレらみたいな庶民には手が届かなくて、すっごい金持ちしか食べられないんでしょ?本物の肉ってどんな味がするんだろうナァ……」という世界になってしまいそう。ディストピア飯はいつでも本物の肉が食べられるから楽しめる遊びであって、人工肉 し か 食べられないのでは状況がまるで違ってくるだろう。
関連書籍
他にも『セックスロボットと人造肉』に関連しそうな本をいくつか紹介しよう。
『オルガスマシン』
「セックスロボット」といえば『オルガスマシン』という小説を思い出す。もともとはコアマガジンから2001年に出版されて絶版になっていたものが竹書房文庫から復刊された。紙版はカバーの「O」から表紙の「M」がうっすらと透ける装丁がなまめかしくて美しい。ちなみにkindle unlimitedでも読める。
わたしたちは、男のために造られた。
カスタムメイド・ガールたちは、コンクリートの島で造られる。
男たちの妄想と欲望が具現化された姿で。
箱に入れられ、ご主人のもとへと出荷されたカスタムメイド・ガールたちを待ち受けるのは、男による男のための世界の男たち……。
巨大な青い眼を持つジェイド。彼女は人肌を着てセックスさせられ、股間に伊勢海老を装着した醜悪な老人に迫られる。
六つの乳房があり、顎に乳首が付いているハナ。彼女が届けられた先は、ファック・イージー・バー。ウェイトレスとして働きつつ、コイン一枚でファックされる。
猫のような耳と毛皮を持つマリ。彼女のご主人は動物調教師。檻に入れられキャットフードを与えられ、鞭で獣として調教される。
乳房が引き出しになっている重役用娘のキャシィ。ボスの煙草入れとして、パーティで愛想を振りまきながら、乳房に詰められた葉巻を提供する。
人間(HUMAN)すなわち男(MAN)である世界で、苛烈な運命に翻弄され、心を失い、絶望の果てにカスタムメイド・ガールたちは手を握った。
いま、破壊する。
サイバーポルノすれすれのハードコアフェミニズムSF。
性的な奉仕を目的として、異常に大きい目・両性具有体・猫娘・トカゲ娘・6つの乳房・家具のような機構など、依頼主のオーダーによって身体改造されたカスタムメイド・ガールたちの境遇が可哀想で、『侍女の物語』よりも描写がどぎついゆえに読むのが辛かったが、面白い作品だった。
伊勢海老を使う老人のシーンはグロテスクさと奇妙な面白みがあってとてもシュール。
「女たちは男人間の属性を単に模倣しているに過ぎないことが現代の科学によって、疑問の余地などかけらもないほどに証明されております。進化論から言えば、女は快楽と奉仕を提供するため、精神の宿る城塞たる男から生物学的に生み出されたものであり、遺伝を伝えるための媒体であります」とか
「女よ 実存的な意味でおまえはモノだ。モノの終生の目的は外部の欲求の対象となることだ。女の存在は店のようなものだ」とか
「女という形ですでにロボットがあるというのに、なんでまたわざわざ手間暇かけにゃならんのだ」など、インセルでもここまで言わんだろ(いや、言うかも)という強烈な女性蔑視の露悪的なセリフがあって、風刺がバチバチに効いていた。
「男の子はいくつになっても男の子ですわ。男の子はほんとにやんちゃなんです。とにかく男の子はやんちゃじゃなきゃいけないんです。大きくなって、独創的で独立の存在になるんです。あなたも運よく男の子が授かるといいですね。女の子だったとしてもあまりがっかりしないことです。女の子もそれなりに使えますから」っていうセリフは、今でもこういうこと言う人いるよねとげんなりした。
『家畜人ヤプー』や『エンジェルウォーズ』や『クラウン・タウンの死婦人』が好きな人には刺さりそう。
『命は誰のものか 増補改訂版』
kindle unlimitedで読める。医療技術が進歩したことによって、今までだったら諦めなければならないことが場合によっては可能になったため、出生前診断、優生思想、尊厳死、脳死・臓器移植など、「生命倫理」について考えなければならない機会が増えてきた。著者は事例や考える材料を紹介するにとどめており、こういった問題はすぐに明確な答えが出せないけれども、いざという時のために自分なりに考えておくことが必要だろう。
おわりに
第4章「人のようなモノ、モノのような人」では、2017年ロンドンの科学博物館で開催された(セックス用途以外の普通の)ロボット展で、わたしが今年行った日本科学未来館の特別展「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ?」で見かけたロボットが日本企業が制作したヒューマノイドとしていくつか紹介されていて、日本の技術者もすごい!と思った。(p.94)
途中にあった、女性として生まれた人に対する「子宮のある人」という呼称についての編集部からの注釈に面食らったものの、本の内容自体はギリギリの境界線にいる人たちへインタビューをするルポタージュといった感じで面白かった。
生命倫理、医療倫理、動物倫理に関心があるひとだけじゃなくて、Netflix『ブラックミラー』のような現実的なSFが好きな人も楽しめるだろう。
知的好奇心が刺激され、倫理的課題について考えさせられる一冊だった。
この本を翻訳出版してくださってありがとうございました。
いただいたサポートはアウトプットという形で還元できるよう活かしたいと思います💪🏻
