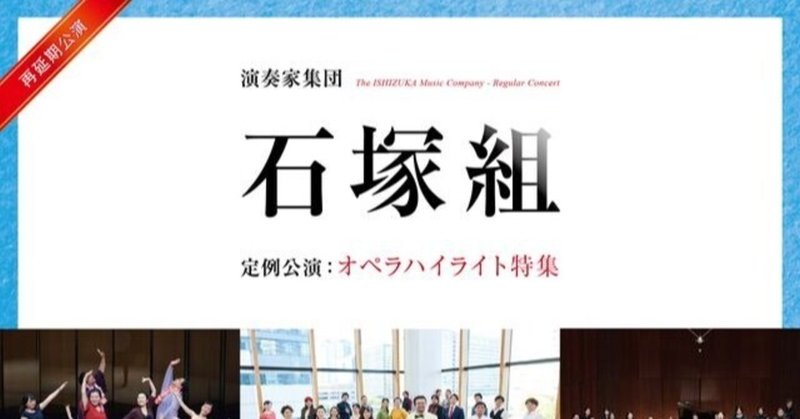
演奏家集団「石塚組」定例公演~オペラハイライト特集~を終えて①
演奏家集団「石塚組」主宰、石塚声楽研究会代表の石塚幹信です。
5月5日(水祝)に渋谷伝承ホールで開催された演奏家集団「石塚組」定例公演~オペラハイライト特集~無観客配信公演から一週間が経過しました。無観客配信に至る経緯については既に記事にしていますが、おかげさまで公演後も公開されている動画に多くのアクセスをいただき、もしかすると初めて我々の舞台を観る方もいらっしゃるかもしれないという事で「石塚組」とは何か、や今回の公演へ至る道のりについて書いていきたいと思います。一応シリーズ化してみますが一体全何回になるのか、どのくらいの頻度で更新できるのか書いてる自分にもわかりません(笑)。「石塚組」マガジンを作ってまとめたいと思いますので気長にお付き合いいただければ幸いです。
演奏家集団「石塚組」とは?
「石塚組」としての定例公演は今回で8回目になります。自分でも「そんなにやってきたのか」と驚いているのですが、第一回のお披露目公演は2016年5月31日(火)に練馬区大泉学園のゆめりあホールで開催しました。はじめの3回は「プロ声楽家によるオペラと合唱の調べ」と題して若手を中心とした声楽家によるオペラと合唱がプログラムの中心でした。この演奏会を企画した意図は大まかに二つあり、ひとつは実力がありながらなかなか出番に恵まれない若手をもっと舞台にあげて多くのかたに知ってもらいたいという事と、もう一つは以前に比べて経験を積む場が少なくなっている現在、少しでもアンサンブル力や表現力を磨くための経験の場を作りたいというものでした。「石塚組」なんて名前を付けたので当初は「石塚が自分がやりたい(歌いたい)曲をやるために若手を集めてなんかやってる」みたいに言われたりもしたのですが、自分は決して自分たちがやりたいものを一方的に送るコンサートを作るつもりはありませんでしたし、この企画では一貫して自分が歌うよりもプロデュースする方に重きを置いています。
ではなぜ「石塚組」などというネーミングになったかというと、実は2015年にこの企画がスタートした時点で既に水面下で「石塚組」という言葉が独り歩きしていて、それは当時石塚はよくアマチュア合唱団や市民オペラにお手伝いに入る「エキストラ」を集めていたのですが、石塚が集めたメンバーがいつしか「石塚組」と言われるようになり、初回のメンバーはそこから声をかけた人が多かったため結果としてこのネーミングになってしまいました。当初は個人的にあまり気乗りがしないネーミングだったのですが5年たってすっかり定着してしまい「組長」と呼ばれるのにもだいぶ慣れてきました(笑)。
「石塚組」公演のスタイル
初回から企画を立てるにあたって大事にしているのは「観ていて面白い舞台なっているか」と「出演者が毎回の企画で得るものがあり成長できるか」という点です。サブタイトルに「プロ声楽家」という言葉が入っているのもこれに通じるのですが、自分はどんなに上手でも自分がやりたいものしかできない人はプロとは言えないと思っています(やりたいものをやってるだけで大勢の人が魅了される一部のスターは除く…)。あくまでお客さんとして観たときに面白いものになっているか、またオペラやクラシック音楽をもっと多くの人に楽しんでもらうためにはどう構成すればよいかという事を考えています。また最近は趣旨に賛同して一緒に舞台を作ってくれる経験豊富なメンバーもいますが、やはり主体は若手と言うことで、有名な団体や世界的なアーティストと共演する舞台に呼ばれる歌手に比べればやはり実力において及ばない部分があるのも事実。でもそういう人でもチケットを買って観に来てくださるお客様に対して一生懸命取り組めば必ず良いものが出来ると信じていますし、自分の中で大事なのは一つ一つの舞台を自分の経験として成長していけることだと思っています。
そのため「石塚組」の企画では必ずしも本人が歌いたいと思うものばかりを選曲はしていないですし、その人の魅力が一番発揮できる曲だったとしても全体の構成の関係でどうしても入れられないという判断をすることもあります。それも含めて自分は演奏家としての勉強だと思っています。特に一本の演奏会を依頼されてプログラムを組んだりリサイタルを開催するときに、自分がやりたい曲をやりたい順番で並べてしまってなんだかちぐはぐなプログラムになってしまうというのは残念ながらよく有ることなのですが、自分は声楽家は他の楽器に比べてこの傾向が強くなりがちだと思っています(これはもちろん理由があるのですがそれはまたの機会に)。
メンバーについて
このような意図で毎回企画している「石塚組」公演ですが、毎回のように参加してくれるメンバーもいますが基本的に「石塚組」に固定メンバーはいないと思っています。茶化して「構成員」とか「組員」とかいう事はありますがあくまで一人一人はそれぞれが独立したいち音楽家として活躍してほしいと思っていますし、自分はこの企画で経験を積んでさらに大きな舞台に呼ばれるようになってくれればそれは喜ぶべきことだと思っています。最近はそうでもないのですがかつては一つの組織に属すると他の団体に出演するのはご法度だったり、先生同士があまり仲の良くない門下生同士だと一緒に演奏会に出るのが憚られたりという事もあったのですが、「石塚組」では一切そのようなしがらみにはとらわれず、囲い込まず、一人一人の演奏家としての活動を尊重したいと思っています。
逆にこれをきっかけに人の縁が繋がり、新しい機会をえられることは歓迎しています。もちろん自分もこの企画に参加してくれたことでいろんな人の新しい可能性を知ることが出来たりして、最近は「参加したい」と集まってくれる人や、いつもなかなかに過酷な要求をするのですが、そこから自分にとって糧になる経験を得てくれる人が増えてきて嬉しく思っています。また「新しいジャンルを開拓してほしい」という意味からも4回目以降はテーマをいろいろと設定し、宗教曲やオペラアンサンブル、ミュージカル、ガラコンサートと多彩な企画を取り上げてきました。もちろんそれぞれの分野が得意な人も参加してくれましたが、「まったく初めてだけどやってみたい」と参加してくれる人がいたのも嬉しい事でした。またレパートリーも「石塚組」で初めて取り組んだおかげで自分の得意レパートリーの幅が広がったという人も居て、当初目的にしていた事が実現できたと嬉しく思いました。
レパートリー拡充と合唱の重要性
そんなわけで個人個人、また「石塚組」としてもレパートリーの幅を広げるべくいろいろな企画を続けてきたのですが、その中でも自分は「合唱」を一つの柱として大事にしてきました。自分がプロとして活動させていただく中で合唱がその活動の中心であるというのもあるのですが、声楽家の活動において自分は合唱は非常に重要な要素であると思っています。
次回は「石塚組」活動における合唱の重要性について書きたいと思います。

この記事は無料公開しています。
「石塚組」活動にご賛同いただけましたら以下の「気に入ったらサポート」からご支援いただければ幸いです。5/5定例公演の無観客配信は石塚声楽研究会のYouTubeチャンネルで配信中です。
https://www.youtube.com/channel/UC-bgoxkLhQiNG6d56tKb6Yg
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
