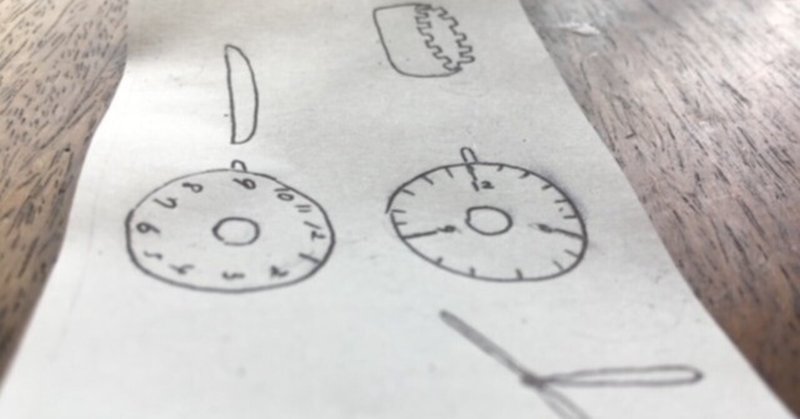
残され残る古本屋
約一年前に記事に書いた、沢山の本で見通しの悪い小さな古本屋の前を通った。厳密には、店の前を通りたかった。
かれこれ二年近く足が遠のいていたところ、先日になって古本屋がある通りを歩いて向かう用事ができたので、丁度気候がよく午後の散歩にはぴったりだったのだ。
こじんまりとした白いビルの一階が見えて、私は建物よりも窪んだところにある扉やガラス窓を覗き込んだ。そうそう、と。
目に入ったのは以前よりも清潔そうな印象の店内と、素早く動く黒い服を来た何人かの人。見覚えのある建物と間取りに、見覚えのない文字と人。
私はここを知らない。
あの古本屋はいつなくなったのだろう。既に別の店が営業を始めているのだから、閉店を知らせる文字や様子は一切なく、二年も離れていた私が感傷に浸る隙もない。
ある、と思ったのだ。
春の午後に夢のような時間を過ごした本屋は、温度や時間の流れが周囲とは若干異なっているようだった。私にとって、日常にあってはいけない場所だったからこそ、頻繁に通うことなく、いつか訪れる日のためにその存在を濃くしていった。
あると信じていたのは、あの空間ではなく、場所だった。
お金を払って何かを得ること以上にその場所で過ごすことに価値のある空間は、その瞬間その瞬間があまりにも魅力的な分、見通しが悪い。その価値を信じていた二年前の私を恥じることはない。あの場所に出合うことができたのは、あのときでしか叶わなかった。
今、別の顔をした同じ場所に立っていても、私の頭の中で古本屋は鮮明な姿で漂っている。それは、フランキンセンスと埃の混ざったあの匂いのせいでもあるのかもしれない。
私の手元には、あの日手に入れた美しい装丁の本が残っている。ようやく埃臭さが抜けたことを今になって寂しく思うが、かたちのない思い出と実態のある証拠の両方を持った私があの場所を失うことはないだろう。
そうは言っても、やられた、という悔しさも確かに存在している。
日常にない空間がいつまでもあると信じ甘えた結果、思い出が残った。
小さい頃から近所にあるカフェ、寂れた商店街の明るいカメラ屋、一年に一度しか足を向けない神社の、何を残していけばいいのだろう。
そういえば、あの古本屋では250円でコーヒーを淹れてくれるのだった。その旨が店の壁かどこかに書かれていて、それはいいと思ったのだが、私は狭い本屋でコーヒーを飲むことを躊躇した。その味を知っておけばよかった、くらいの後悔を残しておこう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
