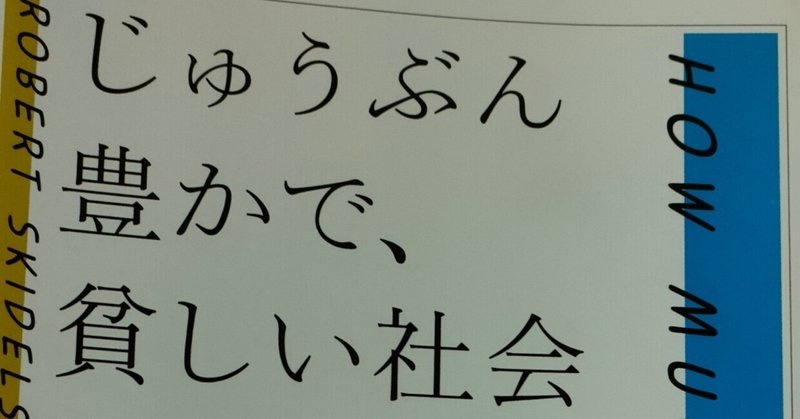
「広告文化を根元で断ち切れる税制改革が一つある。…」
広告文化を根元で断ち切れる税制改革が一つある。それは、広告費を経費として認めず、課税することである。
ケインズが「孫の世代には週15時間の労働で済むようになる」的なことを語った、というのはどこかで聞いたことがある。誰だったか忘れたが、「ケインズの時代の生活水準でよければたしかに週15時間の労働でもう十分かもしれない」と言った経済学者もいた気がする。
「じゅうぶん豊かで、貧しい社会――理念なき資本主義の末路」は後者の言葉とある意味では考えを一にするかもしれない。ケインズは「必要」と「欲望」の区別をつけていなかった。十分を超える欲望を駆り立て、その欲望を満たすことが経済成長の自己目的化しているのが問題なのだと。そして古典を参照しながら、消費中毒・仕事中毒を脱して、よく暮らすことを重視すべきだとする。具体的には健康、安定、尊敬、人格・自己の確立、自然との調和、友情、余暇の七つの基本的価値の実現を目指すべきだと。そのための施策としてベーシックインカム、累進的な支出税、広告の規制、そして保護的な貿易などを提案する。
これだけ書くと説教臭いだけな気もする。面白い点は二つ。一つはそもそも政府は倫理的な価値観を今現在でも反映している分野はあるとすること。酒やタバコへの課税や、欧州での広告への規制がそれに当たる。市場にすべて明け渡しているようで、実はそうでもないのかもしれない。
もう一つは重視すべきは「七つの基本的価値」の実現なので、それ以外はバッサリ斬って捨てており、ともすれば退行的ととられかねない態度を認めるという点。見る人が見れば自由とか人権とかが微妙に後回しにされていると思うだろう。本書は全体的に皮肉っぽい表現が多く面白いが、特に終盤は結構なパンチラインに溢れている。
インドと中国は、同性婚の合法化や動物虐待の法的禁止などを求める欧米の傾向に同調する義務はまったくない。
性の自由が基本的人権の一つとみなされるのは、現代の欧米だけの現象である。
世界のGDPに占める貿易の比率を下げるために、富裕国から貧困国へ流れる資本の一部を融資ではなく無償資金協力にすべきだろう。
私はこの本を荒木優太のツイートで知ったが、まさに引用した箇所に反応していた。攻めているのである。
「インドと中国は、同性婚の合法化や動物虐待の法的禁止などを求める欧米の傾向に同調する義務はまったくない。正義が伝統の放棄を求めるのは、伝統が基本的価値を破壊したときだけである」(スキデルスキー親子『じゅうぶん豊かで、貧しい社会』287)。攻めるね~。
— 荒木優太 (@arishima_takeo) November 29, 2023
著者が参照したのはアリストテレスはじめギリシャ・ローマ時代の哲人や孔子、「ダルマ・スートラ」などの古典だ。だから良くも悪くも結論は自ずと保守的に思えるし、本人もこれがある種のパターナリズムだと明言している。経済の「成長」も価値観の「進歩」にも疑問を投げつけるような本書は実はあまり歓迎されないのかもしれない。それでも消費狂であり労働狂である私には、本書の内容はかなり考えさせるものであった。
ロンドンの金融街で働く人の大半は、自分たちの報酬は多すぎる一方で医者や教師の報酬は少なすぎると認めている。だが彼らは、囚人が牢獄につながれているように仕事の檻に閉じ込められており、もはや慣れ親しんだ生活以外の生き方は想像すらできない。現在のシステムの中で最善を尽くそうとあがいている人々は、きっともっとよいシステムの中で生きることを望んでいることだろう。
以下メモ。
余暇の重要性が説かれている。東浩紀は「ゲンロン15」の論考をリゾートで書いたという。よく暮らすこと(≒倫理)と余暇をつなぐ意味では似ている気もするが、東浩紀がすごしたリゾートはスキデルスキーにとっては欲望の産物に見えそうなきもする。どうなのだろう。あと「暇」といえば国分功一郎か……。
リゾートやテーマパークやショッピングモールは確かに過剰に快適である。非現実的で幻想的である。しかしその幻想を嫌う人々というのは、なるほど政治的には正しく、矛盾や貧困や不正義には敏感なのかもしれないが、逆にそのぶん配慮の余力には恵まれている――つまり暇なのだなと、ぼくはそのとき冷淡に感じたのだった。
余暇の文化が発達した例として江戸期の日本が登場する(p.282)。制限された貿易とか奢侈禁止令とか、江戸時代じゃね?とは端々に思った。
自然との調和の例で庭が出てくる(p.239)。庭の植物は人工とも自然ともつかない意味で、たしかに変な存在ではある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
