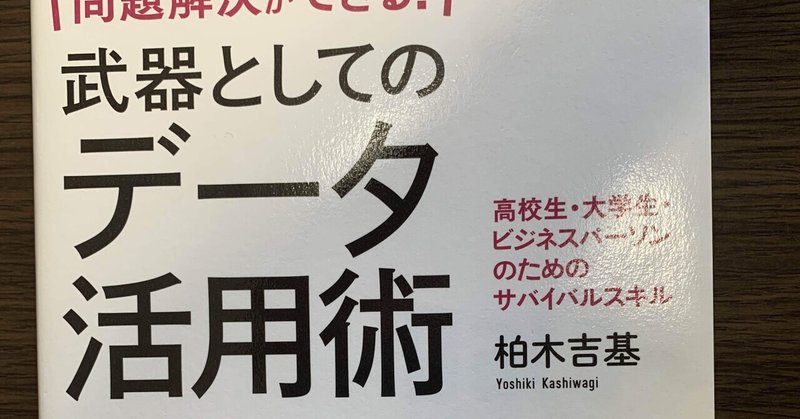
「武器としてのデータ活用術①」
「じゃあどうする?」
わたしたちは、何かが目の前で起こるとすぐにこう考えてしまいがちです。
でも、忙しい社会人が、目の前で起きた現象に片っ端から対応していてはキリがありません。
目の前で起きている現象から、本当に解決すべき問題を定義し、問題を起こしている要因を探り、要因に対する方策を立てることで、難しい手法や複雑なデータ加工をせずとも、より確実で効果のある対処をすることができ、データを活かせるようになるのです。
今回読んだのは「武器としてのデータ活用術」

“データ活用”とありますが、データを使わない人でも、問題解決についての基本的かつ重要な考え方を学べる1冊です。
詳しいデータ活用の順番は以下の通り。
(1)目的・問題を定義する
(2)指標を特定する
(3)現状を把握する
(4)評価をする
(5)要因を特定する
(6)方策を考える
それぞれについて説明していきます。
(1)目的・問題を定義する
データを使う際に一番やってはいけないことは、「とりあえずデータを見ることから始める」こと。分析することが目的なのではなく、課題解決であったり、現状把握であったり、分析で確かめたいことがあるから分析をする、ということですね。
そのために必要なことは何か。
まずは、問題は何かを具体的な言葉で明確にします。
「自店舗の売上について」というような、ぼんやりしたことを問題にすると、自店舗の売上を分析することが目的になってしまいませんか?
より具体的に、「売上前年比が、全国平均と比べて低いこと」とするとどうでしょう。
データを使う際に何と比べ、何の値を見ればいいのかがわかりますよね。
また、問題と要因を一緒にしないことも大事だそうです。
例えば、「ライバル店の売り上げが上がったことで、自店の売上が下がったこと」を問題にするとどうなるでしょう。
「ライバル店の売り上げが上がった」という、売上前年比が下がった要因候補が入ってしまっています。実際に要因がライバル店舗の売上増加にあるのかは、この時点ではまだわからないはずです。データ分析をする際には、極力自分の偏見はなくすよう努力し、フラットな立場で判断するようにしましょう。
(2)指標を特定する
問題が決まったら、その問題を表すのに適切なデータはどんなものなのかを考えます。
平均も、グラフ化も、一つの手法でしかなく、万能ではありません。自分が解決したい問題を表すのに最も適切なデータは何かを考えます。
(1)で、目的・問題をしっかり定義していれば、そこまで難しくはないはずです。
上記の例で考えると、「売上について」が問題の場合、どんなデータを用いればいいのかが定まりませんよね?
「売上前年比が全国平均に比べて低いこと」とすれば、自店と全国の売上前年比を一緒に表示して見せたらいいだけです。
データ分析を教えている著者の肌感覚では、「データをうまく使えない」という問題の2/3以上の原因は、「解くべき問題が明確でない」「定義した問題と使うデータが一致していない」の2つから起きているそうです。ということは、この2つを起こさないようにすれば、「データをうまく使えない」ということが2/3減るはず!
気を付けることは、「正解は無い」ということ。我々が何を問題としてとらえて、何を解決したいのかによってストーリーを作っていくことが大事なんだそうです。
続く
https://note.com/yyyyyyyoooooo/n/n22d1f72fa05b
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
