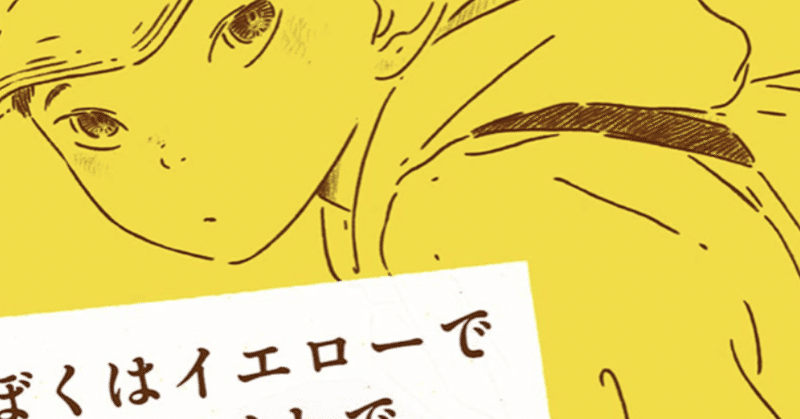
番外編13・ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
旦那さんと息子と英国のブライトンという街に住む筆者。貧困層が多くを占めるこの地域で、最底辺の中学校に進学した息子さんと筆者と、その周りに住む様々な人種、移民、性別の人たちとの話です。
読んでいると達観していて大胆なブレイディみかこさん(筆者)と、冷静で真摯な息子さんとのやりとりに考えさせられます。
子どもの貧困、人種差別、性の差別様々なことが身近にあり、その問題に息子さんは時に母の教えを聞き、時に友達や教師から学び立ち向かっていきます。
この息子さんが本当に素晴らしすぎて。
みんなこの子のようなら争いは無くなるのにと思ってしまいます。
最初は保育士だったみかこさんの感じた英国の保育観も書かれており、興味深かったです。
家庭環境によっては感情表現が乏しくなり(親の様子を見て学ばないため)そのため、相手の気持ちに気づかないから相手の「嫌だ」がわからない子がいる。そのため演劇的な要素を取り入れ(要は大袈裟にリアクションするってことでしょうか)
相手の気持ちに気付き、そして自分の気持ちも表現していくなどなるほどなーと思いました。
あとは息子さんがエンパシーについて考えるところ。
シンパシーは自分と似た境遇、感情なので気持ちがわかるのは当たり前ですが、エンパシーは、全く違う他者のことを理解しようと考えること。
息子さんは自分で誰かの靴を履いてみることと言っていました。なかなかできないことです。
また、貧困層の多く通う中学校の先生が、制服が買えない子のためにバザーをする話がありました。
その先生は、上の人たちは支給されたお金を子どもたちの勉学に使ってしまうと愚痴っていました。
そうじゃないと。まだ勉学するにまで達しない子がたくさんいるんだと。
家にご飯がなくてお腹が減っている子、制服が破れても着続けなければいけない子、、
まずその子たちの衣食住を補償してあげて、それから初めて勉強に目が向くのだと。
「ケーキの切れない非行少年たち」の著書である宮口幸治先生も同じようなことをおっしゃっていました。
家が落ち着く場所ではない子どもに勉強しなさいと言ってできるかと。(究極に曖昧ですが、、)
大人の都合で子どもたちが振り回され不幸になる世界、、耐えられないですね。
SDGSと言いますが、ぜひ具体的にどうするかを考えていきたいです。子どもたちのために。
課題自体は重いですが、文書が軽いので読みやすいです。
ぜひ読んでみてください!
#読書感想文 #おすすめ本#わたしの本棚
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
