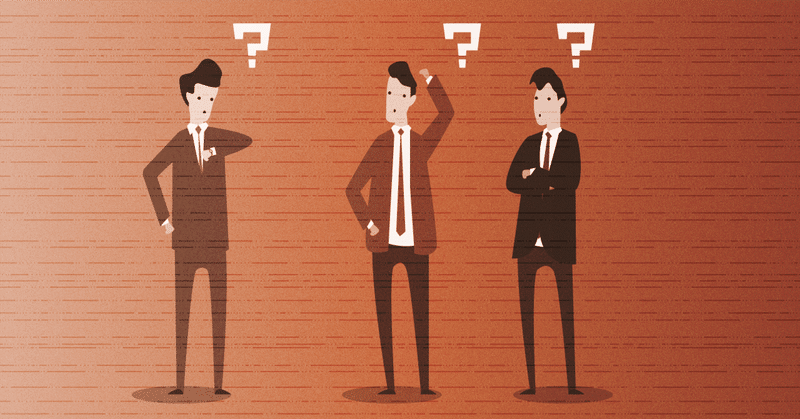
【今でしょ!note#59】 仕事では絶対パスと相対パスを意識しよう
いかがお過ごしでしょうか。林でございます。
今日は、「仕事では絶対パスと相対パスを意識しよう」というテーマで書きます。
絶対パス、相対パスとは?
そもそも「絶対パス」「相対パス」という言葉を聞いたことがない方もいるかもしれないので、はじめに簡単に説明しておきます。
Weblio辞書によると、以下のように定義されています。
絶対パス
コンピュータのファイルシステムにおける、ファイルの所在を表記する方法の1つ。階層構造を持つファイルシステムの最上位のディレクトリから当該ファイルのフォルダまでを列記する
相対パス
階層構造を持つファイルシステムの当該ファイルの位置を、起点となるディレクトリから相対的に記述する
ファイルシステムにおけるIT用語ではありますが、他のものに例えるならば、ある地点の住所をどのように表現するか、というところが違います。
東京タワーの場所を他人にどう説明するか、を例にとってみます。
絶対パスはある場所を最上位概念から説明するものなので、絶対パスの概念に従うならば、
「東京都港区芝公園四丁目2番8号」となります。
一方で、相対パスによる説明の場合は、「今いる場所からの相対表現」となるため、表現方法は無限にあります。
東京タワーの徒歩圏内の西側にいる人にとっては、「ここから歩いて5分東に行ったところ」となりますし、東京タワーから車で10分東にいる人にとっては、「ここから車で10分西に行ったところ」となります。
つまり、相対パスを使った表現の場合、その人がどこにいるのか、何が見えているのか、により、説明の仕方が全く異なるというわけです。
相対パスを使うとよくない例
ご察しの通り、相対パスは、物事を同じ地点から見ている人の間では、共通言語として成り立つため便利な言葉ですが、立場や関係性が異なる人の間でも必ずしも共通言語になり得るかというと、ならない場面の方が多いです。
例えば、会社の上司にあたる人に対して、「前回説明した件ですが〜」と持ち出したり、何かの資料で「前回と今回の比較」のようなものを作ったとしましょう。
毎日顔を合わせて一緒に仕事をしている人の間であれば、「前回」と言うのが「1ヶ月前の定例の時に報告を受けた件だな」とピンときてその後の会話が成り立ちますが、例えば相手の所掌が広く、月に1回しか会わない・話さないような人の場合、単純に「前回」と言われても、それがいつを指しているのか分かりません。
だから、「前回」のような相対表現を使うのではなく、「○月○日の定例の場で説明した〜」というような、できるだけ絶対的な表現で伝えることが必要になります。
仕事で使う略語の類も同じです。
例えば、「TAM」と言う言葉を使った時に、ある市場で獲得できる可能性のある最大の市場規模を示す"Total Available Market"を指すのか、ソフトウェア会社などの"Technical Account Manager"を指すのか、はたまた「株式会社TAM」を指すのか・・・と複数の解釈ができてしまいます。
だからこそ、特に日々頻繁に話す人以外と会話する時には、略語を補足したり、そもそも略語を使わないように配慮しないと伝わりません。
普段頻繁に使っている言葉だと、それが他の人にとって馴染みのない言葉であるという意識自体ができないことが多いです。
だからこそ、不用意に伝わらない言葉を使っていないか、自分自身で意識する癖をつけておくことが大事です。
メールの件名に「本日発生したトラブルについて」などと書くのもイケてないですね。
メールを作成した日であれば、メールを見ている人の間で同じ「本日」をイメージできますが、明日の「本日」は明日になってしまいます。
だからせめて「○月○日に発生したトラブルについて」くらいにしておくのが良いです。
メールを受け取った人にとっては、毎日「本日発生したトラブル」に関するメールが来るので、常に気が気でなくなってしまいます。
仕事ができる人は、必ず絶対パスを使える
これは私の経験則からの意見になりますが、「仕事ができると言われている人」は、必ず絶対パスと相対パスを使い分けて説明ができます。
逆に言うと、上記で示したような説明をしてしまう人や資料を見ると、私は「ああこの説明をしている人はあまりイケてないな」と感じてしまいます。
必要に応じて絶対パスが使える人というのは、「聞き手が分かる言葉で伝えようとする配慮ができて」、「自分がやっていることを客観的に認知している」ということです。
仕事において、「話す」「書く」「聞く」能力はほとんどの業界・業種で必要なベーススキルで、本質的には「何かの事象について、相手に伝わるように説明ができること」になりますから、普段の仕事の中で「相対パス表現になっていないか、絶対パスに変換する必要がないか」というのを意識できると良いかと思います。
数字が良いのは、究極の絶対表現だからです。売上規模が100万円と1億円と示すだけで、業界が異なれど規模の違いをこれだけの言葉で伝えることができます。
仕事のスタンスは自分視点で、スタイルは相手視点で
私は、仕事のスタンスとしては、「自分視点」を持つことが原点だと考えます。
つまり、「Aさんがこう言っているから」とか「こういう決まりになっているから」ではなく、「自分はこう考える」とか「自分はこうしたい」というように、「自分はどうする」という視点を持たないと楽しくないし、「その人の意見が聞きたい」と認知されないので、周囲からもあまり求められない人になってしまいます。
一方で、スタイルとしては、相手視点を持つことを意識します。
学生時代、90分の授業で大学教授の話を聞いていても、ほぼ独り言のようなトーンでひたすら話し続ける人がいましたが、ビジネスシーンでは完全にアウトです。
学生の時は、ともすると「伝わらないのは、聞き手側に責任がある」くらいの感覚が蔓延っていたのかもしれませんが、ビジネスにおいては「伝わらないのは、話して側に責任がある」と言っても過言ではありません。
なぜならば、本質的に仕事というのは、社会に対して何らかの価値を生むために、一人ではできないことを周囲の協力を得ながら実現することであり、周囲の協力を得るためには、自分の言葉で伝えて誰かに行動してもらうことが必要だからです。
「相手に伝わらない説明」というのは、誰かの行動に繋がりませんし、聞き手側に不要なストレスや誤解を与えてしまうことで、意思伝達の摩擦が大きくなりコストが大きくなります。
だからこそ、スタンスとしては「自分がどうしたいのか」を最も重要視するのが大事ですが、スタイルとしては「相手はどう解釈するのか」というように主語を相手に置いてコミュニケーションを設計することが重要です。
みなさんも、意識されてみると良いかもしれません。
誰かのお役に立てば幸いです。
それでは、今日もよい1日をお過ごしください。
フォローお願いします!
もし面白いと感じていただけましたら、ぜひサポートをお願いします!いただいたサポートで僕も違う記事をサポートして勉強して、より面白いコンテンツを作ってまいります!
