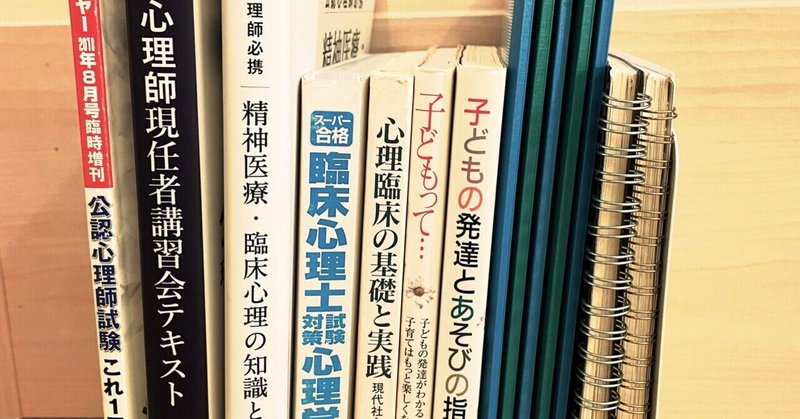
子育てしながらの資格試験。【臨床心理士】【公認心理師】になるまでの話。
こんにちは。yutoriです。
お読みいただき、ありがとうございます。
今回は【臨床心理士】と【公認心理師】の資格と受験についてお話したいと思います。
資格を取るまでの体験を記しますので、よろしければお付き合いください。
臨床心理士を目指したきっかけ
私は子どもの頃からずっと、「先生」になりたいと思っていました。
幼稚園の時は幼稚園の先生。
小学生の時は小学校の先生。
中学生の時は中学校の先生。
今思うと、すごい田舎で育ち、生活圏以外ではテレビの中にしか新しい刺激がなかったので、家族以外で憧れる身近な大人って、先生だけだったんですよね。
高校2年生の時、児童虐待のニュースを見て、「こういう子どもに関わりたい」と考えました。
それで、児童相談所で働きたい、子どもの心理を学びたい、臨床心理士になりたいと思って、心理学部への進学を目指したのです。
大学受験
志望した大学は、私が受験する前年からAO入試を取り入れていました。
自分としては、そんなよくわからない方法の受験なんてしない、と思っていたけれど、母から
「自己PRとかなら、向いてるんじゃないの?」
と言われ、「向いてるのか!」と、素直にやる気になってしまい、AO入試で受ける事に。
「AO」とは、Admissions Office(アドミッションズ・オフィス)の略で、各学校の入学選考事務局を指しますが、評価の基準となるのは学校または学部・学科が提示する「アドミッションポリシー(受け入れ方針)」に基づいた「期待する人物像」です。例えば「自立心を持ち、何事にも積極的に取り組む姿勢を持つ生徒」といった人物像に合致するかどうかがポイントです。
大学・短期大学においては、「AO入試」は令和3年4月入学者対象の試験から名称が「総合型選抜」へと変更され、選考では「学力の3要素」が評価されることとなります。
現在は、呼び名が変わり、学力の試験も必要になっています。
私の頃は、面接とプレゼンの試験がありました。プレゼンは、テーマに沿って情報収集をして、それを発表するという内容でした。
プレゼンなんて初めての経験でしたが、自分なりにまとめて用意してしていったつもりでした。
試験が始まると、私より先に発表した受験生が、私の発表しようとしている内容と丸かぶりの発表をしていました。同じ本を使って用意したんだなと、すぐに分かる発表…。
でも、準備したものしかできないので、予定通りに発表しました。発表中の記憶はありません。
面接では、「児童相談所で働くって、どういう道のりで進むか分かってるの?」と聞かれ、わからなかったので、「大学に入ってから勉強したいです」と答えました。
生意気な受験生だったかもしれないけれど、入学させてもらうら事ができました。
大学院受験
臨床心理士の資格を取るためには、基本的に日本臨床心理士資格認定協会が定める大学院(指定大学院)を修了しなくてはいけません。必要に応じて、修了後の実務経験も求められます。
〈主な受験資格〉
●指定大学院(1種・2種)を修了し、所定の条件を充足している者
●臨床心理士養成に関する専門職大学院を修了した者
●諸外国で指定大学院と同等以上の教育歴があり、修了後の日本国内における心理臨床経験2年以上を有する者
●医師免許取得者で、取得後、心理臨床経験2年以上を有する者 など
受験資格は上記のように様々ありますが、大学生が資格を取ろうとしたら、指定大学院を修了する事が一番の近道ですし、ほとんどの人がこのルートで受験していると思います。
ただ、心理学部の学生だからと言って、大学院進学を目指す人ばかりではありません。
私の学年は、学部生120人くらいのうち、大学院進学者は10人くらい。意外と少数ですよね。
私は通っていた大学の大学院も、指定を受けていたのですが、教育系の勉強をしたいと思い、別の大学院を目指しました。
ちなみに、指定大学院の受験は、心理学部の修了が絶対ではありません。学部関係なく受験できる場合が多いと思います。
ただし、受験では心理学の試験もあるので、それなりの勉強は必要です。私が受けた大学院は、その他に、英語の筆記試験、面接がありました。
大学4年になった頃から、大学院進学を目指す人達で勉強会を開き、教授から(講義とは別に)英語を教わり、対策をしました。
試験当日は、面接の順番待ちをしている時に、50代くらい(女性)の受験生から、いろいろな話を聞かされて大変だった記憶があります。なぜか、つかまってしまったんですよね。
それでも、合格させてもらえたので、彼女を恨まずに済みました。
臨床心理士試験
臨床心理士の仕事は次のような内容です。
臨床心理士に求められる専門行為
①種々の心理テスト等を用いての心理査定技法や面接査定に精通していること。
②一定の水準で臨床心理学的にかかわる面接援助技法を適用して、その的確な対応・処置能力を持っていること。
③地域の心の健康活動にかかわる人的援助システムのコーディネーティングやコンサルテーションにかかわる能力を保持していること。
④自らの援助技法や査定技法を含めた多様な心理臨床実践に関する研究・調査とその発表等についての資質の涵養が要請されること
このような仕事を、医療、教育、福祉、産業、司法などの様々な領域で行う事ができます。
臨床心理士試験は、大学院を修了してから受ける事になります。つまり、働きだしてからの受験するという事ですね。
試験は、
一次試験(10月)に筆記試験。
(多肢選択方式試験、論文記述試験)
二次試験(11月)に口述面接試験。
(一次試験を通過した人のみ)
というスケジュールです。
実は、私は資格試験が苦手で、臨床心理士も公認心理師も2回目の試験で合格しています。
臨床心理士、1回目の試験は「受からなくちゃ」という気持ちが強すぎて、変な間違いが多かったのだろうと思います。
あとは、勉強したつもりだったけど頭に入ってなかったんでしょうね。
大学院の同期がほとんど合格した事もあり、結構ショックでした。友達に付き合ってもらって、ドライブなどをして過ごしていました。
臨床心理士、2回目の試験の時は、りーさんがお腹に入っていました。妊娠中にも関わらず、「1人じゃない」と思うと、なんだか落ち着いて受験する事ができました。
合格後、臨床心理士登録の知らせ、資格証明のカードは4月1日付で届きます。
ちょうど、りーさんを出産したタイミングで届き、産後の病室でその封筒を開けた事を覚えています。
臨床心理士は、5年毎の資格更新、再認定が必要です。生涯学習、専門資質の維持向上が重要ですので、資格更新のためには規定以上の学会や研修への参加などが求められます。
妊娠・育児・介護など、家庭の事情で研修等への参加が難しい場合には、更新時期を延長する事もできます。でも、最近ではオンライン研修も増え、更新の際にも認められるようになったので、助かっています。
公認心理師試験
2015年9月9日に公認心理師法成立。
2017年9月15日に施行。
私が臨床心理士資格を取得してから4年後。ついに心理職の国家資格ができました。
臨床心理士は元々、心理職の国家資格を作る事を目的に活動していた資格です。でも、国家資格ができたからと言って、臨床心理士の資格が不要になるのではなく、専門性を持って活動していくという流れになっています。
ちなみに、公認心理師が「士」ではなく、「師」なのは、臨床心理士との区別するためのようです。ただ、いろいろなところで「公認心理士」という誤った書かれ方を見かけるので、気になってしまいます。
また、公認心理師ではないのに、「公認心理師」や「心理師」と曖昧な言い方をしてはいけないという決まりもありますので、資格はないけど心理関係の仕事をされる方は気をつけないといけません。
公認心理師の仕事は次のような内容です。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
ニ 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
臨床心理士との仕事内容での大きな違いは、四項目ですね。
臨床心理士は、知識の普及を図るための教育や情報提供はなく、自己研鑽や研究が重要とされています。
また、公認心理師は法律で決められていますので、反した場合には罰則があります。その点も大きな違いです。ですが、臨床心理士も倫理綱領が定められており、そこに反した場合には措置があります。重大な場合は資格登録の抹消などです。
どちらも責任の大きい資格という事ですね。
また、仕事の領域は臨床心理士と変わりません。ただし、資格更新がないという点では、違いがあります。
さて、2018年9月9日に第一回目の試験実施。
まず出願です。
公認心理師の受験資格は、大学と大学院で規定の科目を履修している事が重要です。他にも、規定の施設での実務経験などによって、受験資格が認められる事もあります。細かく区分されていますので、受験を考える方はよく確認されてください。
臨床心理士を持っているから優遇されるという事もありません。
私は運良く、必要な科目は全て履修してあったので、すぐに受験できました。
問題は、いかに勉強するか。
当時子ども達は、7歳、3歳、1歳。
仕事もしていたので勉強の時間がない。
ゆーさん(娘)、たっくん(息子)は寝つくのが下手だったので、寝かしつけに時間がかかり、その後の勉強も大してできませんでした。自分も寝てしまいますし。
ただ、
「ただ資格試験は苦手。受かるのは2回目」と自己理解していましたので、「勉強できた分と経験で受けよう」と割り切っていました。
そして、当然不合格。「1年かけて頑張ろう」と思い直します。
子育てしながらの受験。私のコツ。
さて、1年間、どう勉強するか。
要は、いかに効率良く勉強するか、ですね。
合格までにやった事、自分なりのコツをまとめてみました。
使う勉強道具を最低限にする。
ペンや付箋など、たくさん使おうとすると、それを選んだり、用意したりする事に時間がかかってしまいます。
私は、テキスト、ノート、ボールペン、蛍光ペンに絞って勉強し、そのテキストでは分からない事があったら、別の本やスマホを使って学びました。勉強の順番にこだわらない。
臨床心理士試験の時は、テキストを1から順にやる事にこだわってしまいました。でも、途中で止めることもできず、効率が悪かったなと思います。
自分の知識不足の内容、興味がある部分から勉強する事で、頭に入りやすかった気がします。1項目ずつ区切ってやる。
だらだら勉強せず、1つの項目をやったら「終わり」「できた」という区切りの気持ちを持って、達成感を持ちながらやると良いという思います。
勉強の目標も「○分」でなく、何の項目をやるかで考えるようにしていました。
この考え方だと、仕事の休憩中の20分でも取り組みやすくなります。次に勉強できる時に何をやるか決めてから終える。
勉強を終える時には、次に時間ができたら何をやるか決めておき、ノートにはその用語などを書いておきました。
そうすると、何となく気になって、その用語が頭に残りますし、次に勉強する時もやる事に迷わず済みます。子どもに応援してもらう。
ママが何を頑張っているか伝えておきます。勉強用ノートに何か書いてもらうのも励みになりますね。
私はたっくんがいつの間かノートに落書きをしていて、一瞬「やられた…」と思いましたが、それを見る度にほっこりできました。
私なりの工夫ですが、時間がない中でも、まあまあ勉強する事ができました。
でも、本当に勉強の時間がなくて、焦りやら悲しみやらで、泣きながら勉強した事もありました。
本当、2回目で受かって良かった。
受験番号が、りーさんの誕生日と同じだった時点で、「これ、受かったな」とポジティブに思えた事も良かったのだと思っています。
そんなこんなで、無事に資格を取得し、今に至ります。この資格を使って、私がやっている仕事が次の通り。
○ 不登校や発達障害など、学校生活が関係する
課題ついて、子ども・保護者・先生の相談を
受ける。
○子どもの発達検査・知能検査・性格検査を実施
して、結果を書面にしたり、説明したりする。
○学校関係や医療関係の仕事をしている方、それ
を目指す方への、カウンセリングの技術研修、
メンタルヘルス研修を行う。
その他、細々した経験はありますが、主としてはこんなところです。結構いろいろやっています。
写真は試験勉強で主に使った本とノート達。
捨てられず、ずっと取ってあります。
この記事を書くために、久々に見返して懐かしい気持ちになりました。気を引き締めて、今後も頑張ります。
長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
