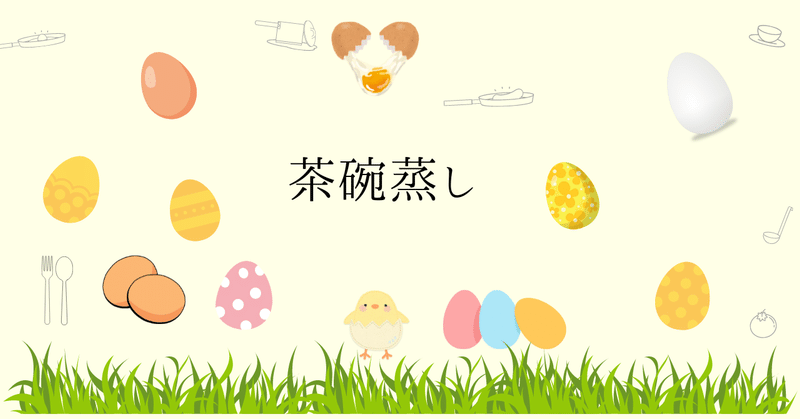
茶碗蒸し
今記事では茶碗蒸しの料理に纏わる私の経験を通して、茶碗蒸しの味や見た目、料理工程が人の自律神経系に及ぼす影響を見るとともに、予兆を感じた際の反射的な心理と余韻を感じている際の心理を見ていきます。
これにより、五感的な美味しさの前後にある予兆と余韻を意識でなぞることで自律神経系のバランスが整い、また皆様方それぞれの物語を通して食事の新しい楽しみ方を得られたならば幸いです。
駆け出しの持ち場である「はこ場」には茶碗蒸しの下準備をして煮方に回す仕事がありました。一日分の米を研ぎ、すし飯を炊いて、漬物を盛り付け、赤出汁の器に具材を入れると、次は茶碗蒸しの器に具材を入れ、玉子地を張り、煮方に回すのがはこ場の仕事の流れでした。この間に先輩から指示された雑用と仕入れ業者から入荷した食材の伝票を確認し各持ち場の保管場所に仕舞う仕事もあり、一秒も無駄にできません。
こういった仕事の流れを一年上の油場の先輩が教えてくれました。彼は板場の世界に人より遅れて入って来た私よりも3つも年下でした。地元の料亭で一年下働きをした後、一念発起して京都の老舗料亭に挑戦したようです。
京都の老舗での修業を想像していたその先輩は思いもよらず大阪店に配属されたことに随分と気を揉み、その後の私との2年弱の付き合いの内にその葛藤を数え切れないほど口にしました。加えて、彼の一つ上の立場である焼き場の先輩は大阪店で2年の経験があるのですが、これは彼の合算した経験年数と同じです。しかし、焼き場の先輩は専門学校を出ており、彼よりも一才年上なのです。彼はこのことにも大きな不満を持っていたようです。
しかし彼は持ち前の人懐っこさと粘り強さで、このギクシャクした関係に決定的な亀裂を生じさせることはありませんでした。常に格式に翻弄され、その鬱憤を彼の良心の許容する範囲で私に向けていたように思います。そして私も彼との付き合いの中で葛藤していきます。彼の感情は幼く、また私も現実を見るに幼かったのです。

茶碗蒸しの器に具材を入れ、先輩に報告すると、
「通路に卵があるし、それ割っといて」
と、先輩は油場からぞんざいに指示しました。すると、別の先輩が、
「お前、ちゃんと教えてやれよ。」
と飽きれた口調で注意します。他の先輩はある人は吹き出したり、ある人は注意を重ねます。きっと他の先輩たちは彼の性格を良く知っていたのでしょう。他の先輩たちの反応とそれまでの接触で、私もこれの意味することを察知して口元が思わず弛みそうになります。
油場の先輩は顔を赤らめています。首を窄め頬を持ち上げ苦笑いすると、ややいかり肩になりながら俯き、口先と眼つきを尖らせてはこ場に早足でやって来ました。そして
「卵はこっちにあるわ」
と、私に一瞥もくれず通路に行きます。私が後に続くと、彼は通路で保管していた卵を抱えます。私は咄嗟に、「僕が持ちます」と声を掛けますが、彼は面倒くさそうな表情をするだけで返事はしません。そして大量の卵を仰々しく持ち上げて運ぶと、はこ場のまな板の上にどさっと置きます。
そしてそれまでと打って変わってゆっくりとした動作になると、私の顔に一瞬目を留めました。右手で卵を一つ掴むと、左手で持ったお玉の裏にコツンと当てます。そして卵をお玉の上に持ってくると、指を器用に使い、ゆっくりと割って見せのです。
卵がストンとお玉の上に落ちました。人差し指を支点にして親指と中指で持ち上げられた殻と手が大空高く上昇するコンドルのようにポーズを決めています。
その姿勢は僅か2,3秒ほどだったでしょうか。彼のポーズと澄んだ瞳で新しい世界を見詰める卵を目にして、私は散瞳し、「おぉ」と内心感心しました。しかし決して声にはなりません。強い光を当てられ私の神経は既に大きな火傷を負っているのです。私はこれ以降も常にこの、大海原を泳ぐ鰹がキラキラと照り返す銀ピカとその身の燃ゆる赤に魅せられ、そして常に疲弊し逃走反応を取るのです。
隣で直角に並んでいた私が反射的に先輩の顔を見ると、片手割りを披露した先輩は上体をやや向う側に仰け反らせながら私の顔を見ました。その目は相変わらず細いもののどこか遠い目をして見えます。口元も相変わらず尖がったままです。そうして一呼吸置くと、引き締まった高い声音で、
「できるか?」
と問い掛けたのです。それはまるで子供に問い掛けるような口振りでした。
この一連の見事な無意識の演劇に私の視界はチカチカと点滅し揺さぶられました。心の内に漏れた吐息の余韻と薄らいでいく意識の先にこの出来事が大きく緩やかな円を描いて刻まれていくように感じられます。
私は胸を大きく開き呼吸すると、
「ありがとうございます。やってみます」
と張りのある声で応じます。そしていかにも苦戦している振りを装いながら、殻を不必要にクシャリとさせて片手割りをして見せました。
「おう。まぁ‥ まぁ、できるやん」
先輩は顔色を変えることなく、ぼそりと言い放ちます。そして全部割り、溶いたら、また声を掛けるよう指示して油場に戻りました。私の胸の内にぬるい風がざわざわと吹きます。
目を瞬いて気を取り直すと、私は100個ほどの卵を前にして、片手割りの連続と早く割る練習が100個の玉子でできることに意気が高揚し出しました。そして息を整え肩を回して体勢を作ると、一気に卵を割り始めます。
お玉の上に割られた卵に血や異物が無いことを確かめながら、手を素早く無駄なく動かしていきます。殻の割れ方の違いや手に付いた白身で指を滑らせ、途中何度もリズムを狂わせながら一気に割りました。
泡だて器を手にしてボールの中を見ると、沢山の卵が目玉のように見え、押し合いながらぷかぷかと浮かんでいます。それまでに見たこともない光景を前にして私の目には無意識に力が入ります。そのギョッとした感覚の余韻がギョッ、ギョッ、ギョッと段を付けて迫ってきます。視界の解像度の変化に眩暈を憶えるのです。
思わず息を止めていた私は呼吸すると、「ほぉー」と細く長い息を吐き出しました。そして再び息を整えると、勢い良く卵を溶き始めます。ところが、なんということでしょう。大きな波に視界が揺れるのです。
「おっ」
と思う間もなく、私の軽い体は右に左に傾いていきます。体勢を立て直し歯を食いしばり踏ん張ろうとも、またしても腰が浮かされるのです。そうして暫くの間、卵と格闘していると、後ろの位置にある八寸場の先輩が見かねて声を掛けてくれました。
「縦や。切るように上下に溶くんや」
八寸場の先輩は少しやって見せてくれました。
要領を得た私は脇を締め、両腕に力を込めて、ガシガシと勢いをぶつけます。腹でボールを抑え、一分、二分と溶き続け、「もう少し、もう少し」と踏ん張りながら、「もう大丈夫だろう」と思うところで力を抜きました。強々とした上半身に胸の中心から熱い風が吹いたかと思うと、首の後ろには冷たい旋毛風が駆け抜けます。
泡だて器でしっかりと溶けていることを確認すると、私は乱れた呼吸を抑え込みながら、
「もうくたばりやがった。ったく、この程度かよ」
と心の内で嘯き、「大した事ねぇなぁー」という素振りを装いながら振り返り、そっと額の汗をぬぐいます。そして油場に向けて颯爽とした声を掛けました。
油場の先輩は目を細めながら再びやって来ると、確認し、出汁を貰いに煮方に行きます。煮方の手前にある向板(造りを引く持ち場)の前で、「うしろ、通ります! 」とやや媚びた声を出すと、向板の先輩がさっと体を引き、人がひとり、やっと通れる細い通路ができました。そこを、大きな体を丸めて風のように通り抜けていきます。それまでに何度も似たような光景を目にしてきた私も声を掛けて後に続きます。
煮方の持ち場では職人がこちらに背を向けて二番出汁を漉していました。大きな寸銅鍋に二本の木の板を渡し、その上に分厚い大きな布を敷いた笊が載せられています。シンクには出汁をとったばかりの鍋に水が音を立てて勢い良く貯められていました。
二番出汁の隣には既に取り終えた一番出汁の寸胴鍋から勢い良く湯気が上がって芳醇な香りを漂わせています。大小の大阪鍋が四つのガス口に並び、鍋の周りから火を噴いているものもあります。よく見ると、五徳は今にも溶け出しそうな色をしており、鍋はコトコトと忙しない音を立て、甘辛い香りをきのこ雲のように拡げています。轟々と揺れ動く炎の中で、赤みがかったオレンジ色の五徳は玲瓏として艶めかしく力強い。その様はまるで火山の火口のようです。
近くの水槽からは滝のように水が零れ、音を立てて床に流れ落ちています。その水槽の上で冷まされている鍋はまだ湯気を上げたものもあれば、怒り狂ったようにくるくると回っているものもあります。
この光景にダクトの堅牢で底知れぬ騒音が、遠くの上空を飛ぶヘリコプターのように、痺れと緊張を胎動させていました。
私の目は焦点が定まりません。この僅かな時間に何を見るべきか戸惑ったのです。
「これやない。あっちのや」
「あっ。すいません!」
煮方の職人の湯気でむせった声に、油場の先輩が体をびくりとさせたのを見て、私の脇に冷や汗が流れます。先輩は水槽の脇にあった一回り小さな寸胴鍋から昨日の残りの出汁を貰うと、煮方の職人に向かい、
「お出汁、頂きました! ありがとうございます! 」
と、上滑りした声でお礼を言いました。すると、煮方の職人は出汁を漉しながら,
「おう!」
と威勢の良い返事を返します。振り向いたその顔はそれまでの体勢と取ったばかりの出汁の湯気で上気して、まるで赤鬼のようです。
はこ場に戻り、先輩は溶いた卵と出汁を合わせると、淡口醤油を何度かに分け入れ、その度に味見します。そして、
「このアタリを覚えとくんやで」
と言うと、合わせた玉子地の入ったお猪口を私に渡しました。
私はアタリとは何だろうと疑問を抱きながらも、「味見をするのだな」と思い、玉子地を味見します。
味付けの経験があまり無かった私は卵に出汁と淡口醤油を足すだけでこんなにも美味しくなるのかと感心しました。それは茶色い大地に草木が生えたような落ち着いたほのぼのとした感覚。そこに、真っ新な紙を前にして上手な絵の描き方を教わったような感覚が重なります。
続けて、先輩は玉子地に塩を少量入れます。そしてこう言いました。
「これで完成や。味を見てみ」
味見をして私ははっとしました。何故なら、大地に生えた草木が先程よりはっきりと見えるからです。光りが差して草木の輪郭が際立ったように見えます。
私がお礼を言い、感心していると、先輩はお玉の上に玉子地を入れたお猪口を載せます。その動きに私の目は吊られます。そして先輩は、「アタリを見て貰いに行くから」と言い、表情を引き締め再び煮方に行こうとしました。しかし、煮方の方を見て動きを止めると、「チッ」と舌打ちし、「あの人、気難しいからな」と呟きます。そして暫くしてから煮方に急ぎ足で向かいました。先輩は煮方の職人の前で姿勢を正し、職人の様子を伺います。それから僅か数秒の後、
「茶碗蒸しのアタリ、お願いします! 」
と頭を下げ、お猪口を載せたお玉を慇懃に差し出しました。作業の切りを見定めた見事なタイミングと上半身の傾斜、そして差し出した腕とお玉が折れ線グラフを進む矢印のように職人に向かっています。この光景に私の目は瞬時に散瞳し、心中溜息が漏れます。
そして、矢印はどっしりとした職人の見事な腹太鼓に響いて跳ね返りました。
「おう! 」
力強い声が軽快に響きます。先輩は目線を下げたまま微動だにしません。私は息を飲んで見守っています。職人はお玉の上に載せられたお猪口を手に取ると味見しました。そして間髪入れず、
「おぉっ」
と重みのある静かな唸り声を発すると、お猪口をお玉の上に返しました。
私は一連の光景を見ながら漸く、「アタリとは味付けのことなのか」と理解し、自分の間抜けさに呆れながらも、そんなことよりも、この仰々しさが意識の上では格好良く見え、しかし無意識では如何にも時代遅れにも見え、自分の頬が弛もうとする動きに堪えていました。
「良かったな。後輩出来て」
「あっ、はい! 」
職人の声は大きく、腹の底から大砲を打ったような張りがあります。表情はにこやかで親しみ深いのですが、その響きに私は瞬時に現実に引き戻されました。話しかけられた先輩は頭を下げたまま上目遣いをしています。そして、まだ何か話しかけられるのかとじっと様子を伺っています。職人は濾した分厚い布を鍋の中でじゃぶじゃぶ洗い出しました。そして水を替えながら、
「一年間、頑張ったもんな」
と労わりました。先輩は勢い良く頭を持ち上げ目を大きく見開くと、
「あっ、ありがとうございます」
とぎこちなく言いながら再び頭を下げて上目遣いをします。
がっちりとした体形ながらも背の低い職人に随分背の高い先輩が、じっと上目遣いをしている光景が私の目に焼き付きます。
伝え聞いた親分子分の強固で血の通った関係への憧れと、形だけが残った縦社会の歪さに憶える侮蔑の疑いが私の目に焦点を定まらせません。視界の対象である現実の、この光景に背景から憧憬が輪郭を帯びて重なろうと浮かび上がってきます。しかしそれはすれ違い、今度はヒリヒリと焼け付く未来が浮かび上がってきて現実と重なろうとするのです。この動きが何度繰り返されたでしょうか。私の胸中は刹那に虚ろになります。
頭を下げ、上目遣いをしていた先輩はもう話はないと判断すると、足早にはこ場に向かいました。その動きにはっとして私も目を白黒させながら後を追いました。私の頭には疑問が浮かびます。「どこで判断したのだろう? 」と。
指示を受けて、はこ場で玉子地を器に流し込んでいきます。その間、先程の光景が思い返されました。そうして私は早く一人前になりたいと逸る心を一瞬で凍らされる気付きを得たのです。
それまで、私は技術を身に付ければ一人前になれると思い込んでいました。故に、修業を始める前から包丁仕事の練習を重ねていました。既に桂剥きもできるし、魚もおろせます。後は料理を覚えるだけだと思っていたのです。ですので、如何に早く、持ち場を上がっていけるかだけに関心を向けていました。「ここにいる先輩は全員、10年で抜いてやる」とまで思っていました。もちろん、本気で出来るとは考えていませんが、取り合えず、「気合い」の上ではそう思い、またそう思わなければ、やっていけないだろうと思っていたのです。
しかし、私は「粘り」、つまり根性こそが重要なのだと気付いたのです。そしてその根性こそが先程の一連の儀式の繰り返しに耐えることなのだと。
「一年間、頑張ったもんな」
煮方の職人の声が私の頭の中に除夜の鐘のように響きます。
儀式を遂行する先輩を見て、私は彼を先輩として見る意識を保つよう心掛けていましたが、無意識に侮蔑していました。そして目標の上で追い越すことも想像していました。しかし、私がどのように技術を高めても先輩と私の間には技術では超えられない、決定的な溝があり、それが慣習を守るということなのだと理解したのです。そして彼は一年間それを実証し、私はそれを幾らも実証していないのです。
彼はその姿勢で私を諭し、いえ、この組織が彼を通して、秩序を守り、より強固にしていく姿勢を見せていたのです。私の気分は一気に憔悴しました。聳え立つ巨壁、茫々とした大河が目に浮かびます。
しかし私の修業は始まったばかりです。前に進まなくてはなりません。私は無意識に気分を入れ替えようとしました。
茶碗蒸しの地を張った器を煮方の冷蔵庫に入れに行きます。慣習に苛立ちながら、また逆に慣習を破ることを恐れながら、器を並べたお盆を何段も重ね、慎重に運びます。煮方の冷蔵庫を前にして、気合の入った透き通った声音で挨拶ができるだろうかと、心に芽生える反抗心に不安が頭に過ります。
冷蔵庫の扉を開けると冷気が漏れ出てきました。空いているスペースに何段にも分けて並べた茶碗蒸しをお盆ごと慎重に押し込みます。すると、顔と首筋に冷気が当たります。その時になって私ははっとしました。そして酸味の勝った料理を食べた時のように頭の中が透き通ったのです。
「茶碗蒸し、冷蔵庫に入れて置きます! 」
その声は隣の向板の先輩をびっくりさせるくらいのものでした。背中から、「おう! 」と職人の声が返ってきます。その声を聞いて私はほっと胸を撫で下ろしました。
冷蔵庫のガラス扉から見える整然と並び積まれた茶碗蒸しを、自分が用意したのだと思うと、モーターの振動でできた玉子地 の微細で動きの速い波紋が、出撃を待つ兵隊 の鼓動のリズムように思えてきて私の胸を 躍らせます。茶碗蒸しはこの後、職人の采配によって何段階かに分けられて蒸されるのです。私は味見を思い出して、きっとこの茶碗蒸しがお客さんを大地に繋がって確かに立っている、そういう安心感のある和んだ気持ちにさせるのだろうと誇らしい気持ちになりました。
そしてはこ場に戻りながら、それを最終的に確実なものにすることを想像させる職人の威勢と泰然とした佇まいを目に浮かべ、私は羨望を憶えたのです。
営業開始の直前に茶碗蒸しが出来上がります。それを貰い受け、今度は配膳場の蒸し器に移して保温します。出来上がったばかりの茶碗蒸しはアツアツです。それを素手で持って移していきます。

一枚のお盆に十数個並んだ茶碗蒸しから、湯気とともにふわりと顔を包む草木の清涼さと土の温かみを思わせる香気の安らぎ、色味と光沢を抑えた目に馴染む優しさ、移し入れる度にぷるぷると震える幼げな真新しさが感じられます。
自分の係わった料理の最終局面を前にして、私はまざまざと見詰め、心を和ませたものです。そして、
「この純真さこそが愛でたい」
と感じました。またこの感覚を得た時、如何に器が熱かろうと絶対に手放してはならないと感じながら、自分は絶対に手放さないだろうとも予感しました。そして手早く、しかし慎重に移したことを覚えています。
さて、皆さんは最近、茶碗蒸しを召し上がられたでしょうか?
日本人なら誰もが見慣れた料理です。食材は卵と出汁、そこにほんの僅かな味付けがあるばかりです。そして味は淡いのです。しかし、ほのぼのと眺め、香りを嗅ぎ、ゆっくりと味わい、余韻を楽しむならば、単純であるからこそ、分かり易い心理を得られ、そこからそれぞれの物語が始まるのではないかと思います。そしてそこで描かれる物語、つまり時と空間に、きっと心を満たされるのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
