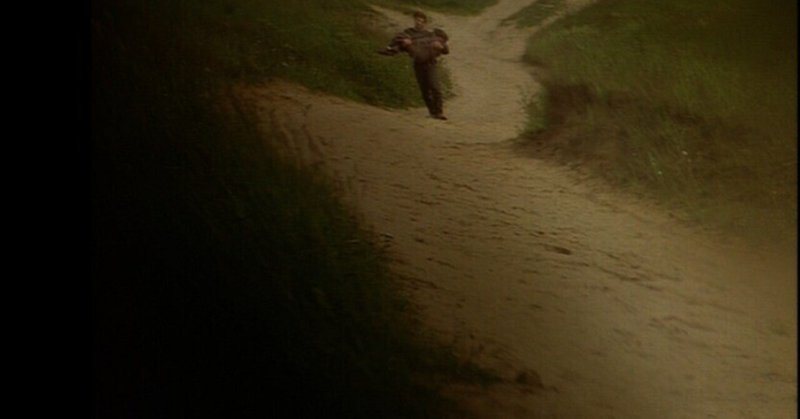
なぜ『そして人生はつづく』のか
『そして人生はつづく』というタイトルのイラン映画があるんだけど、これは1990年にイラン北西部で起きた大地震(ルードバール地震)を題材に撮った作品だ。
ルードバール地震では約4万人が死亡したといわれるが、被害者数を日本の震災と比較することはもちろん意味がない。亡くなった方一人一人に人生があり、生活があったのだから、被害者は「数」ではない。
とはいえ、それはイランも同じことなので、そうかんがてみると死者数4万人というのはとんでもない規模の大災害だったとわかるだろう。
そして、この映画の監督のアッバス・キアロスタミは、大地震の3年前にこの被災地で映画を撮っていた。『友だちのうちはどこ?』という作品で、世界で評判になった作品だ。
単に撮っていただけでなく、地元の人たちにおおぜい出演してもらっていた。そもそも主人公の男の子が地元の子だし、それ以外の登場人物もだいたい地元の人だったらしい。
笠智衆選手権
余談になるけど、キアロスタミ監督はそもそもたくさんのシロウトを使って映画を撮る人だった。こういうタイプの監督はほかにもいて、有名なところではフランスのロベール・ブレッソン監督とか、ロシアのアレクサンドル・ソクーロフ監督などがいる。
そしてぼくはかれらの作った映画が大好きである。ちなみにシロウトを大量に起用して映画を撮るとどういう雰囲気になるかというと、
笠智衆がウヨウヨしている
みたいな感じになると思ってもらえばいい。こう言うと笠さんに失礼かもしれないが、笠さんはもちろんプロなので一見ヘタウマのようで、実は深い味わいを追及していたのだろう。でもシロウトのぼくから見るとセリフを棒読みしているように見える。
そして、「男はつらいよ」シリーズには笠智衆が一人しか出てこないけど、キアロスタミ作品の場合は、出てくる人出てくる人みな笠智衆なので、
笠智衆選手権
のごとき様相を呈する。でも、ぼくはあの「セリフ棒読み大会」的な雰囲気が好きなのである。役者さんのことを「うまいな」とか「下手だな」などと思う必要がなくて、ひたすら映画の光と影に没頭できる。
生き残った人たち
今日のテーマは「死とその後」である。
だいぶ前からアイデアはまとまっており、いつか書こうと思っていたのだが、重いテーマなので後回しにしていた。でも、いずれだれもが向かい合うテーマなので、ぼくの知っていることを書いておきたい。なるべく軽い感じで行こうと思います。
さて、本題に戻ると、アッバス・キアロスタミ監督は、死者数約4万人、負傷者数約30万人というのルードバール地震の起こったその場所で、その3年前に、たくさんの「イラン北西部の笠智衆」を起用して映画を撮っていたわけだ。
そして、続編となった『そして人生はつづく』は、前作に出演してくれたおおぜいの笠智衆たちの安否を気遣い、監督自らがかれらに会いに被災地に出かけるという物語になった。
今ではAmazon Primeで簡単に見れるので、詳しくはそちらを見ていただくとして、生き残った人、亡くなった人いろいろなのだが、再会を果たせるのは、もちろん生き残った人々だけである。
そして、監督がやっとの思いで被災地についてみると、生き残った人々は、すでに前を向いて歩きだしていた。なぜなら、まだまだ「人生はつづく」のだから。死んだ人の時間は震災の日で止まっているが、生きのこった人々には明日がやってくるので、いつまでも死者の元にとどまっていることはできない。
そうやって、日一日と、生者と死者の距離は離れていくのが普通だ。
「決してあの人のことを忘れまい」と思っても明日はどんどんやってくるので、生者のきもちはすこしずつ死者から離れていく。
忘れていく自分を許せない
生者の心の中でやがて死者の存在が薄れていくのは、大昔から人類にとってごくあたりまえのことなんだけど、ぼくはこの当たり前のことを耐えがたいと感じる時期が長かった。
上に名前を挙げたロシアのソクーロフの作品に『マザー、サン』(1997)というのがあるのだが、ぼくの「ほぼベスト映画」といえる作品だ。
母は死の床についており、息子がそばで看病している。その最後の一日を静かに丁寧に追っていく映画で、ラストシーンで母のしわらけの手が大写しになる。そこに蝶々がとまるのだが、もはや母の手は動かない。するとむすこは体を低くかがめて、耳元でささやく。
母さん・・母さん
聞こえているでしょう。わかっているんだ。
あの約束の場所で待っていてください。
あわてないでぼくを待っていてください。
ぼくを待っていてください。
ここで映画は終わる。

マザー役もサン役も「モロ笠智衆」なのだが、そんなことは気にならず、くりかえし見ていた。しかし、そのうちに単に「イイ」などと思えない「ある恐れ」が生まれてきてしまったのだった。
ある恐れ
ふと「自分の人生が『マザー、サン』になってしまったらどうしよう」と思い始めたのである。当時2000年だったから、母はぴんぴんしていたのだが、今振り返ればこの恐れがぼくの人生最大の恐れになった。
そして、それから十数年後に、おそろしいことに本当にあの『マザー、サン』の日がやってきてしまったんですよね。人生ってこういうことがあるから、あなたも気を付けてください。どうやってきをつければいいのかわからないんだけど、こういう話がある。
なんかの自己啓発書で読んだような気がするんだけど、以下、うろ覚えだ。
あるアメリカの富豪だったか会社社長だったか忘れたけど、その人が生前口癖にしていたことがあって、それは
自分のどうしても避けたい死に方は2つある。1つが飛行機の墜落死で、もう1つが火事の焼死だ。
とよく言っていたそうなのだが、実はこの方は飛行機の中での火災事故で亡くなっているのである。
まあ、どう気をつければいいのかわからないけど、あまり悲惨なビジョンにはこだわらず、かるく受け流すほうがいいでしょう。
『マザー、サン』のその後
それで、おそろしいことに本当にあの『マザー、サン』の日がやってきてしまったのだが、その後のぼくの心境はけっして『そして人生はつづく』とはならず、ながいこと『マザー、サン』のままだった。当時はこう思っていた。
いまこんなに喪失感を抱いているのに、やがて
この人のいない世界がふつうの世界だ
と感じるような自分を許せない、と。『そして人生はつづく』を自分に許してはいけないと思ってしまったのだ。今日で時計の針を止めなければならないと。
『マザー、サン』は、時計の針を止めてしまったような動かないラストなんだけど、リアルでそうなろうとしてしまった。しかし、いくら時計の針を止めようとしても、人生はつづいていくので、結局、時間は動き出してしまう。
それで、そういう自分を今でも許せないかというと、そんなことなくて
意外に許せる
のである。なぜなら、『マザー、サン』だった日より、今のぼくは肉体が10年分老いているからだ。
あの44歳のときの自分はあの場所に置いてきたままで、今の自分は54歳の老いた肉体をもつ別な人間だと感じるので、許せるのである。
ひさしぶりに同級生に会うといきなり小学校時代の自分に戻るでしょう。あの感じの逆だと思ってもらえばいい。いいかえれば、小学校時代の同級生に会わない限り、あのときの自分にはもどれない。
同じように、もし母に再会することがあれば、あのときのが自分がはっきりとよみがえるような気がするのだが、母に再会しない限り、あのときの自分はあの場所で永遠に座っているままで、今の自分は別な自分だと感じる。
だから許せる。肉体が10年分年をとったことで不自由を感じることもややあるが、この点だけはありがたいことであり、そのおかげで人生はつづく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
