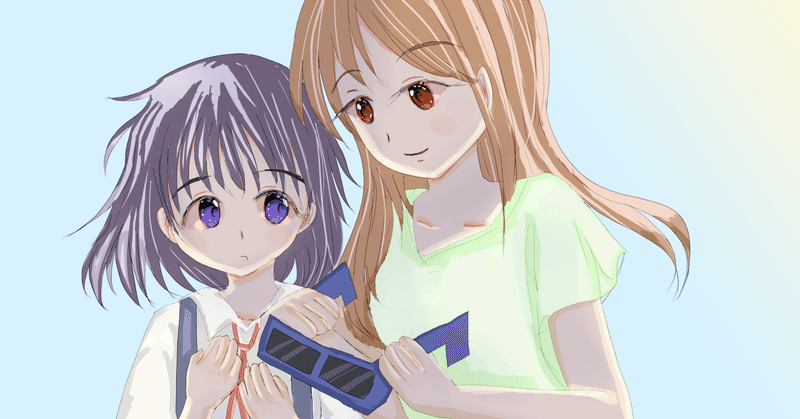
金の指環に魅せられて
初夏の太陽が、ぎらぎらと私の目を焼く。
「うわぁ……まぶしっ……」
目を細めるけど、やっぱりきついなぁ。でも、せっかく早起きして来たんだから、なんとか見えるといいんだけど。
そう思って薄目を開けて、顔を斜めにしながら、懸命に太陽を見ようとしていると、後ろからいきなり頭を小突かれた。
「こらっ、何やってるの!」
「うわあ、すいませんすいません。サボってごめんなさい」
先生かと思って振り向いたけれど、後ろにいたのは色白のお姉さんだった。スラッとした長い手足で、テレビに出てくるモデルさんみたいに綺麗だ。この辺ではあまり見たことのない服装をしている。
「学校サボっちゃったの? ……いや、そうじゃなくて、太陽を肉眼で見たらダメでしょ。学校で教わらなかった?」
「いやー、どうだろ、授業なんかろくに聞いてないし……」
「最悪の場合、失明することもあるんだよ! そんなことになったら困るでしょ」
「はーい。……でも、せっかくの金環日食だし、見てみたかったんだもん」
そう、今日は何百年に1度といわれる金環日食が見られるという、貴重な日だった。だから朝っぱらから部活もサボって、見晴らしのいい場所を探して歩き回って来たのだけど。
「そんなに見たかったのに、日食グラスも持ってこなかったの?」
呆れたというように、お姉さんは言う。
「だって、お小遣い少ないんだもん」
私が口を尖らせていると、お姉さんはカバンをごそごそやって、ただの紙でできたおもちゃみたいなメガネを取り出してくる。
「はい、これ、日食グラス。使っていいよ」
「いいの?」
「うん。……ほら、そろそろ始まっちゃうし。一つしかないから、交互に見よ」
お姉さんはそう言って、私の顔に無理やりメガネをかけてくる。
「あー、でも、私も最初の瞬間、見たいなあ。……貸して」
お姉さんはそう言うと、紙のメガネをぐーっと伸ばしてただの紙にしてしまう。それで、それを私の目のところに当てると、今度は自分の顔を思い切り近づけてくる。
「片目ずつ、見よ。絶対、もう一個の目、開けちゃだめだからね」
「は、はい」
よっぽど見たいのは、お姉さんのほうなんだなあ、と思いながら、仕方なくお姉さんと密着したまま、太陽を見つめる。すると、急に辺りが少しだけ、暗い雰囲気になってきた。迫ってきていた黒い影が中央に入る。
そこにあったのは、太陽が作り出したキラキラの指輪だった。
「綺麗……」
「綺麗だね」
朝とはいえ、初夏の気温では、ひととくっつきたくなんかないものだけど、この不思議な天体ショーの効果なのか、お姉さんにくっつかれるのは、不思議と嫌じゃなかった。お姉さんの身体からは、たぶん香水かなんかの、お花みたいな果物みたいないい香りがしていて、正直、いつまででもくっついていたいような心地よさだった。
だけど、まるで永遠みたいなその時間だって、いつかは終わりを迎える。輪が欠けて、太陽が半月みたいな形になり始めると、お姉さんは満足したように自分の顔を眼鏡から離した。
「金環日食って、どうしてああいう形になるんだろう」
「それはね……」
私がふと漏らした疑問に、お姉さんは親切に答えてくれる。
「なんで、そんなに詳しいの?」
「ああ、私これでも大学生だから。しかも専攻が天文学なんだ。宇宙のことを勉強してるんだよ」
「だからそんなに詳しいんだ。……私ももっと、宇宙について知りたいな」
「ふふ……宇宙、面白いよ。この本とかなら、中学生でもわかるんじゃないかな」
お姉さんはカバンからメモ帳を出して、本のタイトルを書いて私に渡してくれる。すごく綺麗な字だった。
「お姉さんは将来、なんになるの? 宇宙のことを勉強してどうするの?」
ふと気になって聞いてみる。
「内緒」
「えーっ」
教えてくれないんだ。つまんないの。そう思っていると、お姉さんはふふっと笑って答えてくれる。
「嘘。私は天文学の研究者になりたいんだ。でも、そんなに大したこと考えてるわけじゃないの。ただ、憧れの人に追いつきたいってだけで」
「そうなんだ」
なんとなくそれを聞くと、心の中にすーっと風が吹いたような気持ちになる。なぜだかわからないけど、名前も知らないこのお姉さんと、その憧れの人とのことが無性に気になって仕方なかった。
「お姉さんって、名前なんて言うの?」
「私は、葉月(はづき)だよ。あなたは?」
「私は風香(ふうか)。……ねえ、葉月さんって、何歳? どこに住んでるの?」」
気になってついつい、続け様に質問をしてしまう。でも葉月さんは嫌がることなく、その一つ一つに、丁寧に答えてくれた。
葉月さんは大学4年生で、22歳。普段は東京の大学に行っているんだけど、今はたまたま大学のひとたちと、札幌まで旅行に来ているところだったらしい。私がしつこく聞いたら、大学生活の話も教えてくれた。全然想像がつかない世界だったけど、なんだか楽しそうだということはわかった。
「そろそろ行かなきゃ。先生たちが待ってるから」
しばらく話したところで、葉月さんはそう言って、カバンを背負い直す。
「それ、あげる。もう、太陽を直に見たりしちゃだめだよ」
葉月さんはそう言って、私に日食グラスを渡してくる。そして、私の肩をポンっと叩く。
「勉強、がんばってね」
そう言うと、どこかへ走り去ってしまったのだった。
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
