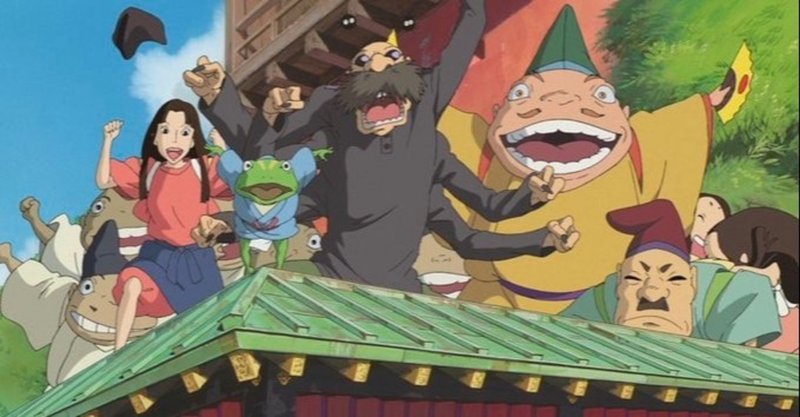
やる気スイッチはどこにある
もう財政課は査定しないって!
配分した枠の範囲であれば自分たちで自由に使い道を決めていいんだって!
#ジブリで学ぶ自治体財政
自治体の予算編成におけるコミュニケーション不足の弊害について,これまで様々な角度からアプローチしてきました。
繰り返しになりますが,財政課が全ての事業の内容,経費の内訳を精査する「一件査定」は,役所の中で膨大な事務作業を要する一方でその前提となる財政状況や優先順位の考え方,あるいは個々の事業の必要性や緊急性についての財政課と事業担当課の相互理解不足から双方にとって満足のいく結果が得られていないという問題があります。
この問題を解決し,予算編成作業の当事者はもとより,市民にとってよりよい予算を編成,執行できるのが「枠配分予算」だというのが私の主張です。
枠配分予算とは,あらかじめ予算編成の裁量権限を財政課から各部局に委ねる金額の範囲とその対象となる事業を定め,その範囲内での予算編成を任せてしまう「組織の自律経営」の手法です。
福岡市では,人件費,扶助費,公債費といった義務的経費や,各部局の裁量を超える需要額や重要な政策課題への対応など枠配分予算の仕組みになじまないものとしてあらかじめ個別に調整・査定することとしたものを除き,各局・区に配分された一般財源の範囲内で各部局において予算原案を作成しています。
各部局の作成した原案は財政課に提出された後は係数のチェックを行いますが,内容について口をはさむことは原則としてありません。
財政課では,枠配分予算の対象外とした義務的経費や個別に調整することとした事業についてのみ,その内容,金額の精査を行っています。
このことにより得られる最大のメリットは事業担当課のモチベーション向上。
限られた財源をいかに有効に活用して市民満足の維持向上につながる予算を組み,それを実行していくかを,現場のことがわかっていない他人から押し付けられるのではなく,現場にいる自分の頭で考え,自分の手を動かし,予算とは関係ないマンパワーやコミュニケーションスキルも投入して自らが直面する課題解決を図るためには,職員のやる気,組織のモチベーションを高め,不断の創意工夫と課題解決のための情熱を絶やさないことが必要になります。
お金のある時代ならお金で解決できたことも,今はお金以外の力で解決していかなければいけないのですから,そのやり方や到達すべき水準の設定,できないことをできないと市民に納得してもらうことの努力も含めて,現場の職員に委ねざるを得ませんし,現場のことを伝言ゲームで聞いているだけの財政課の査定は,俯瞰的に物事を見る力はあるものの,個別の問題解決には力を持ちません。
現場を熟知し,課題解決に最後まで責任をもって担当することができる各事業担当課を信じて,そのやり方を任せることで,現場職員が財政課の査定に従って仕事をするという「やらされ感」ではなく,自分たちで解決するというモチベーションにつながります。
職員のモチベーション向上は組織としての対応力,問題解決力の向上につながり,そのことがひいては市民が納得できる課題の解決,市民満足の維持向上につながると私は考えています。
もちろん,この効果がうまく発揮されるためにはそもそも厳しい財政状況であること,すなわち配分される財源には限りがあることを現場職員が自分事として理解することが前提にはなりますし,そのために財政状況や自治体として抱える課題解決の優先順位など全体を俯瞰する情報についての財政課と現場との共有と互いの役割分担についての意思疎通は十分行われなければいけないことは言うまでもありません。
また,各課,係単位での自律経営だけでは所掌範囲が狭くそれぞれで裁量を発揮することが難しいので,配分された財源を部や局の単位で互いに融通しあうことが必要です。
しかしこの場合であっても,財源配分を受けている部局の単位は普段から同じ政策分野の課題対応に当たっている仲間ですから,全く別のフロアで仕事をしている財政課に調整をお願いするまでもなく,部長や局長のリーダーシップのもとで相互の調整を行っていくことは財政課の査定を受けてそれに従うよりはたやすいし,納得感をもって受け入れることができるのではないでしょうか。
枠配分予算制度は現場の創意工夫を生みます。
例えば財政課から配分される財源以外の収入の確保,あるいは民間企業や各種団体等,他のセクターとの協働・分担による行政負担の軽減です。
また,予算計上に当たってその執行方法を見直せば,浮いた枠は財政課に分捕られることなくほかの事業に回せるわけですから,主体的,積極的に事務事業の見直し,効率化に向かうモチベーションも高まります。
財政課や行革担当課から何度指示されていても進まない事務事業の見直しが,生み出した財源を自分たちで使えるとなったとたんに一気に進むのは,単に自分たちに裁量が委ねられ,意欲が高まったことによるだけではありません。
既存事業の見直し(スクラップ)で得られた財源を活用して新たな事業を始める(ビルド)する「スクラップ&ビルド」では,既存事業の見直しが進まなければ新たな事業を始めることができませんが,その場合ネックになるのはなぜ既存事業の見直すのかという目的の希薄さゆえの改革モチベーションの低迷,「なんでうちがこの事業を見直さないといけないんだよ」という負の感情です。
しかし,新たな事業を始めるために既存事業を見直す「ビルド&スクラップ」であればどうでしょう。
新しいことをやりたいときにそこで得られる課題解決の効果と比較して優先順位の低いものを見直していくのであれば,事業の見直しは目の前にある政策課題の解決という目的を達成するため手法となり,見直しの大義が立つわけです。
同じ政策分野を所管する部局単位で枠を配分する理由はここにあります。
同じ政策分野の中での優先順位の最適化を,その政策分野の責任者である部長,局長が自分の責任において判断し,政策内での施策事業の重要性や求める成果に応じて柔軟に資源配分できることが,政策を所管する事業担当課にとっても,政策の効果を享受する市民にとっても幸せなことであり,しかも限られた財源が最も有効に活用されることで,資源配分全体を所管する財政課もHAPPYになれる「三方よし」の方策なのです。
加えていえば,自治体職員にとっては「やらされ感」ではなく意欲的に働くことができるだけでなく,前回お示ししたような財政課と事業担当課の資料のやりとりやヒアリングを必要最小限に省くことによる時間外労働の縮減,働き方改革の実現も社会的に大きな意義があると思っています(^_-)-☆
★「自治体の“台所”事情 ~財政が厳しい”ってどういうこと?」をより多くの人に届け隊
https://www.facebook.com/groups/299484670905327/
グループへの参加希望はメッセージを添えてください(^_-)-☆
★日々の雑事はこちらに投稿していますので,ご興味のある方はどうぞ。
https://www.facebook.com/hiroshi.imamura.50/
フォロー自由。友達申請はメッセージを添えてください(^_-)-☆
★「自治体の“台所”事情“財政が厳しい”ってどういうこと?」について
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9885
2008年12月に本を出版しました。ご興味のある方はどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
