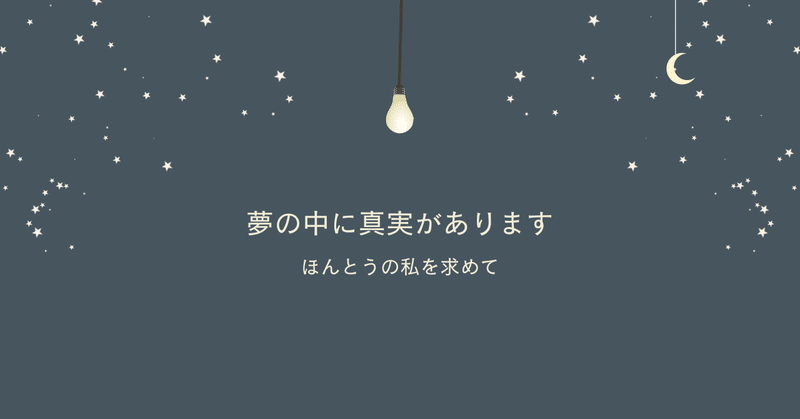
ほんとうの私なんて知らない③:遠藤周作
それまで噂として知っていたようなことを、まるで知らなかった振りで誰かがそれを表に出したことによって一緒になって騒ぐのは正しいことなのでしょうか。ネットで匿名だから、直接言ったことに比べて言われた人はダメージを負わないと考えている人もいそうです。
しかし、文字として残る上、知り合いからの親切心とは思えないわけですから、そのご注進のほとんどが悪意に思えてしまうでしょう。
たとえば、芸能人の不倫。
たとえば、政治家の汚職。
そんな噂は既にあったのに、ある日を境に爆発したように世論を巻き起こすのはメディアの手腕なのでしょうか。あるいは、本当に些細なきっかけなのか。
私は今日の噂の高ぶりは、誰かの思惑が働いているような気がしてなりません。
果たして、私の夢はどんな心象風景を表しているのでしょうか。
他人に対して疑心を持つ私の心は闇深いということでしょうか。
「ほんとうの私を求めて」遠藤周作
美しい表紙です。まるでそこに遠藤周作さんが座っていたようです。
この本について感想を書くと長くなりそうなので、何回かに分けることにしました。今回で3回目です。
遠藤周作さんの人生における問いについて、私はこう思う、実こうだこうだと自問自答して、時に反論しながら読み進めるような内省的な本でした。
エッセイで章と小話に分かれているので、ここについてはこう思うという形で書けばいいかなと考えています。
「私」とは何か:もう一人の私の発見
もう一つの考え方 49頁~
ーこの小説のテーマはもっと複雑ですが、このジョセフという青年のように慾望を「悪いもの」とみて心の底に抑圧すれば抑圧するほど実はそれが彼の最大の関心事となって頭にこびりつくーといった例はこの年頃の男にはよくあるのです。彼は抑えつけるだけで、発散する出口のことを考慮しなかったからです。
ーしかし一寸、頭をひねってみますと、もの事は二分法で割りきれるほど単純ではありません。皆さんは大美人ではないが、といってそれほどブスでもない。まったく幸福とはいえぬが、しかしそれほど不幸ではない三つ目の状態だってあります。悦びと悲しみとの中間の感情だって存在する筈です。人生や人間は二分法で割りきれず、その中間か、もしくは対立した二つのものを併合している状態だってあるのです。だから、これを三分法と言ってよいでしょう。
ー我々はこの社会で他の人たちと共同生活するためには、いろいろな慾望や感情をモイラの主人公のように悪いことだと決めつけてはいけません。また抑えつけていきることが正しいことだと思うのも間違っています。
ここで遠藤周作さんが紹介しているのは、ジュリアン・グリーンの「モイラ」という作品です。まだ読んだことがない作品なので、内容について言及するのは避けたいのですが、上記のような引用をしたために何も説明しないわけにはいきません。
前回か前々回にこの「ほんとうの私を求めて」の感想を書く際に、戦中戦後は同性愛を芸術に落とし込めるような風潮があったと書いた気がします。もしかしたら、北杜夫さんの「見知らぬ国へ」というエッセイの感想でそう書いたかもしれません。
平たくいえば、これもそのような作品で、異性愛に対する潔癖な嫌悪がある主人公が出てくるようです。彼は異性との肉欲を軽蔑するあまり、自分が最も軽蔑するような女性と関係を持ったことに怒りを感じて、女性を殺害してしまいます。肉欲の関心の面では異性だろうが、同性だろうが同じだと思うのですが、愛と肉欲とを分けて考える試みがその頃流行っていたのかもしれません。この話が刊行されたのは、1950年。作者はちょうど50歳で早くも老境に達しようとしていたのかもしれません。
しかし、物事は善か悪かでは割りきれません。これは遠藤周作さんが説明されるところによれば大乗仏教の考えなのだそうです。しかし、キリスト教信者の遠藤周作さんがおっしゃるようにそれが真実なのです。愛に肉欲が伴わない人もいるかもしれませんが、そこからはじまる愛もあるでしょう。愛に肉欲が伴わない人がいるからといって、それが善ということはありえません。種の存続ができなくなります。
また、戦争するA国とB国があって、どちらか一方がより善だといえることは少ないように思います。
ある宗教国のトップが「我々の正義を全うする」ということをおっしゃっているそうですが、結果としては終末期のような世界ができつつあります。
正義が人を殺す、殺人が善行として正当化されるなどということはあってはならないでしょう。
かといって、誰も死人も出さずにもの事を解決するのも難しいので、世界は割りきれないのです。
信念の魔術 56頁~
ーいずれにしろ、前生からの生き方は今生にも多大の影響を与えていると仏教は考えます。これを業というのですが、この前生からの業の影響力がいまだに現世のあなたのアラヤ識のなかで活動しているのだそうです。
ーたとえば、あなたが嫉妬ぶかい行為をしたとします。その行為はあなたの心にある我欲と執着が生じたものなのですが、アラヤ識にはそうした我欲と執着を生む可能性のある種子が活動しているのです。もっとも種子は全て悪い結果や好意を作り出すとは限らず、無量種子といって悪い行為を生む種子を浄化してくれるものもあるのですから、我々の行為は善かれ悪しかれ、その種子の結果だと言えるでしょう。
ー信念は心の底の無意識にしみこみ、それぞれが力となって自分の夢を実現させる方向にもっていくことを、私はその時はじめて知ったのでした。
アラヤ識とは心のなかで(いろいろなものが)溜まっている場所という大乗仏教の言葉です。心のなかでいろいろなものが溜まっている無意識のことを仏教ではアラヤ識というわけです。
無意識のなかにはいろんなものがため込まれていると考えると、無意識の行為にこそ、その人の素が現れるということなのでしょう。日本人としてはとても腑に落ちる考えです。
とはいえ、「念じれば通じる」。私は、そのことを信じることができません。遠藤周作さんはフランス留学を念願してそれが叶ったそうですが、私は自分が何をやりたいのかもよく分からないのです。
人間としては煩悩とか慾望を常に抱いていることが正常なのかもしれないですが、これをしたいとか、あれはしたくないとか、常に決めて割り切ることができません。
その時々の出会いとか気分によって私のやりたいことは変わっていくわけですが、大望など微塵もなく、自分がだれそれの生まれ変わりで業を背負っていると感じることもありません。
死んだら、終わり。だから、なるべく死なないように生きるだけです。
心に美しき種を抱く 62頁~
ー自信のない時、女は美しくなくなる。
ー無意識の力は我々が考えている以上に強力で大きいのですが、意識の方にだけ重点をかける近代の西欧合理主義では、長い間、無意識の力などあまり問題にしませんでした。それがやっと西洋で陽の目を見たのは、深層心理学の探求が人間の内部にメスを入れたためですが、東洋の方では西洋とは逆に意識よりも無意識の方を重視し続けてきたのです。
ーそして合理主義にゆきづまった西洋の思想家たちが、今、無意識をあらためて考え直し、東洋的な思考方法に接近してきた事実をお憶えになっておいてよいでしょう。
美しいとか美しくないとかいう基準を持つことは、果たして当たり前なのでしょうか。「あなたは、美しい」と声をかけ続けて、垢抜けない人もやがて美しくなったというようなことがこの本でに書いてあります。
しかし、大体垢抜けるってどういうことなんでしょうか。
善いことだから実践するという基準でみれば、「美」というものは曖昧です。健康で長生きできるといわれたら、自分のために実践してみようと思います。しかし、自分が美しいかどうかは他人の価値判断にゆだねるところが大きいので、美しいことが良いことだといわれても何だかピンときません。
本の中で遠藤周作さんもあまりに美しい人の人生は多難だと書かれています。
私もそうだと思います。
一方で、誰が見ても美しい容姿という人であれば、そこそこ磨けばそこそこの美貌が手に入って、人生が開けるのでしょうか。
私は、化粧が好きではありません。特にファンデーションが苦手です。何回か肌がかぶれたことがあって、かぶれない化粧品を使っても苦手意識を持つようになりました。今はかぶれることより、匂いの好き嫌いがあり、面倒くさいから化粧などほとんどしなくなりました。マスク生活は、その点非常に快適です。顔によく分からない湿疹ができても、隠していられるからです。
果たして、私はマスクで素を隠しているのでしょうか。マスクを好む私も私らしい私という気がします。
よろしければサポートお願いします。いただいたものはクリエーター活動の費用にさせていただきます。
