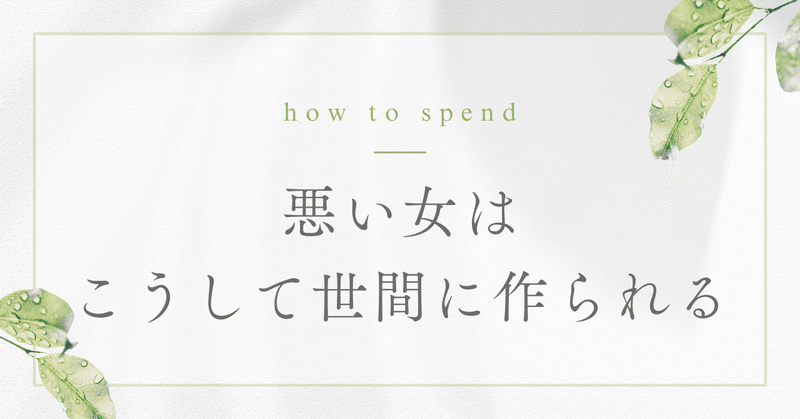
ほんとうの私を知らない④:遠藤周作
私は多少子供っぽい話が好きなので、いまだに少女小説や少女漫画のようなものを読みます。
しかし、もはや雑誌連載ものにはとんと縁がなく、成人してしばらくして”なろう系”小説にハマっていた時期がありました。
いわゆるアマチュアの作家の方が自分の作品を掲載できる投稿サイトに「小説家になろう」というものがあり、そこで閲覧の伸びた作品が文庫本で出版されたり、漫画になったり、実写化したりということが現在でも多くなっています。
小説の投稿サイトは「小説家になろう」を皮切りにその後も増えた印象です。私は30代に入り、まったくお金を払わないのも悪いので、課金もできるような投稿サイトを見る分別がつきました。しかし、そうするとすでに悪化していた視力の低下も手伝いのべつ幕無しの乱読からは遠ざかっていきました。
なろう系小説は当初は特に分野も限ったものではありませんでしたが、ファンタジーものの閲覧数の伸びが良かったのか、10代から20代前半向けの小説がいわゆる”なろう系”と呼ばれるようになったようです。私の認識違いかもしれませんが、大体そんなイメージです。
一時期から今に至るまで特に流行ったのがファンタジーものの『転生系』です。過ちの多かった人生を巻き戻して、幸せを手に入れるというお話です。そんな中でも、さらに細分化されたいちジャンルに”悪女転生”がありました。小説の世界の悪女に憑依して原作の内容を知っている現代人が人生をやり直してあげようとするものです。私も好きでよく読んでいるのですが、結婚や離婚や子育てや領地改革や戦争などおよそ20代前半までには学びえないような内容が多くなっていることに途中から気づいていました。
いわばファンタジーのような"ノリ”で書かれた人生読本とでもいいましょうか。それほど作者が子供向けに書いているという意図も見えないのですね。
そういった政治的な分野に関わるのなら、正統派ヒロインでもよさそうなものなのですが、なぜ作者も読者も悪女にこだわるのでしょうか。
その深層心理の謎がひとつ、この遠藤周作さんの本で解けたような気がします。
要するに”悪女”というものは現代に至るまで書き古されていて、ファンタジーの世界に落とさないと新鮮味に欠けるのです。一方で、小説に悪女がつきもののような外せない読者と作者の期待というものがあるのでしょう。
果たして、この夢は私のどんな心象風景を表しているのでしょうか。
他人に対して疑心を持つ私の心は闇深いということでしょうか。
「ほんとうの私を求めて」遠藤周作
美しい表紙です。まるでいままでそこに遠藤周作さんが座っていたようです。
この本について感想を書くと長くなりそうなので、何回かに分けることにしました。
遠藤周作さんの人生における問いについて、私はこう思う、実こうだこうだと自問自答して、時に反論しながら読み進めるような内省的な本でした。
エッセイで章と小話に分かれているので、ここについてはこう思うという形で書けばいいかなと考えています。
「女」とは何か:もっと豊かに もっと自由に
悪女と思われる方は手紙をください 70頁~
ーそして私はよく世間では女は魔性とか、悪女は怖ろしいとかいうけれど、厳密な意味での悪い女などはこの世には存在しないのではないかと思い込むようになりました。
というのは私の知る限り、よく悪女というのはたかだか二つのパターンにすぎぬからです。
㈠ひとつは男への執着、恋情、愛情のために罪を犯してしまうー。(中略)女の犯罪の80パーセントは男への執着から行われるとある弁護士に聞いたことがあります。とするともし男が彼女を幸せにしていたなら、その女の生涯は狂わなかっただろうということです。
悪女は多くの場合、男のために尽くした女とも言えます。尽くした結果が彼女を悪女にしたのです。
㈡悪女は男次第で善女にもなりえるのであるー。(中略)愛慾の世界では相手への執着がより強いほうが弱者になるのであって、多くの悪女は男の心をつなぎとめたい一心に罪を働いてしまうのです。だから彼女たちは罪を犯しても決して悪女ではありません。(中略)男にとって女性がこわいのは、彼が彼女をひどい目にあわせた時の仕返しでしょう。
やぶれかぶれになると、女は男が一寸、考えられないほどの無茶苦茶をやります。(中略)女は男にくらべて、はるかに無道徳である。
引用が長くなってしまいましたが、現代の”悪女転生小説”のブームを見通しておられたのかという正確さで、世の中の考える【悪女像】というものを解説しておられます。これを書かれたのは30年以上前ですので、恐るべき作者の観察眼とみるべきですが、実際は人間の心理と日本の社会情勢がこの40年50年と変化に乏しいせいなのでしょう。
実際に最近の”悪女小説”というものは、王子様の婚約者となった彼女が尽くした王子に捨てられそうになって嫉妬に狂って破滅を迎えるというものが非常に多いのです。そして、たとえ嫉妬を覚えていたとしてもそれほど倫理に外れた行為をしていないと思える彼女を”悪女”たらしめるのは、悪女と対極にある”ヒロイン”や”聖女”の存在です。悪女転生系小説では主人公は悪女その人なのですが、過去の悪行でさえ王子が悪いと思えるものがほとんどで、真に悪女と思えるようなものは皆無です。もしかしたら、官能小説のたぐいになれば”やぶれかぶれの悪女”もどきが主人公であったりするかもしれませんが、それはただの”男に翻弄される哀れな女”でしかないでしょう。
ファンタジー小説を書いている作家こそが自分の人生を小説の世界で生きなおそうとする”マジメな女”であるために、遠藤周作さんがここに書かれているような人生読本が量産される社会になっているのではないでしょうか。
簿記の知識や行政改革、薬草の知識などもっと広く自分を社会に役立てたいという願望が現れているのかもしれません。
人生を生きなおして最初から悪女が悪女でなかった場合、それは善女になったということです。そして、代わりに悪女になるのが”聖女”たる悪女がヒロインと思い込んでいる女性です。大体王子様がろくでもないのですから、悪い男性に選ばれた”聖女”が悪女であって当然というわけです。そしてその聖女の皮をかぶった悪女は王子など本当に愛しておらず、より悪女に近い姿をしているわけです。
遠藤周作さんや世間の小説のオチを考えれば、愛によって罪を犯す人間は”悪女”などではないのですから、愛を知らない聖女はより”悪”ではなく”女”ですらないということでしょうか。つまり、小説でいうなら淑女ではないのです。
そして、つまり現実にも犯罪に手を染める女性の80パーセントが男性に人生を狂わされた哀れな存在ということになります。
女は心の世界に生きる 76頁~
ー戦争中には戦争社会を守る約束ごとーつまりあの時代の道徳がありました。あの時代の道徳では敵ならば人を殺しても善かったわけです。しかし戦後社会ではそれが一転してすべての殺人はいけないわけです。道徳なんてそのようなものです。しかし倫理のほうは道徳とちがって、その時代時代の社会に左右されません。
私が女が無道徳だといったのは本当は女の人は社会の約束ごとなんか信じていないからなのです。あなたたちも胸に手をあてて考えてごらんなさい。あなたたちは男ほど社会の約束ごとに眼の色を変えはしないでしょう。
女にとって生きる動員になっているのは心のなかにある無意識世界なのです。
この章では年上と結婚し、年下の若い男性を次々と乗り換える女性の話が出てきます。その話に手を出すと全文書き写すことになってしまうので割愛します。自らの不倫に悩む女性の方はご一読されてもよいかもしれません。端的に言えば、その女性は年上の男性は裏切るものと思いながら年上男性に惹かれ、一方で裏切らぬ男がほしいという思いからマジメな年下男性を常にそばに置かねば気が済まないのでした。
私がこの章を読んで気づいたのは、女らしい人は倫理道徳の守られた社会の実現を願っているわけではないということです。不倫した女性議員をことさらに責めるのは、遠藤周作さんの書かれている通りそういうコメントをネットに残す女性に不倫願望が強いのかもしれません。
一方で、イスラエルがガザで行っている虐殺は道徳的で正義だ(正義だといえるのは道徳観念からくる言葉でしょう)と執拗にネットにコメントしながら、日本で起こるテロはいかなるものでも不正義だと言い切ってしまえる男性は自分の中の道徳観念がしっかりしているのかもしれません。
しかし、遠藤周作さんの言葉を借りるならば、道徳観念というのは社会情勢によっていかようにも都合よく使われてしまうものなのです。
もっと普遍的なもの、たとえば愛する人を傷つけないとか、愛し合っていたら裏切ってはいけないとか、一見すると不確かそうで大昔から変わらず言われてきたようなことを大切にするのが、”女らしい人”なのかもしれません。結婚という約束事が大事なのではないのです。愛しているなら、愛しているほうに心を傾けるべきで、説明のつかない不道徳、つまり倫理を踏み越えてはいけないということでしょう。
そんなこと言っても、不倫は男性がしても女性がしても倫理違反には違いありません。
女の不思議 83頁~
ーそういう女の部分、魔性の部分は、末の息子のメダカを見ている彼女の心から永久に消え去ったのでしょうか。
消え去るはずがない。それはいまは一時的に鎮火している筈だ。しかしそれはまた、いつ炎となって燃えるかもしれない。そんなことは彼女にはまだわからない。
新聞や婦人雑誌の投稿欄にのった中年女性のしみじみとした文章には、ほのぼのとした暖かさがありますが、と同時に今言ったような薄気味悪さもかくれているのです。
家庭の倖せ、母の悦びーそれだけがその人にとって本当にすべてか(すべてなら、こっちも気が楽なのですが・・・・・)、彼女はその倖せや悦びがあたかも絶対的でいつまでも続くような書き方をしているけれど、それは薄氷のようなもろさがあるのではないか。
そして小説家の私はこの書き手である母親の過去をあれこれと想像してしまう。
彼女にも女としてのさまざまな経験があったにちがいない。子供たちのお父さんとなった男性と家庭をもつまで、別の男性に傷つけられたり、泣いたり、相手を傷つけたり、もっと烈しい愛慾の炎に身をこがしたりしたでしょう。しかし、そういう過去の匂いはこの随筆のどこにもない。
ー作家といえど男性である以上、いくら客観的に女をみようとしても「こう、あってほしい」女性のイメージはその作品に織りこまれてしまいます。彼の無意識のアニマがひそかに浸透してしまいます。
だから私は「女を書いてみごとだ」といわれる作品は眉唾といつも警戒してしまいます。たとえ、それが女性作家のものであれ、男性文学から影響をうけている限りは、やはり、完全に女を書いているとは言えないでしょう。
「女は真理を欲しない。女にとって真理などなんであろう。女にとって真理ほど疎遠で憎ったらしいものは何もないー女の最大の技巧は嘘をつくことであり、女の最大の関心事は見せかけと美しさである」
(『善悪の彼岸』ニーチェより)
このニーチェの言葉を読めば、女性はすべからく腹を立てるだろうが全否定もできないだろうと、この章で遠藤周作さんは述べられています。
私はそもそも心理という言葉の意味が分からなかったので、ネットで検索してしまいました。
真理:確実な根拠によって本当であると認められたこと。ありのまま誤りなく認識されたことのあり方。真実。
どうでしょうか。確実な根拠があって本当であると認められていることなんて世の中には少ないので、男の人でもそれほど真理を追い求めない人も多いのではないかと私は思います。それこそ遠藤周作さんが述べられているようにニーチェも作家だから、真理の重要性を認識しておられただけではないでしょうか。ひとが確実な真理に基づいて行動するなら、現代社会ではもはや宗教など求めないでしょう。宗教に真実があるというのならば、真理というのはむしろ嘘であると言いたくなります。
前回までの話に、ひとがつける仮面のことがありました。
母という仮面、妻という仮面。しかし、世の中は個人主義に移り変わり、以前とはつける仮面の種類も違ってきています。
男も女も愛慾にとらわれない人が少数ではなくなってきたのです。
一方で、不倫は依然として社会問題として叩かれています。
それは人々の隠れた願望が炎のように燃え盛っているだけではなく、自分が経験せず理解しえないことに対する恐怖も含まれているのではないでしょうか。
他人の家庭の崩壊がまるで自分に今後起こることのような気がするというのは、無意識のアラヤ識にその願望が隠れているからだけではないと思うのです。第二次世界大戦は終わりましたが、恐怖は依然として人々の身近にあります。
一途ではなく多くの愛を求めること。それによっと起こる崩壊。
例えば、縋る先は男性ではなく誰かが作った偶像で神とも呼べぬ醜悪な壺神であったりするのです。
そして、その壺神に献身することも愛ではなく己の恐怖を払拭するために行われています。
よろしければサポートお願いします。いただいたものはクリエーター活動の費用にさせていただきます。
