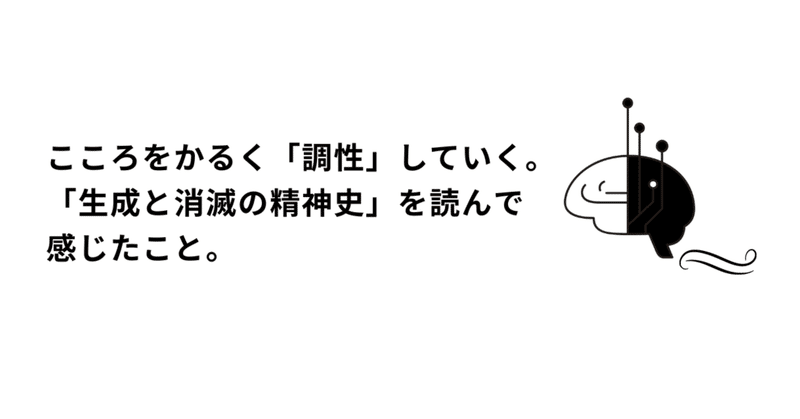
こころをかるく「調性」していく。「生成と消滅の精神史」を読んで感じたこと。
ChatGPT使っていますか?調べものをするとき、文章を書くとき、翻訳をするとき、いろんなケースで使用している方は多いと思います。どんな状況でも適切に優しく答えを返してくれる、良き上司・良き部下・良き友人・良き家族(?)のような存在ですよね…。
個人にとってここまで重要な存在となったAI。いったいこのAIは、人にとって、どのような意識の変化をもたらすのでしょうか。
先日読んだ下西風澄さんの「生成と消滅の精神史」は、そういった意識の変化に対して理解を深めてくれる、大変おもしろい本でした。哲学の歴史の全体像がつかむことができ、このAI時代においての「こころ」との向き合い方にもヒントを与えてくれた気がします。
今回はこの本で印象深かったエピソードを引用しながら、こころや意識について探っていきます。
西洋哲学と東洋哲学
この本では、日本の哲学を論ずる前に、西洋哲学の歴史が時系列で解説されています。ギリシア哲学から始まり、ソクラテス、デカルト、パスカル、カント。そして意識の哲学の章ではフッサール、ハイデガー、最後に認知科学の解説まで。
近代以降の西洋哲学の苦難とは、暴力的に論じてしまえば、神なき人間がいかに生きるべきかの根拠を設定し直すことの困難であった。(中略)カントは神の力が衰えつつある一八世紀に人間だけで成立可能な普遍的な倫理原則を構想したし、ヘーゲルは神の助力を借りつつも人間の歴史の必然性を見出すことでその物語を描いた。
西洋哲学の歴史を見ると、神の考え方と人々の意志の認識は、時間と共に大きく変わっていることがわかります。全知全能の存在として神を受け入れた時代、そしてその信念から解放されるために心の定義を再構築をしてきた時代。西洋では「神と人々の関係」をとらえなおし、そして神なしでどう人間が生きるべきかに、長い長い時間をかけて解釈を重ねてきたんですね。
いっぽう、仏教と神道が8割以上を占める日本は心をどう捉えていたのでしょうか。
日本ではあらゆる万物に神を重ねていたという表現をされていますが、まさに自然と一体化している表現が万葉集によく見られるようです。万葉集では「見る」動詞をよく使い、身体的な知覚経験がそのまま「自然・自己一体」という人間存在のあり方を規定していた。
つまり、「日本の心は、自然(神)とともに生成する共存在」であったようです。万葉集、古今和歌集、そこから時代を経て江戸時代においても、自然とともに心が行き交う様子が俳句や和歌に見られます。
日本の意識の変化
しかしこの自然と心のうつろいのなかで、急激な変化が訪れたのが明治時代です。「個」や「自我」「意識」といった西洋の概念が、それまでの自然を基本としていた価値観に大きな変化をもたらしました。
江戸末期から明治にかけて生じた近代化の運動は、心から自然を切り離し、心と世界が一体化して響き合っていた魔術的な世界を物質的で均質な対象へと解体していくプロセスであった。(中略)日本では、鳥の声、花の声、波の声が聞こえなくなった時、自然は沈黙し、新たなる自律的な心を創造する必要が生じた。
自然と一体化していた日本。それが急に切り離され、機械化が進み、物質的なもので溢れ、人間の自己を重視する風潮が広がりました。これだけの変化に対し、当時の日本人は心の「よりどころ」をどこに求めたのでしょう…。うまく対応できたのでしょうか。
私たちは今なお、グローバル化された西洋的な価値観が飛来する度に、一方ではその表面的な価値に憧れつつ、他方では「日本的」な伝統を参照してその慣習との間で激しい摩擦を起こしている。(中略)主体性の発揮よりも環境への適応を重視するこうした態度は、自律的な心というモデルが日本では徹底的に根付かないことの証左である。自然なき心、完全に自律した心というモデルは十分な歴史的な蓄積なくしては不可能なのだ。
長年苦労して神との決別や自律的な心を育んできた西洋とは違い、日本の場合はじゅうぶんな歴史的蓄積はありません。そのため、表面的には対応できたようには見えるが、いまだに「自律」や「主体性」を獲得できてはいないとのこと。
そして、いまだに心の母体となる「自然」もしくはその代替を常に求めてしまう、ということを本では指摘しています。
夏目漱石は、山に登ることでこの現実を離れた桃源郷を求めた。別の言い方をすれば、彼は全体論的意識 - すなわち私の個々の意識が独立して生きるのではなく、他者や自然と混じり合って混交する魂の領域 - に捕らわれていたということである。(中略)村上春樹が常にパラレルワールドを描きながら、意識の荷重をできるだけ取り去って風のように軽快に現実を過ぎ去ろうとするのは、漱石的な問題に対する処方箋であったのではないか。日本に限っても、漱石的な課題は現在進行系の問題である。
今の日本人は、もはや自然を見ても安定と感じられるだけの感性もありません。私たちは鳥や花や草木を見ても、自分たちとは別物として捉え、そこに感情を重ね合わすことはできません。ましてや都市に住んでいると、身近な自然さえ眼に入ることはないのです…。
つまり母体を求めても、手に入れることはできない。ユートピアを求めながらさまよっている状態といえます。
AIは心の不安を止める鎮魂歌か
では、この西洋と東洋の哲学的視点を踏まえたうえで、神でも自然でもない、AI技術は私たちのこころと意識にどのような存在となるのでしょうか。
思考はアルゴリズムに委ねましょう。そうした網の目が、いま無数に私たちの精神のノードを奪いつつある。精神はあなたの身体にある資産ではない。精神はネットワーク上の変数として、アルゴリズムにデータを与える変数としてはじめて価値を持つ。こうした現代の問題の核心は「心を持つことのコスト」に起因している。自分で自分の意思決定をすることのストレス。AIもインターネットも、宗教も、資本主義も、あるいはマスメディアと連動した民主主義さえも、これら現代を覆う巨大なシステムたちは、いかに心のコストを代替する装置としてうまく機能するかという覇権争いをしている。
本では、「AIへの欲望や期待は、精神を持つことのコストに耐えきれない人間たちの精神のアウトソーシング」という言い方もしています。
先日見たニュースでは、大学生がAIに「バイト先への断りのメールの文章」を書いてもらっていました。まさに心を持つことで生まれるストレスを肩代わりしてもらう使い方ですね。
二〇世紀が機械によって人間の肉体や行為を代替していった時代だったとすれば、二一世紀は同じような速度で人間の精神やコミュニケーションを代替していく時代になるだろう、と本ではそう予測をしています。
たしかにこれだけ人々がAIを求める現代を見ていると、そんな雰囲気はあります。意識がコンピュータのようなものであると考えるならば、すべてを委ねる時代は来るかもしれません。
ただ、それは心の全体性を代替するものではありません。たしかに、人間の複雑な心の一部を助け、解放するためのツールとしての役割を果たしています。とはいえ、万葉の時代に、自然と結びついている独特の感覚は、AIに求めることは難しいのかもしれません。
これからのこころとの向き合い方
神や自然から切り離され、AIがその役割を果たせないとしたら、わたしたちはどこに「心の母体」を見つけるべきなのでしょうか。それとも、「心の母体」を求める必要性自体を再考するべきなのでしょうか…。
人間は儚い。人間は弱く、愚かだ。しかし、人間はたんに儚く、たんに弱いのではない。むしろ人間は強くあろうとすることによって弱く、賢くあろうとすることによって愚かになる。(中略)人間の心ははじめから弱く脆かったのではない。子どもの頃に喜びに満ちて野原を走っていたこと、虫たちを追いかけて転げ回っていたこと、石を拾うだけで笑っていたことを思い出してみる。
そう。子どものころは軽やかだった。それが大人になるにつれ、なぜか固く重くしんどく捉えるようになってしまった。ではその軽やかなこころを手に入れるには…?
本ではその解決までは描かれていませんが、以下の文章に少しのヒントがあるように思います。
日本の心の思想史は明らかに身体的な感覚を中心に自然と癒合するというモデルが中心にあって、そこに侵入してきた意識の支配性やその形而上学というのは、奈良・平安では中国からの、明治では西欧からの、矯正的に導入されたガジェットのようなものであり、その拘束具に混乱をきたすというのが日本の典型的なパターンであったように思える。
個人的には茶道が趣味なので、身体的な感覚+自然とつながれる+哲学といったら、茶道を思い浮かべてしまいます。ここ最近、自分のまわりには茶道を始めるひとが増えているので、こういった時代の背景を映しているのではとさえ思ってしまいます。
とはいえ、ひとそれぞれ。今のこの時代に、何かこころの荷重を軽くする、「こころを今のトーンに調性できる手段」を考えてもいいのではと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
