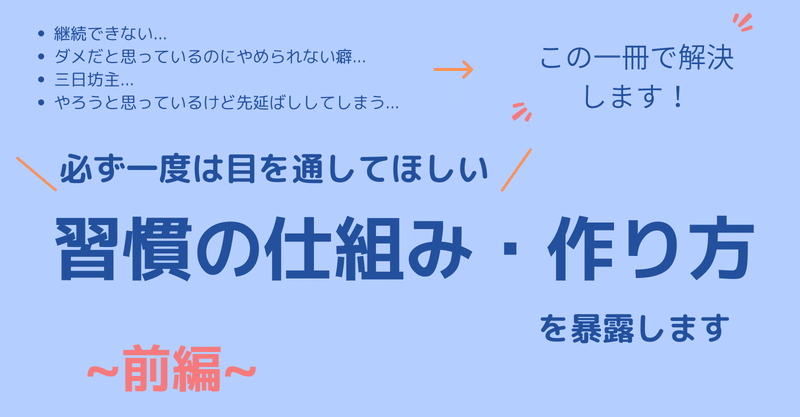
誰しも必ず一度は目を通してほしい習慣の仕組みと作り方~前編~
こんにちは。ゆきのです。
こんな悩みはありませんか?
・なんだか、一日の時間を無駄に過ごしている気がする...
・三日坊主...
・やろう!と意気込んだはいいものの、途中から続かなくなってる...
・人生変えたいけどなんとなくもやもやするような漠然とした不安...
あなたも経験したことがあるのではないでしょうか。今では頻度はかなり減ったものの、ズボラというくらいですから、過去は連発していました。
ですが、習慣の仕組みを仕組みを知り、未然に防ぐことで改善する行動が出来ています。
習慣なんて...と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、個人的には人生を変えるスキルといっても過言ではないと思っています。
なぜかというと、過去のあなたの行動の繰り返し、すなわち習慣が今のあなたを作っているからです。
1日10分の読書を継続してあなたの知識に、1日30分の作業があなたのスキルになります。もっというと、毎日歯磨きをするという習慣があるから大量に虫歯が発生していないんです。
思考習慣、食事習慣、行動習慣など、過去の習慣が今を作り、そして今の習慣が未来のあなたを作っていくのではないかと思います。
得たことを日常に取り込み、継続していくことで人は変わっていくのではないかと思っています。
よく、マインドを整えようという人もいるのですが、人は意識やマインドだけでは変わりません。意識を変えても行動が伴っていないとやはり現状は変わらないですね。行動に結びつけることが死ぬほど大事です。ここに気づけたあなたはもう周りの人よりも100歩ほど先を行っています。
じゃあ行動を変えるにはどうすればいいのかというと、習慣を変えます。
じゃあ習慣を変えるのかをこのnoteでお伝えします。
私は習慣によって時間の使い方もうまくなりましたし、(以前は大学の課題で手がいっぱいだったのが読書やプログラミング、こうしてnoteも書けるようになりました)無駄な時間も減りました。
もう一度言います。習慣化は能力でなくスキルです。誰でも身につけることが出来ます。
ではさっそく、習慣について知るところからはじめましょう。
このnoteを読むべき人
・習慣化したいことがある
・習慣にするには強い意志が必要だ!と思う人
・やめたい習慣がある人
・三日坊主
・ズボラ
・人生変えたい人
・習慣や行動に少しでも興味のある人
・行動に科学的根拠が欲しい人
・時間が足りないという人
こちらに当てはまる人はぜひこのまま読み進めていただきたいです。あなたの行動、習慣には理由があります。正しい習慣の知識をつけていきましょう。
このnoteを読むべきでない人
・既に習慣化できていて困っていない
・特に習慣にしようと思っていない
・毎日気分で過ごしたい
・習慣とかどうでもいいと思う
・誤った方法でも特に気にしない
こちらに当てはまる方はブラウザバックしていただいて構いません。時間の無駄です。このnoteを読む時間をあなたにとって重要な他の時間に充ててください。
このnoteを最後まで読んだ人の未来
・正しい習慣の知識が身につく
・間違った習慣の身につけ方をしなくなる
・具体的にどうやって習慣を身につければよいのか分かる
・あなたの行動の理由がわかる

あなたがこれは習慣だなと思う日常の行動はどのくらいありますか?
人間の行動の約40%が習慣であると言われています。
このうち、私たちが習慣だと認識している行動は40%程度だということが分かっています。つまり、残りの60%は無意識による行動で、全体の行動の24%(なんと全体の約1/4!)を占めていることになるのです。
(数字が多くて面倒だという方は上は飛ばしてください。とりあえず日常に占める習慣の割合は思ってるより高いよってことを言ってます)
人間の行動の約半分を占めている行動パターンを自分でコントロールできるようになるとその後の人生がより良いものになるはずです。
おそらく、自分の習慣なんて気にしたことないという方が大半ではないでしょうか。
習慣と聞くと、どうしても”歯磨き”、”トイレに行く”、”勉強する”などというイメージがありますが、それと同時に”夜酒する”、”間食を多くしてしまう”、”暇になったらついスマホをいじってしまう”などの良くない行動も習慣になっている可能性があります。
このように、新しく習慣を身につけたいという人だけでなく、ついつい勉強ではなく、スマホをいじってしまう...ゲームを手に取ってしまう...という止めたい習慣がある人も必見の内容となっています。
ここに書いてあることは全て私の経験に基づくことと科学的に根拠のある内容で構成されています。
ぜひ参考にしてください。
また、後編まで受け取ってくださった方には特典をつけました!きっとお役に立つと思います。
後編には具体的な習慣の作り方の一つをお伝えします!ぜひこちらも合わせて読んでいただき、行動に繋げていただければと思います。
目次(前編)
はじめに
習慣化とは
習慣の仕組み
習慣のメリット
なぜ三日坊主になってしまうのか
まとめ
では、ここからが本題です。
ここまで習慣について語ってきましたが、習慣化して具体的にどのようなメリットがあるのかについてお話しします。

時間が増える
習慣化すると時間が増えます。もちろん、物理的な時間が増えるわけではないのですが、一日の時間を無駄に過ごしているなという感覚がある人ほど時間をうまく使うきっかけとなります。
そもそも、時間がないというのは何に対して時間がないと言っているのでしょうか。
おそらくですが、自分のやりたいことに対する時間がとれていないときにそう感じるのではないでしょうか。
ですから、充実したと思える時間の使い方ができれば時間がないという感覚が軽減されるのだと思います。
充実した時間の定義は人それぞれだと思います。資格の勉強だったり、副業のための作業かもしれませんし、大切な家族との時間かもしれません。
どんな内容でも習慣化によって自分のやりたいことをする時間を割り当てることができます。
家に帰ったら目的もなくテレビをつけてしまう、食事の前後に何かをするわけでもなくSNSを見て時間を過ごしてしまうなどの時間を見直し、読書や自分のやりたかった勉強に充てるだけでも満足度の高い時間を過ごせると思います。
決定疲れを軽減させる
私たちは日々、意思決定をしています。決定疲れとは意思決定を下すたびに精神的に消耗してしまう現象のことです。
皆さんも朝や昼はそうでもなかったのに、夜になると食べてはいけないと分かっているのにやけ食いをしてしまったり、今日はもういいや。と言って投げやりになることがありませんか?
これは日中の決定疲れによって正しく意思決定をする力が消耗されているからなんです。
習慣となった行動は決定疲れを軽減させることが出来ます。これによって、重要な物事を処理する能力を残しておくことができるのです。
スティーブジョブズが毎回同じ服装で出社していたりすることも決定疲れを減らすためだったと言われています。
感情のコントロールが効き、行動に対するストレスのレベルが少ない。
習慣になっている行動をするときはプラスの感情もマイナスな感情もあまりありません。
歯磨きを例に出してみます。
歯磨きをしている最中に、
「あの、くそ上司ぃぃぃいい!!!」
と思うことはあっても、
「なんか、今日の歯磨き気持ちいいな。いい感じ♪」
と思うことはほぼないのではないでしょうか。
これは歯磨き(習慣化した行動)に対する意識レベルが0になっているからです。そのため、行動しながらも意識は会社の上司に向けることが出来ています。
習慣にすることができれば、自分の感情に大きく左右されることもないため、行動を始める前後や行動している最中のストレスレベルも下がることにつながるのです。

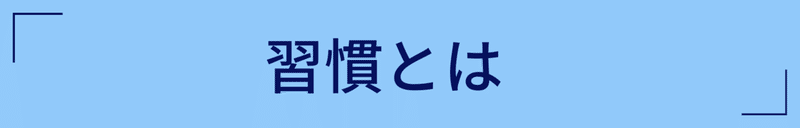
まず、ここでの習慣について定義しようと思います。
習慣とは、ある時点で意図的に作り、やがてほぼ考えずに毎日行うようになるもののことを言います。
意図的に作ったわけではないにしても、作ることで生活にメリットがあったり、毎日繰り返すことで自然に習慣となったりします。
これは良い習慣、悪い習慣の両方に言えることです。
良い習慣を作り、悪い習慣を断つにはどうすればいいのかということをこれから解説していきます。
習慣の仕組み
習慣とはどうやって形成されるものなのでしょうか。
簡単に説明します。習慣は次のように発動します。
きっかけ(トリガー)→習慣(ルーティン)→報酬
この3つの結びつきが強くなったものが習慣として日常に定着していくイメージです。
順を追って解説していきます。
きっかけ(トリガー)とは文字通り、習慣となる行動をするための合図のことです。
習慣(ルーティン)は習慣となる行動そのものを指します。
報酬は習慣となる行動を行うことで、得られる達成感や快楽、楽しみのことです。
例えば、夜、仕事から帰宅したとき、玄関のドアを開けた状況を考えてみます。
まず、ドアを鍵を開け、ドアを開けて中に入ります。すると、真っ暗でほとんど中が見えません。(きっかけ)
↓
電気をつけます。(習慣)
↓
明るくなり、周りが見えるようになりました。(報酬)
きっかけとなる状況から報酬をもとめて習慣という行動をとっているのが分かると思います。
つまり、あるきっかけによって引き起こされる行動が私たちに報酬をもたらすことを期待することによって習慣(人間の行動も)は形成されています。
この例は皆さんも毎日ほぼ無意識的にしていると思います。
無意識的な習慣ほど状況が合図になり、知らぬ間に発生しています。(意識できていない習慣の割合が高いのはこのためです。)
横からくる自転車を見たら避ける、のどの渇きを感じたら水分をとるなど、ほとんどが自分の意志と関係なく状況が行動を起こすことのきっかけになっています。
問題なのは、脳は悪い習慣の報酬も良い習慣の報酬も区別が出来ていないことです。
例えば、
帰宅後、仕事でいらいら。目の前の酒を見る(きっかけ)
↓
酒を飲む(習慣)
↓
酒がおいしい、ほろ酔いが気持ちいい(報酬)
これも脳にとって立派な報酬です。だらだらする習慣、ジャンクフードを食べる習慣など、断ちたい習慣をなかなかやめられないのはきっかけと報酬がセットになっていて、なおかつ即座に得られる快感だからです。


みなさんはこのような経験はありませんか?
別におなかがすいているわけではないけど、なんだか口が寂しいような、何か食べたいような...冷蔵庫に何かあったかなー...そうだ!買ってきたスイーツ食べよ!
食べたくもないのに食べてしまう、飲みたくもないのに飲んでしまうという経験は私にも少なからずあります。
ここで、少し考えてほしいのが「おなかがすいた」と感じていなければ「食べたい!食べたい!!」とそこまで思ってはいないのではないでしょうか。
でも食べてしまう。おかしいですね。別に食べたくもないのに食べているという意志と行動の矛盾です。
これは、食べ物を想像したときにおなかがすいているかどうかに関わらず、その食べ物を脳が期待し、求めてしまうんからなんですね。
「おなかがすいた」という感情が起こらなくてもこの欲求に抗えずに食べてしまうという現象が起こります。この欲求が満たされることで脳が満足しているのです。
もう一度だけ考えてみてください。
意志と行動が矛盾してますよ?普段、何かを継続しようとするときにどうしていますか?
「英語の勉強をしよう!!」
「筋トレをしよう!!」
「ダイエットをしたいから食事制限しよう!!」
これらは全て意志ですよね?勘の良い人はここで気づくかもしれません。意志の力で習慣にしようとすることの問題点に。
意志と行動は矛盾する可能性があるのです。英語の勉強をしようと思っていても実際にはスマホを開いてしまったり、筋トレをしようと思っていても今日はいいやとなってしまったり...
この原因は先ほど述べた習慣の流れが関係しています。大事なのでもう一度書きます。
習慣は
きっかけ(トリガー)→習慣(ルーティン)→報酬
この順番で起こります。
「よし!英語の勉強をしよう!!」と思っていても机の上にはスマホが置いてありますし、普段はその環境でスマホを見てツイッターやネットサーフィンをしています。
習慣は状況(きっかけ)に左右されるのでした。あれ、目の前にスマホが置いてありますよ。
だから「英語を勉強するぞ!!」という意志があるのも関わらず、目の前のスマホがきっかけになり、「ちょっとだけ気になることがあるからスマホ見よ」となって、いつもと同じようにスマホを見続けてしまうのです。
あなたに強くこびりついた以前の習慣は意志の前に立ちはだかります。しかも習慣が勝ってしまうことも珍しくないと思います。
ですから、やはり意志とは別の観点から習慣を作りに行った方が良さそうです。
あなたが習慣化できないのは意志が弱いからではありません。
強い意志は確かにもともとの習慣に勝てるかもしれませんが、毎回勝負となるとやはり限界があります。
そもそも習慣に必要な要素に意志はありますが、それは最初だけですし、一番重要な要素ではありません。
大事なのは習慣の要素である「きっかけ・習慣・報酬」にフォーカスを当てることです。
これらの要素に焦点をあてて習慣を作る方法は後編で紹介します。

ここでは、三日坊主の原因となることについて話していこうと思います。
まず大きく4つほど原因があげられます。
・そもそも忘れてしまう
・やる気やモチベーションで習慣にさせようと思っている
・目標が大きすぎること
・人間の脳は目先の利益を追ってしまうこと
詳しく解説していきます。
・そもそも忘れてしまう
これは正直あるあるだと思います。私はあるあるでした。
実際に私は「お風呂から出たら化粧水を塗る」というなんともシンプルすぎる習慣を新しく身につけようとしたのですが、ドライヤーで髪の毛を乾かしているときに「あれ?化粧水は?」と慌てて化粧水を取り出す始末です。
「お風呂上がりの肌の水分の蒸発は早いらしいし、その前に保湿をするのが良さそう。だからお風呂上り直後にしよう」と理由付けをしたにも関わらずです。
この原因としては以前からずっと「お風呂から出ると→歯磨きをする→そのあとにドライヤーで髪を乾かす」という習慣が身についていたため、意識しないでいると簡単に元の習慣がぶり返してしまうことにあると思います。
なので、化粧水をつけていないのはなぜか?と聞かれても
「いや、単純に忘れてた...というか気づいたらドライヤーを手に持ってた...」
となってしまうのです。
これを解決するには、スマホでの通知や、メモしておくなど単純に忘れなければ良いと思います。
・やる気やモチベーションで習慣にさせようと思っている
これは先ほど言った意志の話に似ています。
習慣を作る時には意志に頼りすぎてはいけないのでした。意志と行動は矛盾する可能性があるからです。(正確にはこびりついた元の習慣が意志に打ち勝ってしまうんでしたね。)
やる気やモチベーションは意志の力を高めてくれる効果があるイメージをしてもらえると分かりやすいと思います。
やる気があるとき、モチベーションが上がっているとき...そのときは「やるぞぉぉぉお!!」と思っていると思います。
しかし、やる気とモチベーションの正体は感情です。
感情は日や出来事によって影響されてしまいます。時間帯によっても波がありますよね。
習慣は日常の中でほぼ考えずに行動することです。そのときそのときで波があるものに頼ると習慣にしにくいのは容易に予想がつくと思います。
やる気がない日はもちろん行動に移せないことになりますし、これが三日坊主の原因となります。
・目標が大きすぎる
前提として、人は未来の自分に過剰な期待を寄せる生き物です。
例えば、
「英語のテキストを今週中に終わらせたい!よし!毎日5ページずつだ!」と思っていたものの、いざやってみると
「あれ、まだ3ページしか進んでない...今日はもう遅い時間だし、明日も早く出社しなきゃいけないし、今日はもう寝ようかな。
明日7ページやればいいや。」
となるのですが、実際に次の日になってみると、
「なんか全然進まない。5ページはとりあえずできたけどこれ以上だと睡眠時間が少なすぎて明日持たない...」
となってしまうことありませんか?
普通に考えたら一日5ページが難しい状況で7ページをこなすって鬼だと思います。でも、やる前はできてしまう気がするんですよね。。
そもそもこの5ページが適切なのかも疑わしいです。新しい習慣を身につけたいとき、それが時間的にも体力的にも可能なのかどうかをしっかりと見てください。
一度やってみてダメだったら引き返して見直すのなら良いのですが、このままやめてしまう人も多い気がします。
もともと無理な計画を立てていたにも関わらず「自分はこんなこともできないのか」と落ち込んでしまう人もいます。
これが挫折の要因となるのです。
これについては次の章の習慣の作り方にも書いているのでぜひ読み進めてみてください。
・人間の脳は目先の利益を追ってしまうこと
これは上の二つと違って人間の脳の性質によるものです。
これも一つ例を挙げます。
例えば、これから筋トレとして腹筋を毎日30回やるとしましょう。腹筋の効果は計り知れません。
まず、腹筋が割れたらモテる。
そして、以前よりも筋肉がついたおなかを鏡で見て自分に自信がつく。
しまいには、水着が着れる。
もういいこと尽くしじゃないですか!!さて、毎日がんばるぞ!!!
と思っている矢先においしそうなシュークリームが目の前でまるで自分に食べられるのを待っているかのようにこっちを見つめています。
このとき、脳の中ではパイ生地のサクサク感とカスタードのあまーい味が再生され、脳は「食べたい!」という欲求に駆られます。
このような欲求に駆られると避けるのは難しくなります。
「ぱくっ」
もう、一回食べちゃったからいいや!と言って筋トレをそっちのけにしてエクレアを食べ、クリームパンを食べ...というのが挫折につながってしまいます。
筋トレのメリットは分かっているのにもかかわらず、それは長期的な目線です。短期的な脳の快感が優先されてしまう傾向があるのです。
脳のつくりがそうなってるんだったら変えようがないじゃん!と思う方もいるかもしれませんが、これの対策はちゃんと後編にて紹介させていただくのでご安心ください。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます!一度まとめをさせていただきます。
まとめ
習慣化をするメリットとして
・時間が増える
→SNSやyoutubeをだらだら見る時間を減らし、自分にとって充実度の高い時間を増やすことが出来ます。
・決定疲れを防ぐ
→人は何かを決断するたびに精神的に消耗してしまいます。習慣により決定する頻度を減らすことが出来ます。
・感情に左右されにくい
→習慣はやる気やモチベーションに左右されにくいです。行動を始めるときのストレスも軽減させることが出来ます。
の三点がありました。控えめに言って、自分のやるべきことを精神的に消耗することもなく、感情に左右されずにこなすことで時間を増えることは最高だと思います。
増えた時間をしっかりと自分にとって大切なことをすることに充てるが出来ます。
習慣が形成される仕組みは
きっかけ→習慣→報酬
の三段階です。人間の行動のほとんどはきっかけという状況から報酬を意識して行動に移しているのでした。
なかなか継続できないという人は
・そもそも忘れている
・やる気やモチベーションに頼りすぎている
・目標が大きすぎる
・長期的な報酬よりも短期的な報酬に脳が反応している
という原因がありました。ここで挙げたのは主な原因で、やはりここは個人によっても違いが出てきてしまうかもしれません。ただ、多くの人は当てはまっているのではと思います。
前編を読んでいただきありがとうございました!
ここまで長いnoteを読んでいただきありがとうございます。8000字を超えていますし、習慣について原理から詳しく書かれているnoteも多くはないのではないかと思います。
初めて聞くこともあったと思います。ぜひ何度も読み返して理解を深めていただければと思います。また、あなたが知らないということは他の人も知らないということです。ここで他の人と差がつきます。
後編では習慣化がどのように作られるのかを踏まえたうえで具体的にどうすればよいのかをお伝えしていきます!!
後編の受け取り方法
こちらのnoteを引用RTしていただいた方にDMで後編noteのリンクを送らせていただきます!(リプもしていただけると分かりやすいです🙇♂️できるだけ漏れのないようにしようと思います。)
DMの開放をしてお待ちください🙇♂️
こちらのツイートの引用をお願いいたします↓
【15000字を無料公開】
— ゆきの|ズボラでも習慣化 (@yukino_jsbook) July 15, 2021
何かを達成・習得したい人へ
スキルの習得、資格の勉強、副業...どれにも共通して必要なのが継続というスキルです。なのに誰も学ぼうとしていません。人の行動はどうやってで習慣となるのか、習慣を新しく作る方法、これ知っているだけで相当違います。https://t.co/OioIIq3TV7
それでは、後編でお会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
