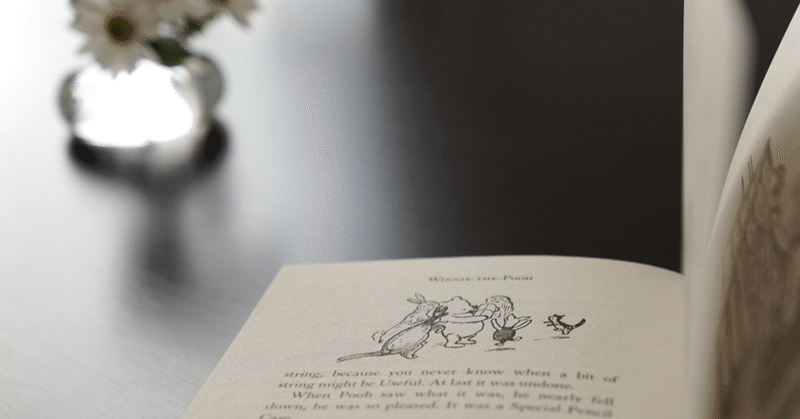
何のために、読みやすくするのか。
無意識を言語化して、意識する。
昨日の記事に書いた。
言語化。
最近のキーワードな気がする。
いろんなことを言語化したいなぁ。
どうしてそう思うのか。
まずはそもそも、言語化することが好きだ。
だからこそこうして、毎日noteを書くことができている。
たとえば仕事関連のマニュアル作りなども、とても好きで。頼まれてもないのにすすんで文章にしては、こそっと残してる。
言葉にすると、もやもやっとしたものが輪郭を帯びるようで、スッキリする。そのスッキリする感覚が、好き。
もやもやした事象に輪郭をつけると、今度は誰かに「伝える」ことができる。
もちろん、言語化されているからといって全てが伝わるとは限らない。あくまで「伝える」ことの手段の一つ。
でも「伝える」が「伝わる」になる可能性が高くなるのは確か。
たとえばマニュアルに書いてあることを、全て口頭で共有することは難しい。
絶対に忘れてしまう。
膨大な時間もかかる。
言語化されている(文章に残されている)と、伝わりやすくなる。
*
ここからが本題。
昨日の記事に貼りつけた一年前のnoteが、内容はさておきとても読みにくいと感じた。
はじめてこれを読む人が、果たして最後まで読んでくれるだろうかと。
比べると、今はいくらか読みやすくなっている(と思う)。
他の方から、私のnoteを「読みやすい」と言ってもらえることも増えた。
きっと自分なりに何かしら、工夫を重ねてきたのだと思う。
少し前にこんなnoteも書いた。
これも工夫の一つ。ただどちらかといえば、「書くときのスタンス」に近い。
一年前のnoteで感じた読みにくさと、今のnoteの違い。
それを言語化するべく、今日は書いてみようと思う。
※あくまで「読み手への配慮や優しさ」という意味での「読みやすさ」と捉えていただけると幸いです。
*
3行程度で改行を入れる(PCの場合)
やはり、文字が続きっぱなしになると読みにくい。PCの3行は、スマホの4~5行。PCの5行は、スマホの7~8行(もちろん端末によるけど)。
スマホで読む人が多いことを考えて、適度な個所で改行を入れるようにする。
そうすると、スクロールされてしまう可能性も少し下がるのかな、と。
改行の回数を使い分ける
読みやすさとしての改行を入れる際は一回だけ。
何らかの意図があるときは、二回以上改行する。
例として、以前の文章を書き直してみる。
▼以前の文章
「子どもとの関わり方に正解はない」という言葉は、これまで子どもの仕事に携わる中で、たくさん耳にしてきた。同じように、子どもに関わる仕事をしている人は、おそらく一度は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。
確かに、正解はない。「子ども」と言ってもひとくくりでは語れず、一人ひとりみんな違うし、置かれている状況も違えば、唯一の正解の関わり方なんてあるわけない。
↓改行を入れてみる。
▼書き直した文章
「子どもとの関わり方に正解はない」という言葉は、これまで子どもの仕事に携わる中で、たくさん耳にしてきた。
同じように、子どもに関わる仕事をしている人は、おそらく一度は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。
確かに、正解はない。
「子ども」と言ってもひとくくりでは語れず、一人ひとりみんな違うし、置かれている状況も違えば、唯一の正解の関わり方なんてあるわけない。
「確かに、正解はない」の前が「~でしょうか」という問いかけで終わっているため、少し考えてもらうために、余白(改行)を多く入れてみた。
読み手に考えてもらいたいときや、文章のまとまりとしていったん区切れる(区切りたい)と思う箇所は、複数回改行をして、余白をつくるようにしている。
すっきりさせる&短文に
その言葉がなくても意味が伝わるのなら削る。また、長文は短文に分けられないか考えてみる。
そうすると残った言葉や、一文一文が際立つ。
結果的に、読みやすくなる。
さっきと同じ個所。
▼以前の文章
「子どもとの関わり方に正解はない」という言葉は、これまで子どもの仕事に携わる中で、たくさん耳にしてきた。同じように、子どもに関わる仕事をしている人は、おそらく一度は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。
確かに、正解はない。「子ども」と言ってもひとくくりでは語れず、一人ひとりみんな違うし、置かれている状況も違えば、唯一の正解の関わり方なんてあるわけない。
↓これをすっきり&短文にしてみると。
▼書き直した文章
「子どもとの関わり方に正解はない」という言葉。
私はこれまで、たくさん耳にしてきた。
子どもに関わる仕事をしている人は、一度は聞いたことがあるんじゃないだろうか。
確かに、正解はない。
「子ども」は一人ひとりみんな違う。置かれている状況も違う。唯一の「正解」なんて、あるわけない。
だいぶ削いで、短文にもしたけれど、内容的には削られていないと思う。
内容を削る必要はなく、あくまで重複している箇所があったり、その言葉がなくても伝わる箇所があれば削るイメージ。
上記の文章で言えば、冒頭の「子どもの仕事に携わる中で」という部分をそのまま削った。
ここで書かずとも、noteを読み進めれば私が子どもの仕事に携わっていることは、わかるからだ。
*
読みやすい、わかりやすい文章がいい文章とは限らない。だから上記の工夫をしている文章が絶対にいい文章だとは思っていない。
私がどうして読みやすい文章にするために(無意識でも)これまで工夫してきたのかというと、私の文章に出会った人には、できれば最後まで読んでほしい、と思うからだ。
大量のコンテンツがあふれる中で、出会ってもらえることが奇跡。
出会ったのなら「やっぱりやめよう」と途中でいなくなってしまうのはさみしい。
私の文章を読んだ人にプラスになるようなことがあるのか、つながりや交流が生まれるのか、それはわからない。
でも「読んでもらう」ことができてはじめて、次につながる可能性が開ける。
だから出会いの初めの段階は、できるだけ多くの人に開かれているようにしたい。
とまあそれっぽく書いているのですが。実は書きながら、こうやって考えていたんだなーとはじめて気づいたのです。笑
やっぱり、言語化する過程には学びがある。
これからも「無意識」を見つけたら、言語化していきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
