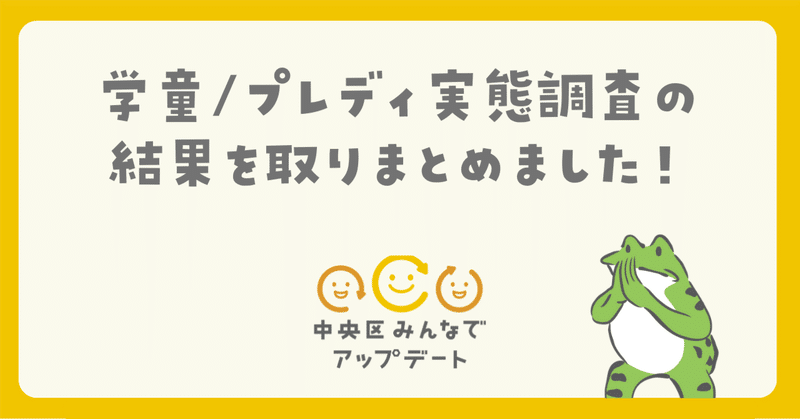
学童/プレディ実態調査の結果を取りまとめました!
今回の記事では、先日まで実施していた「学童プレディ実態調査」の結果についてまとめます。
「学童プレディ実態調査」とは?
この調査は中央区における主要な小学生の放課後対策の施策である学童クラブとプレディについて、お子さんと保護者の率直な意見を集約することで、今後の運営改善に役立ててもらうことを目的としたものです。
調査実施の背景
中央区は2023年4月に260名もの学童クラブの待機児童を出すなど、都心でも有数の学童クラブに入りにくい区です。1-3年生の低学年のうちは利用できるというのが一般的な感覚ですが、中央区では2年生時点から大半が落ちるというのが通例となっています。
この状況に対して、中央区は抜本的な対策を打ってきませんでした。いわゆる放課後子ども教室、中央区で言う「プレディ」でその需要は吸収するという方針で、長年学童クラブの施設増は行われないまま。
このプレディで学童クラブと同等のサービスが提供されていればそれはそれでOKなのですが、プレディに対する利用者の評価は決して高くなく、その代替としては不十分という声が多数ありました。
そんな中、直近の区の基本計画2023においては2024年度から新たに小学校内に学童クラブを設置するという、政策の大きな転換がありました。
この転換は望ましいものですが、その運用設計はしっかりとした現状把握に基づいて行われるべきものです。にもかかわらず、区としては特に利用者に対しての実態調査は行わないというスタンス。
やはり実態調査は行うべき、とわたしは考えまして、この問題に関心を持つ有志の方を募って独自に実態調査を企画・実施したのでした。それがこの調査です。
調査の概要
構成としては下記のような感じになっております。
調査名称:学童/プレディ実態調査
調査実施方法:Googleフォーム
回答対象者:以下に該当するお子さんがいる保護者の方
現在、学童クラブやプレディを利用している
過去に学童クラブやプレディなどを利用していた
将来、学童クラブやプレディなどの利用を予定している
調査期間:7/20 - 8/20
回答件数:116件
上記のとおり116件もの回答をいただき(回答いただいた方、拡散いただいた方ありがとうございます!)、その結果をまとめたのが下記の報告。
かっちりした文書としては学童クラブやプレディ、今後のプレディプラスの運営に携わる直接の担当課長に要望書というフォーマットで8/29にお渡ししてきました。が、それだと22ページにも及ぶボリュームであることから、グラフや自由コメントの内容を一部抜粋して短くしたのが以下のバージョンです(それでも1万字以上ありますが。。。)。
参考までにですが、区に提出したバージョンはこちらです。
中央区の放課後対策のさらなる充実に関する要望書 - Googleドキュメント
1.回答者の属性
まずは、どういった方から回答いただいているかについてざっと示しています。
1-1. 回答者のお子さんの学年
まず、回答者のお子さんの学年。

直接の当事者である「1年生」「2年生」など小学生低学年が多いものの、「未就学」も多いです。これは、ママ友・パパ友経由などで「学童に入りにくい」という件についてすでに把握されていて、今後に対して不安を感じていることが示唆されます。
1-2. 回答者の居住エリア
次に、居住エリアについて。一見するとかなり「月島エリア」の割合が高いのですが、人口比で見ても「月島エリア」が多いのでエリア別の子どもの人口の割合も並べてます。

上の「回答割合」が今回の調査でのエリア別の回答の割合。下の「人口割合」がエリア別での子どもの人口の割合。「京橋エリア」の回答割合が低く、「日本橋エリア」「月島エリア」が多めにはなっていますが、人口の割合を見るとそれほど極端に「月島エリア」の回答が多いというわけではないということが分かるかと思います。
1-3. 施設への登録状況
次に、学童クラブやプレディの利用状況。

「今後、登録を予定している」の方は現在未就学のお子さんがいる家庭で、それ以外が学童クラブやプレディを利用している/していた家庭です。
1-3. 利用している/していた施設
次に、現在利用している/していた施設について。数はそれほど多くないですが、民間学童に通っているお子さんのいる家庭も回答いただいています。

2.施設の評価
お待たせしました。各施設の評価についてです。学童クラブとプレディに対して、利用している/利用していた方たちがどのように感じているのかを以下の11の評価軸によって明らかにしていきます。
1. 遊び道具や遊び場所が十分に提供されている
2. 子どもが活動するにあたって十分なスペースが提供されている
3. 子どもが自ら進んで施設に通い続けられるような支援や配慮がある
4. 子どもの発達に応じて遊びや生活ができるようスタッフが援助できている
5. 子どもの個々の活動を支えるためのスタッフが十分配置されている
6. 子どもが主体的に参加できるイベント等が多く用意されている
7. 障害等の援助が必要とする子どもに対して適切な支援が行えている
8. 適切な時間帯におやつや食事を提供できている
9. 子どもの安全や衛生を確保する体制が整備されている
10. 施設の利用時間が保護者の就労状況等に柔軟に配慮されている
11. 利用にあたっての手続きや準備等が保護者に対して柔軟に配慮されている
この11の評価軸はわたしが勝手気ままにモウソウしたものというわけではなくて、厚生労働省が公開している「第三者評価内容評価基準ガイドライン(放課後児童クラブ版)」に基づいたもの。

社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定していて、個々のサービスに対して評価基準をどんな感じで設定すべきかについて厚生労働省がガイドラインを出しています。今回の調査では、この評価基準をベースにしています。
2-1. 学童クラブの場合(評価)
こちらが学童クラブ分の回答結果をまとめたもの。直感的に分かるように、設問に対してポジティブな回答はオレンジ系、ネガティブな回答は青系にしています。

一見して分かるとおり、学童クラブは全体的に高い評価を得ています。特に、「1. 遊び道具や遊び場所が十分に提供されている」「8. 適切な時間帯におやつや食事を提供できている」への評価が高いです。特に「おやつ」についてはすべての回答が「そう思う」もしくは「どちらかと言うとそう思う」となっています。
他方、強いて言えば「そう思わない」が多かったのは「7. 障害等の援助が必要とする子どもに対して適切な支援が行えている」、「11. 利用にあたっての手続きや準備等が保護者に対して柔軟に配慮されている」の部分。障害を持つお子さんへの対応、そして保護者負担の部分についてはまだ改善の余地があるということが分かります。
2-2. 学童クラブの場合(コメント)
次は、上記の評価に対する補足のコメントについてです。こちらには回答者の方々の思いのこもった長文を多数いただきました。以下に紹介するのはその抜粋で、ポジネガそれぞれに整理しています。
□ ポジティブな意見
・施設・運営・スタッフの方への満足度は高いです。子供は学童に行くのを楽しみにしており、安全基地になってくださっていると感じます。また、面談や保護者会の頻度も多く、連絡帳での丁寧なやりとりもあり、きちんと子供と親に向き合ってくださっているように思います。
・子どもたちが先生方のことを大好きで通っているのを感じます
・学年を超えた交流、メンコ大会など子供が喜ぶイベントを先生方が考えて手作りで開催していただくなど、とても感謝しております。
■ ネガティブな意見
・先生方は柔軟に対応してくださるが、子供の人数に対して場所が狭いと感じる。ぎゅうぎゅう詰めで勉強や遊びなどしていて、窮屈そう。
・定員より多くの児童を詰め込んでいるために、手狭な印象を受けます。また、個々へのサポートを十分に行えるまでの人員は配置されていないと感じます。とにかく児童の数が多すぎるのが一番の問題点だと思います。
・あまり活動に参加できずに過ごす時間が多かったようです。生徒の数に比して先生の数が少なかったのかもしれないと記憶しています。
・特認校の児童は、スタッフの付き添いはなく、保護者が下校時間に合わせて仕事を抜けて学童まで送迎し、一人で行けるようになるまで本当に大変でした。
ポジティブな意見は先生方の対応に対しての声が多いです。ネガティブな意見は利用人数に対する手狭さに関するものの他、特認校利用であることによる移動の大変さ、障害児であることによる付き添いの大変さについてのコメントがありました。
2-3. プレディの場合(評価)
今度はプレディの方です。評価軸は先ほどと同じです。

学童クラブのグラフと比較すると全体的に低めの評価となっています。オレンジ部分が減って青部分が増えていることが一見して分かるかと思います。特に、「2.子どもが活動するにあたって十分なスペースが提供されている」に対してポジティブな評価をしている方は10%足らずという結果に。「5.子どもの個々の活動を支えるためのスタッフが十分配置されている」も低く、これらの傾向は後段のコメントや改善要望にもはっきり現れています。
2-4. プレディの場合(コメント)
同様に、上記の評価に対するコメントの抜粋です。
□ ポジティブな意見
・スタッフの方は子どものことをちゃんと見てくださり、楽しいイベントも用意されており、親としてはよい施設だと感じています。利用票の書き間違いがあっても電話で連絡をくださり柔軟に対応してくださいます。
・プレディの先生方は優しいらしく、我が子は夏休み中もプレディへ行きたがります。
・土日も含めイベントなどは積極的に運営いただいている
■ ネガティブな意見
・人数が多すぎて、子どもの状況を把握できる状況ではない。毎日の利用者数を把握できていないと思われるので、必要な人員が確保できているとは思えず、安心して利用できません。
・昨年利用登録していましたが、春休みに3回だけ利用し、その後本人がつまらなさすぎる、と言って行かなくなりました。まだコロナ対策もそれなりに行っていたため、教室以外での活動制限、玩具、本が限られており、保護者が聞いても全く楽しくなさそうでした。またヒステリックに怒る先生が怖いということでした。
・学校のスペースをかりるなど努力はされているもののプレディルームが狭すぎることにより全く通わなくなりました。ゲーム参加を無理強いされたり、大きな声で叱る(本人はしっかりやってるのに全体的にむけて叱られる)等で嫌な思いもしたのも原因です。
調査の性質上、プレディに対してネガティブな意見が多いであろうということはある程度想定していましたが、もちろんそればかりではなく上記のとおり好意的なコメントもありました(結論ありきでなく、実態について公正に評価いただいた結果と思います)。
とはいえ、全体を見ると上記の評価結果を見て分かるとおり決して満足度は高くなく、コメントも厳しめのものが多い印象です。特に、スタッフの質に対しての疑義のコメントがいくつかあったのは特徴的でした。
2-5.両方の施設を経験した方の評価
これまでは現在利用している施設に対する評価でした。この結果でもおおよそのそれぞれの評価は分かるものの、もちろんこれは現在の施設に対する主観的な評価です。
ということで、この調査では学童クラブとプレディのそれぞれを経験した方を対象として、先程と同じ評価軸を用いてどちらの方が優れているについて回答していただきました。
その結果がこちらです。「学童クラブの方が優れている」という回答が緑系、「プレディの方が優れている」という回答は紫系としています。

見てのとおりで、全ての項目で「学童クラブの方が優れている」という評価が圧倒的です。「プレディの方が優れている」という回答はほぼありません。
評価指標は冒頭に書いたとおり、学童クラブの評価のためのものであることから学童クラブの方が優位になることは言ってみれば当然ではあります。ただし、一方でここまで差が開いているのはプレディが学童クラブの代替として機能していないということの何よりの現れであると考えられます。
中央区は学童クラブの定員が足りないという問題に対して「学童クラブをプレディと一体的に運営する」という答弁を繰り返し、学童クラブの定員を増やさないという選択をずっと続けたわけですが、少なくとも学童クラブとして利用したい層からすると代替にはなっていません。
2-6. 両者の比較(コメント)
上記の回答に対する補足のコメント抜粋です。
・プレディの項目にも書きましたが全てにおいて学童の対応が完璧でした
・不満だらけのプレディに対し、学童クラブは不満は全く無かったが、枠が少なすぎです。最初から入れないと諦めている家庭がかなりあります。
・土曜日の保護者会、個人面談など保護者と生徒に寄り添った運用がされている。おやつのメニューが配布されるのでどのようなおやつを食べているか保護者が把握できる。弁当の宅配など柔軟に対応していただける。職員と保護者で話す機会がある。(学童クラブ)
・入れるのであれば学童に入れたい。2年生で学童入れずに渋々プレディ、しかし内容に満足できずに行かなくなる、というパターンを多く聞いた。
・親の介入が少なくて済む(学童は保育園同様、父母会の活動負担が大きかったです。おやつが多くてよいという利点とは裏腹に、親が選定しなければならないという状況はどうにかしたかったですね、、会計係をやりましたが、それもとっても大変でした。。)(プレディ)
・上級生になっても利用できないことがないので大変ありがたい(プレディ)
評価結果と同じように学童クラブに対しての高い評価がある一方で、プレディには厳しい意見があります。ただ、一方で親の介入が少なくて済むこと、上級生まで利用し続けられることを挙げて、プレディに対して好意的な声も一部ありました。
3.今後の運営に対する要望
これまでの設問は現状に対する評価でしたが、最後は今後の運営に対しての改善要望です。様々なご意見をいただいてすべて読んでいただきたいのですが、ボリュームも相当にあるのである程度カテゴリ分けをした上で一部を紹介します。
3-1. 学童クラブへの要望
1) 定員枠の拡大
もっとも多かった要望は定員枠の拡大です。せめて小学校低学年の時期までは学童クラブに通わせたいが、多くは2年生の時点で利用できなくなることへの不満が多くあります。
定員確保に対しての区への疑念も多くの方が指摘しています。定住人口の増加施策を続けていれば当然にファミリー層が増え、需要は増えることはある程度事前に分かっているにも関わらず施設の増設などの受入への対応を怠ってきたのではないかといったような意見です。
★ 中央区には学童が圧倒的に不足している。同じ都心の千代田区より弱い。特に、特認校はプレディすらなく、特認校学区に住む職住近接の共働き家庭は、民間学童に高い費用を払っている。特認校を含めた全小学校内に学童を設置してほしい。
★ せめて小学校低学年の間は通いたかったです。 他区の私立小学校に通っているのもあり、プレディでは居場所がなかったので、学童に通い続けたかったです。
★ 既存の施設は良いのですが全体に施設数が地域の子供数に比して不足していると思います
2) 保護者の負担軽減
次に多かった要望は保護者負担の軽減について。中央区では学童クラブにおいて父母会が設置されていて、一部のイベント開催や保険の手続き、おやつの準備などの役割を担っています。この運営について負担があるので、それを学童クラブ側で担ってもらうなり、民間委託するなりしてほしいという意見です。
わたし自身、最初のおやつの選定はわりと大変でした。「1週間あたりの予算はN円で、その範囲内でN人分を生協のカタログから選定する」というミッションなんですが、ご存知のとおりお菓子はモノによって袋あたりの個数は違うので購入個数は違ってくるのでいちいち単価計算が必要だったり、いざ選定して合計してみたら全然足りなかったり思いっきりオーバーしていたり、そしてアレルギーへの配慮もしないとだったり。。。
また、利用者全体の会であるにもかかわらず、実態としては役員のなり手が決して多くないこと、そして役員となった一部の人に負荷が集中してしまうことへの不満も見られます。
長期休暇中の弁当に対する声もありました。学童クラブでは最近になって注文弁当が許容されるようになりましたが、おやつと同様にその発注の手間はあるのでそれに対してのさらなる対応への要望です。
★ おやつ・お弁当は港区のように区主導で導入していただきたいです。現在は保護者会が主導していますが、学童のスタッフの方々も色々な制約があり動きにくいのではと感じます。
★ 父母会で書記をやっていたので、紙からリスト作り、夜なべしてやりました。フォーム入力の仕組みがあると一発でまちがいもない、と思います。
★ 夏季休暇中のお弁当は業者に発注できますが、保護者が個別に1日ごとに発注をする形で、うっかり発注期限を過ぎてしまったり子どもがアレルギーで食べられないものだったりすると(現在2社が利用できますがどちらもアレルギー対応はありません)、お弁当を持たせることになります。全日お弁当を持たせるより助かることはもちろんなのですが、いっそ給食、副食を学童で提供してもらえたら、色々な点で安心だし本当に助かります。
3) その他
この他、上の2つほどではないにせよ要望として挙がっていたものはこちらです。
(手続きの簡素化/IT化)
★ 保育園と学童で区の提出書類がわずかに異なり、兄弟がいると二度手間なのは至急改善していただきたいです。
★ プリント類を電子ファイルでも配布して欲しい。
★ 学童と家庭間の連絡にICTツールの活用に力を入れて欲しい
(勉強へのサポート)
★ 一応学習時間は設けられていますが、勉強するもしないも子ども自身に委ねられているため、ほぼ機能していません。学童で宿題をやってこないと、18時過ぎに帰宅してからやるのは親子ともに結構な負担です。宿題をやるように促す仕組みをもう少し整えていただけたら嬉しいです。
(開館時間の拡大)
★ 8:30以降に登館してほしいと言われています。親の出勤時間のことを考えるとシビアな時間です。せめて小学校の登校時間(8:10〜)と同じであればとても有難いです。
(外遊びの増加)
★ せっかく公園も近いので、外遊びできる日が増えるとありがたいです。
★ 外遊びが出来ないので、学童に隣接する臨海公園で一日1-2時間遊べると有難い
3-2. プレディへの要望
今度はプレディに対する要望です。
1) スペースの改善
プレディへの要望としてもっとも多かったのは利用するスペースについてです。プレディは学童クラブと異なり定員を設けていない一方で部屋が無尽蔵にあるわけではないので、利用者が増えれば当然1人あたりの利用可能なスペースは狭くなってしまいます。
コロナ禍では利用制限があったことでマシになっていたようですが、緩和後は机も利用しづらいような意見もありました。また、スペースが狭いことにより、静かに遊びたい子どもと騒ぎたい子どもの棲み分けができないといった面もあるようです。
★ あまりに多い児童数が一部屋に入っているのを見てとても窮屈に感じました。日により利用人数の変動はあるかと思いますが多いときのパーソナルスペースが果たして配慮できるのか、又、夏休み中お弁当持参ということから利用者が少ないかもしれないが、注文弁当になった際は利用者も増える可能性があり、子供達の食べるスペースが充分足りるのかなどは心配しています。
★ プレディではうるさすぎて、聴力検査で再検査になる確率が高いという話しを聞いてます。大人たちの対応スピードの遅さにより、子どもたちへの健康被害が心配です。
★ 騒ぎたい子、静かに本を読みたい子などでお互い不満が募ったりするので部屋が分かれていたら良いのにと思います。お互い平和。子どもの世界でも住み分け大事だと感じます。
2) 施設スタッフの改善
次に施設のスタッフについて。このような意見は学童クラブの方にはほぼなかったのでプレディ側の特徴と言って良さそうです。
もちろん全員ということではないのでしょうが、回答によれば「大声で怒鳴る」「言葉遣いが荒い」「雰囲気が暗い」といったような資質に欠けるスタッフもいるようです。そのうえで、外部評価を求める声もあります。
★ 施設長が若く、失礼ですが、多数のスタッフを取りまとめたり、子供に合った対応をしていく経験が不足しているのではないかと懸念してしまいます。
★ 職員の怒鳴り声が何度も響いている、かつ言葉遣いも悪いようで、子供が行きたがらなくなっている。限られた空間に大人数が利用していてスペースが狭い。
★ プレディの先生の質を外部評価でしっかり確認してほしい。(ヒステリックな先生は何年もいるようです。なお、現在の在籍状況は不明)
★ スタッフはバイトなのか?所属が分からない。 雰囲気が暗いし子供の扱いに慣れている感じがしなくて不安
★ 先生の言葉づかいが悪い 映像ばかりみせてる
3) 長期休暇中の弁当への対応
具体的でかつ切実な願いとして多かったのが夏休みなどの長期休暇中の注文弁当への対応。学童クラブでは保護者の側からの働きかけによって最近になって対応可能になったものの、プレディではまだ一律で対応できないことになっており、これに対する不満です。
単純に準備するだけの手間暇の負担軽減という点に加えて、炎天下での食中毒防止という観点での意見もあります。
★ 宅配弁当をプレディでも利用できるようにしてほしい。学童では宅配弁当を利用できたにもかかわらずプレディでは利用不可。特に夏休みは例年に無い暑さの中での通学時の持ち運び、プレディの前に夏季水泳教室、サマースクールに参加する場合はどのような環境で弁当が保存されるかも分からず食中毒の点からも非常に懸念している。
★ 長期休暇のお弁当作りが大変。学童のように仕出し弁当の利用がてきるとありがたい。
4) おやつ提供の改善
次に、おやつの提供についての要望。学童クラブとプレディで大きく違っているのがおやつの時間。学童クラブでは15時頃におやつの時間となっていますが、プレディの場合には17時頃。
17時がプレディの中での1つの区切りの時間帯で、それ以降も残る子どもに対しておやつを提供するという建付けのようですが、そうなるとその時間帯まではお腹を空かせることになり、それが耐えられない子どもは早めに自宅に帰るしかありません。また、その時間で食べるとなると、晩ごはんに影響がある場合もあります。
この他、その調達は学童クラブと同様に保護者が担うことになっており、その運営の大変さについての意見もありました。
★ おやつが17時まで食べられない理由が分かりません。そのため、16時下校になってしまっています。帰ってくるとすごくお腹をすかせている様子で、不憫です。
★ おやつの時間が17時以降だが、家庭での夕食時間を考慮すると前倒しして欲しい。
★ おやつの提供は保護者負担ではなく、利用料を支払うので区で対応して欲しい。
★ おやつを親が調達するのは今時普通なのでしょうか(予算も一食50円と区が一方的に定めており、結局日持ちのする駄菓子ばかりになります)。区の財政として、業者のサービスの質向上をすることはできないのでしょうか。
5) その他
この他、要望として挙がっていたものはこちらです。保護者の負担軽減や手続きの簡素化/IT化、開館時間の拡大など、学童クラブの方と共通する要望もあります。
(保護者の負担軽減)
★ プレディの利用票の保護者の記入は、保護者の手書きのサインが必須で判子の捺印は不可です。一方、学校での担任の先生への連絡は、保護者印を捺印する欄があり、印鑑が原則です。細かすぎる独自ルールは止めて、少なくとも小学校と統一した運用をしていただきたい。
★ プレディの利用日は利用票を子供に持たせることになっているが、webから入力・提出できるようにしてほしい。
★ 長期休暇中は上履きを毎回持参させず、学校内なので自身の下駄箱を使わせて欲しい。(持ち帰った上履きを翌日弁当と一緒のリュックに入れるのが不衛生なため手持ちになり煩わしい。)
(手続きの簡素化、IT化)
★ 区からの案内にあった、おやつの会、連絡帳はほぼ機能していません。実態の伴わないサービスを委託するより、tetoruのような連絡アプリを全体で導入したり、塾のようにカードなどで入退館を管理するなどDXを取り入れ、中抜けも含めた柔軟な利用を可能にするとともにスタッフの事務作業にかける時間をこどもたちのためにふりわけてほしいです。
(開館時間)
★ 夏休みのスタート時間が遅く、学校の下のベンチで待たせることもある。8時からだといいなと思う。
(外遊び)
★ お外遊びがもっと沢山出来る環境を望みます。
(遊具の充実)
★ 知育玩具は増やして欲しい。将棋、囲碁、チェス、カプラ、百人一首くらいは置いてもよいのでは?
3-3. 民間学童に関する要望
今回の調査では民間学童の利用者の方も回答していただいています。この回答から分かることは、学童クラブの待機を見越して自主的に民間学童を利用している層の存在です。
民間学童は公立の学童クラブのように必要性に応じた利用調整が行われるわけではないのですが、毎日通うとなると10万円以上といった多額の費用が
かかります。したがって、その利用に対する補助や、2023年4月に初めて設置された「ベネッセ学童クラブ月島」のように民設民営の学童クラブのさらなる誘致を求める声もあります。
★ 周りの保育園の方をみても、2年生以降に学童に入れない実態から諦めて民間学童を最初から申込みしている。我が家も同様。無料でなくて構わない。月3、4万円の負担に抑える形で区が運営をしてほしい。民間学童は月10万円程度かかり、負担が大きい。学校から遠い場所に学童が設置されており、送迎がないことも不安要素である。(晴海5丁目など)保育園と同様に認可学童のような形で店員を増やしていって欲しい。
・区立学童に落ちた子が民間学童を使う際の補助金支給の検討をお願い致します。
★ 2年生以降、4年生頃までの十分な学童保育環境を確保するために、1年生からフルで民間学童に通っています。費用負担は大きいですが、施設には満足しています。一方で、公費援助はなく全てが自己負担になっていること、公立学童の不足に不満がある統計に自分たちが入っていないことは残念です。
3-4. 区政の運営全般に関する要望
上記にカテゴリに当てはまらないものとして、区の放課後対策全般に対する不満と要望も多数ありましたので主要なものを紹介します。
やはり多いのが、これはわたしもこれまで何度も発信していることですが、このような待機児童の状況を招いたのは区の計画がずさんだったためではないかという点です。保育園の利用者が増えれば将来的に学童クラブを利用を希望する人が増えるのは道理です。そして、保育園の利用開始からは5年以上もあるわけです。
この他、学童クラブやプレディの違いや状況などについてもっと情報発信してほしいこと、そもそも区として実態調査を行うべきといったご意見もありました(まったくもってそのとおりです!)。
★ 学童の定員拡充。人口動向は遥か前からどうなるか知っていたはず。対応できないのは怠慢では?
★ 中央区は、取り組みが進んでいる他区があるのにできない言い訳はやめてほしい。やるために何をするかをきちんと考えてほしい。
★ 昨年度から長期休暇のときに注文弁当が利用できたのは助かったが、父母会が手を尽くして実施に至った。職員は事勿れ主義の前例踏襲で家庭への歩み寄りが感じられない。
★ 中央区はこれだけファミリー世帯を入れている割に本当に子育て支援を軽視していると思うので、ハードやソフトを揃えてから流入させて欲しい
★ 現状だと、リアルのママ友がいない自分のような人間は何も情報を仕入れられない。もっとネット上で情報を得られるようにしていただきたいです
★ 区として、実態調査をすべき
4. 今後、早急に実施すべきこと
最後に、これらを踏まえて今後早急に実施されるべきことについてまとめます。これは、以下の4点と考えています。
学童クラブの定員枠の拡充
特認校を含む全校でのプレディプラスの早期導入
民間学童のさらなる誘致
プレディのさらなる運用改善
施設スタッフ/スペースの改善
長期休暇中の弁当対応、おやつ提供時間の改善
保護者負担の軽減
おやつ/イベントなどの父母会負担部分の委託
利用にかかる手続きの簡素化/IT化
民間学童補助の導入
学童クラブを希望して利用できなかった家庭への費用補助
最後に
今回の記事では、先日まで実施していた「学童/プレディ実態調査」の結果についてまとめてきました。総じて言えることは、ある程度は分かっていたことではあるものの、
現状のプレディは学童クラブの代替とはなり得ていない!
という1点です。同じ評価軸で双方の施設を評価していただいた結果の差は明白です。そして、それぞれの施設を経験された方からの評価についても同様です。
これまで中央区は学童クラブの定員足りない問題についてプレディで補うという運用を続けてきたわけですが、その結果がこれらの声として現れています。
中央区にはこれらのひとつひとつの声にぜひ耳を傾け、今後の中央区の放課後対策がさらに充実することを強く要望していきます。先日、さっそく担当部署の方に取り急ぎ結果を報告して早期の対応をお願いしたところではありますが、それだけで物事が進むほど甘い世界ではありません。粘り強く現状の課題と早急に何を実施すべきかについて継続して訴えていく必要があります。この点については引き続き発信していきます。
最後になりますが、これまで多くの方々の協力なしに、この調査は行えませんでした。調査内容や項目に相談に乗っていただいた有志の方々、SNSで拡散していただいた方々、そして回答していただいた方々。本当にありがとうございました。
超余談なんですが、1件質問いただいたので。なんとなく最初から最後までこの調査のアイコンとして使っていたカエルの絵。「ダ鳥獣ギ画」という鳥獣戯画をモチーフにしたイラストをフリーで公開いただいているサイトから拝借しております。特に意味はなくて、「キャッチーな何かがあった方が良いかな」くらいのノリでした。カエルさんもありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
