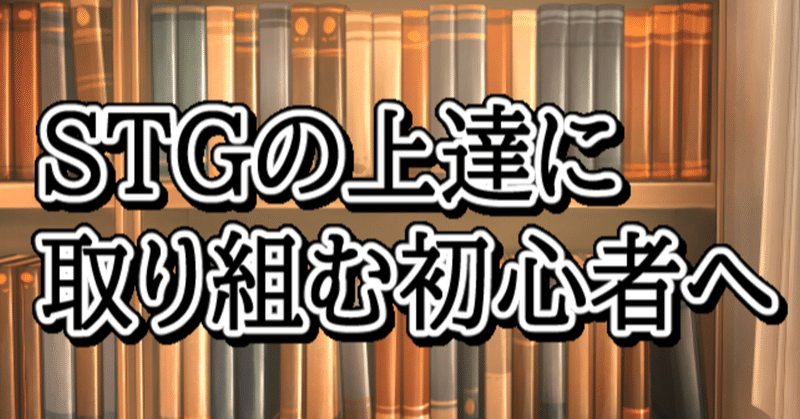
【STG初心者が上達するには?】STGを上手くなりたいと思った時に意識するポイント
この記事は私、夕姫が20年弱に渡って2Dのシューティングゲーム(主に弾幕STG)を遊んできた中で、初心者から今の上級者と呼ばれるような立場になるまでの中で考えたこと、上達を目指す初心者・初級者の方に向けた話をまとめています。
また上級者の方は、始めたての方や上達途中の方にアドバイスを求められた際に、こういった視点を持って言葉をかけてあげて欲しいという思いを込めた文章にもなっています。
少々長いですが読んで頂けると幸いです。(約8000文字あります)
※この記事の本文は、2021年5月に頒布された同人誌、東方花映塚攻略本『DEHANA』に寄稿した内容を改変無くそのまま記した文章となっています。
※記事内に東方花映塚に関する用語など出てきますが、基本的には一般的なステージクリア型STGの文法に則った話をしています。
※
本文の前にまず断っておきますが、STGの楽しみ方は攻略が全てではありません。
操作感を楽しむ、派手な画面を楽しむ、世界観を、BGMを楽しむ、色々あり自由に遊んで良いゲームです。それらを否定するものではありません。
しかしその中で、上手くなりたい!より深い攻略を楽しみたい!という方に向けて、今の自分が贈れる文章を書いたつもりです。よろしくおねがいします。
※
はじめに
STG初心者が上達するには?というトピックには、おそらく数多の人が意見を持っていて、それぞれ自身が上達した経験を元に語られたりするものだったりします。
人によって上達までの過程、上達へのモチベーションは千差万別で、またそれを自分以外の誰かに体系的に伝えるのも難しいため、誰が言う言葉が正しいかというのは一概には決められません。
そのため本稿は私自身が考え、伝えられる範囲のものであり、一つのコラムとして楽しみ、参考にしていただければ幸いです。
初心者へのアドバイスについて
経験者が初心者に対してアドバイスをする際、おそらく耳タコなレベルでよく聞くフレーズがあります。
「とにかく基礎を練習しろ、数をこなせ」です。
ゲームにおいても、例えばスポーツ、芸術芸能、どのジャンルに行こうがこれを聞きます。
初心者がこれを聞いてモチベーションが上がるわけがないのですが、実際この言葉は結論としてこうなってしまうのであって、確実に正しい意見です。
本稿でも結局のところ、最終的に結論はこの言葉に収束してしまいます。
しかし、これは決して突き放した言葉ではなく、ここに収束する理由、理屈があります。
その一つ一つを説明するには膨大な項目が必要となり、往々にして説明が省かれがちであるため、受け手には壁を感じる言葉になってしまっています。
そのため、今回はなるべく具体的な指標、意識の持ち方を語りたいと思っています。この言葉に含まれる意味を自分なりに噛み砕き、ぜひモチベーションを上げていって欲しいです。
ゲーム固有の攻略と地力
STGにはそのゲーム特有のシステムや攻略の視点があります。
特に花映塚のような特殊なシステムの場合、その部分の習得による伸びしろは絶大です。
しかし、固有の攻略方法にも、実行難易度というものがあります。
「頭では分かっているが、なかなか実行できない」
RPGのようなジャンルと違い、初心者が攻略を見ても躓くところはここではないでしょうか。
(STGの攻略記事があまり出回らないのもこの点が大きいのではないかと考えています)
花映塚は「上手い人の真似をする」というのが視覚的に分かり辛いという点も、通常のSTGとは違う特徴的なところです。
状況が刻々と変化するため、再現性のある状況でパターンを固定することが難しく、その時の画面状況やプレイヤーの判断から動きを読み解く必要があるからです。
つまりゲーム固有の攻略も、自身で噛み砕いて身に付けていく力が必要となってきます。
そしてそれができるかどうかは、本人の現在のSTGの能力(=地力)次第です。
もちろん片方の能力だけがあっても十分ではないので、両面から攻めることが重要です。
片方に行き詰まったら片方を伸ばす意識をするのでも良いでしょう。
意識さえしていれば徐々に伸びていきます。
意識がないと伸び悩んだところで止まってしまいますので、思考は大切です。
STGの基本
STGというジャンルは、いわゆる"地力"がすべての下地になります。
地力は「自機移動精度」「弾道予測能力」の2つに大別されると考えています。
この2つを合わせると、弾幕STGにおいては単に「避け能力」と呼ばれたりするものになります。
これらは短期間で得られるものではなく、本当に少しずつ、少しずつの積み重ねで上達していくものなため、その心構えが大事です。
操作精度について
STGにおいて最も重要、かつ上手さの指標と考えている能力に、自機の操作精度(移動精度)があります。
自機を画面内で自在に動かせる力のことで、ちょん避け・位置取り・移動の全てに必要な能力です。
通常初心者であればあるほど自機の移動感覚に自信がなく、自機を見つめたまま移動させて現在位置を把握するという形になりがちです。
移動精度に自信がつき、コントローラーの入力と自機の移動が頭の中で一致するようになると、自機位置の確認は時々、もしくは周辺視野のみでできるようになってきます。
自機移動感覚が正確になると「自機から目を離せる」時間が増える、つまり自機以外のところに注意を向けられる時間が増えるわけで、画面把握や弾道予測など、全て先の行動に繋げることができます。
つまり、ある意味では自機操作ができてようやくゲーム固有の攻略に取り掛かることができるのであり、自機操作精度の上達は全ての根幹に関わる最初の一歩でもあるのです。
「ゲームが上手い人」というのはつまり「入力デバイスの操作が上手い人」に他ならない、というのが私の持論です。
そして、ここが上手くなってくると、ゲームに取り組むのがより楽しくなります。
ゲーム内と脳内が直結し、思い通りにキャラを動かせることにより、視野を広げられる。
誤操作による予期しない被弾などのストレスが減り、理不尽な怒りが減る。
たとえ被弾しても今のは予測が甘かったなときちんと反省できる。
つまりメンタル管理にもなり、結果的に精神的な疲弊が減り、長時間プレイもできるようになります。
長時間できれば当然時間を掛けることになるので上達に繋がり、上達により今まで頭で考えながら行っていたことが無意識にできるようになります。
空いた脳のリソースで更に一歩先のことを考えることができるようになり、できることが増えると楽しくなり、上達することが楽しくなるといった正のスパイラルの完成です。
上達の楽しささえ感じられるようになれば、後はもう勝ったようなものです。
操作精度のトレーニング
自機移動感覚の向上には、コントローラーの入力と自機移動幅のフィッティングが重要になります。
自分が指先でちょんと押した入力に対して、画面内の自機はどのくらい動くか、というのを把握します。
なぜちょん押しかというと、長めに押しっぱなしにする移動は移動量の把握が非常に難しくなるため、目視による自機位置確認がほぼ必須となり、自機から目を離したままの移動が難しいからです。
ちょん押し1回でどれくらいの幅移動するかの感覚が掴めれば、ちょん押しを1単位とした移動ができるため、それを2回、3回と押した場合の移動量も単位的に理解しやすく、目を離したままでも自機位置が把握しやすくなります。
スーッと移動するのでなく、トントントンといった移動の方法を心がけてみましょう。
おそらくほとんどの人は無意識にこのような移動を繰り返していたりします。
最小ちょん避け入力の反復練習をするのも良いでしょう。
感覚が掴めてくれば少しずつ1回の移動量を増やしていって、長めの距離もいつしか自然に動かせるようになります。
あえて自機から視点を外したまま、なるべく長く操作してみるトレーニングも有効です。
最初は不安だと思いますが、少し背伸びしたことも定期的にやっていくと、だんだんと慣れてきて自在に動かせるようになってきます。
当たり判定の把握
もちろんですがこれも非常に大事です。
自機グラフィックのどの辺りが判定か、弾は種類ごとにどこまで重なったら被弾するのか、というのをきちんと把握します。
自分からぶつかって行き、ギリギリ当たる場所、ギリギリ当たらない場所を確認して見極めます。
これと上記の移動精度が組み合わさることで、自機の感覚的な把握が完成します。
これができると、自機を自由自在に動かせるのももちろんですが、被弾の理不尽感を減らすことができるので、無用なストレスを軽減することができます。
当たり判定の感覚がズレているために「えー今の当たって無いでしょ?」といったどうしようもない不満が出てきてしまうのが初心者時代ではありがちです。
被弾した場合に原因をしっかり自認して振り返ることができれば上達への正しい足掛かりとなります。
弾道予測能力について
自機操作と並んでSTGで重要な能力は弾道予測です。
弾を避ける、また花映塚では弾消しのためにも軌道を見極める必要があります。
設置系の弾への意識は別として、基本的には弾が自機に当たる軌道であるかを見極めるものです。
当然自機は刻々と動かしていくものなので、「自機の移動量」+「弾の予測地点」の相対位置を考えなくてはいけません。
これが初心者のうちは、自機を見る→弾を見る→自機を見る→弾を見る、という形で交互に行わなくてはならず、弾道の認識に時間が掛かります。それゆえ弾量が増えてくると処理しきれずそのまま押しつぶされるといった形になってしまいます。
ここで自機の移動量が感覚的に把握できていれば、弾道予測にある程度集中することが可能です。
前項で操作精度が最も重要と言った理由はここにあり、自機移動感覚が正確になると「自機から目を離したまま」でいられる時間が増えます。
つまり自機以外のところに注意を向けられる時間が増えるわけで、弾道予測、画面把握、スペルポイント把握など全ての"次"へ繋げるための下地となるわけです。
弾道予測のトレーニング
この能力はまさに経験によって積み重ねで育てていく他ありません。
おそらく単発の弾だけを見つめられる状況であれば、軌道予測がよほど難しいということは無いかもしれません。
難しいのは何発も同時に襲い来る弾幕を断続的に処理しないといけない状況であり、弾幕STGではそれが基本にもなっています。
この際に意識するポイントは「見るものを絞ること」です。
初心者は自機周辺を集中して見てしまいがちです。
これは自機操作に不安があるからでもありますが、自機周辺に視界が絞られているので、狭い範囲の弾だけに集中していられるからでもあります。
見る範囲を絞っているため1発2発の弾の軌道であれば認識できますが、画面上に何十発とある無数の弾の軌道を同時に処理しようとするとキャパオーバーになり、一つも軌道が分からなくなります。
これはたとえ上級者であっても同様で、多数のものを同時に処理するのは基本的にできません。
イメージとしては、人はマルチタスク処理でものを同時に処理する能力が弱く、シングルタスク処理を常に順繰りに割り当てて多数のものを処理している形です。
人の処理できる能力には限界があり、個人差もありますが、弾道予測においてはたとえどのような上級者でも同様の処理を行っています。
そしてこれを行うためには「見るものを絞ること」が弾幕処理において非常に重要です。
これはランダム弾でもパターン弾でも、全ての弾幕で有効な意識すべき点です。
例えばざっくり10発くらいの弾が降ってきた場合、最初に瞬時に大雑把な方向が把握できれば、自機近くに来ない軌道の弾はもう"見なくてもいい弾"になるので、向かってきそうな1,2発のみに集中して軌道予測の精度を上げることができます。
「弾を見ないこと」が弾の軌道予測の向上と同等、もしくはそれ以上の意味合いを持ってくるわけです。
精度が高い予測ができるなら先読み行動ができ、次は自機をこう動かそうというキー入力ができ、ではそこに移動した場合他の弾が重なってこないかという更に先読みの軌道予測をしに行けます。
弾避けが上手い人というのは、このシングルタスク処理の繰り返しを断続的に、更に瞬間的に繰り返しできる人のことです。
上級者がものすごい弾幕の中をスイスイと掻い潜っているようなプレイでも、実際はほとんどの弾を見ておらず、要点だけをギュッと集中して見ているわけです。
その他のアドバイス
視点のパターン化
弾道予測にあたって、意外と重要なのが視点の位置です。
つまりモニタに対する顔の位置、距離感です。
普通にゲームをするのであれば、モニタの正面に座って正面から見るのが普通でしょう。
しかし例えば、画面の下側から覗き込むように上を見上げるような姿勢で見たらどうでしょうか。
画面の下側をメインに見ることになり、下部は見やすく上部は多少見辛くなるかもしれません。
画面の左寄りから、あるいは右寄りから見たら、見やすくなるポイントと見辛くなるポイントがそれぞれ出てきます。
また、画面に思い切り顔を近づけて見たらどうなるでしょうか。
細かい部分が見やすくなる代わりに、周辺視野はほとんどカットされます。
つまり弾道予測の話における「見るものを絞る」ことを強制的に行うことができます。
顔を大きく近づけてみると小さい弾、細い隙間などへの反応力が非常に上がります。
例えば花映塚では「高速で狭い弾幕である霊夢C2の隙間を避けるときにだけぐっと顔を画面に近づけて見る、避けたら元の位置に顔は戻す」といった視点のパターン化を自分の中で作って攻略の形としておくのも良いです。
花映塚なら他にも自分の得点を見る、相手の得点を見る、白弾の送られてくるタイミングを見るといった行動をどのタイミングで行い、どのように視点を持っていくかという「画面の状況に左右されない視点のパターン化」という意識を一度持ってみると良い形が見つかるかもしれません。
とにかく色んな角度、視点から一つのものを見つめてみるのは新しい発見にも繋がるので効果的です。
プレイ環境 - コントローラーについて
ありあわせで何とかしている人はやはり多いですが、自機操作精度に関わるコントローラーが自分に合っているかどうかは非常に重要です。
人によって千差万別のコントローラーですが、例えば私はプレイステーション型のコントローラーは十字キーが苦手なため、操作精度が幾分落ちます。
アーケードで何年かSTGもやっていたのでアーケードスティックの経験もありますが、そちらもどうしても思い通りの自機軌道が描けず、肌に合いませんでした。
逆に東方からSTGを始めたがアーケードスティック操作が合うようになり、後にアーケードシューティングゲームで全1タイトル持ちにまでなったような知人も居ます。
ものすごく操作精度の高いキーボードプレイヤーも居ますし、何が自分に合うかは試してみないことには分かりません。
自分に合った良い道具を使うことで、思い通りの操作がしやすくなります。
それは自機移動へ割く意識負担の軽減に繋がり、プレイ中の視野を広げることにもなります。
上達効率が上がるので、初心者ほど良いコントローラー探しをしておくことは助けになると思います。
プレイ環境 - モニタについて
これは意外と見落とされがちな点ですが、ゲーム中はモニタの輝度を上げると弾の認識力が上がり、かなり良い効果が見込めます。
PC用のモニタでは、基本的にブラウジングなどで日常的に使う場合、あまり明るくすると眩しいため、大抵の人が明るさを抑えています。
その設定のままゲームを起動すると、少々沈んだ色合いとなり、知らず識らずのうちに夕暮れ時のような見辛い画面を見ているかもしれません。
設定で、明るさ、コントラスト、輝度などの項目を上げてみて、標準より明るい画面で一度プレイしてみてください。
毎回切り替えるのは面倒なので、普段使いとゲーム用にプリセットが設定できるようなモニタであれば良いのですが、こればかりは物によります。
もしかしたら見違えるほど見やすくなるかもしれないので、できれば一度試してみて欲しい項目です。
動画やリプレイファイルを見る
自分がプレイしていると操作することに意識を取られているので、プレイ中には気づけないことが多々あります。
そういった点を客観的に見る方法として動画やリプレイファイルがあり、他人のプレイを見ていると色んなことに気づくことができます。
岡目八目というやつですが、これの効果は絶大なので、他人のプレイ、自分のリプレイや録画は見返してみると良いです。
自分のプレイを見返すことは、自分の操作の記憶+その時の画面状況がよく見えることで、ゲームメイクへの理解力がかなり高まります。
特にこれは花映塚以上にオーソドックスなSTGの攻略において絶大な効果を発揮します。
ただただプレイを繰り返すことだけが上達のための唯一の道ではないことも覚えておきましょう。
効率を求めるなら反復練習
練習効率ですが、基本的には単一のことを、短スパンで反復練習するほうが身になることがほとんどです。
例えば1~5面の通しプレイを毎日2セット5日間するよりも、各面繰り返し10プレイを5日間日替わりで行う方が上達しやすいです。
もちろん後半面のほうが難しいので割り振りは後半面重点が良いです。
ある意味一定期間は結果が出せないのでモチベーションとの兼ね合いもありますが、この意識を持ったほうが最終的にバランスよく上達します。
特に最初のうちほど多くのことを一度に覚えられないので、習得があやふやなまま次へ次へとやっていると、通しで見たときにどこが良くてどこが悪かったかというポイントが自覚し辛くなります。
自分の苦手を洗い出し、重点的に練習すべき点を自覚することが大事というわけです。
花映塚であればキャラ別練習、特定の状況下での動き方と意識の割き方の練習に当たるでしょうか。
おわりに ~ 上手くなるために
STG能力の基礎となる自機移動精度も、弾道予測能力も、一番基本的なところはやはり回数をこなして体に染み込ませることが必要です。
ここに来て最初に挙げた「とにかく回数をこなして練習しよう」に戻ります。
ただ闇雲に言うのではなく、意識の持ち方やステップアップのビジョンは多少示せたかと思います。
しかしここまでの話も、すべての人に当てはまるセオリーかどうかは分かりません。
認識力や処理能力にはたとえ鍛えたとしても個人差があり、上達過程にも個人差があります。
それを忘れないようにしてください。
他人より上手いか上手くないか、ではなく、過去の自分より上手くなった今の自分、というのを意識しましょう。
「できなかったことができるようになる楽しさ」
これが全てといっても過言ではありません。
そしてこの上手くなるための基礎について最も重要なことなのですが、これらは別に花映塚でやらなくても良いのです。
これはSTGというジャンルの良いところで、何をやってもすべてのSTG能力の下積みとなって経験が一切無駄にならないのです。
これを体感できるようになると、どんなSTGを遊ぶときでもモチベーションが湧いてくるようになります。
なんなら同じ操作デバイスを使うのであれば、アクションゲームのようなものだって良いのです。
間接的にSTGが上手くなる、間接的に花映塚が上手くなる、そう考えることで、ゲームを楽しんでいるうちにいつの間にか上達しています。
STGは上手くなればなるほどできることが広がり、楽しめることが増えていくジャンルです。
上手くなること、成長すること自体が楽しいと感じられるようになればもう後は無敵で、いくらでも上達するし、どんなゲームでも楽しめるようになります。
今少しでもSTGが楽しいと思えているのであれば、それは才能です。
楽しいと思える才能を存分に伸ばしていってください。
出典
【花映塚攻略本】DEHANA
https://dehanac99.tumblr.com/
https://booth.pm/ja/items/2906695
おまけ
この記事について読み上げながら少し補足した内容を語った時の配信アーカイブになります(2021/12/07)
記事がどこかの誰かの役に立っていれば幸いです。
