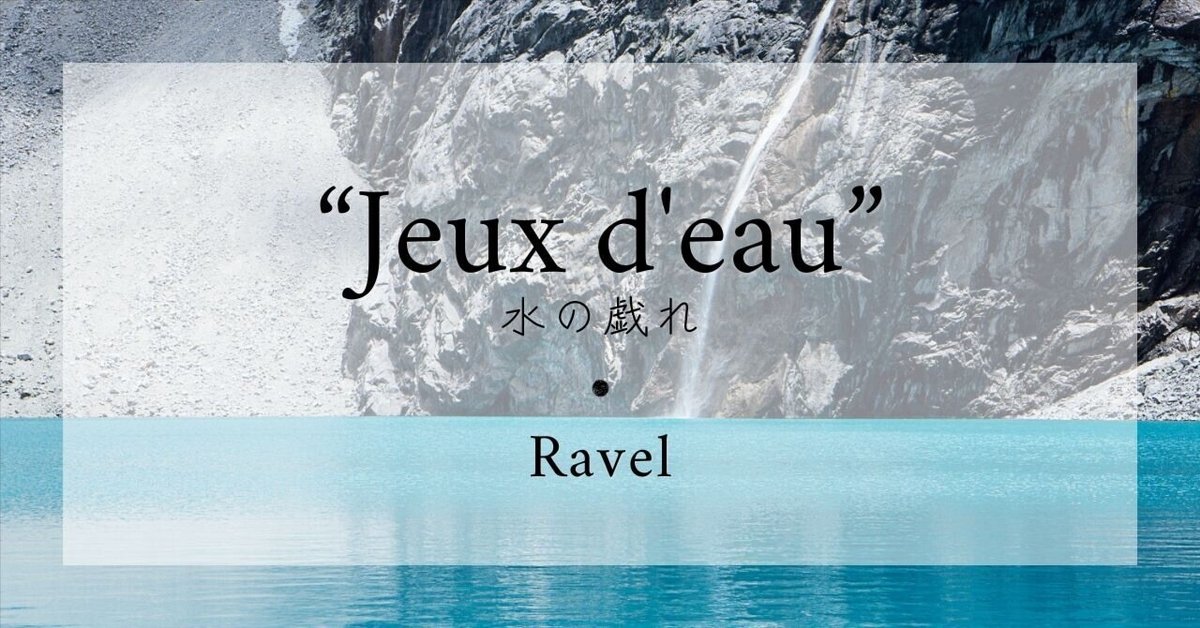
水の音楽・ひんやり清澄な水【クラシックピアノを聴いて感性を磨く】
こんにちは!yukiです。
今日は、
「クラシックピアノを聴いて感性を磨く」
シリーズの3回目です。
クラシックに馴染みのない方も、
気軽に楽しめるように書いています!
今回取り上げるのは、
フランスの音楽家・ラヴェル作曲の、
「水の戯れ」。
幻想的な音世界を
楽しめる作品です。
それでは、どうぞ!
【この企画への想いはこちらに綴っています】
水の戯れ
さっそく、演奏動画を紹介しますね。
ラヴェル作曲、「水の戯れ」です。
ひんやりと澄んだ水が、
するすると流れたり、
跳ね上がったり、
変幻自在に変わっていく情景が
目に浮かぶようですね!
東洋の雰囲気
僕は、この曲から
東洋的な雰囲気も感じます。
どことなく、
“水を用いた東洋の儀式”
が頭に浮かんでくるのです。
終盤では、“浄化”を感じます。
日本でいったら、
「禊(みそぎ)」でしょうか。
ラヴェルは東洋の文化に深い興味をもち、
インスピレーションの源としていました。
実際、この「水の戯れ」でも、
東洋各国の民族音楽で使用されてきた
音階が使われているのです。
その音階は、
5音音階といいます。
5音音階とは、
ドレミファソラシドのような
7つの音ではなく、
5つの音で作られた音階。
民族により多様な組み合わせがあり、
日本だと「ヨナ抜き音階」や
「琉球音階」が有名です。
5音音階の特徴は、
自由な組み合わせで音楽になる
ということ。
ピアノやキーボードをお持ちの方は
ぜひ試してほしいのですが、
ピアノの“黒鍵だけ”を使って、
音とリズムを自由に組み合わせて
弾いてみてほしいのです。
すると、
なんだかアジアっぽい音楽になるはず。
知っている童謡や唱歌なども
奏でられるかもしれません。
その理由は、黒鍵の5つの音が、
まさに5音音階になっているからです。
(全くピアノを弾けない方も、
ぜひ試してみてくださいね!
簡単に即興演奏ができますよ。)
ちょっと話がずれましたが、
「水の戯れ」を聴いて、
「何だか東洋っぽい」
と感じられる部分があるのも、
こんな理由があるのでしょう。
超キッチリさん
第1回のドビュッシー、
第2回のセブラック、
そして今回のラヴェル。
この3人は、
同時代に生きたフランスの作曲家です。
各人の水の音楽を紹介しましたが、
はっきり個性が異なるのが面白いですね。
ドビュッシーは、
輪郭をぼかした印象派的な音楽。
セブラックは、ロマン的な音楽。
そしてラヴェル。
斬新なハーモニーやリズムを使いながらも、
輪郭がはっきりした音楽です。
ラヴェルは、
かなりのキッチリさんでした。
私生活では、
いつもフォーマルな服と香水をまとい、
美術品に囲まれながら暮らす紳士。
音楽においても、
「スイスの時計職人」
とあだ名をつけられるほど、
緻密で完璧な作品を作ったのです。
そして、作品が完璧であるがゆえ、
演奏者にそのバランスを崩されるのが
許せなかったそう。
音楽には、
「ルバート」
という表現方法があります。
これは、演奏する人の裁量によって、
テンポを早めたり緩めたりするもの。
ラヴェルは、
ルバートすら許せなかったのです笑
しかしルバートが全くないと、
機械的な音楽になってしまいます。
ではどうしたかというと、
“テンポ通り”に弾けば勝手にルバートっぽく
聞こえてくる書き方をしたのです。
「私の作品を弾くピアニストは、
書いてある通りに弾けばいいのですよ」
でもそれだと演奏の自由がないんじゃ…
と思う人は当時からいました。
そんな人に対して、
ラヴェルはこう言ったそう。
「ピアニストは、
作曲家の奴隷ですから」
奴隷ですか笑
ともかく、
そんな性格のラヴェルが作った作品は、
演奏者があまり自由にやりすぎると
妙な感じになってしまうのです。
この「水の戯れ」もそう。
感情は入れずに無機質に弾くと、
作品の良さが出てくるのが面白いですね。
(「無機質」と「音楽的でない」は違います!)
真似しちゃう人
「水の戯れ」の表現技法には、
多くの作曲家が影響を受けたようですが、
ドビュッシーもその1人です。
「水の戯れ」の中間部、
一番盛り上がるところ。
(先の動画の2:30あたり〜)
ここを聴くと、
「すごっ!」
ってなりますよね。
ドビュッシーはその効果を、
自分の曲の中で真似しています。
同じ音型をくり返して緊張を高める
両手で交互に連打
最高音域から、一気に最低音へ
上記のような盛り上げ方を、
「喜びの島」という作品の
クライマックスで使っているのです。
(次の動画の6:00あたり〜)
もちろん、効果は抜群!
両作品とも弾きましたが、
「そっくりじゃん、これ笑」
って思いました。
他にもあります。
「水の戯れ」の終盤、
高音域で細かい音が動き、
低音域でメロディーが奏されるところ。
(先の動画の4:50あたり〜)
ドビュッシーはこの効果を、
組曲『版画』の「塔(パゴダ)」で
取り入れています。
(次の動画の3:50あたり〜)
人のアイデアを抽象化して
借りるのは便利ですが、
これは少しあからさまな気もします笑
まあ、「水の戯れ」は、
真似したくなるほど魅力的な
作品だってことですね!笑
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました!
それでは、今日もよい1日を!
(今回のカバー写真は、
ペルーアンデスの湖でした!)
【関連記事】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
