
【前編】超個人的 音楽アルバム10選 〜普通のLP編〜
みなさんは普段、音楽を如何様に聴いているだろう?今の時代、大抵の人はスマホやPCでサブスクをメインに使っているのではなかろうか。かくいう私もSpotifyユーザーである。月額1,000円程度で世界中のあらゆる音楽を聴き放題。好きな曲を聴いていれば、勝手にAIが新たなおすすめを提示してくれる、とんでもない時代だ。
しかし、こんな便利なサブスクにも難点がある。目的の音楽に直ぐに辿り着くアクセス性の良さ故に、好きな音楽だけを聴くようになり、どうしても『偏食』になってしまうのだ。
私も今年で20代後半に入る世代。
流行りの音楽に最も多感だった中高生時代の音楽の聴き方と言えば、TSUTAYAでCDを借りてきて、PCを経由してWALKMANやiPodに取り込む、というものだった。名付けるとすれば、『アルバム5枚千円レンタル世代』。同世代の音楽好きな皆様なら、この限られた5枚を如何に選ぶか、毎回頭を抱えていたに違いない。
要するに我々は、「音楽をアルバム単位で聴いていた末期の世代」である。アルバムリリースはアーティストにとってもおそらく一つの集大成であり、活動の節点でもあっただろう。必然的に、その時代の各アーティストの気概や有様が現れてくるものなのだ。
まえがきが長くなったが、今回はこれまでに出会った音楽アルバムの中から、1曲目から最後まで聞き通した時に身震いしたような、アルバムという1つの芸術作品として深い味わいのあるものを、必死に絞って10選としてご紹介させて頂こうと思う。
①夕風ブレンド / スキマスイッチ

初手では万人受けを狙って安牌を配置、誰もが知っているであろうスキマスイッチの作品から1枚。
このアルバムのリリースは2006年の11月末。小学生の時、親の運転する車の中で、前作の空創クリップと併せて何度も繰り返し耳にしていた。
このアルバムで特筆すべきは、なんといっても全体的にどこかアンニュイな雰囲気が漂っていること。「全力少年」のようなめちゃくちゃ明るい曲もなければ、「奏」のような“ザ·バラード”のような曲もない。いつ何度聴いてもその独特な空気感に引き込まれていってしまう。
最後が「1+1」で〆られているのも、このアルバムが非常に印象深く残る要因の一つではなかろうか。ピアノ伴奏に歌声だけというこのアルバムの中で最もシンプルな編成での演奏。これから国民的アーティストの道を駆け上がっていくお2人の覚悟と気合いが強く現れている作品のように感じられる。
②猛烈リトミック / 赤い公園

「好きなバンドはなんですか?」と聞かれた時に真っ先に答えるのが赤い公園。そんなバンドに出会った最初の1枚がこのアルバム。
1曲目は「NOW ON AIR」。この曲は、赤い公園が世に大きく広まるきっかけとなった言わば代表曲的ポジションでありながら、実はシングル曲ではない。つまり、おそらくそれまでの赤い公園史上、最もポップでキャッチーな曲だったであろう。アルバムの幕開けとしても、新たなリスナーも取り込むためのつかみとしても、完璧に役割を果たしている。
しかしそうして作られた赤い公園のイメージも、2曲目にして早速崩壊する。
「絶対的な関係」。
たった1分40秒の超短曲でありながら、ギターもベースもありえない歪み方をしている。そんなロックな曲に乗っかってくる鉄琴と囁くようなコーラスが、なんとも不気味な雰囲気を醸し出している。
その後の3曲は再び比較的ポップで耳馴染みの良い曲が続くが、そこに6曲目の「私」がやってくる。この曲のポイントは静と騒の緩急。長調なのにどこか物悲しく、ここで完全にアルバムの世界観に引き込まれ、7曲目の「ドライフラワー」へ。ここで赤い公園ワールドの爆発である。世界観への引き込み方としてあまりにも華麗すぎる。こんなの好きになっちゃうに決まってるじゃねえか。
「TOKYO HARBOR」はKREVAとのコラボ作。当時はかっこいいなあくらいしか思っていなかったが、今改めて聴くとKREVAの超贅沢使いだ。津野さんの弾くギターフレーズのハネ感と、KREVAのラップとの親和性がとてつもなく高く、作曲家&ギタリストとしての津野米咲の魅力に虜にさせられてしまう。
その後も「ひつじ屋さん」で赤い公園ワールドを炸裂させておきながら、それまでの赤い公園には信じられなかったようなポップでキャッチーな曲が、「サイダー」「楽しい」と2曲続く。もうここまで来ると、赤い公園というバンドの手札の多さと独特の気持ち悪さに魅了されてしまっている。
最後の2曲は「風が知ってる」と「木」。
この2曲で完全に赤い公園のカッコ良さと異質さに惹き込まれたところでアルバムは終了。
つかみはキャッチーなのに、気づけば唯一無二の世界観の中に連れ込まれてしまっている、良アルバムの典型パターン。
③真っ黒 / tricot
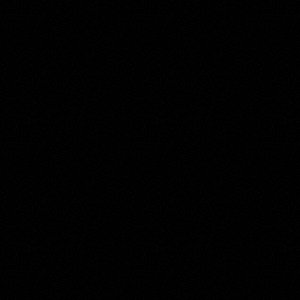
「好きなバンド何ですか?」と聞かれて赤い公園を答えた時に、「知ってる!」と帰ってきた時にだけ追加で伝えるバンド。理由は簡単、赤い公園を知らない人がtricot を知っている可能性はかなり低いから。
そんなtricot(トリコ)は変拍子を多用するマスロックに分類されるバンドで、実は赤い公園ともかなり親交が深い(初期の赤い公園にはマスロック的な楽曲もよく見受けられる)。
この作品は、そんなtricotのメジャーデビュー後初のアルバム。また、ドラムスの吉田雄介氏が正式加入したあとの初めてのアルバムでもある。
アルバムとしては、さすがメジャーデビュー作なだけあってかなり手が込んでいる印象。1作前の「3」よりも変拍子要素は少し控えめになっているものの、元から強かったバンドアンサンブルのタイトさがより増し増しになっている。全曲、どの楽器に耳を傾けていてももれなくカッコ良い。また、フロントマン3人が全員女性で、そのコーラスワークの美しさもtricotの大きな魅力の1つ。ぜひイヤホンやヘッドホンをして爆音で各パート各フレーズを舐め回すように聴いていただきたい1枚。
最後の曲「真っ黒」を聴き終えた時には、感嘆のため息が漏れること間違いなし。
また、もしこのアルバムで初めてマスロックに触れるという方がいらっしゃれば、おそらく戸惑いを隠せないであろう。でも、tricotはマスロックバンドの中でもポップス要素を含んだかなり聴きやすい方のバンドなんです。そしてtricotの面白いところは、無理に変拍子にしようとしている感が無いところ。基本的にセッションで曲を作っているというだけあって、作っているうちに気がついたら変拍子になってました、というような自然な感じが聴きやすさの所以なのかもしれない。
この作品を入口に、よりマスロック要素を感じたい方は、ぜひ1作前の「3」も一聴いただきたい。
④kikUUiki / サカナクション

今や国民的有名バンドとなったサカナクションの4枚目のアルバム。身の回りのバンド好き界隈で「サカナクションの1番好きなアルバムは?」という話をすると、大抵見事な程に各アルバムに分散するのだが、私はこの作品一択。理由はアルバムとしての楽曲の展開が凄まじすぎるからである。
1曲目の「intro=汽空域」。歌詞のない不思議な楽曲なので飛ばしてしまいたくなるが、じっくり聴いて翌耳に焼き付けておいて欲しい。アルバムを聴き終わった後、改めて聴くと印象が変わるはず。
スローテンポながらも、しっかりと1歩1歩踏みしめて前へと進んでいくような力強さを感じる1曲、「潮」でアルバムはスタートする。「激しく胸打つ思想に 踊らされ生きてた」サビの歌詞。過去形で記されてある。過去形である=今では違うというふうに捉えると、このアルバムの味わい深さが増してくる。
ベースラインがメロディアスでグルーヴィーな3曲目「YES NO」に続いて、名曲「アルクアラウンド」で気持ちがMAXに持ち上げられ、興奮が冷めやらぬままさらに静と騒の緩急が最高に気持ちがいい「Klee」へ。
6曲目のインスト曲「21.1」で一旦ブレイクタイム。楽器陣のグルーヴに酔いしれたところで「アンダー」。海の中を漂っているような広がりのある楽曲。そしてそのまま深海へと潜り込み、出会うのはシーラカンス。
9曲目「明日から」。深いリバーブのかかったたった一音のピアノの音が水面に水滴が落ちる画を連想させる。続く「表参道26時」は、これまでのサカナクションにはなかったような新感覚の楽曲。サビでボーカルが山口氏ではなくなるのだが、この声は一体誰の声なんだろう。
そしてアルバムはクライマックスへ。11曲目「壁」。この曲は歌詞が非常に耳に残る。今回この記事を書くにあたって改めて聴き直してみると、これまでと感じ方が全く違った。おそらく“孤独感”がこの曲のテーマなのではないだろうか。“孤独”ではなく、“孤独感”。身の回りに誰か人がいたとしても、一人ぼっちのような感じがする、それが孤独感である。これまた不思議なことに、この“孤独感”が強い時は、周りから手を差し伸べられていたりしたとしても、極力関わりたく無くなってしまって、結果的により一層“孤独感”が増す悪循環に陥ってしまうのだ。この時の自分を山口氏は「壁」と表現したのかもしれない。この“孤独感”から抜け出す明確な方法はおそらく誰も分からない。時の流れに任せるしかないのだと思う。この時のモヤモヤした感じもこの曲の終わり方で見事に表現されているように感じる。
アルバムを締める12曲目は言わずもがなの名曲「目が明く藍色」。楽曲中盤で展開がガラリと変わるとても大胆で味わい深い1曲。一説によると山口氏はこの楽曲を制作するのに9年を費やしたのだとか。あらゆる苦しみや悔しさや心情の変化が詰まっているようにも思われるこの曲については、あらゆる考察がなされているので気になる方は様々調べてみてください。
このアルバムに出会ったのは中学生の頃。最初に通して聴いた時は、まるで映画を1本見終えたかのような深い余韻に浸ってしまったのを今でも覚えている。アルバム単位で音楽を味わうことを教わった大切な1枚なのです。
⑤SABRINA NO HEAVEN - THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

前半最後に取り上げるのは、平成のロック史には欠かせない伝説のロックバンド、ミッシェルのラストアルバム。初めは「ミッドナイトクラクションベイビー」目当てで聴いていたが、アルバム全体を通して流れている深い深い哀愁に完全に魅了されてしまった。
ミッシェルといえば、マシンガンカッティングと言われるギタリスト アベフトシ氏の超絶カッティング技法が有名だが、このアルバムではあまりそれらがフィーチャーされている感じがない。それ以上に、これまでの作品よりもクールさが増している点や、やや不穏なコードワークが多用されているように感じられる点から、終わりに向かっている感が際立っているように思える。もちろん、解散後に聴いているからかもしれないが。
特に、「水色の水」からのラスト3曲の流れは、何故こんなにかっこいいのに切なさが溢れて出しているのだろうか。「PINK」のギターソロなんて、代名詞のカッティング奏法は一切出てこない。なんか、ズルい。6曲目の「夜が終わる」に至っては、2コードでまわるギターにまさかのピアノを乗せたスローなインスト曲で、それでアルバムもミッシェルの歴史も〆なのだ。
最後の最後までしっかり自ら演出しきって解散。そしてチバもアベも、そそくさと次の世界へと旅立ってしまった。
「俺たちが日本のミッシェルガンエレファントだ!」1998年のフジロックフェスティバルで、名だたる海外アーティストに混じって戦いに出たチバが、MCで叫んだ言葉。
魂の乗った本物のロックンロールを後世に伝える、伝説のバンドのラストアルバム。ぜひご一聴を。
自分の語彙力の無さに絶望しながら、なんとか絞り出した語彙で魅力を伝えてみたがどうだろうか。後編ではさらに幅広いジャンルのアルバムを5枚紹介しようと思うので、後編もお楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
