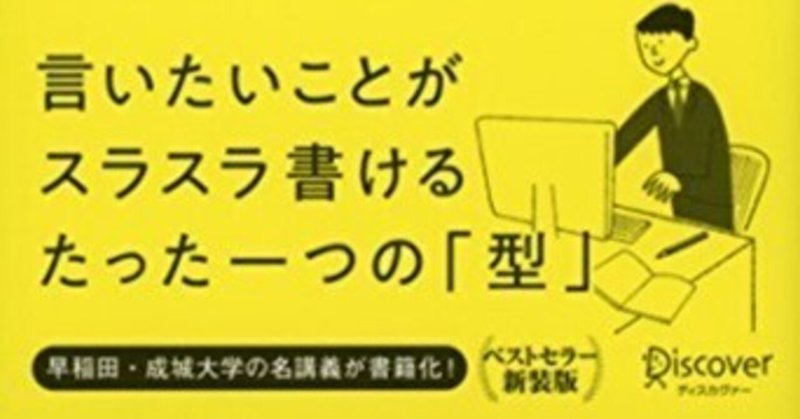
『説得力のある文章を書きたい人にオススメ』伝わるシンプル文章術 著者:飯間浩明【読書記録】
どんな書籍か?
タイトル
伝わるシンプル文章術
著者
飯間浩明
読み終えるまでの平均時間
2時間56分
なぜ、読もうと思ったのか?
書く仕事をするにあたって勉強のために
本の種類
Kindleunlimited
感想
タイトルと内容の一致度【100】
読みやすさ【90】
内容の満足度【90】
『反論を呼び起こし、かつ論破する』伝わる文章が誰でも書けるようになる本です。ちょっと内容が多かったので読むのに時間がかかりましたが、読んで良かったです。クイズ文という形式で文章をつくります「問題」→「結論」→「理由」これで伝わる文章の完成です。理由には確かな情報を裏付けすることで説得力が増します。また、反論を予想し、それを論破することで文章が完成されます。読み終わると理解できるのですが、実際に書いてみないとわからないので、近いうちに書いてみようと思います。
どんな人におすすめできる本か?
・説得力のある文章を書きたい人
・文章を書くのが苦手な人
・ブログを書いている人
読むとこんな変化が感じられます。
・説得力を出すためには確かな情報が必要
・自分でもできそうな気がするが実際に書いてみないとわからない
・ブログで活用できそうだ
いつ読み返すべきか
・クイズ文を使いたくなった時
気になった部分抜粋
この「問題」「結論」「理由」という形式の備わった論理的な文章のことを、私は「クイズ文」と呼んでいます。私が編み出した形式ではなく、論理的な文章では普遍的に使われる形式です。優れたクイズ文を読んだ読者は、納得し、書き手を支持し、場合によっては書き手の望む行動を取ってくれます。
考えを伝え、理解してもらうためには?
自分の考えを読者に確実に伝え、「なるほど、あなたの考えることはこうですね」とはっきり理解してもらえるような文章を書くためには、どうすればいいでしょうか。 それには、「 クイズ文」を書けばいい、というのが私の答えです。 クイズ文とは耳慣れないことばですが、私が作った用語です。テレビや本に出てくる、あのクイズそのままの形式を持つ文章のことを、こう名づけています。もっと具体的に言えば、「問題・結論・理由」の三つを備えた文章のことです。
考えの伝わる文章を書くということと、読みやすい文章を書くということは別物です。読みやすい文章だからといって、筆者の考えを読者が間違いなく受け止めてくれるかというと、必ずしもそうはなりません。
読者がそれぞれ好きなように受け取っていい文章、先ほどの表現を使えば、水彩画的な文章である疑いが濃厚です。これを一種の論文と考えて、受験勉強などのために使うのは避けたほうがいいでしょう。 ▼考えを伝えるには、「問題・結論・理由」を備えた「クイズ文」が有効。 ▼読みやすい文章でも、筆者の伝えたいことが分からない文章がある。
人間の脳というのは不思議なもので、疑問形を耳にすると、脳は即座に回転しはじめます。特に、「か」という助詞が、脳を回転させるスイッチになります。
たとえば、友だちといっしょにいて、相手が「ああ、おなかが減った」とつぶやいても何も感じないという人でも、「今晩、何を食べようか」と聞かれると、「そうだなあ……」と、とたんに考えがはたらきます。
クイズ文では、「~か」という問題の部分が、筆者の考えの出発点(考える契機)となります。同時に、読者の考えをはたらかせるスイッチの役割を果たします。
明快に書かれた一つの結論は、読者に賛成または反対の意見を生じさせます。読者がどちらかの意見を抱いたということは、筆者の結論を理解したからと言うことができます。 賛成ならともかく、反対意見を生じさせては困ると思うかもしれませんが、有意義な反論は筆者のためになります。筆者も、反論に対しては文章の中で備えておきます。自分の結論が確かな理由(次項参照)に支えられていることを示したり、想定される反論への反論をあらかじめ述べたりします。
そこで、自己紹介をする人に、教師からあらかじめ一つの問いを投げかけておきます。簡単なところで、「あなたの嫌いなものは何ですか」というのはどうでしょう。自己紹介をする人は、それに答えます。ただ答えるのではなく、理由を添えることにします。名前は最後に言います。するとこうなります。 「私の嫌いなものは、テレビのバラエティー番組です。なぜなら、たいていいつも、だれかを笑い者にしているからです。あれはどう見てもいじめです。A野X恵です」 「私の嫌いなものは、出席をきびしく取る授業です。なぜなら、学生の興味をひく努力をせずに、学生を強制力で従わせているからです。B山Y太です」 「私の嫌いなものは、ブロッコリーです。なぜなら、小さないぼいぼが集まった形で、気味が悪いからです。C川Z平です」 このような形式に則って自己紹介をすると、それぞれの人の物の見方がよく分かります。聞いている人は、「そうだそうだ」と共感したり、「自分は違うな」と別の考えを持ったりします。全員の話を記憶に留めることは無理としても、ただの自己紹介よりはよほど印象が強いし、第一、聞いていて楽しくなります。このことは、私の教室で実験ずみです。
↑クイズ分は共感と批判を呼ぶ
ところが、C川さんの出した理由に対しては、聞き手は反論ができません。「ブロッコリーのいぼいぼは気味悪くはないですよ」と言っても、C川さんが「でも、私は気味が悪いと思う」と言えば、それで終わりになります。このように、どっちが正しいか論争できない考えのことを、主観と言います。C川さんの理由は主観的です。この本で目指す本格的なクイズ文には、主観を入れてはいけないことにします。
▼「クイズ文」と、実際のクイズの形式はそっくりだ。 ▼「問題・結論・理由」にはそれぞれ役割がある。 「問題」は「~か」の形をとる。筆者の考えの出発点であり、読者の考えをはたらかせるスイッチ。 「結論」は一つ示される。読者に賛成または反対の意見を生じさせる。 「理由」は問題から結論に至る考え方の道筋を示す。結論で残った読者の疑問を解消する。 ▼クイズ形式は、数学や理科の時間など、いろいろなところに出てくる。自己紹介などで練習することもできる。
LESSON3 クイズ文の反対は「日記文」 ふつうに目にする文章は「日記文」
日記文というのは、このように、主として出来事を書いて、場合によって、それに対する感想を加えた文章のことです。
また、「事実」と「感想」の記される順番は、固定したものではありません。場合によって、「感想→事実→感想」「事実→感想→事実」などとなる場合もあります。ただ、感想は事実から導かれるものですから、「事実→感想」の順に並んでいるのが、最も自然な形だと考えられます。
「事実・感想」を定義すると?
そこで、「事実」というのは、「出来事」と「客観的な性質」とを含む概念というふうに定義しておきます。
また、感想は、文末の言い方によっても表されます。「~だろう」「~はずだ」「~にちがいない」など推測・予想を表す語句、「~しよう」「~たい」「~てほしい」など意志・希望を表す語句、「~べきだ」「~なければならない」など、当然を表す語句などが文末についた場合は感想です。 このうち、「~てほしい」「~べきだ」「~なければならない」は、ただ感想を述べるときだけでなく、「彼を無罪にすべきだ」のように、人に要求するときにも使われます。要求を通すためには、きちんとした理由が必要なので、これらの言い方を使う文章は、日記文よりもクイズ文の形が適当な場合が多くあります。
正しいかどうか確かめられる文は「事実」です。正しくないことが分かっても、それは「正しくない事実」です。
日記文とクイズ文の違いは、すでに述べたように「事実・感想」の形式をとるか、「問 題・結論・理由」の形式をとるかによりますが、別の観点からまとめるならば、次のように言い表すこともできます。
日記文―主観(感想)を含み、言いたいことを複数盛りこんである。 クイズ文―主観を排し、一つの考えを確実に伝えようとする。
今までのところで、なんとなく、日記文のほうが低級で、クイズ文のほうが高級であるような印象を与えてしまったのではないかとおそれますが、そうではないと念を押しておきます。すぐれた日記文を書くことも、すぐれたクイズ文を書くことも、同じくらいの努力が必要です。ただ、私たちは、比較的、日記文に小さいころからなじんでおり、練習も積んでいるというだけのことです。
日記文は反論できない
クイズ文は反論ができる
反論を呼び起こし、かつ論破する ある程度の長さのあるクイズ文では、書くときに、あらかじめ読者の反論を十分に想定して書くことができます。 「このようなことを言うと、○○という反論が出るだろう。しかし、その反論についてはこう答える。また、××という反論も出るだろう。その反論についてはこう答える」
説得力のある文章とは、始めからしまいまでまったく読者に反論を思いつかせない文章ということではありません。むしろ、いくつもの反論を呼び起こします。そして、それを一つずつ論破していきます。クイズ文が反論のできる文章だということは、この場合にも当てはまります。
○考えを確実に伝え、理解してもらうためには、「クイズ文」の形で書くといい。 ○クイズ文とは、「問題・結論・理由」の三要素でできている文のこと。 ○クイズ文の反対は「日記文」。日記文は「事実・感想」からできている。 ○日記文は読者によっていろいろに受け取られる余地がある。一つのことをどうしても伝えたいときは、クイズ文が適している。 ○クイズ文には反論ができるが、日記文には反論できない。そして、説得力のある文章とは読者の反論を呼び起こし、かつ論破する文章だ。
クイズ文を、疑問文の形式に従って分類すると、以下の四つの型に分かれます。 ①Yes or No 型(ディベート型) ②How型(課題解決型) ③Wh-型(択一型) ④Why型(理由探求型)
①Yes or No型(ディベート型) 「はい(肯定)」か「いいえ(否定)」の形式の結論を求めるクイズ文です。ディベート(肯定側・否定側に分かれて討論を行う競技)で使うテーマが典型例です。たとえば、「レジ袋は有料化すべきかどうか」「電車の優先席は廃止すべきかどうか」といったテーマが、ディベートではよく取り上げられます。 この型のクイズ文は、結論が「はい」か「いいえ」かのどちらかに決まっているので、一番単純なものです。ディベートで使うというと、なんだかむずかしそうですが、じつは、最も基本的な論争形式です。結論が単純明快だからこそ、勝ち負けを決める競技にふさわしいのです。クイズ文の初心者にとっては、最も入って行きやすい型です。
②How型(課題解決型) 問題が「どうすれば?」「どのように?」といった言い方になるクイズ文です。未解決の課題を解決するための方法を論じるクイズ文です。 世の中は未解決の課題に満ちあふれています。もしかすると、このHow型は、最も必要とされている型かもしれません。「どうすれば、マンション建設を阻止できるか」「どうすれば、A社との交渉を有利に進められるか」「どうすれば、○○大学に合格できるか」などなど、この型の問題は次から次へと現れます。単純な「はい」「いいえ」ではなく、知恵をしぼった結論が求められます。 「どうすればやせられるか」という問題に対して、「それには、わが社の○○サプリメントが一番です。なぜなら、このように成功の声が続々集まっているからです」などと結論・理由を示している広告がよくあります。一見、論理的ですが、その理由が本当に信頼に足るものかどうかについては、気をつけなければなりません。 私の書いているこの本の趣旨は、次のようなHow型のクイズ文で表すことができます。 「自分の考えを文章にして確実に伝えるにはどうすればいいか。─『クイズ文』を書けばいい。なぜなら、クイズ文は、問題と結論がそれぞれ一つに決まっており、読者が文章から何を読み取ればいいか迷わないからだ」 読者に、このメッセージは伝わっているでしょうか。
③Wh-型(択一型) 「何が(何を)?」「だれが(だれを)?」「どこが(どこを)?」「いつ?」「どっちが(どっちを)?」(What? Who? Where? When? Which?)などを問題にするクイズ文です。「何個か?」「何本か?」もこれに含めていいでしょう。「何個か?」は英語で言えば‘How many...?’ ですが、日本語では「何」を用いるからです。なお、「Wh-」で始まる疑問詞でも、「Why?(なぜ?)」を問題にするクイズ文は特殊なので、別に④として立てることにします。 Wh-型は、いくつか考えられる結論の中から、一つを選び取る(択一する)ものです。たとえば、「次の総理大臣はだれがふさわしいか」「今度の旅行はどこへ行こうか」「今晩何を食べようか」「祝儀袋にいくら包もうか」などは、この型の問題です。 先に示した「電車内のヘッドホンの音漏れの責任はだれにあるか」は、このWh-型のクイズ文です。 ディベートの試合でも、「A案がいいか、それともB案がいいか?」と二者択一を問題とするものがあります。これも、Wh-型のクイズ文に含まれます。肯定側がA案を示したのに対抗して、否定側が、それとは相いれないB案を突きつけるものです。 たとえば、「インターネットなどで漢字を目にする機会が増えたので、新しい常用漢字を二〇〇字増やすべきである」と肯定側が主張した場合、否定側が「常用漢字の数は増やすべきでない。その代わり、書けなくても読めるだけでいい『理解漢字』を二〇〇字増やすのがよい」と対案を出すのがそれに当たります。すると、「新常用漢字」か、「理解漢字」かという二者択一の議論になります。 Wh-型では、複数ある案のそれぞれの得失をよく考えなければならないので、議論としては複雑なものになります。もっとも、実際には、「次の総理大臣はだれがふさわしいか」などは、さしたる議論もなく決まっているようです。
④Why型(理由探求型) これは、ちょっと特殊な型のクイズ文です。というのも、この型では、問題の形が「なぜ……なのか?」となり、結論の形が「なぜなら……だからだ」になるからです。結論で「なぜなら」、つまり理由を言うのですから、「結論イコール理由」という形式をとることになります。 この型は、「なぜ空は青いのか」「なぜ恐竜は滅んだのか」「『いろはうた』はなぜ作られたのか」など、ものごとの原因・理由を学問的に探求するのに向いています。そのことを本格的に研究する覚悟がないかぎり、いきなりこの型を使ってクイズ文を書くのはむずかしいと思います。 以前、学生に自由題でクイズ文を書かせたところ、「なぜ、ハトは首を振って歩くのか」という問題を設定した人がいました。そういうハトの習性はたいへん興味深いのですが、首を振って歩く理由をその学生自身が解明したのではありません。何かの本で調べたことを、クイズ文の形にまとめたようでした。これでは、人の結論の紹介であって、自分で結論を出したとは言えません。Why型の文章を書くためには、自分自身が調査または研究して結論に至る必要があります。
▼クイズ文には四つの型がある。 ①Yes or No 型(ディベート型)……「はい(肯定)」か「いいえ(否定)」の形式の結論を求める型。結論が単純明快なので、一番書きやすい。 ②How型(課題解決型)……問題が「どうすれば?」「どのように?」といった言い方になる型。未解決の課題を解決するための方法を論じる。 ③Wh-型(択一型)……「何が(何を)?」「だれが(だれを)?」「どこが(どこを)?」「いつ?」「どっちが(どっちを)?」を問題にする型。いくつか考えられる結論の中から一つを選びとるもの。議論は複雑になる。 ④Why型(理由探求型)……結論と理由が一致する型。ものごとの原因・理由を学問的に追究するのに向いている。 ▼一番単純なのは①Yes or No 型。これから試してみるのがいい。問題の性格によっては②How型(課題解決型)も論じやすい。
ディベートとは、どちらかに決めなければならない問題について、二チームで手分けをして資料を探し、その結果を比べるもの と考えればいいでしょう。どっちのチームがより役立つ判断材料を探したか、その腕前が問われます。真実に迫らないどころか、真実を明らかにするために非常に有効な方法です。
( POINT ) ▼ディベートの発言を読むだけでも、クイズ文の要領がけっこう身につく。 ▼ディベートは「なぜなら」の部分がしっかりしているほうが勝つ。そのために一級の資料を集める必要がある。
素人考えかどうかはともかく、私がここで示したいのは、ディベートの形式を踏まえて文章を書くことは、考えを進展させるということです。文章を書きながら、「こういう批判があるかもしれない。その批判に対しては……」と、理論武装をかためていくうちに、当初は頭になかった考えが生まれます。そうなったら、その新しい考えを組み入れて、もともとの「問題・結論・理由」を練り直します。結果的に、より考えの深まった文章が書けます。これは、ディベート型クイズ文の効用の一つです。
( POINT ) ▼ディベート型のクイズ文の構造は次のようになる。 「○○という提案は妥当か。妥当だ(妥当でない)。なぜなら、○○だからだ。これに対しては、○○という反論があるかもしれない。だが、その反論は○○という理由で当たらない。したがって、○○という提案は支持できる(支持できない)」 ▼ディベートの形式を踏まえて文章を書くと、考えを進展させ、より考えの深まった文章を書くことができる。
[ 第2章のまとめ ] ○クイズ文には、「Yes or No型」「How型」「Wh-型」「Why型」の四つの型がある。型の選択を誤ると、適切なクイズ文に仕上がらない。 ○ディベートは「Yes or No型」のクイズ文を述べ(立論)、それに第一反論・第二反論を加える形で試合を進める。 ○ディベートを台本にしたものを朗読するだけでも、クイズ文の要領が身につく。 ○ディベートを踏まえて文章を書くと、より考えの深まったものになる。
・音楽の授業では歌が下手な子どもを低い成績にすべきか
・児童公園の野外遊具は、事故防止のため撤去を進めるべきか
・駅などのエスカレーターは片側を空けておくべきか
・公共トイレをきれいに使ってもらうにはどうすればいいか
・ビュッフェ(バイキング)レストランで残飯を減らすにはどうすればいいか
・子どもに嫌いなものを食べさせるにはどうすればいいか
問題の文を一読するだけで、答えを考えたくなるものばかりです。その点で、どれも優れた問題です。問題設定がいいからといって、必ずしも成功したレポートになるわけではありませんが、成功する可能性は非常に高まります。
( POINT ) ▼「問題」は読み手が思わず考えてしまうようなものにする。原則として「~か」という疑問形で書く。 ▼不適切な問題設定は ①漠然とした問いかけのもの ②主観的なことばを伴っているもの ③仮定を伴うもの ④明らかな事実で、議論の余地のないもの ▼「結論」「理由」はクイズ文を書いているうちに考えが変わるかもしれないので、むずかしく考えず、当座のものを用意しておけばいい。
一読してお分かりのように、「~か」で終わる文がやたらに出てきます。すでに繰り返したとおり、「~か」は問題を示す目印です。この目印が複数回出てくると、読者はそのたびに考える態勢に入ります。何度も「~か」を使われると、読むほうは混乱して、何を考えればいいのか分からなくなります。 こういうことを避けるため、クイズ文では、「~か」のつく文は、問題を含むただ一文だけにしぼることにします。問題以外の部分では、一切「~か」を使いません。
一般的には、よく、文章の最後で、「われわれはもう一度考えてみる必要があるのではないだろうか」などと、「~か」を使うことがあります。クイズ文ではこれも禁じ手とします。出された問題に結論を出すのがクイズ文の目的なのに、一番最後で「~か」を使ってしまっては、未解決の問題が残されることになります。
結論は、問題の含まれる文のすぐ後の段落に、間を置かずに示します。
( POINT ) ▼結論は問題のすぐ後に示す。 ▼結論の述べ方がよくない典型的な例として、次のようなものがある。 ①結論が書かれていないもの ②結論が弱いもの ③問題と結論がかみ合わないもの
出世をするのに必要なのは、学歴よりもまず独創性、そして、努力の量であると感じる。
論理の誤りに関する例を二つ見ました。こうした誤りを犯さないように文章を書くには、論理学の初歩を知っておくことが有益です。分かりやすく、おもしろい入門書として、野矢茂樹『新版 論理トレーニング』(産業図書、大学生以上)、小野田博一『 13 歳からの論理ノート』(PHP、中学生以上、一般にも)を挙げておきます。いずれも、短い文章を読んで、その論理の適否を答えさせるようにしたもので、知らず知らず論理力が身につきます。
「思う」は、自分の感想を述べるときに使う動詞です。感想とは、日記文の中で述べるものであり、クイズ文に入れてはいけません。クイズ文の中で「思う」が使われていれば、その部分は証拠能力がないことになります。クイズ文では「思う」を禁止ワードにすべきです。
……という反論があるだろう。 たしかに、もし……ならば問題がある。 しかし、実際は……だ。したがって、反論は当たらない。 だいたい、右のような骨組みに則って、筆者が一人で反論と再反論を進めていきます。
▼文章に説得力を持たせるには、 ①資料的な裏づけを取る ②反論に備える ▼タイトルには問題か結論を要約したものを用いる。 ▼段落のまとまりごとに適宜改行しないと読みにくい。
○「問題」は、原則として「~か」という疑問形で書き、読み手が思わず考えてしまうようなものにする。 ○「結論」は、問題のすぐ後の段落に、間を置かずに書く。さらに、文章の終わりにもう一度繰り返して確認する。 ○「理由」は、結論の後の段落に書く。結論と論理的につながっていることが大切。 ○文章の説得力を増すためには ①信頼できる資料によって、裏づけを取る。 ②反論を想定して、それに再反論する形で書く。
ことばはどうすれば伝わるか
非論理的な人のための 論理的な文章の書き方入門
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
