
<書評・芸術一般>『Duchamp love and death, even(デュシャン 愛と死、さえも)』
『Duchamp love and death, even(デュシャン 愛と死、さえも)』 Juan Antonio Ramirez ファン・アントニオ・ラミレス著 1998年 Reaktion Book Ltd. London 原著は1993年にスペイン語で発行され、1998年に英訳が発行された。

20世紀を代表する芸術家マルセル・デュシャンの研究書。Henri Robert Marcel Duchamp アンリ・ロベール・マルセル・デュシャンは、1987年7月28日に、フランス北部ルーアンからほど近いブレンヴィーユ・クレヴォン村に生まれた。父は事務弁護士(司法書士より弁護士に近い仕事)をしている、中産階級として裕福な家庭だった。しかし、父は美術が趣味であったため、兄弟は皆画家などの美術関係の仕事に就いている。デュシャンは、大学で哲学と文学を学んだものの、こうした家庭環境に影響されて美術を没頭し、やがて世界有数の芸術の都となっていたパリに出る。そこで、印象派、象徴主義、フォービズム、キュービズム、シュールレアリスムなどに感化されたが、その後こうした前衛芸術運動のグループと離れ、孤高の独自な世界に入る。
ナチスドイツの恐怖から逃れてアメリカのフィラデルフィアに移住し、生涯そこで暮らしたが、1968年10月2日に仕事の関係でパリ滞在中に亡くなった。若いころにフランスの自動車王の娘リディ・サラザン・ルヴィアソルと結婚するが、わずか一週間で離婚する。その後、ピエール・マティス(アンリ・マティスの子でニューヨークの有名な美術商)と結婚し、3人の子供を持っていたアレクシーナ(ティーニー)と再婚し、最後まで幸せに暮らした。
1923年にマン・レイは、デュシャンをこう評している(新潮社美術文庫『デュシャン』93頁から引用)
「今、コマーシャリズム、功名心、あらゆる流行や運動、自分自身の才能からさえ自由であり、この自由を長い生涯にわたって維持し続けたデュシャンは、そのおおらかで高い精神、すぐれた人格、美しい容姿、かざりけのない態度、その知性とユーモアで、つねに周囲の人々を魅了したという。画家としてのありあまる才能に恵まれながら、未練げもなく、いわゆる『芸術』」の制作を放棄し、チェスのゲームにうつつをぬかして、それを心から楽しむ一方、偉大なる偶像破壊者として伝統的な美学に根ざした神聖な芸術とそれに対する崇拝とを破壊しつづけた彼は、そのすぐれて予言的な前衛性のゆえに、逆説的にせよ、今や現代芸術の新しい神話、新しい偶像、新しい伝統となっている。」
デュシャンの生き方と正反対なのは、この「コマーシャリズム、功名心、あらゆる流行や運動、自分自身の才能」をもって、「『芸術』」の制作」をしつづけ、巨額の富を得るとともに世界的な名声を得たのが、パブロ・ピカソであった。だから、デュシャンの姿には、どこか鴨長明や宮本武蔵のような清貧な世捨て人のイメージが重なる。
ところでデュシャンは、日本でもシュールレアリスムの芸術家として有名で、特に本人曰く「網膜的な」絵画を卒業してオブジェの世界に入った後、大ガラス「彼女の独身者によって裸にされた花嫁、さえも」を発表して、これが代表作となっていた。その後しばらく活動をやめていたと見なされていたが、死後に公開された遺作「エタドンネ(与えられたとせよ):(1)落ちる水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ」を製作していたなど、神秘的な芸術家のイメージを持たれている。また何よりも、例えば印象派の絵画やピカソやダリのような現代芸術と比べて、その作品のメッセージを読み取ることが非常に難しい一方、世界中でいろんな人たちが勝手な解釈をしていたが、それは日本の美術評論家の世界でも同様だった、稀有な芸術家である。
こうした中で、日本で唯一といっても過言ではないシュールレアリストの瀧口修造は、デュシャンと親交があり、本人からその女性としてのペンネーム「ローズ・セラビー」の使用許可を得ていたという歴史がある。また、『デュシャン語録』という美術書も瀧口は製作している。したがって、デュシャンと日本との関係は意外と強い絆があるように感じている。
ところで私は、サミュエル・ベケットの文学作品と現代美術を探索するうちに、デュシャンという面白くも難解な「氷山」に出会った。そして、これまで様々な日本の解説書を読んでわかったつもりにはなっていたが、今回読んだ本書からは、これまで読んだ日本の解説書よりはるかに詳細に研究した成果を得ることができた。
デュシャンとチェスについて書いた、私のnote記事
そのなかで、本書の解説から私が喚起された事項を列記してみる。
(1)なぜ、デュシャンを含めたダダイストたちは、オブジェとして20世紀初頭に出現した機械―蒸気機関利用による複雑な歯車や構成による機械―に魅了されたのか?そして、なぜその機械の姿に、男性的性的イメージを持ったのか?
ドボルザークが蒸気機関車の走る音から、新世界の第四楽章のテーマを思いついたのと、どこか関連するものがあるように思う。また、デュシャンは電気機械にも関心があった。20世紀は蒸気機関の発明による動力革命のみならず、電気信号によって科学と人の生活が飛躍的に発展した時代だった。
それは、動力としての電気のみならず、信号手段=通信手段としても電気が使用された上に、医療用にも効用があると信じられた。すなわち電気信号は、魔法の力そのものだった。そのため、デュシャンの「大ガラス」にも独身者と花嫁の間に交わされる電気信号の痕跡がある。
蒸気機関や電気信号が「大ガラス:彼女の独身者によって裸にされた花嫁、さえも」に表現されていることを考えれば、「大ガラス」とは、20世紀の歴史と文化そのものを象徴している作品となるだろう。

(2)一方、題名そのものにもあるように「大ガラス」に表現された性的なものはどういう意味があるのだろうか。
近代的な機械は、ロボットにより近づいた印象がある。そして、古代に来訪した宇宙人は、純粋な生命体ではなくロボットであった可能性がある。そういう観点から考えれば、現生人類の深層心理の中には、ロボットを慕う気持ちがあり、それがそのまま性的なイメージとつながっているのかも知れない。
(3)「Rrose Selavy」は、デュシャンの別名であり、また女性名でもある。本書によれば、フランス人のデュシャンがユダヤ系の名前に変えたものと説明されている。
一方で、ローズ(バラ)は、フランス語で「性」を意味し、セラヴィはフランス語の「これが人生」と同じ発音であるため、「愛の生活」を意味していると解いている。
また、デュシャンの遺作「エタドンネ(与えられたとせよ):(1)落ちる水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ」に出てくる女性の裸体像も、デュシャン本人が女性に変貌したものではないかと推測している。
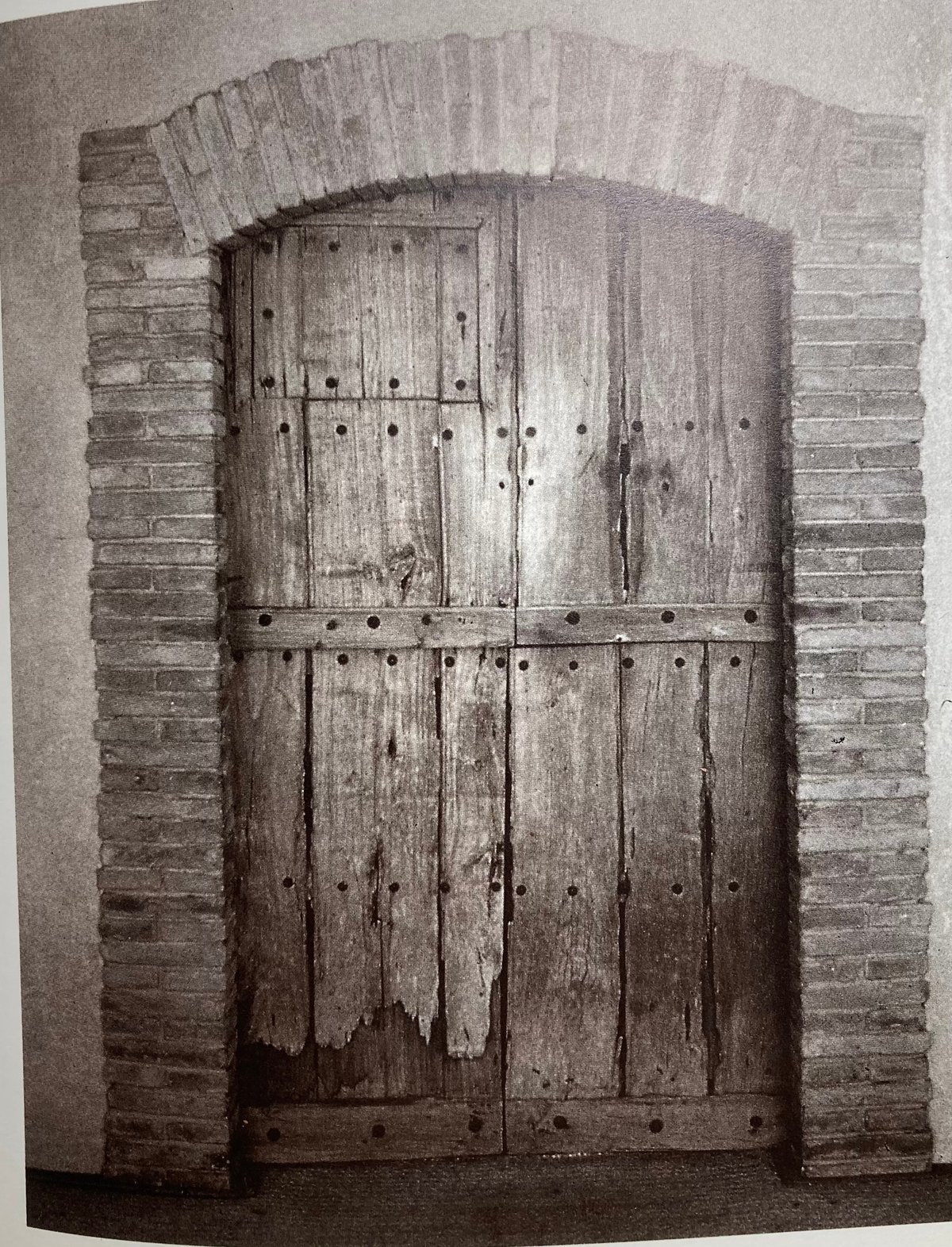
(4)デュシャンの遺作の世界は、大ガラスの世界を発展させたものだと言うのは正しいと思う。
一方、デュシャンが20世紀初頭の機械文明に感化されて、大ガラスを作り、また写真と映像に感化されて遺作を作ったというのも正しいと思う。そして、両方に共通する性的なイメージというのは、まさにDHローレンスが『チャタレイ夫人の恋人』で追い求めたような、人としての原点は性であるということにつながると思う。

つまり、20世紀は機械・写真・映像というのが急激に発達した時代であったのは、誰もが指摘するところだ。そのなかで人の精神構造は、この急激な非生物化についていけなかった。いやついていった結果、人はどんどんと非生物化していった。これに対する反論あるいは人が生物であることを再確認する手段が、性であったのだ。
(5)「遺作:エタドンネ」の女性の裸体の右奥には、電気仕掛けの滝が流れている。
デュシャンは、滝=水力発電所をイメージしており、そこに女性の性的なパワーを表現していたという。一方、男性の性的パワーは「大ガラス」の「チョコレート粉砕機」によって表現されており、そのパワーは、「裸にされた花嫁」に行く着くことなく、雲または霧となって消えている。
同様に女性の性的パワーも、滝が流れ去るように消えているのではないだろうか。そして、この女性の性的パワーである滝から生み出されたエネルギーが、どこに行ったかと言えば、女性が左手に持つ「照明用ライト」につながっているのだろう。
もちろん、ここで発電された電力が照明用にされているとすれば、題名の「照明用ガス」と異なってしまう。また、ガス=電気エネルギーとはならないから、やはり「照明用ライト」の光源はガスであり、水力発電による電気ではないのかも知れない。
そこから類推すれば、やはり「大ガラス」同様に女性の性的パワー=電力も、滝から上空に浮遊してしまい、女性の手に持っている照明には届かない。そのためのガスは、実は「大ガラス」で行き場を失っていた、独身者たちがチョコレート粉砕機で生じさせた男の性的パワー=ガスと同じものかも知れない。
(6)ところで、性=生として、20世紀は特に性的なイメージが強調され、拡散された時代だったと言える。
その傾向は、21世紀になっても継続しているが、それまでスキャンダルであった性が、例えばLGBTQなどの性的マイノリティーに対する存在承認運動に代表されるように、一般的な市民権を獲得しつつある。つまり、性に関する表現はやがては特別なものではなく、日常の景色になっていくのだろう。
その時、人の精神構造はどう変化するのだろうか。それは、性によって生を取り戻したと言えるのだろうか。あるいは、もはや性すらも、機械・写真・映像(21世紀においては、コンピューターの情報データとして一括される)の中に取り込まれてしまい、生につながる方法から脱落してしまうのだろうか。
もしそうなったら、人はもう生の世界にいることはできないのだろう。デュシャンが大ガラスで表現したような機械のような存在、または遺作で表現したような視線=意識のなかでしか存在しないものに、「進化」するのかも知れない。
(7)本書に誘発されて私的デュシャン論を述べてみた。
しかし、本書でも言及しているように、デュシャン曰く「答えはない、なぜなら問いがないからだ」ということで、デュシャンは、自らの作品の解説はしないし、作品を解釈されることに対して否定も肯定もしなかった。
また、マルセル・デュシャンという名前が、そうしたデュシャンの芸術に対する意識を良く表現していると、本書は示唆しているが、デュシャン芸術を味わうためには、これが一番の「答え」なのかもしれない。
それは、マル=海(フランス語のメールに近い)、セル=空(フランス語のシエルに近い)、デュシャン=畑の中で(フランス語で、デュは場所を表し、シャンは畑を意味する)。
そう、(茫漠とした)海と空(に近い)畑(野原)に、ただ佇んでいるのが、デュシャンの芸術なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
