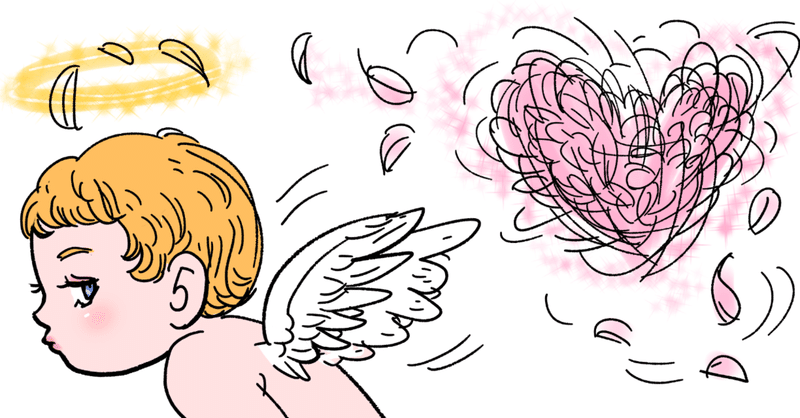
キューピットの弓矢はある日
わたしの名前はキューピット。ギリシャ神話に登場する、あのキューピット。この星の文明が急速に発達しだした頃からわたしたちは次々と送り込まれるようなった。送り込まれるかたちのわたしたちの姿は人々には見えない。まあ見えたら意味がないから透明な状態でいる。そしてわたしたちはご存知のとおり、弓矢を持っている。そう、恋の弓矢を。(これも当然見えたらびっくりすると思うから人間の目では見えないけどね)
この地球で使えるのは、たった一本の弓矢。だからこれはという人に向かって放つ。男性か女性かはケースバイケース。つまりは状況によって男性に放つときもあるし、女性に放つときもある。恋愛も多様性の時代だけれども、わたしたちの場合はある最終的な目的があるために男女間の恋愛に限られている。なので決して同性間の恋愛を蔑視しているわけではない。わたしたちはその最終的な目的のために、ふたりの恋が成就するいちばんのタイミングで、放つ。したがって成就してもらわないことには取り返しのつかない大変なことになってしまう。どんな大変なことになるかはおいおいわかってくると思う。
わたしたちには七日間という猶予が与えられている。七という数字はとても重要で特別な意味を持つ。万物のサイクルと言ってもいい。なので七日目になっても放てなかったら、そのときはまた次の機会まで待たなければならない。そうなってしまったらふたたび無となって母なる宇宙へと還るというわけだ。次の機会はいつ来るかはわからない。わたしもずいぶん待ったような気がするし、それほど待たなかったような気もする。矢を放てなかったような気もするし、生まれ変わりのような気もしなくもない。そこはとても曖昧だ。矢を放つための叡智は与えられているけれど、そこはほんとうにぼんやりとしている。曖昧なまま七日という期限があるから、ギリギリ七日目の最終時刻でとりあえず弓矢を放つキューピットもいなくはない。かれらの、また待つくらいならと思う気持ちもわたしにはじゅうぶん理解できる。しかしそうなったらそうなったで、あとあとこれも急いては事を仕損じる的なことになってしまうから、そこは本当に慎重にならなければならない。そういうわけだから、のほほんと地球を満喫している余裕は、わたしたちにはない。
さて、矢を放ったら放ったらで、わたしたちの地球の滞在時間は延長される。ふたりの、ある日まで。それまでわたしたちは刺したほうの人間をひたすら応援する。弓矢以外にあまり周知されていないわたしたちだけど、夢の中でそっと応援してあげるといった能力も実は備わっている。夢をみるほど、恋していく。恋の持続的パワーが源になって、相手に見合う自分へと成長していく。そしてその想いはらどんなに離れていようとも、相手のハートに必ず届くようになっている。
それから、もうわたしたちという言い方で察しているかもしれないけれど、この地球にはある一定数のキューピットが毎日のようにやって来ている。それはあくまで再三言っているある最終的な目的のために存在する宇宙のからくりのひとつ。そのためにわたしたちには先ほど話したような能力の他にもさまざま能力が身についている。たとえば、恋の矢がすでに刺さっているかどうか、わたしたちキューピットには見ることができる。はっきりとハートに矢が刺さっているのがわかるから、二本目の矢が刺さるということはない。万が一タイミングがまったく同じでも、どっちかが刺さらないようになっているからそこは心配いらない。そこの判断はわたしたちにはわからない。何か決まりがあるのかもしれないし、たんなる気まぐれで決めているのかもしれない。そういうことだから、その矢は無効となり、矢は弓へと帰ってくるというよくできたシステムとなっている。わたしたちは他のキューピットは見えないし、透明だからぶつかることもない。見えないのだから話すこともない。わたしたちにあるのは思念というもので、人の意識や夢にはその思念でもって送っている。(テレパシーというやつね)
いやはや、ちょっと脱線ぎみに前置きが長くなってしまった。それではわたしの、『大切なある日』までのものがたりを語ることにしましょう。
誰もいない海辺。夏の始まり。そこへ、Tシャツに色褪せたジーンズ姿のひとりの青年がやって来た。青年は持っていたケースからアコーディオンを取り出した。ちょっと年季の入ったボタン式のアコーディオンだった。ところどころに切り傷やかすり傷がある。そのなかに深い一本の短い切り傷があった。それを青年は指でゆっくりと撫でていった。それから青年はアコーディオンに軽くキスをして、そして何かダンスような儀式めいた彼特有のスタイルでアコーディオンを肩にかけた。青年は何回か大きく息を吸い込むと、自分のなかにある、ある意味のあるタイミングでもって弾き始めた。すると青年のまわりに、メロディーの景色が走馬灯のようにあわれてきた。わたしには、確かに、それが見えた。そこはどこか懐かしい石畳の路地で、左右に建つアパートメントの窓から、うら若き女性たちが次々と身を乗り出してはこちらに投げキッスをしてくるというものだった。青年の上空を、やわらかな風に乗った海鳥たちが羽ばたかずに旋回しながら飛んでいる。波まで音を立てないように、いつの間にか静かになっていた。彼のら音楽を、風も、波も、鳥たちも聴きたいようだった。
街の繁華街近くの広場。年に一度の夏祭り。青年はそこでのイベントに呼ばれていた。すでに午後のステージが始まっている。青年の直前の大道芸人のマジックは大ウケだった。青年は舞台裏で椅子に座って静かにスタンバイしている。青年は立ち上がると、肩にかけたアコーディオンにそっとキスをした。会場の人々はパンフレットのスケジュール表を見ている。アナウンスがあって青年が登場する。青年はあいさつもそこそこにさっそく弾き始めた。どうやら喋りは、あまり得意ではなさそうだ。しかし青年が弾き始めるやいなや、会場全体が一瞬にしてパリになったようだった。人々はうっとりとして、いつか憧れたパリの情景をそれぞれが思い描いているようだった。体でリズムをとっている人。目を閉じて懐かしい思い出にひたっている人。広場に棲む野良猫も楽しそうにしっぽを振っている。青空に流れる雲も、その速度を落としたようだった。やがて、パリをめぐる一連のメドレーが、終わった。拍手が沸き起こる。うれしそうに、頭を下げる青年。拍手がやみ、青年は語り始めた。
「ありがとうございます。パリ、思い浮かびましたか?」
観客のひとりが、
「思い浮かんだ!」と叫ぶ。
笑いがドッとわく。
「よかったです。今度はサンバの国ブラジルにご案内しましょう」
青年は弾き始めた。
観客たちは、ひとときの音楽旅行を楽しんでいた。
青年はステージを終えて、裏の控え室用のテントから出て来た。
そこに、小学生と思われるワンピースを着たひとりの少女が立っていた。
「あの」
少女は青年に声をかけた。
「ぼく?」
「そう」
「何かな?」
「アコーディオンっていうの? それ」
青年は抱えているケースを、一度見た。
「うん、そうだよ」
「むずかしい?」
「う~ん、まあ、かんたんではないね」
「そっかあ」
「かんたんではないけど、楽しいよ」
「へえ~」
「その歳から始めれば、すごい演奏者になれるよきっと」
「うち、買えないから」
「えっ?」
「高いんでしょ? だから、買えないから」
「ああ」
「でもオルガンは弾けるよ」
「それはすごいね」
「オルガンは家にあるの、おばあちゃんの代から。最近ドの音だけが鳴らなくなってるけどね」
「そう……あっ、このアコーディオンもね、父親のおさがりなんだよ」
「うちのオルガンも、今はわたしのものだよ」
「そっか。じゃあ、オルガンをうんと練習しとけば、アコーディオンもすぐに弾けるようなるよ」
「お父さんも弾いてたんだよね」
「そう」
「元気?」
「父さん?」
少女は、深くうなずく。
「いや……人をかばってね、天国にいってしまった」
少女は視線を落として、二度小さくうなずいた。
「あのね、わたし、ピアニストになりたいの。伴奏、したいから」
「伴奏?」
「あなたの」
「ぼくの?」
「うん。ピアノの伴奏があったら、もっと素晴らしくなると思う」
「そうだね。そう思うよ」
「お兄さんは、今いくつ?」
「二十歳だよ」
「わたしは十一歳。昨日が、誕生日」
「それはおめでとう。約はんぶんだね」
「うん。でも、あと七年経てば自由に結婚できるよ」
「まだ未成年じゃない」
「ううん。数年後には法律が変わって、十八歳が成人になるの」
「よく知ってるね」
「お兄さんは、独身?」
「うん」
「じゃあ、あと七年待って」
「えっ?」
「夫婦になって、世界中を演奏してまわろ」
青年はどう答えていいのかわからなかったので、とりあえず笑った。
「七年後の今日、この時間、ここで待ってるからね」
少女はそう言うと、サッときびすを返して帰って行った。
七年後の、その日の前日。広場の芝生の上に、仲の良い年上のピエロの格好をしたジャグリングの大道芸人のハナさんと青年が座っている。広場の一角では、毎年恒例の夏祭りのイベントが行われていた。
「そんな話、まさか本気にしているわけじゃないよな」とハナさん。
「そんな話を思い出したって話だよ」と青年。
「それ、どこ?」
「ここ」
「ここ?」
「明日」
「明日?」
「そう」
「そりゃまた。で、その後その少女には会ったのかい?」
「いいや、会ってない。会いにも来ていない」
「まあそうだよな。てか、夢見がちな小学生の女の子の話だろ。君の演奏にえらく感動してしまって、その感動のまま訳もわからずそんなふうに言ってしまったんだよたぶん。まあわかってやれよ」
「わかってるよ、もちろん」
「ませてる子はいるもんだよ。俺も親戚の女の子が小学生のときに、俺と結婚するって言ってきかない時期があったよ」
「その子、今どうしてるの?」
「医者と結婚して今は二児の母親だよ」
あはは、と青年は笑った。
「そんなもんだって」とハナさん。
「だよね」と青年。
「それ本気にして、今まで結婚しなかったわけじゃないだろ?」
「まさか」
「だよな、本気にするだけバカをみるって」
「そうだね」
「じゃ、そろそろ俺出番だから」
「うん、がんばって」
「ああ」
翌日。その日が来た。わたしがあの日狙ったのは隣にいた当時二十歳のお姉さんのほうだった。お姉さんは青年にもっともふさわしい相手だと思った。妹の凛ちゃんが、わたしが矢を放った瞬間になぜかお姉さんに抱きついたのだ。矢は、まるで身代わりになるように凛ちゃんに刺さってしまった。そうなってしまったものだから、わたしは今日まで凛ちゃんを陰ながら応援してきた。凛ちゃんは本当によくがんばった。学校はすべて、ピアノの特待生として入学して、家計を助けた。来春、私立高校の音楽科を卒業する。彼女はいくつかのコンクールにも出場した。優勝こそ逃したものの、成績は常に上位だった。
しかし彼女の夢は優勝ではなかった。もちろん優勝するための練習をすれば彼女にだってその二文字は不可能ではなかった。あくまでも、彼女の夢は青年の演奏を彩ることだった。それしか彼女の頭にはなかった。彼女は青年のあげる動画を何度も何度も繰り返し観ていた。そして、青年のその演奏に見合う伴奏を徹底的に研究し、それを毎日繰り返し繰り返し練習した。そんな彼女だから、彼の演奏技術が観るたびに進化しているのが、彼女には胸が痛むほどによくわかった。そうしてある日、青年のすべての動画の曲が『ド』から始まっていることに彼女は気づいた。そのことがまた彼女にさらに火をつけた。彼のその動画は彼女だけに向けてつくられている愛のメッセージだと彼女は確信した。そうして迎えた、今日だった。舞台裏のテントの前に彼女はいた。約束の日。約束の時間。約束の、スペックで。
青年は午前中のステージを終えてテントから出て来た。約束の時間までまだ二時間ほどあった。あの日のステージは午後だった。あの日の少女が来るとしたら、その時間だ。青年は、少し躊躇した。けれどハナさんにああ言った手前、ハナさんに見つかってしまうのが恥ずかしかった。青年は、何バカなこと今日まで考えていたんだと自嘲した。それから頭を振って、気持ちをきりかえて、次の予定もあるのでやって来た駅行きのバスに乗った。
凛ちゃんはまだテントの前に立っていた。約束の時間を過ぎても、まだ。テントから出て来たパフォーマーたちは、彼女に一度目をやっては通り過ぎて行く。しばらくして、ハナさんがテントから出て来た。ハナさんは彼女の横を何気なく通り過ぎてから、ふと立ち止まった。それから、ハナさんは、ハッと振り向いた。
「君もしかして、アコーディオンのら彼、待ってる?」
凛ちゃんは、振り返って言った。
「はい」
「マジだったんだ」
「えっ?」
「いや」
凛ちゃんは、泣きそうに微笑んだ。
「彼は午前中のステージで終わって、もう明日のイベント会場に移動したよ」
「知ってます。パンフレット見ましたから、午前中だったのは。それに、駅行きのバスに乗るところも、見てましたから」
「彼のステージは?」
「観ました」
「彼は、気づかなかった?」
「はい」
「まあ気づかないか、こんなきれいなレディになって」
凛ちゃんは、少しはにかむ。
「ねえ、それでも、待ってるの?」
「はい……」
と、凛ちゃんの顔がパッと笑顔になった。
ハナさんがまさかと振り向く。
青年が、ケースを抱えてやって来ていた。
ふたりは結婚し、コンビを組み、個人事務所をつくって世界中を演奏旅行した。青年はまるでオーケストラを聴いているような演奏を可能にした最新の電子アコーディオンを自在に奏でた。彼女はスタンドも椅子も一緒にバッグに入れて持ち運べるグランドピアノの音を再現できるデジタルピアノを美しく奏でた。彼女の伴奏で、彼のアコーディオンはより一層輝いた。思い浮かんできていた風景に、足音や、息づかいや、わずかな珈琲カップの音まで加わって、それはそれは臨場感あふれるものになった。ふたりが紡ぎだす音楽は、今まで誰も聴いたことがない画期的な音楽世界だった。それは世界じゅうの人々に少しずつ、自分のなかにすでにある宝物へのまなざしを目覚めさせてゆくものだった。
そんなふたりにCDデビューの話が舞い込んだ。ふたりは個人事務所から大手の音楽事務所に移ることにした。CDの表題曲は映画のエンディングに使用されたりして、それから数ヶ月後に出したデビューアルバムは世界中で大ヒットした。ふたりにはマネージャーや大勢のスタッフが付くようになり、全国コンサートを開くまでになっていった。
そうして定期的なアルバムとコンサートで、ふたりは何不自由ない豊かな暮らしを手に入れた。コンサートの中には、ハナさんとの楽しい掛け合いのパフォーマンスも取り入れられていた。ハナさんはそれがきっかけとなってテレビに出演するようになり、いまやお茶の間の人気者となっていた。
夢のような人生を歩むふたりは、気がつけば三十五歳と二十六歳になっていた。そして凛ちゃんがある日、妊娠した。青年は飛びあがって喜んだ。わたしの陰ながらの応援もこれまでだった。間違って矢が刺さってしまったけれど、それはそれでよかったのかもしれない。あの日、凛ちゃんがなぜお姉さんに抱きついたのかわたしはやっとわかった。お産が近いため入院していた凛ちゃんのもとへお姉さんが訪ねて来たときに、ふたりがあの日のことを笑って思い出しながら話したのだった。あの日、青年の弾くアコーディオンのメロディーに心底うっとりしてしまって立っていられなくなったのと、凛ちゃんは姉の問いに答えた。家にあるオルガンのドの音が鳴らずに弾いていた凛ちゃんにとって、ドレミの七つの音が生み出すあまりにも美しいメロディーに、死ぬほど心打たれたと言うのだった。それを聞いてわたしは、ふたりは運命だったのだと思った。もしかしたら、お姉さんに彼を渡さないという凛ちゃんの本能がわたしの矢をさえぎったのかもしれない。やはりそれは運命と言う他ない。恋の矢が彼女の運命の手助けになったのなら、こんなうれしいことはない。人間にはやはり、何か計り知れない崇高なまでのさだめが与えられているのだ。わたしたちの恋の矢は、きっと、ほんのきっかけにしかすぎないのだろう。
わたしはふたりの子供として産まれた瞬間、わたしのすべての記憶はリセットされる。一度恋の火が消えてしまったり、相手が誰かと結ばれたり、ふたりの最初の赤ちゃんとして産まれる可能性が完全になくなれば、キューピットは永遠に無となってしまう。もう待つこともないし、弓矢を持つこともない。大変なことになるとは、そういうことだ。これはそうならなくて済んだ、わたしが誕生する大切なある日までのものがたり。ああ、もうすぐ産まれそうだね。どうぞよろしく、お母さん。よろしく、お父さん。もっともっと、しあわせになってね。ああうれしい、その気持ちだけで赤ちゃんはみんな産まれてくるからね。だからね、この誕生するという『ある日』は、宇宙でいちばん素晴らしい日なんだよ。何よりも何よりも大切にされている最上の日。わたしたちはそれを絶えさせないために存在しているのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
