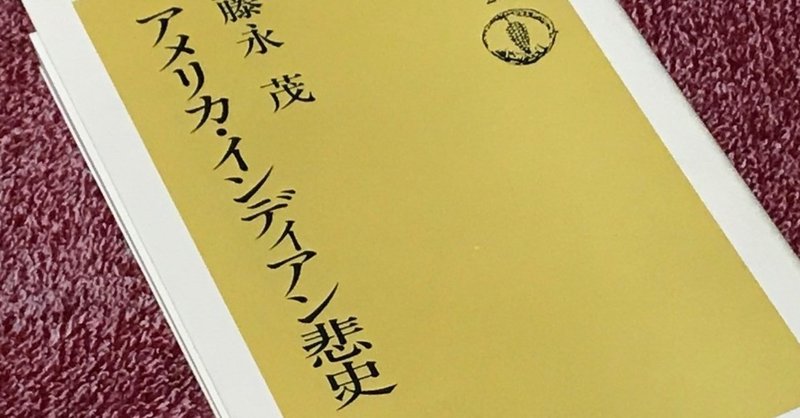
『アメリカ・インディアン悲史』を読みました。
アメリカ・インディアン悲史
著者:藤永茂
内容紹介
北米インディアンの悲史をたどることは、そのまま「アメリカ」の本質を、くもりのない目で見さだめることにほかならぬ。アメリカという国に好意を持つか反感を持つかなどという、生ぬるいことではない。「アメリカ」は果して可能か――黄色いアメリカ、日本は果して可能かどうかを、未来に向かって自らに問いただしてみることだある。
『戦争のはらわた』という映画がある。
タイトルだけを聞けばB級感満載だけど、原題は『Cross of Iron』、軍事勲章のことである。
『えじき』だの『はらわた』だのという邦題が流行っていたのだろうか、こんな残念な邦題の映画にもかかわらず、良質な映画なので、ぜひ一度観ていただきたい。
この映画が少し変わっているところがあって、それは何かというと、舞台は第二次世界大戦で、連合国側からではなく、ドイツ軍側から描いた作品なのだ。
しかも、ナチとドイツ軍が仲が悪い。
ナチ=ドイツ軍という知識しかなったのでそこには驚いてしまった。
第二次世界大戦を舞台とした映画であれば、まあそれ以外でも、ナチは悪側となることの方が圧倒的に多い。
これは映画における暗黙の了解といってもいいかもしれない。
この手の話で言うと、マカロニウエスタンでは、メキシコ人が悪側になることが多いだろうか。
そして西部劇におけるインディアン(アメリカ先住民(ネイティブ・アメリカン))だ。
全ての西部劇で、と言えば言い過ぎになるだろうが、基本的にはインディアンは悪い側として登場させらているイメージがある。
西部劇、細かいことを言えばマカロニウエスタンが好きで、以前からこの時代のメキシコ人、そしてインディアンには興味があった。
チラリとは耳に聞きかじっているのでちょいとだけの知識はあった。
本書を読めば読むほど、『悲史』という言葉以外では表しようのない歴史を目の当たりにした感じがする。
新大陸アメリカにイギリスから来た移民の人達と、はじめから敵対したわけではなかった。
新世界での開拓生活は困難を極め、疾患、食糧不足などで、半数近くが春を迎えられなかった。
そんな開拓民に、インディアン達は食料を与え、農作業の知識や技術も教え、共に感謝祭をしたほどだった。
開拓民は感謝した。
インディアン達の不幸は、その感謝した先がインディアンではなく、開拓民が信ずる神様だったということだろう。
食糧問題も解決に向かい、人口も増えて行ったとき、白人にとって、土地を所有するという概念のないインディアン達は、隣の良き隣人ではなく、植民地の発展をさまたげる野蛮人となっていった。
争いはときに戦争にまで発展し、局地的には勝利をおさめるものの、その歴史は敗北しかなく、16000人の1300キロ大移住という悲しい末路がまっていた。
その『涙の踏みわけ道』と呼ばれる大移動では、約4000人(正確な数字はでておらず、4000人が妥当な数字と言われている)4人に1人が亡くなった。
読んでいて思ったことは、これを遠い国の悲劇としてとらえるだけはいけないのではないだろうか?ということだ。
何に、どう、生かせる知識となったのか、いまだに答えはでないものの、ぼんやりとそう思った。
そして本書の最後で、こう綴られている。
インディアン問題はインディアンをどう救うかという問題ではない。インディアン問題はわれわれの問題である。われわれをどう救うかという問題である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
