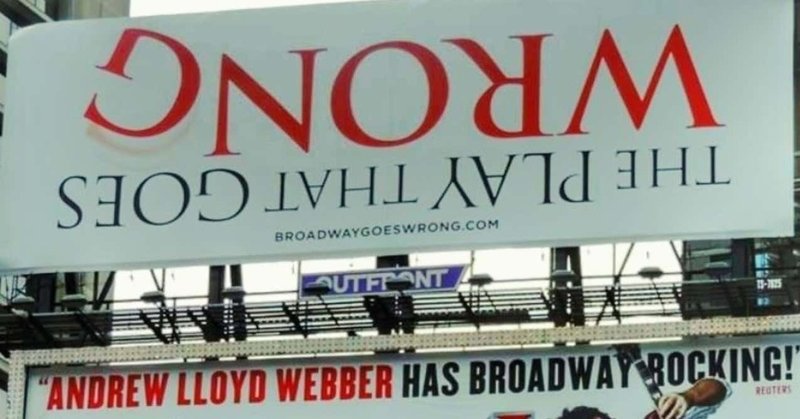
共通テストの要項がようやく発表されたものの…
▼河合塾の基礎シリーズ(1学期)も間もなく終講です。広島校・福山校は比較的早い時期に対面授業が始まりましたが,それでも全12講のうち第7講からのスタートでしたから,今年の基礎シリーズは,生徒さんとようやく顔なじみになってきたのにもう終了,という感じです。
▼東京ではコロナウイルスの新規感染者が再び増加傾向にあり,まだまだ油断はできません。もっとも,コロナウイルス禍が落ち着くにはあと1年か2年はかかるとも言われていますから,特効薬もワクチンも存在しない以上,この厳戒態勢が今後もずっと日常として続くことはほぼ間違いないでしょう。
共通テストの日程が決まったが…
▼さて,2021年1月に行われる大学入学共通テストの募集要項がようやく6月30日に発表されました。本来は「2年前ルール」に従い,2019年1月の時点で確定して公表していなくてはならなかったにもかかわらず,ここまでずるずると引き延ばし,多くの若者を振り回してきた文部科学省の罪は大きいと言えますし,そもそも改革の必要などなかったはずなのに,なぜか無理筋の「入試改革」を言い出した政治家や官僚がいて,それに伴って民間英語検定試験の導入や記述式問題の導入が計画され,無謀で場当たり的で利益相反行為を含み,教育のことなど全くと言っていいほど考慮していない杜撰な「大学入試改革」のお粗末な制度設計が,この混乱状態を招いてきたのです。民間英語検定試験導入は2019年11月に見直しがなされ,記述式導入は2020年1月になって見直しがなされました。しかし,政治家も官僚も,誰一人としてこの混乱に対する明確な責任はとっていません。おそらく「たかが大学入試」と軽く見られているのでしょう。なお,こちらがその元凶となった,教育再生実行会議「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について(第四次提言)」(2013年10月31日)です(PDFファイル)。
▼さらに,2020年になってからコロナウイルスが猛威を振るい,入試どころか通常の学校教育すら棚上げにされる事態に見舞われました。そんな混乱を経て先日ようやく発表された要項ですが,コロナウイルス対策を考慮した異例の日程になっていました。
追試験の位置づけが変わった
▼これまで,センター試験では本試験の1週間後に追試験が行われましたが,今回は「本試験」「追試験」という呼び方ではなく,「大学入学共通テストの実施期日は,入学志願者が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の
遅れ(以下「学業の遅れ」という。)に対応できる選択肢を確保するため,次のとおりとする」として,以下のような日程となりました。
令和3年度試験実施期日
・令和3年1月16日(土)、17日(日)
・令和3年1月30日(土)、31日(日)※1
・特例追試験 令和3年2月13日(土)、14日(日)※2
※1 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の遅れを在学する学校長に認められた者
及び1月16日,17日に実施する試験の追試験を受験する者を対象として実施
※2 1月30日及び31日の追試験として実施
▼以下,1月16日・17日を「第1日程」,1月30日・31日を「第2日程」と呼ぶことにします。
▼これまでのセンター試験の「追試験」は,次のような場合に受験可能な試験でした。
追試験が認められるケースには、病気や負傷、事故、その他やむを得ない事情(両親の危篤、自宅の火災)などがあります。特に、センター試験は体調の崩しやすい1月に実施されることもあり、当日に病気になってしまう受験生も少なくありません。インフルエンザ、ノロウィルスなどの感染症を発症した場合、医師の診断書があれば、追試験の受験が可能です。ただし、単なる発熱や頭痛など、病院で感染症とは診断されない症状は、追試験が認められない可能性があります。
▼今回の共通テストの第2日程は,こうした従来の追試験受験生に加え,「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の遅れを在学する学校長に認められた者」とされていますから,各高等学校の裁量で受験できることになります。しかし,そうなると浪人生はこの措置の対象外ということになります。また,受験生は出願時に第1日程にするのか第2日程にするのかをあらかじめ選択しなければなりません。
この試験について大学入試センターは、高校3年生は、通学する高校の校長が認めれば休校の期間や居住地に関係なく、受験できるようにすることを明らかにしました。
受験する生徒は、ことし9月下旬から始まる出願の際に、本試験とこの試験のいずれかを選択する必要があるということです。
▼センター試験では「追試験の方が難しい」という噂がまことしやかに流れてきました。そもそも本試験と追試験とでは受験者の母集団が異なる以上,追試の方が難しいかどうかを検証することは不可能です。逆に,年度や科目によっては追試験の方が易しかった,という可能性も否定はできません。ただ,一つ,確実に言えることは「2回の試験で難易度を全く同一にすることは不可能である」ということです。
▼これは今回行われる共通テストの場合も同じことだと言えるでしょう。しかし,先ほどの噂話を信じ込んでいる受験生も少なからずいると考えられますから,大半の受験生は第1日程を受験するのではないかと思います。まして,1月30日・31日だと医学部を中心に私大の受験が既に始まっている時期ですから(関関同立は例年2月1日から),その点からも第2日程を敬遠する受験生も多いと思われます。
「特例追試験」の問題点
▼こうした第1日程・第2日程に加えて,さらに2月には「特例追試験」を行うことになりました。この「特例追試験」については,次のように規定されています。
令和 3 年 1 月 30 日(土)及び 31 日(日)に実施する試験を疾病,負傷等やむを得ない事情により,受験できない者を対象として,次のとおり特例追試験を実施する。
① 実施期日は,令和 3 年 2 月 13 日(土)及び 14 日(日)とする。
② 試験場は,原則として全国を 2 地区に分け,地区ごとに 1 か所を設定する。
③ 特例追試験の受験については,所定の基準により,各大学において申請事由を審査し,許可するものとする。
④ 特例追試験は,「令和 3 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針」(令和 2 年 6 月 30 日一部変更)によらないものとする。
⑤ 特例追試験の出題教科・科目の出題方法等及び時間割は,別紙 2 のとおりとする。
▼おそらく,第2日程を受験することになっていたのにコロナウイルスやインフルエンザなどに感染して受験できなかった受験生のための救済措置ということなのでしょうが,問題は〈特例追試験は,「令和 3 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針」(令和 2 年 6 月 30 日一部変更)によらないものとする〉という規定です。
▼この「特例追試験」の英語について,実施要項には以下のように明記されています。
「コミュニケーション英語Ⅰ」に加えて「コミュニケーション英語Ⅱ」及び「英語表現Ⅰ」を出題範囲とする。
【筆記】として,発音,アクセント,語句整序などを単独で問う問題も出題する。
【リスニング】の聞き取る音声は,全ての問題において2 回流すものとする。
▼なんと,特例追試験だけはセンター試験の形式のままの問題なのです。というのも,これはセンター試験の予備問題を用いるためであり,そのため,英語以外の科目でも同じことになるようです。以下の記事によれば,具体的には「2013年度~2015年度に作成されたセンター試験の予備問題」を使うということです。
第2日程をやむを得ない理由で受けられなかった人を対象とする特例追試(2月13、14日)では、2013~15年度に作成された大学入試センター試験の予備問題を使用する。共通テストの予備問題を用意していなかったためだが、両テストの出題コンセプトは異なり、科目によっては試験時間にも違いがあるため成績の比較が難しくなる。大学入試センターの担当者は「特例追試の成績をどう扱うかについては、各大学で判断してもらいたい」と話している。
▼3つの試験のうち,2つは同じ形式の問題を使い,残る1つが別の形式の問題を用いるとなると,3本のモノサシのうち1本だけが異なるのですから,不公平になるのではないかという危惧があります。いや,それ以前に,そもそも第1日程・第2日程にしても,同じ形式の問題とはいえ,母集団が異なるのに公平に得点で序列をつけることができるのでしょうか。
▼萩生田文部科学大臣は次のように述べています。
2021年の大学入学共通テストにおいて、第2日程の追試として行われる「特例追試験」で、大学入試センター試験の緊急対応用の問題を活用することについて、萩生田光一文科相は7月3日の会見で、「そのことで不利益を被ることはない制度設計になっている」と述べ、一部の出題形式が異なっても、共通テストとの間の公平性に大きな問題は生じないという認識を示した。
▼大臣は「不利益を被ることはない制度設計」と言っていますが,1つ前に引用した記事では〈大学入試センターの担当者は「特例追試の成績をどう扱うかについては、各大学で判断してもらいたい」と話している〉とあることから,現段階では各大学に「丸投げ」されることが考えられるため,はたして本当にそのような制度設計がなされているのかどうかすら疑問に思わざるを得ません。
▼こうした複数日程の問題について,京都工芸繊維大学の羽藤由美教授は,Twitterで次のように述べています。
「駿台共通テスト模試」と「進研共通テスト模試」のどちらかしか受けてない人たちがいて、その得点を一律に並べて、上位から大学の合格者を決めて構わない? 共通テストの本番では、それと同じことが起こるのだけど構わない? 受験生や保護者はそれに納得してる?
— 羽藤由美 (@KITspeakee) July 4, 2020
共通テスト導入の初年度。第一日程と第二日程のテスト内容が似ていれば似ているほど第二日程組が有利(第一日程しか受けられない浪人生は圧倒的不利)。テストの内容が違えば違うほど、2つのテストの得点を比べて合格者を決めることの不合理・不公平が増す。
— 羽藤由美 (@KITspeakee) July 4, 2020
共通テストの一本化を!皆で働きかけよう!
▼また,以前から共通テストの含む様々な問題点について熱心に取り組んでいる城井崇衆議院議員も次のように指摘しています。
7月2日、共同会派文部科学部会を開催。令和3年度大学入試日程等について文部科学省より聞き取り。
— きいたかし(城井崇) (@kiitakashi) July 2, 2020
受験生救済が名ばかり、共通テスト第2日程の1週間後ろ倒しだけで出題範囲に変更なく学びの遅れへの配慮が不足、複数回の共通テストでは難易度がそろわず公平性担保がない等私からまず発言。
(続く) pic.twitter.com/HyijOsdwZe
その他にも、共通テストの救済対象と効果が不明、共通テストだけ後ろ倒しで2次試験の準備期間は短縮される影響への配慮がない、2次試験の科目指定は単なる要請で各大学の対応はばらける、なども指摘しました。
— きいたかし(城井崇) (@kiitakashi) July 2, 2020
(続く) pic.twitter.com/5b977pCuIu
入試日程等の方針は全国高校長アンケートの結果を踏まえた高校・大学関係者の協議結果に基づくとの説明を繰り返す文部科学省。問題作成や実施の関係者が大人の事情を貫いた結果、結局受験生にそのしわ寄せを押し付ける結果に。公平な入試機会のため引き続き具体的な改善点を文部科学省に訴え続けます。
— きいたかし(城井崇) (@kiitakashi) July 2, 2020
▼先に書いたように,萩生田文部科学大臣は「不利益を被ることはない制度設計」と述べていますが,その具体的な内容は一切明らかにしていません。もっとも,どのような「制度設計」を行おうとも,そもそも複数回の試験を導入する以上,羽藤教授や城井議員が言うように不合理・不公平さは解消できません。
特例追試験で国公立二次の出願は間に合うのか?
▼さらに,次のような問題点も指摘されています。
大学側への成績提供時期は第1、2日程ともに2月8日以降とした。予定より1週間程度遅れるため、共通テストを使う私立大は日程調整が必要となる見通し。特例追試の成績提供は同月18日以降となり、国立大前期日程の出願に間に合わない可能性もある。
▼特例追試験で使用するのはセンター試験の過去の予備問題で,成績の利用方法は各大学任せ,おまけに「国立大前期日程の出願に間に合わない可能性もある」となると,いったい何のための特例追試験なのか,と疑問に思わざるを得ません。もちろん,コロナウイルス禍という異常事態下での対応であることは承知していますが,受験生や大学の現実を無視し,「とりあえずかたちだけ整えた」という「お役所仕事」の極みにすら思えます。
共通一次試験導入の経緯
▼そもそも,なぜ国公立大学の入試は一次・二次と分かれているのでしょうか。1979年に国公立大学の共通の一次試験として「共通一次」が導入されましたが,それ以前は各国公立大学が独自に一次試験・二次試験を行っていました。そして,一次試験の役割は基本的にいわゆる「足切り」と呼ばれる二段階選抜のためであり,一定水準の基礎知識を有する受験生であるかどうかをふるいにかけることが目的だったわけです。
▼しかし,各大学が独自に問題を2回に渡って作成・採点するのは非常に大きな負担がかかります。当時は現代のようにコンピュータやマークシートリーダーが発達していたわけではありませんから,各大学はすべて手作業で採点をしていました。また,大学独自の入試の場合,高等学校までの学習内容の範囲からの出題が担保されず,難問・奇問が出題されることもありました。だとすれば,基礎知識を問う足切りだけの役割であるならば,何も各大学が独自に作成しなくても,文部省(当時)が大学入試センターを設立し(1977年),全国で共通の一次試験を行って,その成績を各国公立大学で活用すれば済むのではないか,となったわけです。
▼なお,共通一次導入の背景に「あさま山荘事件」(1972年)があった,という指摘もあります。1949年から1978年まで,国公立大学は一期校と二期校に分かれて入試が行われていました。
1949年
一期校 北海道大学、岩手大学、東北大学、東京大学、東京農工大学、東京工業大学、東京藝術大学、東京教育大学、一橋大学、電気通信大学、新潟大学、福井大学、名古屋大学、愛知学芸大学、三重大学、京都大学、京都学芸大学、奈良学芸大学、大阪大学、大阪外国語大学、神戸大学、島根大学、岡山大学、山口大学、徳島大学、高知大学、九州大学、福岡学芸大学、長崎大学、宮崎大学
二期校 室蘭工業大学、帯広畜産大学、小樽商科大学、北海道学芸大学、山形大学、弘前大学、福島大学、茨城大学、宇都宮大学、千葉大学、お茶の水女子大学、東京学芸大学、東京外国語大学、群馬大学、埼玉大学、信州大学、横浜国立大学、富山大学、金沢大学、山梨大学、静岡大学、名古屋工業大学、岐阜大学、滋賀大学、京都工芸繊維大学、奈良女子大学、大阪学芸大学、和歌山大学、鳥取大学、広島大学、香川大学、愛媛大学、九州工業大学、佐賀大学、熊本大学、大分大学、鹿児島大学
1977年
一期校 北海道大学、岩手大学、東北大学、東京大学、筑波大学、東京藝術大学、千葉大学、お茶の水女子大学、東京工業大学、東京水産大学、一橋大学、新潟大学、富山医科薬科大学、金沢大学、浜松医科大学、名古屋大学、三重大学、滋賀医科大学、京都大学、奈良女子大学、大阪大学、神戸大学、鳥取大学、岡山大学、広島大学、徳島大学、高知大学、九州大学、九州芸術工科大学、長崎大学、熊本大学、宮崎大学、琉球大学
二期校
北見工業大学、旭川医科大学、帯広畜産大学、小樽商科大学、北海道教育大学、室蘭工業大学、弘前大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、福島大学、茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、電気通信大学、東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京学芸大学、東京商船大学、東京農工大学、横浜国立大学、富山大学、福井大学、山梨大学、信州大学、静岡大学、愛知教育大学、名古屋工業大学、岐阜大学、滋賀大学、京都教育大学、京都工芸繊維大学、奈良教育大学、大阪外国語大学、大阪教育大学、和歌山大学、島根大学、山口大学、香川大学、愛媛大学、九州工業大学、福岡教育大学、佐賀大学、大分大学、宮崎医科大学、鹿児島大学
▼太字にした大学は旧帝大ですが,このように旧帝大はすべて一期校に含まれていたため,「一期校=エリート」という意識が生まれ,「二期校コンプレックス」という言葉も生まれました。そして,あさま山荘事件を引き起こした連合赤軍メンバーに二期校の大学出身者が多かったことから,国会で次のようなやり取りがなされました。
そのころ,大学入試改善会議報告では否定的な見解となっていた,一,二期校の一元化問題が再燃した。そのきっかけは四七年二月に起こった連合赤軍のあさま山荘ろう城事件である。なぜこのような異常な過激派の事件がおきたのか,また対策はどんなものかを審議した国会に参考人として出席したある国立大学長は,過激派を多数輩出した理由を問いただされて「二期校コンプレックス」について述べて,議員の共感を得た。これに当時の奥野誠亮文相が乗せられた形となり,文部事務当局に対して,一元化の至急実現を支持したと言われている。
(黒羽亮一『戦後大学政策の展開』,玉川大学出版部,2001,pp.138-139)
▼つまり,国公立大学共通の統一試験としての一次試験導入は,①大学が2回の試験を行うことの負担軽減,②難問・奇問を排除し,高等学校学習内容を問う入試の必要性,③一期校・二期校の区分による序列化の解体,という目的のもとに行われたわけです。
▼しかし,皮肉なことに,試験を一元化したことにより,逆に偏差値による序列化が進み,③の目的は達せられるどころか逆に序列化が加速したことになります。
▼その後,1990年に私大も参加可能な「大学入学センター試験」へと改称され,受験科目数も柔軟性を持たせたものになりました。そして2021年の1月から「大学入学共通テスト」へと改称されることになったのです。
▼ここまでの流れをまとめると以下のようになります。
1949年~1978年:一期校・二期校時代(各大学独自の一次・二次試験)
↓…1965年頃から「統一共通テスト実施」の議論
↓
↓…1972年「あさま山荘事件」
↓
1979年:大学共通第一次学力試験(共通一次)開始
↓
↓…共通テストへの私大の参加を検討
↓
1990年:大学入学センター試験開始
↓…2006年 英語にリスニング導入
↓…2013年 教育再生実行会議第四次提言
↓ 英語を民間検定試験に→2019年11月に撤回
↓ 国語・数学で記述式問題を導入→2020年1月に撤回
↓
2021年:大学入学共通テスト開始
▼こうして振り返ってみると,結局,名前が変わっただけで,共通の一次試験を行うことの是非や,そもそも国公立大学が一次・二次と2回試験を行うことの是非については一切議論されず,また,一期校・二期校時代からの「序列化」がますます明確になっただけで,過去70年間に渡って何も変わってこなかったのではないか,という気さえします。
共通の一次試験は必要なのか?
▼大学入学後の一定の学力を担保する,という意味での大学入試そのものは必要だと思いますが,はたして,各大学に共通の一次試験を維持する必要はあるのでしょうか。私自身は,共通の一次試験は廃止して,各大学が独自の選抜を行うべきだと考えています。
▼仮に,二段階選抜のためだけに導入するのであれば,各大学が独自に一次・二次を行うか,1つの試験の中に基礎知識を問うAパートと論述力を問うBパートを混在させ,「Aパートで一定以上の得点を挙げた答案のみ,Bパートを採点する」という方式にすれば済む話です。あるいは,英語,数学などの科目試験を一次試験扱いとし,二次試験として小論文を課して「一次試験で一定以上の得点を挙げた受験生のみ二次試験を採点する」という方法も考えられるでしょう。
▼一元化による序列化を解体するには,各大学が独自のものさしを導入し,受験生が自分の能力や適性に応じて,自分に合ったものさしを使った試験に臨めるようにすることが必要です。それには各大学が統一試験にゆだねるのではなく,最初から最後まで自らの教育方針,アドミッションポリシーを反映させた選抜方式を確保することが必要です。
▼しかし,もちろんこれだけでは序列化は解体できません。大学の外側の社会の側が人材を登用する際に旧来の「一つのものさし」を捨てる必要もあります。
▼コロナウイルス禍によって,日本だけでなく世界の未来も一層混沌としてきました。もはや「統一化されたものさし」は存在しません。明治政府樹立から第二次世界大戦終了までの「富国強兵・殖産興業」というスローガンや,戦後の「高度経済成長」という目標は,ある意味「わかりやすい」ものさしで,それに見合った試験を導入すれば済んだわけですが,バブル崩壊以後,現代に至るまで,そうした明確なものさしは姿を消しました。共通テストにおいては「グローバル化に対応する」というのが一つのものさしではありますが,そのものさしの下で「グローバル化には英語だ」という狭隘な視点でしか物事を考えられず,「そのためには民間英語検定試験を導入すれば良い」という無責任な丸投げの姿勢で制度設計を行ってきたのですから,もはや共通テストという枠組みそのものを解体し,「混沌」と立ち向かうための学びを重視することが必要なのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
