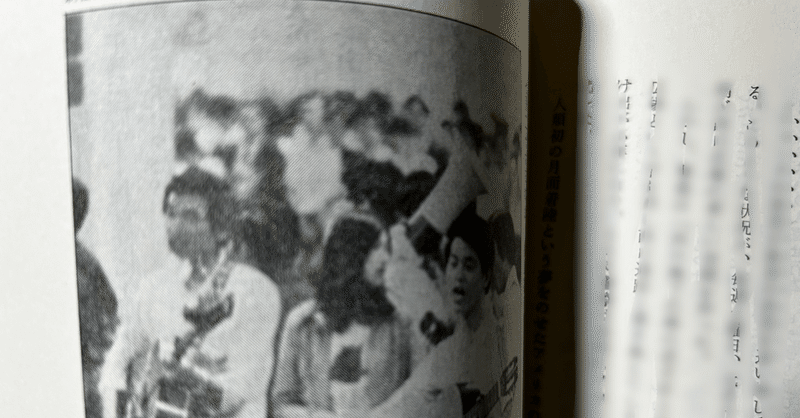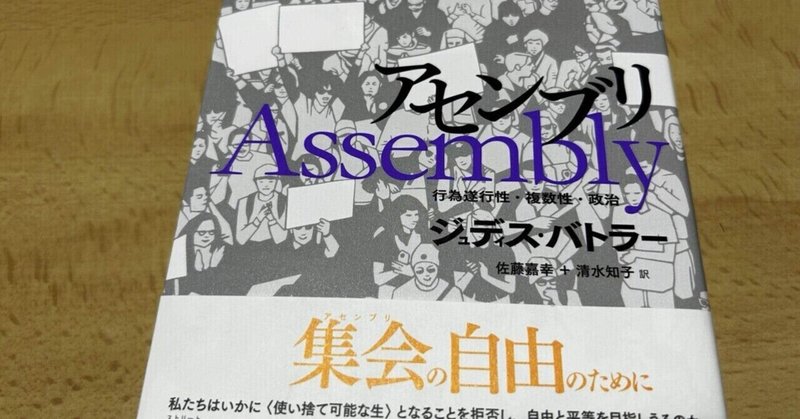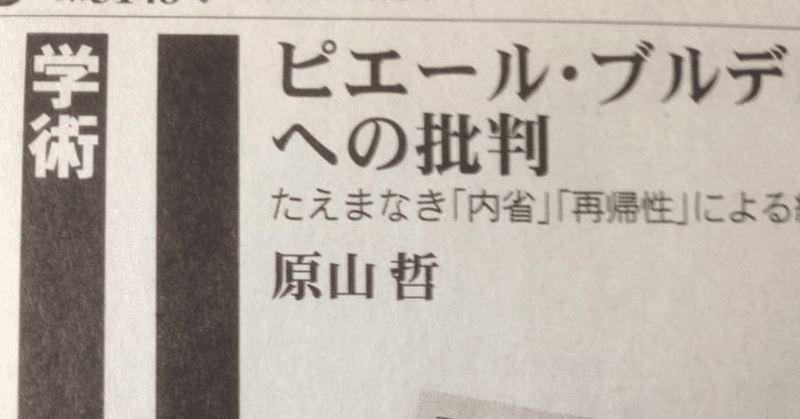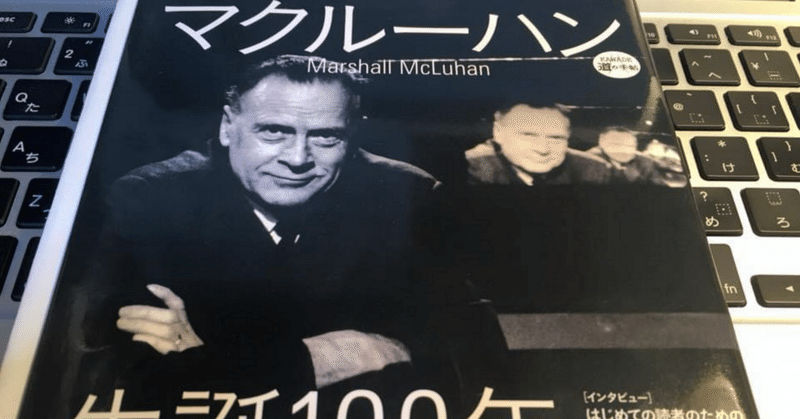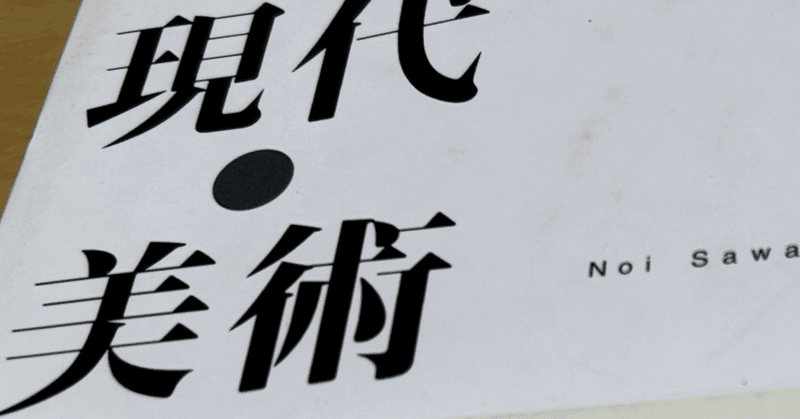2024年2月の記事一覧
パフォーマティヴな言語行為についてのメモ
今日の研究。
パフォーマティヴの理論と言語行為論は、ジュディス・バトラーが身体をめぐる行為(行動)にまで広げていることと関連して言語が実践の問題として応用されているということも含めて理解されるべきであろう。
バトラーは身体性、物質性ということを強調しているが、『ジェンダー・トラブル』はむしろ言語、言説という上部構造の問題をパフォーマティブに実践するという方法ではなかったかと思われる。
私は、修
マクルーハンから視聴覚文化へ
マクルーハンはメディアとの関係から時代について考えていた。哲学者、アンリ・ルフェーヴルは、「空間」の問題を「空間的実践」「空間の表象」「表象の空間」という概念から考察していて、ここで「空間的実践」を視覚優位の近代社会における「知覚されるもの」「知覚された空間」と認識していたが、マクルーハンは現代(1960年代)を電気メディアの時代と捉え、この時代から「グローバル・ビレッジ」という新しい部族村につい
もっとみる謎の百科事典もどき「Expedia」
粟谷佳司 - 謎の百科事典もどき「Enpedia」
ノート 大阪万博と日本の前衛芸術家たち 戦後文化の歴史社会学その1(吉田秀雄記念事業財団助成研究の別バージョン)
2017年のFacebookの投稿から。
1970年の大阪万博において芸術家が多く参加していたことはよく知られている(例えば、椹木野衣『戦争と万博』)。ここでは多くの芸術表現が見られた。音楽に関しては、戦後日本を代表する前衛音楽家が多数参加している。
そして万博における芸術家たちの活動を考察する上で、日本政府館に音楽作品を提供し、鉄鋼館のスペースシアターの前段階で構想され結局は頓挫した「大原立