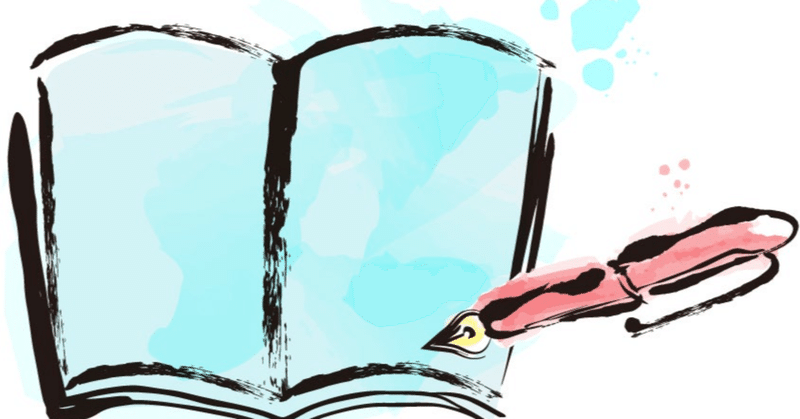
理系大学生向け推薦本を段階的に紹介する その1「理科系の作文技術」
高校までの教育課程とは異なり、大学ではアウトプットの機会が多く設定されている。実験レポート、研究室(ゼミとも呼ぶ)や学会での発表、論文といった具合に年次が上がるにつれてより高度なアウトプットを求められるようになる。しかしながら私が思うに、現行の大学教育ではアウトプットのトレーニングを学生に十分に積ませていないために研究室に所属してからの指導教員の負担が増加しており、かつ研究室によって学生の質にばらつきが生まれてしまっている。
本稿では理系の大学生が自らアウトプットの訓練をしたいと考えた時に役に立つ本を数回に分けて紹介する。いずれの本も大学4年の間に一読を勧めたいが、社会人になってから読んでも遅くはないだろう。
概要
第1回となる今回は「理科系の作文技術」を取り上げる。古典的名著であり、必読…というよりも大学入学直後に本書の内容について数時間講義するだけで多くの理系大学生が救われるのになぜしないのかがわからない。高校生が読むには難しい部分もあるが、日本語で論文を書くよりも前には必ず目を通しておきたいので大学生になったら早い段階で読んでおくべき本である。
本書の主題はわかりやすい文章を書くためにはどうすればよいのか?というものだ。誰もが心を揺さぶられるような小説チックな文章を書くためではない。理系の人間が仕事で求められる文章を書くうえで、執筆前の準備方法や微視的・巨視的に注意すべき事項について簡潔にまとめてある。古い本なので時代遅れの記述もある※がそれでも学ぶべき部分は多い。
※ 例えば学会講演の項でスライド操作を映写係に任せている記述があるが、PowerPointを使う現代人にとっては理解できないだろう
内容
本書の内容を要約しつつ私個人の見解も書いていく。
序章
理系の人間が仕事のために書く文章は、他者に事実と意見を伝えるための媒体である。詩や歌詞、ブログの文章とは異なり、心情的要素を含まないのである。事実と意見を他者へ伝達するのが第一義であるがゆえに、書き手は明快で簡潔な文で論理的に文章を組み立て、かつ読者の期待に沿う形で情報を整列させるべきである。カメラの取扱説明書を例に挙げると、カメラを手にした人間が真っ先に知りたがることへ繋がるように情報を提示する必要がある。

明快な文章を書くためには、文章の構成だけではなく一文の単位でも注意が必要である。筆者は以下の3点を心得として挙げている。
①表現が一義的に読めるように記述する
②明言できることは言い切るべきであり、ぼかした表現は使わない
③なるべく普通の用語で短く文章を構成する
文書作成の準備
文書を作成するにあたっては何を書いて、何を書かないかを決める必要がある。しかし理系の文書では表現すべき内容は決まっているはずである。あなたが作成しようとしている文書は、学会に提出するあなたの研究要旨であることもあれば、先週行った銅線の抵抗が示す温度依存性を観測するための実験のレポートかもしれない。文書が担う役割は明確にしたうえで書く内容を決めるべきである。
文章の組み立て
起承転結ではなく、重点先行主義を貫いた方が良い。読者がその文章を読む価値があるかを判断できるようにするために、表題と書き出しの文を含めて文章のエッセンスが伝わるようにすべきである。これは学術論文を読んだことの無い人間にはわかりにくいかもしれないので補足しておく。一般的に学術論文ではタイトルの後にabstract(概要), introduction(序論), method (手法), results and discussion (結果と考察), conclusion (結論)と続く。大部分の読者が論文のどの部分まで読んでくれるかといえば、タイトルとabstractだけである。論文を読むために使える時間は限られているため、タイトルとabstractだけで「読む価値がある論文か」を読者は判断する。少なくとも私はそうしていた。タイトルでざっとどんな方向性の研究なのかを掴み、abstractを読んで研究内容(=著者は何をstateしたいのか)を理解する。一番重要な情報を文章の先頭付近に配置して読者による論文の取捨選択に要する時間を省略するのが学術論文における文章構成の傾向である。そしてこの傾向を他の文章でも貫くべきだというのが筆者の主張である。

パラグラフ
パラグラフではトピックセンテンスを設けるようにする。そのパラグラフで何について何を言おうとしているかを概論的に言い切る文章を書く。原則として重点先行主義に倣い先頭の文章をトピックセンテンスとすべきである。しかし他のパラグラフとのつなぎの文章を要する場合もあるのでこの原則を完全に守るのは難しい。
文構造の注意点
文章は著者の主張に沿って一本道でなければならない。脇道に逸れたとしても最後まで読めば文意が取れるように記述するというのは望ましくない。筆者はこの主張を「逆茂木型の文章は避けるべきである」と表現している。逆茂木とは、木の枝をとがらせて地面に固定し、敵の接近を防ぐ障害物の一種である。
私なりに逆茂木型の例文を書いてみた。
「目隠しされた状態でデッキ内の存在する望みのカードを引き当てる所業を達成するために使用したと思われる技術が、デッキからカットした一部のカードの枚数を数えることなく目視や指先の感覚で枚数を正確に推定するマジックの技術の一種であるエスティメーションであり、後に映像で行動を見返した際にその場に居合わせた総勢10名の科学者である我々によって推定された事の顛末である。」
本文章では前置修飾節が長い。エスティメーションという単語を修飾節で説明しようとするあまり頭でっかちな文章になっている。最後の「我々」という単語に対して複数の修飾句が紐づいており、修飾句がどの語にかかるのかが最後まで読み込まないと理解できない。
筆者は逆茂木型の文章を避けるために三つの心得を示している。
①一文の中では二つ以上の長い前置修飾節は避けよ
②修飾節の中の言葉には修飾節はつけない
③文や節は前の文章とのつながりが浮き立つように書くべき
長すぎる文は細かく分割し、前置修飾節が修飾する単語は前に出すと良い。

はっきり言い切る姿勢
事実と意見を峻別し、はっきりと言い切る姿勢を貫くべきだ。「…デアロウ」、「…ト見テモヨイ」などのように曖昧な文末を取ると、事実なのか意見の一種である推論なのかを読者は判断しかねる。事実であるならばはっきりと言いきり、推論であるならば「私は…と考える」と明記した方が良い。
わかりやすく簡潔な表現
前章までは巨視的視点で文章の技術をまとめていたが、本章は微視的視点での技術である。一言で本章の内容をまとめれば、「文は簡潔にして簡明な表現を使用し、日本語として正しくあるとともに、一義的に読めるものにすべき」と要約できる。
例文1
「施設栽培で問題となるのは、前回の講義で述べたように、寒冷地とそれ以外の地域で栽培方法が異なったりする。」
この文章は末尾を「ことである」としなければ格が正しい文章にならない。
例文2
全ての増幅器は安定でない
いかなる増幅器もみな不安定であると言いたいのか、増幅器の集合の中には安定でないものが存在すると言いたいのかが不明瞭である。これは否定を意味する「でない」が、「全て」と「安定」のいずれか否定しているのかがわからないため生じている。
本書を勧める理由
分かりやすい文章を書けるというのはそれだけで価値があると私は考えている。上司にかつて「君の文章を読んで私もまったく同意見だと思ったよ」と言われたことがあるが、私が支離滅裂な文章を書いていたらこのコメントは到底得られなかっただろう。
少々厳しいことを言えば、他人の書く文章に目を通すとがっかりすることも多い。「この文章は接続詞が多すぎる。パラグラフ同士の関係を接続詞を使わなければ表現できないなんて文章を論理的な構造にできていない証拠だ」となったり、「パラグラフ内での文章は引き締まったいい文章なのだが、タイトルの内容に対してアンサーを出している箇所が全く分からない。情報を提示する順番に欠陥がある」と思ったりする。私としては不満もあるのだが、文章を分かりやすく書ける能力を全員に求めるのは酷な話だと今では考えている。

分かりやすい日本語を書くと口で言うのは容易いが実行するのは難しい。習得するためには意識的な訓練が必要になる。高等教育で学べるかと思えばそうでもない。研究室では自分が書いた論文を教授なり助教なりが添削してくれると思うが、それまでの4年間にまったくアウトプットの練習をしないと研究室には入ってから多大な苦労をする羽目になる。大学生になったら早い段階で読んでおくべき本であると冒頭で私が述べたのは、実験レポートを書く段階で本書の内容を実践してほしいためである。実験レポートで練習をしておけば研究室に入ってからの苦労が減るだろう。
当然大学教授たちもアウトプットの練習の場として実験レポートを位置付けている。以下は大阪大学のwebページに書かれた文章である。
自分が行った仕事や研究は、まとめて発表しなければ、誰も知らず、誰にも利用してもらえない独りよがりにしかすぎない。
行ったことをまとめて発表する。
これが大切であるが、他人に誤解無く理解してもらうことはとても大変なことだ。そのことを物理学実験では、レポートを書くことで勉強し、将来に備えてもらおうと考えている。
ここに書かれたことには完全に同意するのだが、指導教官たちも多忙であるためあなたの提出したレポートの一言一句までは注意しない。「全ての増幅器は安定でない」とあなたが書いたとして、「この分は一義的に読めないので別の表現にすべき」とまで添削してはくれないのだ。だからこそ、自分で意識的に学ぶ必要がある。本書はその手助けとなってくれる良書である。ぜひとも手元に置いて、レポートを書く前に一度読み込むようにしてほしい。短めの本であるため、定期的に読み直すのもオススメである。
最後に、私が尊敬する加納学先生のnoteを張り付けておく。「何度も繰り返すが,しっかり読んで実行して欲しい.確実にレベルアップできるから.
」というのが加納先生の弁だ。肝に銘じておこう。
余談
ちなみに今回ブログで取り上げるにあたって読み直したが、現時点での私からすれば「何を当たり前のことを言っているんだ?」と思う記述も多くあった。自分の文章に筆者である木下是雄先生の意思が受け継がれているのを感じて実に気分がいい。己の成長を実感した瞬間である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
