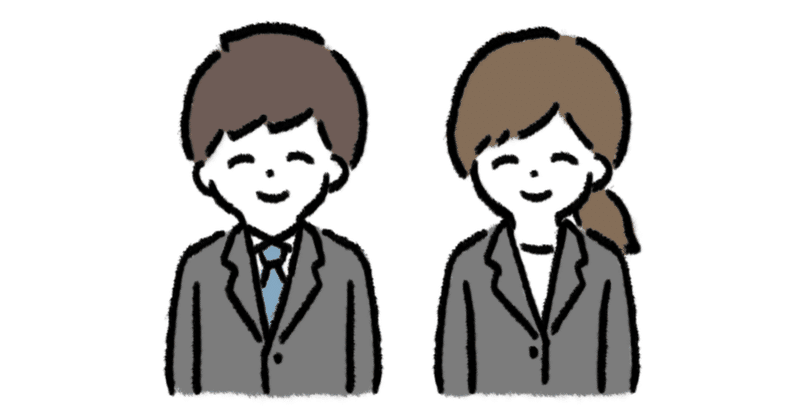
教採対策@養護教諭②🔥二次試験対策
みなさんこんにちは!
養護教諭@仕事効率化&教採応援🎌です🙋♀️
今回は二次試験対策について
記事を書いていきたいと思います!
二次試験対策というと
どのような対策をすればいいの?と
悩んでいる人も多いと思います🤔
そしていつ頃から始めればいい?と
思っている方もいるでしょう
二次試験は…
思い立ったらすぐに
対策することがおすすめです!
「一次試験が終わってからでも大丈夫でしょ!」
と思っている方もいるかもしれませんが
面接や小論文などの二次試験の科目は
繰り返し対策を行うことで
自分の力になるのです💪
一次試験と並行しながら
対策をするのは大変ですが
合格をつかみ取るためにも
早めからの対策を心がけましょう!
さっそくおすすめの試験対策を
紹介したいと思います!
複数人で行う対策だけでなく、
一人でもできる対策も紹介するので
時間のある時にぜひ取り組んでみてください💁♀️
〜面接編①〜
面接は練習あるのみ!
ほぼ全部の自治体で面接は
あるのではないでしょうか?
でも、面接って一番緊張しますよね😣
私も苦手意識があり試験を受けた時さえ
自信がなかったくらいでした💦
むしろ面接以外で合格したのでは?と
思ったくらいです笑
(成績開示をしていないので分かりませんが💧)
でも、繰り返し練習したことで
自分の中で考えがまとまってきた
感覚がありました😊
おすすめは人に聞いてもらうことです!
恥ずかしいですが、聞いてもらうことで
自分の話し方の特徴や
文の長さがちょうどいいかなどが
明らかになると思います💡
学生であれば教採対策センターや学部の教授、
講師のみなさんは管理職や同僚の先生などに
お願いして聞いてもらうと良いです🙆♀️
東アカなどが近くにある場合は通ってみるのも
いいと思います!
考えがなかなか出てこない!という人のために
もう1つおすすめの面接対策を紹介します!
〜面接編②〜
面接ノートを作り、自分の考えをまとめましょう!
一人で面接対策をする時は
面接ノートを作り、お題に対して
自分の考えを書き込むようにしましょう!
図書館やカフェなども集中してできると思うので
おすすめです👌
お題は過去問(協同出版でも出ています)などを
参考にすると良いです🙆♀️
実際に書く時は面接で答えることを想定して
短すぎず長すぎずで考えると良いです!
文で書くよりも箇条書きで書く方がスッキリして
見やすいと思います!
まとめたものは試験会場で
直前に確認するのにも使えるので
しっかりまとめるておくことがおすすめです📖
〜小論文編〜
たくさん書いて形式に慣れましょう!
初めて小論文を書こうと思った時、
こんなに短時間でたくさん書けるのかな?
と思いませんでしたか?
私もそうでした😂
構成もよく分からず時間も
かなりオーバーしてしまい…💦
だが大学の教採対策センターで
何回も添削してもらい
繰り返し書いていく中で
構成の工夫や時間配分ができるように
なってきました😊
最初は時間をかけて書いて大丈夫です!
何回か書いてみて慣れてきたら、
時間内に書けるように練習してみましょう!
構成は最初から意識しながら
書いていくと良いです👍
序論:本論①:本論②:結論を
2:3:3:2くらいの配分で
書いていくと良いです!
共同出版などの過去問を参考にしながら
受験する自治体の今年の時間、文字数に合わせて
練習すると良いです🙆♀️
自治体によっては、過去問と同じような内容が
出るところもあるので、過去問を遡りながら
練習することがおすすめです!
こちらも内容や言葉遣いなどを
大学のセンターや管理職・同僚の先生などに
見てもらうことがおすすめです!
〜模擬授業・場面指導編①〜
実際に時間を決めて実践してみましょう!
模擬授業や場面指導は10分間などの
制限時間があることが多いと思います💁♀️
なので制限時間内でどれだけ指導できるか
実際にやってみることで実感してみると
良いです!
(仮に制限時間が10分として)
10分以内か10分でできるところまでかは
自治体にもよりますが
基準として授業の場合は
10分でできるところまででOK、
それ以外の指導は10分以内で
しっかりまとめられる(短すぎるのは×)のが
良いと思います!
過去問の傾向をつかみ、
過去問を中心に実践すると良いでしょう!
人前であまり緊張せず試験に臨むためにも
模擬授業・場面指導は誰かに見てもらうことが
おすすめです!
教採対策センターだけなどではなく
友達などに見てもらうことも良いと思います!
次はどんなお題が出たとしても対応できるように
おすすめの勉強法を紹介します🌟
〜模擬授業・場面指導編②〜
構成やミニ指導案を作成して備えておきましょう!
こちらも図書館やカフェで勉強する場合に
おすすめです!
模擬授業であれば保健の教科書の単元、
場面指導であれば過去問を中心に
ノートなどに構成をまとめておくと良いです📓
保健の単元すべての構成を考えておけば
怖いもの無しかもしれません…🤭笑
こちらも試験会場での直前の見直しに
使えると思うので
たくさんネタを書いて備えておきましょう☺️
〜集団討論編〜
複数人で練習して慣れましょう!
こちらはもしかするとコロナ禍では実施しない
自治体が多いかもしれませんが
記録として残しておきます✍
集団討論は複数人での練習が大切です!
他の受験者との協調性も見られているので
同じく受験する仲間と一緒に
対策を行うことが良いです!
注意事項としては、
「相手の考えを否定しない」
ことです!
もし直前に話した人と異なる意見がある場合は
「○○さんの意見は〜でとても〜だと思います。それに付け加えて〜だとより〜だと思います。」
などと相手を立てながら付け加えると
考えも深まって良いと思います👍
それとなかなか発言できないと
アピールすることができませんが
その逆の話しすぎることも注意が必要です⚠️
多くの人が意見を言えるように
話す頻度にも気をつけると良いと思います!
集団で話すことに自信がない…(私もそうでした)
という方も多いと思いますが練習あるのみです!
教採仲間と練習を行ったり、
近くに東アカなどがある場合は
講座に参加してみるのもおすすめします🙋♀️
〜実技編①〜
実際に器具や模型を使いながら練習しましょう!
実技は受験科目に無かったので
対策はしていませんが、
私が考えた対策を少し紹介したいと思います💁♀️
実技の内容としては三角巾や包帯の固定、
心肺蘇生、熱中症やアナフィラキシーが
起きた時の救急処置などが
多いのではないでしょうか?
なので、学校で起こりうる
比較的大きめな事故などについての対応を
器具や模型などを利用しながら
練習すると良いでしょう!
あくまでも参考なので過去問から傾向をつかみ、自治体に合った内容の練習をすると良いです👌
制限時間もあると思うので
たくさん練習して手際よくできるように
しておくと良いと思います!
〜実技②〜
実技の練習・番外編(講習への参加)
もし、実技試験で三角巾や包帯、救急処置などが
多く出る自治体で、比較的時間がある場合は、
赤十字社主催の「救命救急講習」を
受けることをおすすめします!
(時間のある学生にもおすすめです!)
基礎講習と救急員養成講習があるので
どちらも受講するのが良いでしょう🚑
全国的に開催されており、
講習料も2つの講座合わせて
3000円ちょっとくらいなので
気軽に参加できると思います!
詳しくは、赤十字社のホームページを
ご覧下さい🙇♀️
実際に申し込みたい場合は
「赤十字 救急法 講習 ○○(都道府県名)」で
検索すると詳細が出てきます🔎
※ コロナ禍の現在では地域によっては開催が中止になってる場合もあるかもしれません。ホームページで必ず確認するようにしてください⚠️
※ 学生で受講予定の方で、学校によってはこちらの講座が大学等のカリキュラムの中に含まれていることもあります。心配な場合は大学等の先生に講習を受けたいことを伝え、カリキュラムに含まれているか確認すると良いでしょう!
❁❀✿✾
いかがでしたか?
二次試験は一次試験のように筆記がない分
少し気が緩みがちになってしまうかも
しれませんが、
意外とやらなければならない対策が
たくさんあるので
最後まで気を抜かずに頑張っていきましょう💪
みなさんが試験に合格することを
心から望んでいます🌸
ぜひ頑張ってください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
