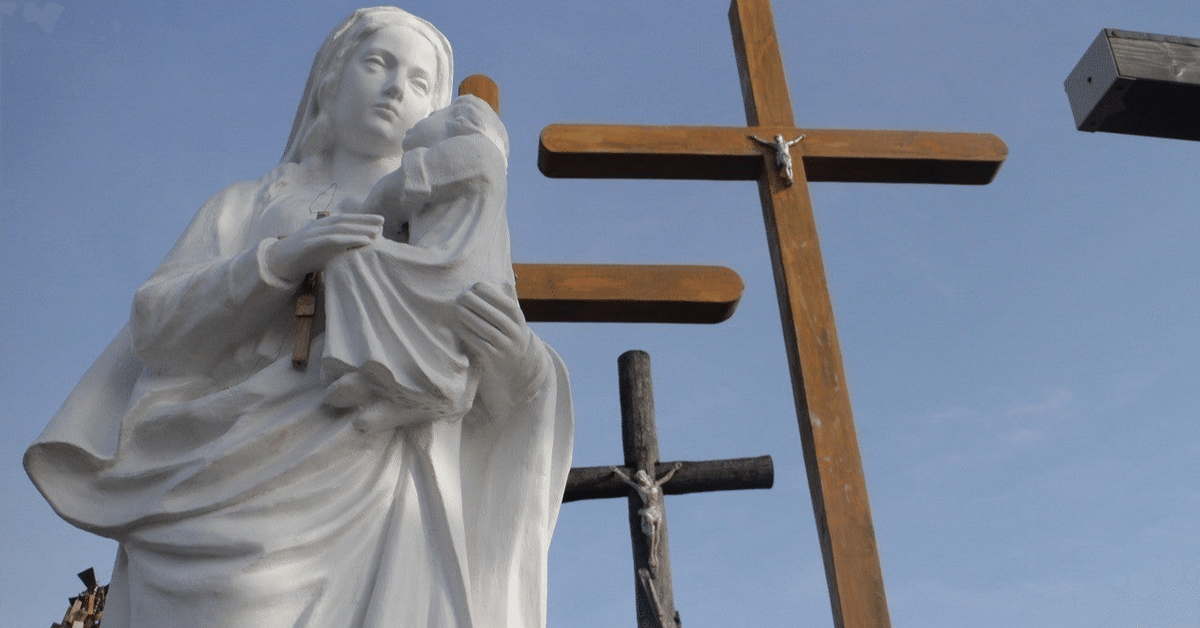
ホラーが「救済」になる日
怖いものは苦手だけど、ホラー映画は好きだった。『輪廻』や『箪笥』など、怖いけどギリギリ悪夢を見ないですむレベルのホラー映画を選んで鑑賞した。
怖いものが苦手なのになぜホラー映画は好きなのか自問した。恐怖を楽しみたいから、ではなかった。
ホラー映画ではだいたい、
「心霊現象が起きる」
「主人公が恐怖体験に苛まれながらも原因を探っていく」
「元は生きた人間だった幽霊の悲しい過去などが明らかになる」
こういう流れで話が展開する。
この「忘れ去れたもの、覆い隠されたもの」が心霊現象となって表出し、恐怖におののきながらも諦めずに真相を追求しようと頑張る主人公によって謎が解明され、「幽霊が成仏する」などでそれが解決していく様子が見たくてわざわざホラー映画を見ていたのだと思う。(なので、特に原因もわからずただ怪物が襲ってくるだけのホラー映画は好まなかった)
そこには「癒し」と「救い」があった。悲しかったこと、辛かったこと、それが誰にも知られず、救済もされないまま闇に葬られ、怨霊と化すしかなかった。自らが恐怖の超常現象となることでやっと誰かに知ってもらえる。わかってもらえる。「辛かったね」と言ってもらえる。その行程に私もどこかで癒しを得ていたのではないだろうか。
「宗教ホラー」が最近流行りだ。「宗教ホラー」という呼称で呼ばれているかは知らない。私が勝手にそう呼んでいる。(代表的なのは記憶にも新しい『ミッドサマー』だろう)
前段で、私が個人的にホラー映画から癒しを得ていた話をしたが、最近、ホラー映画が社会的な癒しを担い始めているのではないか、とどうにも感じるのだ。
社会的な癒しとは何か。それはずばり「Toxic Masculinity」の解体だ。ホモソーシャル(男性同士の社会的な繋がり)はマチズモ(男性優位主義)やミソジニー(女性嫌悪)をベースに構築され、Toxic Masculinity(有害な男らしさ)が蔓延し、女や子供、弱者を押さえつけ痛めつけるだけでなく、マチズモ的な男社会で生きる男性自身も苦しめ追い詰めている。そのToxic Masculinityを表現上でいかに解消・解体していくかは、コンテンツ業界の至上命題になっていると言っても過言ではない。
ではなぜ「宗教ホラー」がToxic Masculinityの解体になっているのか。最近見たいくつかのホラー作品から、特に印象に残っているものを例に挙げたい。(多少のネタバレあり)
まずは『ミッドサマー』。いわずとしれたアリ・アスター監督のファンタジックな雰囲気でしっかり怖いホラー映画である。主人公のダニは繊細さや思いやりを持つ女性だが、「恋人のクリスチャンとその男友達」というホモソーシャルな環境に身を置いている。「男同士のつながり(時にミソジニスティックですらある)」になじめず、居心地の悪さを感じている。そんなダニと、クリスチャン率いる男連中が、スウェーデンのホルガ村で行われる九十年に一度の夏至祭に参加し、次々に恐怖体験に見舞われるというあらすじだ。ホルガ村は独自の価値観で生きている。七十二歳になった男女の老人が公衆の面前で崖から飛び降りて自殺したり、ルビ・ラダーを盗撮した男をバラバラ死体にして土に埋めたり、クリスチャンを村の若い娘とセックスさせたりと、現代社会の常識が全く通用しないルールで生きている。ダニは初めこそ怖がりながらも、なんだかんだホルガ村に馴染んでいき、ダンスで優勝し五月の女王として君臨する。哀れクリスチャンは、ダニの命令で熊の生皮を着せられ小屋の中で燃やされ壮絶な死を迎えるのだ。
つぎにNetflixオリジナルの『真夜中のミサ』。閉鎖的な漁村の小さな教会で次々と奇跡が起き、人生を半ば諦めていた住人たちは歓呼する。村の人々も、神父も、聖書に書かれた通りの「奇跡」を期待した。古い記述や、予言の再来を期待したのである。しかし、それは実は神父が吸血鬼の力を利用して人為的に起こしたまがいものの奇跡だった。住人、ならびに真犯人であるところの神父は、奇跡への願望に取り憑かれかえって追い詰められていくが、最後にはその願望を手放し、自らの死を受け入れるという優しいラストで終わった。
こちらもNetflixオリジナルの『ザ・ミスト』。スティーブン・キング原作の映画『ミスト』のリメイク版である。面白くなくてシーズン1で打ち切りになっちゃったらしい。私は結構面白いと思ったのになあ。
『ザ・ミスト』というタイトル通り、アメリカのある町がある日突然濃霧に包まれる。霧の中からは正体不明の怪物が出てきて人を襲う。人々はショッピングモールに避難し、極限状態のなか助けを待つ…というあらすじだ。
映画版『ミスト』では「カルトおばさん」なんて呼び方をされている有名なキャラクターが出てくる。独自の聖書解釈をヒステリックに叫び、ショッピングモールの人々を扇動しようとするカーモディ夫人だ。Netflixのドラマ版『ザ・ミスト』ではフランセス・コンロイ演じる老婦人ナタリーが「カルトおばさん」的立ち位置なのだろうが、映画版とは随分異なるキャラクターとして描かれている。まずカーモディ夫人のように怒鳴らない、叫ばない。つねに穏やかで、にこやかで人当たりがいい。か弱く、守ってあげたい気持ちにさせられる。ナタリーは以前より陰謀論好きだったという、ちょっと危ない経歴がありつつも、基本的には人畜無害で、人とトラブルも起こさない。そんなナタリーが、霧の中で夫を殺され、悲しみにくれながらも教会に避難し、同じく教会に避難してきた人々から同情されながら、次第に独自の思想にのめりこみ、周りの人たちにもそれを説きはじめる。優しそうなおばあちゃんなものだから、みな話を聞いてしまう。その思想とは、「自然こそが神であり、この霧もわたしたちの味方」なのだそうだ。霧の中で殺されても、それは浄化だか回帰だかなんだかであって、恐れるべきものではないと。この教えを避難先の教会で説き始める、というのが良い対比になっている。教会のなかで別の神を信望するなんてタブーだ。当然、神父は止めようとするが、霧の中の怪物によって殺されてしまう。
この老婦人ナタリーに一番骨抜きにされてしまうのが、警察署長のコナーだ。コナーには母親がおらず、父親に虐待されながら育った。結婚し、一人息子ができたが、妻は早くに死に、男手一人で息子を育てている。誰にも守ってもらえなかった傷や寂しさを、「男らしさ」という価値観で蓋をし、警察署長という権力を得て傲慢に振る舞いながら、一人息子も「男らしい一人前にしてやらねば」と、勝手なプレッシャーを自分と息子に課している。そのコナーが、母のように優しく接してくれるナタリーに骨抜きにされてしまうのだ。ナタリーの教えを信じ、彼女の言うことならなんでも聞いてしまう。ナタリーが殺せと言えば人だって殺してしまう。警察署長として市民を守らねばならないはずなのに、という葛藤ももちろんある。しかしナタリーに優しくよしよしされながら「偉かったわね、よく頑張ったわね」と言われ、またフニャッフニャになってしまうのである。コナーが潜在的に求めていた、慈母の姿をそこに見出したのだろう。
『ミッドサマー』、『真夜中のミサ』、ドラマ版『ザ・ミスト』、この三つのホラー作品に共通するものはなんだろうか。それは「既存の概念の解体」である。『ミッドサマー』ではホルガ村の価値観によってマチズモはこてんぱんに解体される。『真夜中のミサ』では凝り固まったキリスト教的価値観、「熱心な信仰を持つもののみが救われる」という「聖別」とも取れる考え、「人生とはこうあらねば」というプレッシャー、そんなものが優しく破壊されていく。そしてドラマ版『ザ・ミスト』では、前述の通り、ホモソーシャルで権力を得、生き抜いてきたコナーが老女ナタリーとその教えによって骨抜きにされる。
「既存概念」や「Toxic Masculinity」を破壊するには、「異なる価値観」を強烈に見せつけるのが一番良い。だからこそホラーという形態が似合うのだ。それが心霊であっても自然現象であっても、とにかくホラーでは「通常では起こり得ないこと」が起きている。つまり「従来の常識が通用しない」のである。「従来の常識」とはだいたいホモソーシャルのなかで形成されたものだ。たとえば、「男は強い、腕力がある」という共通認識があったとしよう。しかし幽霊に腕力は通用しない。これだけですでにマチズモの解体だ。多かれ少なかれ、Toxic Masculinityは人々の常識や価値観に、それこそ毒のように蔓延している。そんな従来の常識の中で生きている人間たちを、まるごと異常空間に放り込む。そしてそこに新しい価値観を樹立する。それを怖い、脅威だ、と感じるものもいれば、『ミッドサマー』のダニや、『真夜中のミサ』のエリンや、『ザ・ミスト』のナタリーのように、それを受け入れ、癒しや救いを感じる者もいる。
『ミッドサマー』を鑑賞して、セラピーだと感じた人が多かったらしい。一見異常なものが襲ってくるように見えても、それが既存概念を破壊し、誰にも触れられなかった孤独や苦しみにそっと触れてくれるようなものであれば、それを救済だと感じる人も多いのではないだろうか。そしてホラージャンルは、特に「宗教ホラー」を通じて、その「救済」の表現に向けて試行錯誤している最中のように、私には見えるのである。
ドラマ版『ザ・ミスト』のコナー、一周して羨ましかったなあ。私もフランセス・コンロイによしよしされたい。(フランセス・コンロイは、『ジョーカー』でアーサーの母親ペニー役を演じた女優さんです。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
