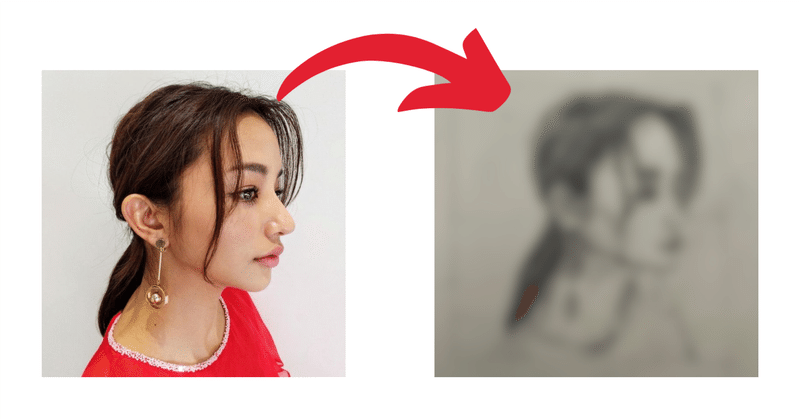
ど素人がデッサンを学んでみたら、1つのコツでデッサンが上手くなった
こんにちは、よすです。
今回は、『趣味をさがせ!』企画の第2回です。
あなたには「これがわたしの趣味です」と胸を張っていえるものは何かありますでしょうか?
ぼくにはほとんどありません。
特に独身だと、友達と会える時間がだんだんと減ってきて暇な時間をなにに使うかが悩みのタネになってきますよね。で、あるとき気づくんですよね、「趣味がない」って。
また、AIの登場により、将来は人間にとって「いかに遊ぶか」が重要になってくるといわれてもいます。
そんな日常生活で、「ひとりでもできるおもしろい趣味を探してみよう!」というテーマがこの企画の趣旨です。
ということで、今回はデッサンを学んでみました。
なぜデッサンか?
絵が上手い人ってかっこいいですよね。
ぼくは絵が下手です。こんな絵しか描けません。

絵が上手い人って、見たものを正確に描く能力が高いなと思います。例えば、人物を描くにしても動物を描くにしても、絵が上手い人は現実世界をちゃんと描けるんですよね。逆に下手な人は、現実ではあり得ない方向に手や足が交差していたり、遠近感やバランスがバグっていたりする絵を描いたりします。
なので、まずは基本的な「見たまま描く技術をつけよう!」と思いデッサンを学んでみることにしました。
どんな絵を描けるようになったか?
結果から見せると、最終的にはこんな人物画デッサンが描けるようになりました。


横顔が綺麗な芸能人を探していて高橋メアリージュンさんの画像を見つけたのでデッサンモデルとして参考にさせていただきました。もうちょっと丸みを正確に描ければよかったなという反省はありますが、全体的なバランスや明暗のつけ方などはまあまあ上達した気がします。
ではどのようにデッサンを独学したのか、学習中に描いた他の絵と共にシェアします。
用意したもの
デッサンを学ぶために以下のものを用意しました。
『決定版 脳の右側で描け』からデッサンを学びました。
デッサン上達までの道
ステップ0. 「脳の右側で描く」とは?
『決定版 脳の右側で描け』の要点は、「見た通りに描け」です。「見るのなんか当たり前じゃん」と思ってしまいますが、下手な人が人物のデッサンを描こうとした際、目の前にいる人物を見ながら描いているようで、実は「人間とはこういうもの」という思いこみを頼りに描いてしまっています。目の前にいる人物を見ているようで見ていないんですね。
「右脳で描く」とは、そのような脳のショートカットを使わずに、対象物をしっかりと観察して忠実に写し描くことを指します。「見る」がコツなのです。
ステップ1. 上下逆さまに描いてみる
対象物を上下逆さまにすることで、脳によるショートカットを妨げ、「見る」姿勢を取り戻す練習です。

スパイダーマンをスパイダーマンとして見ず、各部位を模様として観察しながらデッサンしました。スパイダーマンを描こうとして描いていないのです。模様を写しとるイメージです。
ここで気づきました。デッサンには、見たままを描く忍耐力が必要なんだと。よく観察するのは注意力と持久力が必要なんです。自分勝手なイメージで描く方が楽なんですね。
ステップ2. 手のシワの観察
続いて、手のシワを観察する練習。これが一番精神的にキツかったです。

ただただ観察するという行為への耐性をつけるための練習でした。
ステップ3. いよいよデッサンの練習
画用紙を4分割して、その枠の中に見たものを写す練習です。
少し本の指示内容と異なるのですが、いろんな手のポーズをスマホで撮影して観察しながらデッサンしました。



「手はこういう形をしているだろう」という先入観を捨て、4分割された各エリアに入っている模様として見て、正確に写しとっていきました。
ステップ4. スペースに意識を向けることを学ぶ
デッサンにおいて、例えば椅子を描く際に「椅子を描く」のではなく、椅子によって区切られているスペースを描くように意識すると観察能力が上がるとのことでした。

つまり、上の絵で言うと、脚と脚の間のスペースを描くつもりで描く。つまり、台形を描く。「椅子の脚」を描こうとしないのです。哲学的でおもしろいですよね。
ステップ5. 消失点を学ぶ
自分から見ている景色の消失点(奥行きの先)を守りつつ、遠近感や奥行きを描く練習です。

たまたま実家にいて題材があまり適してなかった気がしますが、描いていた位置から見たキッチンの一角を見たまま描きました。
ステップ6. いよいよ人の顔へ
人の顔を描く際には、各部位のサイズ感や位置関係が非常に重要です。「耳は大体このサイズでこの辺りにあるでしょう」という先入観で描くことを避けます。よくよく観察して正確に描いていきます。


ステップ7. 光と影を学ぶ
そして、最後に光と影で表現する方法を学びました。線で描くのではなく、光によって生まれた影を描くことで、対照的に人物を立体的に浮かび上がらせる技術です。

これも人の顔を描こうとしていません。光と影の明暗を描くことで結果的に顔が浮かび上がりました。頬骨や鼻筋をなんとか表現できていますね。
おわりに
ざっと振り返ってみましたが、1枚の絵に平均1.5時間くらいはかかった気がします。その間没頭できて時間があっという間に過ぎていました。描いているうちに「もう少し描き込もう」ってついつい熱中してしまうんですよね。
デッサン楽しかったです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
