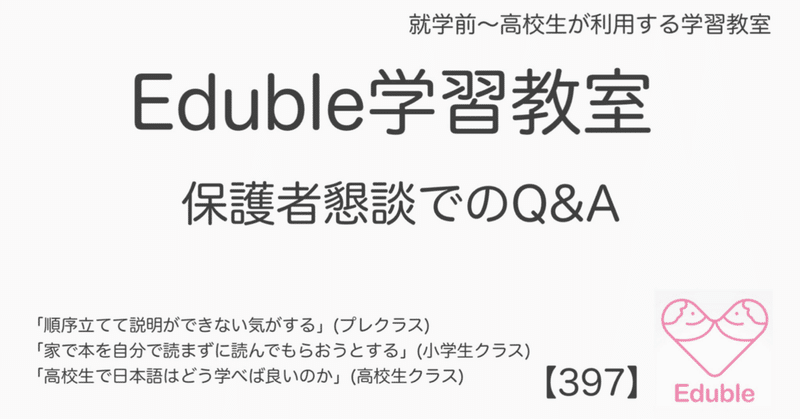
保護者懇談でのQ&A〜Eduble教室だより【397】
3月の最終週に、夕方の教室でのレッスンをお休みにして保護者の方とお話しする懇談週間を設定しました。日本国外で生活をする場合、日本語を継続的に学ぶというのは非常に難しいことです。1週間に一度の教室での90分の学習よりも、圧倒的に時間が長くなる家庭での日本語環境をどのように考えるのかが重要です。
そこで私も言語の専門ではないものの、この4年間で私自身が文献などで学んだことと、実際にいろんな環境にいる子どもたちの継承語の学習を見てきた経験が少しでも役に立てばと思い、個別でお話しをさせていただくことにしました。
懇談では、日頃の教室での様子や学習の取り組み方、私自身が大切にしている「子どもの日本語を育む環境」についての考えを共有させていただき、その上でご家庭での言語環境やそれぞれの家庭に合わせた日本語環境の設定の仕方について一緒に考えていきました。
今回の記事では、保護者の方からいただいた質問をもとに私が懇談で回答させていただいたことを記録しておきたいと思います。
懇談Q&A
今回懇談に参加してくださった保護者の方はそれぞれの悩みを持っておられました。まだオランダに来たばかりの方、これからもオランダ生活が長く続く方やこれから日本に帰ることが決まっている方、保護者が置かれている立場によって考えなければならないことも異なります。家庭で日本語の本の読み聞かせはどうすれば良いのか、日本語やそれ以外の言語での説明が上手にできていない、日本に帰ることがある程度分かっているけれどどの学校にするかを悩んでいるなど、ご相談をいただきました。その他に、日本在住の方やオランダ以外の国に住んでおられる方も含まれています。
もちろん、私から正解となるような答えを提示することはできませんが、それぞれのご家庭にあった方向性はどういったところにあるのかを考えるための情報整理のお手伝いをさせていただいています。
それでは、以下各クラスの保護者と話し合った内容について共有いたします。
プレクラス(就学前)
・物事を順序立てて話すのが苦手な気がする
・家で複数の言語を話すため、日本語も含めてどのようなサポートをしていけば良いのか
就学前の子どもの論理や語彙
複数の言語で生活されている場合、どれかの言語だけを見るとモノリンガルよりも表現が少なかったり、話し方が拙いことで心配される保護者の方も多いと思います。私がこれまでに学んだり経験したことからお伝えできることは、言語の数だけそれぞれの発達は若干ゆっくりになるけれど、複数言語を持つことのメリット(思考の広さや他者への共感)があるので、そちらを育みつつ言語の発達を促してあげたら良いと考えます。
つまり、語彙や論理性での不安を感じるご家庭に対して、モノリンガルに比べて習得がゆっくりになることは当たり前のことだと捉え、決してドリルなどの機械的な学習に頼らないようにしてほしいと伝えています。むしろ、日常生活の中で自然な刺激を加えることを考えていただきたいと思います。
例えば、本の読み聞かせの中で言葉の意味をさりげなく「○○ってどういう意味かわかる?」「このきつねって最初どこに住んでいたんだっけ?」と質問してみたり、食事中の何気ない会話の中で「へえ、それからその子はどうなったの?」などと聞いてあげたり、大人同士の会話の中で「今の言葉ってどういう意味?」と聞いてきたら答えてあげると、自然と語彙力や物事の順序が理解できるようになって、やがて自分から説明できるようになっていきますし、会話の中で語彙も増えていきます。
大切なのは、就学前のお子さんは全てが発達過程であるために、できないことにフォーカスするよりもその子の得意なことや楽しめることに焦点を当てていただきたいと思います。
小学生クラス
・これから小学1年生の年齢になるが、どのようなサポートを家で行うのがよいのか(新1年生)
・語彙が少ないのはどうしたら良いか(新1年生)
・一度に作文で書く分量をもう少し増やした方が良いのか(新6年生)
・作文の力を付けたいが、理科と社会は続けた方が良いのか(新6年生)
・助詞や接続詞の表現が弱い(新4年生)
・日本の学校を選ぶときにインターにするのか公立にするのか悩んでいる(新5年生)
遊びが学びにつながる環境
小学生の年齢になったばかりの子どもたちは、まだまだ「遊び」が中心の世界にいます。私がレッスンをしていても、ごっこ遊びや何かを作ることはとても楽しそうです。そういう期間は、読み書きを極端に機械的なものに変えるのではなく、遊びながら学ぶことを中心にしたら良いと考えます。
小学生になると学校での勉強が進むようになるので、日本語でも同じように勉強することを求めるご家庭もありますが、日本語を学校で学ぶ機会がないのであれば学年が進むのと一緒に進められると考えるのはとても不自然なことだというのを理解する必要があります。
小学校低学年であれば、まだ「学習」というものを日常から切り離すのは難しく、リアルな世界の中で学ぶことを大切にした方が学びは深まります。そのため、読み書きの中でも日常で出てきやすいものなどを使って、なるべく話している言葉と文字が一致するようにしていきます。もちろん、それだけでは子どもたちは退屈してしまうので、日本語を使って遊ぶ時間も大切にしています。日常生活の中に日本語で学べるチャンスは、1日の過ごし方などをよく考えると結構あるものなので、探してみてほしいと思います。
語彙や文法の表現
語彙の問題については、プレクラスの方法と変わらず日常生活の中で触れられる機会が重要だと考えます。助詞の「は、を、へ」などは日常の生活で「○○ちゃんが、ブランコに乗りたいんだね」や「私はドーナツを食べたいな」など意識して伝えたり、教室の学習時間の中で助詞を当てはめる練習問題などを取り入れて、実際にどんな場面でそれを使うのかを話し合ってみるのも良いかと思います。このように学びと実用が往復できると定着しやすいのかもしれません。要は、どれだけ現実の文脈の中でそれを使うかになります。
本帰国の際の学校選択
本帰国されるご家庭のご相談として、学校の選択についてお話を伺うこともありますが、これはお子様の意思や住む場所、経済的な負担がどれぐらいまで可能なのかによります。いろんな条件と選択肢があって混乱しがちかと思いますので、まずは、保護者として何を優先しなければいけないのか(住む地域や学費に当てられるお金の事情などの変えられない条件)を考えていただき、それに合わせて現実的に範囲を絞り込んでいくと良いと思います。
中学生クラス・日本語(オンライン)
・海外生活が今後も続く中で、どのように日本語学習を進めていけば良いのか(新2年生)
・日本に帰国予定だが、IBか英語に特化した日本の学校にするかを検討している(新3年生)
・帰国生向けの面接・小論文対策はいつ頃から始めると良いのか(新3年生)
・IBDPで日本語を選択する予定だが、今からどんな準備をしておけば良いのか(新3年生)
中学生ぐらいになってくると、保護者が横について勉強をするという形は当然難しくなってきます。小学生ぐらいの時は、半ば強制的にでも日本語を「させる」ことは可能かもしれませんが、それまでの積み重ねてきた成果が、良くも悪くも中学生以降の生徒の日本語学習との向き合い方に現れるように感じます。
中学生以降はレッスンだけでなく、日常的に日本語で書かれた本を読んでいるかどうかで中学生以降の文章が読めるかどうかに影響してきます。ただ、子どもの日本語学習の目的によって学習内容も異なり、例えば「小学生レベルの文章や漢字が理解できていれば良い」のであれば小学生の漢字を何度も復習し、文章を読んで自分の考えなどを話せるようにするので十分だと思います。つまり、中学生ぐらいからはそれぞれの学習目標を明確にし、それを共有することで、生徒自身が学習を管理できるようにしていくことができるようになるのが良いと思います。
現在の私のクラスでは、それぞれの日本語レベルに合わせた漢字と読解に加えて、中学生の理科や社会で扱うようなテーマでのディスカッションなどもしています。そうすると、日本語のレベルに関わらずみんなが自分の意見や学校で習ったことを日本語でアウトプットするきっかけにもなります。日本語を学ぶというよりも、日本語でいろんな分野の話をしたり知っていることをみんなで共有する面白さを味わってもらいたいと思います。
学校選択に関しては、中学生ぐらいだと日本語をメインにするのか、英語で学ぶ学校にするのかということを自分で判断できると思います。ただし、学び方や進路選択をするときの選択肢が変わってくるので、その辺りも考えた上で変更できない条件(住む地域や学校に通うのに充てられる費用)も合わせて判断されるのが良いと思います。
そして、帰国生向けの小論文対策やIBDPの日本語Aの準備については、日本語で文章を書くためのトレーニングが必要です。しかし、日常的に文章を書くというのは学校や日本語を学ぶ教室などでないと取り組めないことが多く、ここが最も難しいところだと感じています。
私のイメージとしては、「自分の考えが頭にあるけれど、うまく日本語で表現するのか難しい」という生徒だとスムーズに進みます。しかし、「日本語の文章を読んだり漢字も書けるけれど、どんなことを書いていいのかわからない」という場合は、考えるトレーニングから始めないといけないため、書けるようになるまでにかなりの時間がかかる可能性があります。
その反対に、自分が進みたいと思う進路が明確で、そこに作文があるからその力を伸ばす必要があると本人が理解できていて、先ほどのようにアイデアがしっかりともてる場合は、トレーニングを重ねていく中で次第にうまく書けるようになっていきます。
以上から、作文をサポートする立場としてアドバイスをするとしたら、漢字や読解問題などのドリルに頼る学習をするのではなく、好きな本などを通して日本語に触れ、日本語でいろんなテーマについて話せるようにしておくのが、必要な準備だと感じます。
高校生クラス・数学(オンライン)
(日本の)高校に進学して、数学がずっと欠点しか取れていない。改善するためにどのような取り組みが必要なのか。
私は数学ⅠA・ⅡBまでを大学受験で勉強したので、カリキュラムの変更には完璧に対応できていないまでも、数学が苦手な生徒向けのレッスンは保護者の方からのご要望をいただきレッスンをしています。
8年間社会科の教諭として授業をし、その後4年間言語を教える仕事をする中で、数学については高度なレベルまでは私は対応できませんが、基礎的な部分として「言語をきちんと理解できることで数学的な思考ができるようになる」と考えて、「これがこうなるからこういう計算ができる」という解答のプロセスを言語化して、考える力を伸ばすようにしています。
私がこれまでに教えてきた経験から、数学が苦手な原因は「問題文で書かれていることが正確に理解できない」「答えを求める時に、どの手法をどのような手順で使うのかという論理的に考える力が不足している」ところにあると感じます。問題文を読んですぐに答えを出そうとするのではなく、問題文で聞かれていることをしっかりと理解して、どうすれば答えを出すことができるのかを考えるトレーニングが必要です。そのため、私は数学の基礎を学ぶ場合は、「言語的な観点」から数学の力を付けるようにしています。
数学は、算数からの積み重ねがありますので、高校数学で欠点ばかりになっている場合は、どのポイントから躓いているのかを確認する必要があります。春休みや冬休みなどの一定期間の休みに入る時に学年を遡って復習をしてみると、やはり躓いているポイントが見つかります。そこで、何度も練習を重ねてできるようになるのか、それともそういったことが必要ない科目や進路を選ぶかということを考えてもらいます。
高校生クラス・国語と社会(オンライン)
保護者の仕事の関係で日本を数年離れる予定だが、日本の大学に進学予定。海外で生活する間、どのような勉強をしていくのが良いのか。
中学卒業までは日本の学校に通っていたとなると、日本語としての能力はほとんど問題がないと考えて良いと思います。高校1年生の場合、大学受験に直結した対策をするというよりは「日本語の文章を正確に理解できること、自分の考えを正確に表現すること、自分の考えの範囲をなるべく広くしておくこと」が大切です。
この問い合わせをいただいた生徒が社会科目を学びたいということだったので、高校の「歴史総合」に沿って授業を進めています。歴史総合については、基本事項について一緒に確認し、歴史的な考察などを授業の中で行い、世の中の捉え方や考え方を広げるようにしています。
言語としての「国語」では、高校生向けの文章を読んで内容について確認したり、いろんな形式のもの(説明的文章、小説、詩など)を読んで、表現の工夫について理解したり、内容に関する議論をして視野を広げる取り組みを進めています。
生徒の「学習ニーズ」を考えることが重要
子どもの学習において「これで十分だ」ということはなく、求め出すとキリがないということに気づき、「最低限どんな環境が必要なのか」というところに念頭をおいて考える必要があります。
そして、何よりも子ども自身が「なぜ学ぶのか」を全く理解できないまま学習を進めるというのは、なるべく避けたいところです。「こちらから無理にでもやらせないと子どもはやらない」という状態は、保護者が先手を取りすぎている状態が続いていると考えられます。その状態から、子どもが自主的に学ぶという環境を作るのは難しいかもしれませんが、「自分で何かに取り組んでできるようになった」や「これまでできなかったことが努力をすることで自分の力でできるようになった」という経験を少しでも積ませてあげることが、継続的な学習に必要です。
情報化によって何もかもがスピーディになってしまった現代において、子どもを「待つ」ということは大変難しいことです。意識していないと、つい社会や大人のスピードで子どもにいろいろなことを求めてしまいます。もう一度「子どもにとって何が必要なのか」「子どもの学習のことでイライラしてしまう状態は本当に幸せなことなのか」を問い直し、学習によって子どもが社会で生きる力をつけられるような環境設定を考えていただきたいと思います。
子どもたちは一人ひとり「自分で成長する力」を持っています。必要なのは「環境」であり、子どもがのびのび成長できるようにするためにはどうするのが良いかを考えていくと良いのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
