
えほん「ざんこくな鬼」
あるところにざんこくな鬼がいました。
鬼は、1年中野花が咲き乱れる故郷、鬼ヶ島を愛していました。
鬼は182歳の時に、世界の仕組みがどうなっているのかを明らかにするために旅に出ました。もっともっと世界の色んなことを知りたかったのです、感じてみたかったのです。
鬼は世界中でたくさんの人に出会います。
顔の白い目の赤い鬼、白玉の形をしたネコ、頭から足が生えた人間、ほんとうにたくさんの人と鬼は出会いました。
鬼はいろんな人とお酒を呑んで語り合い、すばらしい景色を見たり、時には恋をしたり、世界を知るためや欲望から人と寝ることもありました。
毎日毎日異なる文化で暮らす内に、鬼はハッとします。
人とは、いろんな形状や色、匂いがあり、そのように明らかにわかることのみならず、中身も全く違うものであると。当たり前に空だと思っていた「空」は全員にとっての空ではありませんでした。
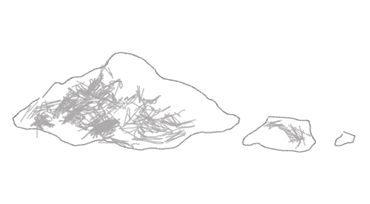

そのうちざんこくな鬼は、異なる文化で暮らすことが日常になってしまい、旅をすることに飽きてしまいます。
鬼が282歳になった頃、ついに鬼は故郷の鬼ヶ島に帰ることにしました。
長い鬼の人生からみれば、ほんの少し世界を旅していただけのことでしたが、帰ってきた故郷に、まったく違う場所であるような懐かしいような不思議な気持ちにさせられます。
見慣れた人達である、母鬼、父鬼、ペットのネコ、親友の人間、すべてが鬼にとって自分とは違う人であり、そして共にこれまでを生きた大切なもののように思えました。
年中飽き飽きするほど見慣れた野花の風景も、ひとつひとつの種子が運ばれていく命の動きを感じるほどくっきりとみずみずしく見えたのです。
故郷での暮らしに慣れてきた頃、鬼は、見慣れない女性を鬼ヶ島唯一のブリュワリーで見つけます。
女性は、鬼ヶ島にいる人とは違う風な血筋とわかる風貌をしており、目の色が黒く、黒目が通常の倍以上大きく、角がある所にはふわふわした羽毛のようなものが絡みついて風にゆれており、浅黒い肌で、人の中でも鬼やネコではないようで、人間のように見えました。
「外からきた人だな」とすぐに気付いた鬼でしたが、島には珍しい外の人も鬼にとっては驚くようなことではありません。
鬼にとっては、この女性も世界中で出会ったいろんな人のひとりと同じようなものです。
鬼は気付いていませんでしたが、今の鬼にとって、鬼ヶ島以外の人は同じような人だと思っていたのです。
鬼は世界中でそうしてきたように、その女性と心の高さを同じようにして話しかけます。ざんこくな鬼は、人のなかでもたくさんの人と会ったことがあるので、外の人間としゃべるときのコツもわかっていました。

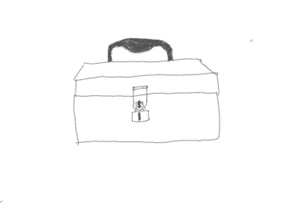
浅黒い女性ははじめ、警戒していないフリをして話していたものの、鬼のあまりに心の高さが同じことを感じて、ついつい人にとって一番大切な心臓を鬼にあげてしまいます。
ただし、心臓は外からはわからないよう一番大切な1室は、見えないように細工をして鍵を閉めて他人からは決してわからないようにしていました。
ところが心臓をもらうことに慣れている鬼は、すぐにその室に気付き、部屋を開けてしまいます。
室の中にあったものに気付いた鬼は、これはこの女性にとって大切なものなので、本人に気付かせてあげようと思い、ブリュワリーのカウンターに中身を並べて見せてあげました。
女性は582年間どのような間柄の人にも見せたことのない、生暖かい中身を並べられたことに気付きます。
何度もこの中身が溢れだしそうになるたびに、少しだけの、世界にとって他愛のないウソをついて、生暖かい中身が溢れないように隠していました。
心臓の他に、人が共通して持っているものに右脳と左脳がありました。
しかし、見た目はおなじでも右脳と左脳どっちを使うかは、生まれたときからあらかじめ決められていました。
この女性は、右脳を使うように生まれてきたようでした。
ただ、女性は右脳を使うにはとても心臓が弱く、生きるために左脳を使って生きていました。
左脳を使うことで人の社会でもなんとか生きていくことができた女性でしたが、大事な中身は右脳を使わなければ社会に持ち出すことのできないことでした。
中身を溢れ出させたいと思うたびに、女性は左脳を使って中身を隠してきました。
中身を隠すことは、女性にとって、自分が生きるための手段だったのです。


中身を見せられて怖くなった女性は、「彼の心臓をもらえば中身を明かしても大丈夫かもしれない」と思います。
女性は、ざんこくな鬼に「あなたの心臓をひとつだけでいい、ほしい」とお願いします。
ところが、ざんこくな鬼は、「それじゃああなたの心臓は返してあげる。中身も元通りにしておいてあげるね」と言って心臓を女性に返し、自分の住みかへと帰っていきました。
おわり
