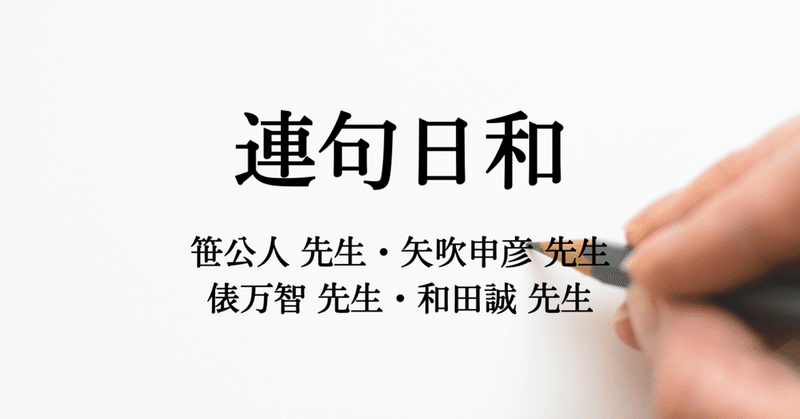
「連句日和」笹公人先生・矢吹申彦先生・俵万智先生・和田誠先生
※ネタバレを含みます。閲覧にはご注意ください。
※あくまで個人の感想・書評です。
俳句に親しむシリーズ・第2弾
以前私が漫画から俳句にハマって呼んだ入門書のレビューを書きました。
今回は私の中での俳句に親しむシリーズ第2弾と題しまして、連句(れんく)に触れてみようと思い、読んだ本作をレビューしたいと思います。
ここが大事なのは、「私は! 俳句に関して! まったくの素人!」と、いうことです。なので、私が書く話は「俳句素人が連句について見るとこういう感じなのね、ハハ」とひろ~い目で見てくださると幸いです。間違ってたらバンバンご指摘ください。勉強させてください。
連句って、何ですのん?
連句って、知ってる人どのくらいいらっしゃるんでしょうか。私は漫画「ほしとんで」で知りました。
知らない人に(素人が)説明すると、連句は一人、もしくは複数人で俳句を詠みあう連想ゲームです。(※厳密には、一人で詠む連句は「独吟」というらしい。)
まず「発句(ほっく)」と呼ばれる句(五七五)を詠み、次の人がその句から連想される言葉などを入れながら七七の句を詠む。(これを「付ける」というらしい。)で、次の人はまた五七五の句を詠む。これを繰り返して三十六句作る。みたいな感じです。
連句は様々なルールが存在します。「この順番の人は春の季語入れてね」とか、「次の人は恋の句を詠んでね」とか、「最初の六句は重い話題はナシね」とか、「前の前の句を連想させる言葉は入れない方がいいよ」とか。
ここまで読んで「いやいやメッチャ連句のルールややこしいやん。何がおもしろいん……」と思ったそこのあなた。思いますよね。わかる。私も「いやこれ、人生の酸いも甘いも嚙み分けた落ち着いた大人がやる高度な遊戯やん」と思ってました。
でもこの「連句日和」を読んで、その堅苦しいイメージがちょっと和らいだかな? と思います。
連句って、そんなに気張らなくていい遊びなのかも!
本作はイラストレーターの和田誠先生の呼びかけで集められた四人で巻かれた連句を集めたものです。(※連句をやることを「連句を巻く」って言うよ!)そのメンバーは、歌人の俵万智先生、イラストレーターの矢吹申彦先生、歌人の笹公人先生と、職業や年代も住んでいる場所も様々な皆様。メールやFAXで時には数時間、時には何日かかけて連句を巻いていったそうです。
本書は連句が掲載されたあと、その連句を巻いていった過程を四人で語り合う形式で展開されていきます。
まずは、連句を味わう。「俳句」というと、こう……しみじみとした情景を読むイメージが強いと思うんですけど、たま~にポップな句があって面白いんですよね。
十四歳が破るジーパン (笹先生の句)
とか、「ああ~光景が浮かぶ~」ってなりますもんね。笑
言い方が合ってるかわからないですけど、俗っぽいというか。俳句の懐の広さがうかがえます。
また、メンバーの皆さんが「どこに着目して、どう連想して次の句を詠んだのか」を知るのも楽しい。予想できるものもあれば、「へえー! そんなところから発想したのか!」と新しい視点を得られるものもあります。あと時勢やそのときされていたお仕事、環境などの影響も句に表れていて、「なんか短い交換日記みたいだな」と思いました。
離れていても通じ合える、言葉の連なり。
連句の良いところとして、遠く離れている仲間とも楽しめる遊びだな、と思いました。「あの人はどう考えてこの句を詠んだのかな」「次の人はどう受け止めてくれるかな」なんて考えながら、十七音、十四音、十七音……と短い言葉を交わしあう。遠く離れていても仲間のことを想いながら、短い手紙のような気持ちで句を詠むっていうのもイイなあ、と思いました。
正直、ルールはあるので、本格的に俳句を詠まれている方からすると「そんなふうに遊んでいいものじゃありません!」と言われちゃうかもしれません。
でも初心者だし……。最初は探り探り巻いていくのもアリなのでは? と思いました。もちろん、最低限のルールは調べて、ですが。
何事にもチャレンジ! 今度、私も連句を巻いてみようと思いました!
まあ、一緒に巻いてくれる人が見つからないので、しばらくは「独吟」しかないかもしれませんが。笑
終わり!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
