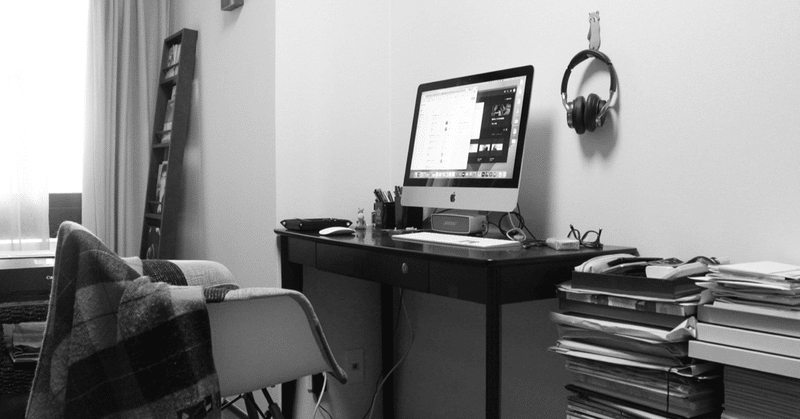
デザイナーという職業と、デザインすることについて
𝑡𝑒𝑥𝑡. 養老まにあっくす
僕がデザイナーになったわけ
「デザイナーをやっています」と言うと、羨ましいものでも見るような目で見られることがあります。広告の仕事をしているときもそうでした。普通の人からすると、広告代理店やデザイン事務所というのは、とても華やかな職場に見えるようです。しかし、現実はそんなに明るいものではありません。
まず、デザイナーという仕事は、どうしても夜遅くなりがちです。デザインというのは、アートと違って自分だけで完結するものではありません。途中の段階を何度もお客さんに見せて、確認してもらいながら少しずつ作るわけです。でも、そういったレスポンスって、朝イチで送ってくれる人はまずいないんですね。自分が逆の立場でも同じことをすると思うのですが、どうしてもそういう返事は夜になることが多い。だから、取り掛かるのも自然と夜からになります。あと、昼間はメールが来たりほかの雑務が入ったりして、集中して取り組めるのはどうしても夜遅くなってから、ということもあります。
お金も稼げません。1件の仕事で何百万みたいに稼げるのはごくひと握りのデザイナーだけで、たいていは普通のサラリーマンほども稼げません。一度リクナビやマイナビの求人を眺めてみてください。これっぽっちしか稼げないのかと、悲しくなるほどです。では、なぜデザイナーをやっているのか。それはこの仕事が好きだからです。好きでなきゃ、こんな仕事やってられません。この仕事をしていると、本当に時間を忘れます。
「デザインが好きかも」と気づいたのは、広告代理店にいたときでした。僕はデザイナーさんが作ったデータを出版社などに入稿する仕事をしていました。入稿する前には必ずデータが仕様通りに作られているかをチェックします。ほとんどの人は最終的に出力されたものしか見る機会がないわけですが、僕はそのデザインがどうやって出来ているのかを、好きなだけ見ることができました。「そうか、こうやって作られているのか」と驚くと同時に、なんだか自分にもできそうな気がしてきました。せっかく仕事でIllustratorやPhotoshopが触れるのだから、真剣に勉強してみよう。それが僕のデザイナーとしての第一歩でした。
どうすればデザイナーになれる?
「デザイナーになるにはどうすればいいですか?」という質問もよくされます。センスがないと、デザイナーにはなれないと思っている人もいます。でも、それは違います。よく、デザイナーには感覚派と理論派がいるという言い方をします。たとえばですが、おしゃれな人は洋服のセンスがいい。でも、プロのファッションコーディネーターなら、なぜその服装がおしゃれに見えるのか、きちんと言葉で説明できるはずです。つまり、ファッションにはちゃんと理論があって、その理論が理解できてさえいれば、センスがなくてもおしゃれはできるわけです。
デザインもそれと同じです。デザインというのはじつは理論のカタマリみたいなもので、理論がわかればデザインはできるのです。じゃあ、感覚派はどうやってデザインするのか。多分ですが、理論派がA=B、B=C、ゆえにA=Cという風に答えを出すのに対して、感覚派は最初からA=Cという風にパッとわかってしまうのだと思います。僕はどちらかというと感覚派です。先に答えがパッと見えて、後から理屈を考えている感じです。
「デザインの学校に通う必要がありますか?」これもよく聞かれます。これはYESともNOとも言えます。というのも、ここまで「デザイン」と一括りにして話してきましたが、デザインといっても非常にさまざまだからです。たとえば、デザインはデザインでも、広告のデザインとファッションデザインがまったく違うものだということは、素人の方でもおわかりだと思います。同じように、WEBデザインもそれらとはかなり異なる分野です。自分が何のデザインをやりたいかによって、学校で習ったほうがいい場合、そうでない場合があると思います。ちなみに、僕は全部独学です。なので、学校に行かなきゃ絶対なれないというものでもありません。
ただし、絶対に学校に行かないほうがいい場合があります。それは、あなたがもう新人と言える年齢ではなく、中途採用でデザイナーを目指す場合です。この職業は、なんのかんの言っても実務経験が命です。未経験の人をポテンシャルで採用してくれる会社であっても、即戦力になってくれる人があればそちらを採用するに決まっています。ですから、中途採用でデザイナーになるなら、少しでも早く実績を積み上げることが何よりも重要です。極論すると、正社員よりも入りやすいアルバイトの求人とか、あえてブラック企業で働いて、手っ取り早く実績を積むというのもひとつの手だと思います。
勉強を勉強と思わない
デザイナーに向いているのはどんな人でしょうか。デザイナーというのは、じつは日々勉強です。企業のロゴを例に取ると、たとえばApple Computerのロゴは、いちばん最初はリンゴの木の下で本を読むアイザック・ニュートンのイラストでした。それが虹色のリンゴになり、現在はリンゴのシルエットだけになりました。Instagramのアイコンも、昔はカメラの絵でしたが、いまではほとんどただの記号です。こうした変遷は、時代とともにスピードが求められるようになり、リッチで手の込んだデザインよりも、扱いやすくシンプルなデザインが好まれるようになっていったという背景があります。
このようなトレンドを理解することはとても重要です。したがってデザイナーは、何を見てもデザインのことを考えています。街を歩いていても、電車に乗っていても、雑誌を読んでいても、いつもデザインを見ています。「このデザインは美しい」と思えば、なぜ美しいのか理由を分析します。逆に、「自分だったらこうするのに」と考えることもあります。そうやっていつもいつもデザインのことで頭がいっぱいなのが、デザイナーという人種です。
一方で、IllustratorやPhotoshopなどのアプリケーションも日々進化しており、遅れないように着いていくことが必須です。ソフトウェアの技術は、昔に比べると格段に便利になりました。最近だと、AIをデザインにどう取り入れるかというのも重要な課題です。こうしたことを、常に勉強し続けなければならないのがデザイナーです。ただし、僕はこれらの勉強を勉強だと思ったことはありません。なぜなら、自分はデザインが好きであり、そのために必要なことだからです。この「勉強を勉強だと思わないほどデザインが好き」という感覚が、じつはデザイナーになるためのいちばん重要な資質かもしれません。
AIの進化でデザイナーは不要になるか
AIの目覚ましい進歩は多くの人にとって、「自分の仕事がAIに奪われるのではないか」という不安の種でもあります。デザイナーという職業もまた、そのような脅威にさらされていると言われます。しかし、僕はだいぶ楽観的に考えています。少なくとも自分の目の黒いうちは、AIにそんなことはできないだろうとタカを括っています。
たしかにAIは、人間のデザイナーにはできないようなことができます。たとえば、何百個ものロゴを数秒で生成したりするなどです。これは人間には逆立ちしてもできないことです。しかし、AIには苦手なこともあります。人間のデザイナーならあなたが言うことを少なくとも理解しようとしてくれますが、AIの場合はあなたがAIの理解できる言葉で話しかけなければなりません。なるほど数秒で作ってくれるかもしれませんが、が出来上がりに満足できなければ、あなたは永遠に命令を繰り返さなければならないのです。
結局、「AIが人間を超えた」と言ったところで、それは「オートバイは人間よりも速く走れる」というのと何が違うのでしょう。もちろん、パソコンが発明されたときのように、多くの作業が機械化されることは確実です。しかし、AIが人間の仕事を次々と奪っていくといったディストピアにはならないだろうと思います。僕が怖いのはAIよりも人間です。どういう人間かというと、AIで満足してしまう人間です。「ロゴなんて、AIが作ったやつで十分さ。」僕はAIと闘っているのではなく、そういう人間と闘っていると思っています。
ここから先は
¥ 500
養老先生に貢ぐので、面白いと思ったらサポートしてください!
