
「サステナビリティのヒントは温泉にあり」?ワンプラネットカフェのエクベリ夫妻に聞く、SDGsの原理・原則。
スウェーデン1位、日本は17位――。
何の順位かご存知でしょうか?
実はコレ、国連の「SDGs(持続可能な開発目標)報告2020」における世界ランキングです。2021年の最新ランキングでは1位フィンランド、2位スウェーデンとなりましたが、日本は18位。ここ数年、徐々に順位を落としている日本。それに比べて北欧のスウェーデンはこの6年のうち4回も1位の座についているのです。
その差は一体どこにあるのか?
日本がスウェーデンから学ぶには?
そんな疑問を持った私は、両国をよく知るうえ、サステナブルな社会をつくるべく講演活動や視察ツアー、さらにバナナペーパー事業なども手掛ける、ワンプラネット・カフェのペオ・エクベリさんと聡子・エクベリさんご夫妻を訪ね、この質問をぶつけました。
ヒントは、なんと日本の「温泉旅行」にあるそうです(笑)。
啓蒙だけじゃなく、ものづくりも。
――「サステナビリティをリアルに」と掲げたお2人の活動にとても共感していて、私も「SDGsオンライン視察ツアーinスウェーデン」に何度か参加させてもらいました。
ペオさん:すばらしい。ありがとうございます。
聡子さん:ジュリさんがサステナビリティ・マネージャーをしているハリズリーとは、どういう会社なのですか?
――土屋鞄製造所を母体にしたものづくりメーカーを抱えた企業です。鞄やランドセル、江戸切子など日本のクラフトマンシップを世界へ発信することもテーマのひとつです。
ペオさん:クラフトマンシップといえば、スウェーデンにある私たちのオフィスは、ゴットランドという島にあるんですね。そこはライムストーン(石灰岩)でできた島で、中世から続く石造りの古い街並みと相まって、明るくとても雰囲気があるんです。
そんな土地にインスピレーションをうけたデザイナーやクラフトマンが多くいます。彼らはサステナビリティの意識も高いんですよ。
――素敵ですね。まさにそれで、モノをつくるうえでは、環境や社会に対して責任を果たす必要がありますよね。サステナビリティを強く意識した企業活動を、まずは私自身が考えたい。そこでこうした形で、先を走っていらっしゃるエクベリさん、そしてスウェーデンから学びたいなと。
あらためて、お二人がどんな活動をしているか、から伺っていいですか?
聡子さん:まず私達の会社、ワンプラネットカフェのミッションは「サステナビリティを形にしよう」です。持続可能な社会や世の中を願い、夢想するだけではなく、「行動に移していこう」という想いで事業を行なっています。


ペオさん:具体的な事業は3つです。
ひとつは「Talk」。サステナビリティ、SDGs(※)について理解を深めるための講演や研修を実施しています。
もうひとつは「Show」。スウェーデンなどで、サステナビリティの現場を視察体験してもらい、行動につなげるためのツアーを実施しています。ジュリさんに参加いただいたのはオンラインで実施したものですね。
そして、最後が「Do」。自らも現場を持とうということで、これまで捨てていたバナナの茎の繊維を使ってつくった紙「バナナペーパー」の事業を行なっています。話やツアーなどの啓蒙活動だけではなく、ものづくりにまで踏み込んで活動しています。

![]()
SDGs17のゴール、すべてにつながる「バナナ・ペーパー」。
――この紙、すばらしいですよね。バナナの茎を原料にして、しかも日本の和紙の技術で紙をつくっている。
聡子さん:そうなんです。原料はアフリカ・ザンビアのオーガニックバナナ畑で採れるバナナの茎。
もともとバナナは一度実をつけた茎からはもう実がならないので、収穫後は切ってしまう。1年後には新しい茎が生え、そこに新しい実はつくのですが、切った茎はただ捨てていたんです。
ペオさん:茎といっても3メートルから5メートルの長さ。捨てた茎はそのまま土に戻るけれど、もったいなかった。
聡子さん:そこで、福井県の越前和紙の工房でその加工をしてもらい、バナナでできた再生紙をつくり、名刺やメモ帳、ハンガー、パッケージなどとして販売しています。
たとえば東京芸大は修了証書に、あるいは化粧品やバス用品で知られるLUSHは世界13カ国で私たちのバナナペーパーでできたパッケージと紙袋を使ってくれているんですよ。
\バナナペーパーができるまでをご紹介/

オーガニックバナナ農家から廃棄されるバナナの茎を集める。

茎を専用の機械に入れ、バナナペーパーの原料となる繊維を取り出す。

茎から取り出したバナナ繊維を乾かす。

ザンビアの現地では、バナナ繊維と古紙を混ぜて、手漉きの紙を作っている(日本では、和紙工場などで生産)。

バナナペーパーのできあがり。

化粧品やバス用品で知られるLUSHのショッパーもバナナペーパー。

バナナペーパーでできたハンガー。

名刺や包装紙など、さまざまな商品に使われます。
- - -
――バナナの茎は1年で再生するので、他の木材などを使うよりもずっと効率的でエシカルな素材。CO2削減につながる、まさにサステナブルな仕組みをプロダクトでつくったわけですね。
ペオさん:はい。もっとも、環境問題だけじゃなく、17あるSDGsのゴールすべてにつながる事業でもあるんです。
たとえば、ザンビアの工場がある村は貧困地域ですが、20人の雇用を生むことができています。1人あたりで10人ほどの生活が支えられると言われるので、200人の方々を貧困から救えている計算です。
強制労働や児童労働も行いません。仕事による収入が増えたお陰で、子どもの教育の機会も増え、健康と福祉にもつながった。飢餓もありません。また村では、貧困が原因で密猟などをせざるを得ない状況がありますが、私たちのチームメンバーはそういったことに手を染める必要がありません。
もちろん私達だけの成果ではないですが、今では周辺地域で減り続けていたゾウの数が増えてきたと聞きました。


――すごいですね。SDGsゴール15の「緑の豊かさを守ろう」や12の「つくる責任つかう責任」はもちろん、ゴール4の「質の高い教育をみんなに」などまで解決しているなんて。どんな経緯でバナナペーパーといったプロダクトまで、「Do」まで踏み込まれるように?
ペオさん:偶然なんです(笑)。
聡子さん:2006年に2人で野生動物を見に行こう、と旅行でザンビアを訪れたんですね。すばらしい国立公園があって、ゾウやキリンや多くの野生動物を間近に見られて、心が震えました。
ただ、そのすぐそばにある村は貧困が深刻なことが同時にわかった。それが密猟や違法な森林伐採にまでつながっていることが見えて、知ってしまったのです。
ペオさん:私たちが講演などで話していたことが、目の前で行われていた。そうなると、なにかアクションをしなければと思いますよね。また色んな試行錯誤の後に、村にオーガニックバナナの農園があることを知り、バナナの繊維を使った紙ができるのではないか…とソリューションにまでつながった。

――偶然とおっしゃいますが、実際にお二人が行動にうつし、ビジネスとして立ち上げられたところに驚きます。
聡子さん:いや、2人だけならできませんでしたね。現地の20人のチームメンバーはもちろん、日本やスウェーデン、イギリスなどの多くの企業に賛同してもらい、パートナーシップを組んでいただいたからできた。
ペオさん:もともと彼女は環境コンサルタントで、私は環境ジャーナリスト。私は、どちからというと昔は「大企業は信じない!」といったスタンスがあったのですが(笑)、専門家だけでは何も進まないんですよね。
――「バナナペーパー」というプロダクトやビジネスモデルがシンボリックでわかりやすいことも、そうした賛同企業を増やす一員だったのでしょうね。
ペオさん:そうですね。なのでジュリさんの会社でも、まずひとつサステナビリティに特化した商品をつくるのはおすすめです。多くの方の力を集めやすく、ノウハウも集まりますよ。
――なるほど。プラットフォームにもなるプロダクト、いいですね。



「SDGsは“サイエンス”です」
――お二人のみならず、スウェーデンはとてもサステナブルな環境、社会に対する意識が高い。H&MやIKEA、ヌーディージーンズといったスウェーデンのブランドは、とても企業姿勢に社会や環境に対する姿勢が明確です。その理由はどこにあるのでしょう?
聡子さん:ひとつは教育でしょうね。環境やSDGsの前に、小学校の頃から「科学をベースに物事をとらえて、考えること」が教えられ、習慣として根付いている。これは大きいと思います。
背景には、もともと資源が少なく、人口も少ないことがある。「グローバルな視点で、社会で活躍できる人材を育てる」ことが命題として常にあるんです。

――ノーベル賞もスウェーデンですものね。ただ、なぜ科学ベースで考える習慣が、サステナビリティにつながるのでしょう?
ペオさん:政策などの約束事は必ず数字で示し、徹底して検証することが当たり前になっている。だから、約束事が推進され、実現しやすいんです。
たとえば、スウェーデンの家庭ごみの資源リサイクル率は50%を超えます。エネルギーリサイクルを入れたら99%です。1990年代と比べると、1/3にまで減らしています。
国土の農地の20%はオーガニックです。企業の取締役の40%ほどが女性で、男女平等社会としては世界で5位といわれています。それでいて、経済成長率は2~3%アップしているんですね(コロナ前)。
――数値化したデータで、「環境や社会に対する正しい施策は、経済成長を邪魔しない」と証明している。
ペオさん:そうです。こうした数字を照らし合わせて、効果があること、経済を停滞させないことも確認しながら、環境に正しいことを実践し続けているんです。
Sustainability is not an Opinion. It's Science.(サステナビリティは意見ではない、科学)なんですよ。
直感や感覚で「いい・悪い」と議論するものではない。数値で計って、改善していくもの。
――確かに。日本だとまだサステナビリティはふわっとした意見、意見やスタイルのように思われていそうです。そこが1つの差なっているのかもしれないですね。
ペオさん:私はよく言うんですが、それは「体重計のないダイエット」と一緒。数値でしっかり図りなら科学的に検証しないと、ダイエットもサステナビリティも実現できないんですよ。
聡子さん:あとは『ナチュラルステップ』の影響も大きいですよね。
――『ナチュラル・ステップ』ですか?
ペオさん:1990年代に環境NGOのナチュラル・ステップが、地球環境が抱える課題に、何があり、どう解決できるかというルールをまとめました。大勢の専門家やNGO/NPOを集めて、それこそ科学的に検証した結果です。
これを『ナチュラル・ステップ』と名付けた絵本にして、スウェーデンの全世帯の家庭と、全国の学校に配ったんですよ。
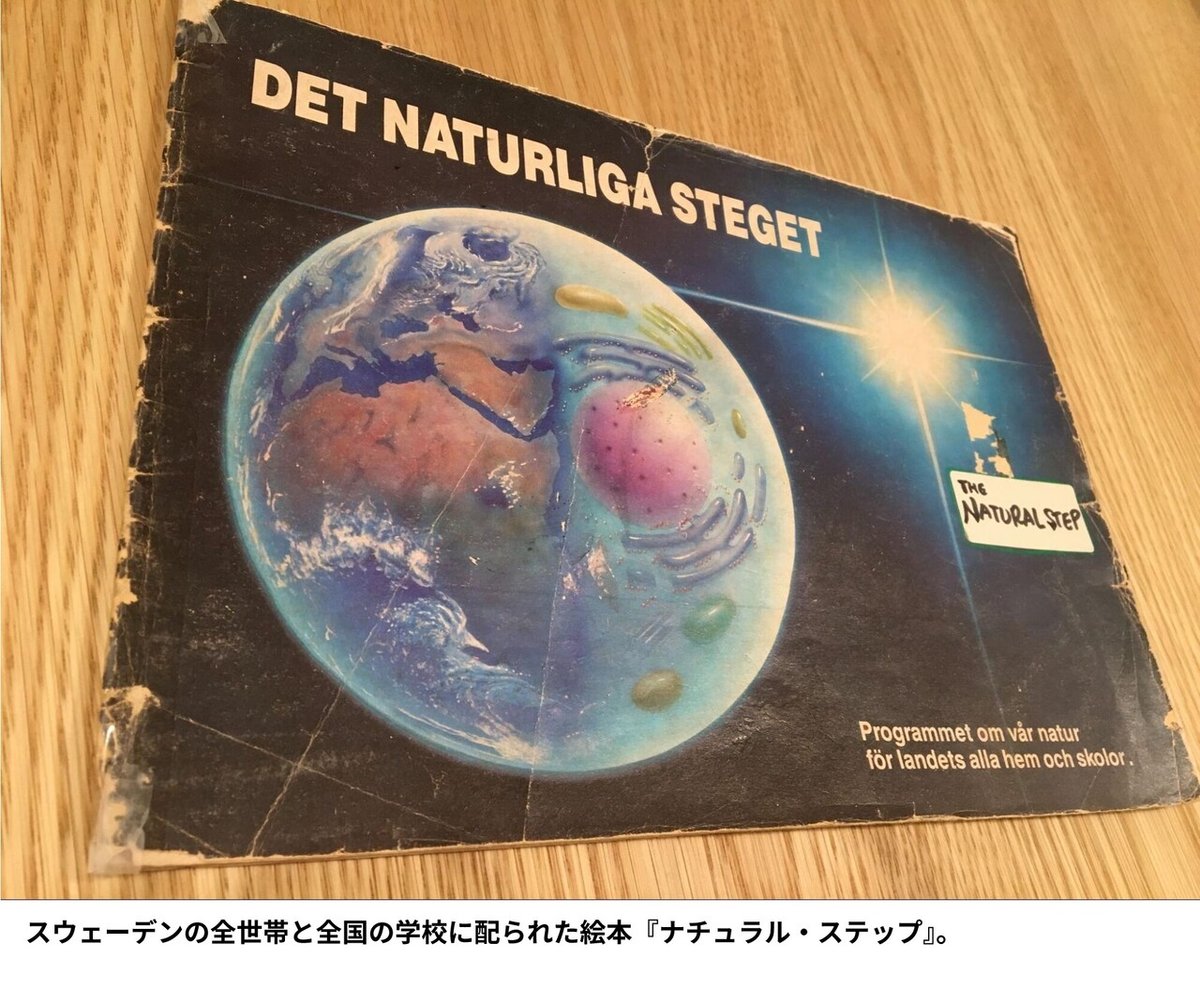
――たとえば、どのようなルールが書いてあるのですか?
ペオさん:わかりやすいのが「地下と地上」のルールです。

ペオさん:地球温暖化の原因のひとつはCO2の増加ですよね。そもそもCO2は、私たちをふくめた生きものが活動をして排出しています。
そして本来、地上の活動だけであれば、CO2が過剰に増えることはありません。排出された分のCO2は植物などが吸収するため、バランスが取れるのです。
ところが、私たち人間は、地下から資源を掘り出し、加工し、使っています。
――石油や石炭などですね。
ペオさん:そう。例えば石油は数百万年前から数千万年前の動植物が、深い地中のなかで変化したものです。これをあえて地下から地上へあげて、燃やすから、地球上に余分なCO2が生まれてしまっている。
石油からつくられるプラスチックは、加工しやすく安価ですが、実際は数千万年かけてつくられたもの。もとの形、石油へとリサイクルさせるには2000万年もかかるんです。しかも新たなCO2を地上へ排出させることになり、温暖化にもつながる。
――「だからできるだけ地上にあるものだけを使いましょう」ということですね。
ペオさん:そのとおりです。CO2が増えるから「人間や動物は息をするな」という話ではないんです。地下からわざわざ石油をとって、CO2を増やすことはやめましょうというシンプルな話。
話を戻すと、スウェーデンのほとんどの国民が、このようなルールをしっかりと学んでいる。地上と地下の話、これは「環境循環」の話ですよね。
こうした骨太の原理原則が根付いている。ホリスティックシンキングといいますが、包括的な見方、考え方がスウェーデン国民のコンセンサスとしてあるから、「環境に優しい」ではなく「環境に正しい」ことが当たり前に推進できるんです。

聡子さん:そうなんですよ。そうしたコンセンサスが揃っていない、包括的に環境や社会をとらえないまま、「ガソリンエンジンはどうなんだ」「ストローは是か非か」と、細かな話がされている気がします。だから議論になって、なかなか推進もしづらい。
けれど、スウェーデンは個人も、国も、みんなが羅針盤として、環境の原理原則を共有できているから、方向性が明確で、政策もダイナミックですよね。たとえば、修理やリサイクル品に関しては消費税が半分になる。
さきほどジュリさんがあげていたヌーディージーンズは、こういった背景があるので一生無料でジーンズの修理を受けてくれるんです。それは顧客サービスであると同時に、サステナビリティへの寄与で、またそれをしやすい政策があるからできているんですよ。
――そうかあ。「原理原則をつかむ」「包括的に考える」。私たち日本人が苦手なところでもある気がして、サステナビリティが浸透しづらい要因なのかと、少し気落ちしてきました(笑)。
聡子さん:いや。そんなことはありませんよ。逆に日本人には別のサステナビリティにフィットする感性がある。
たとえば「思いやり」という言葉です。
サステナビリティと、思いやりと、温泉旅行。
――「思いやり」ですか?
聡子さん:「思いやりを持ちましょう」といったときに、すっとその感覚が共有でき、他人の気持ちになって考え、行動できる。これは日本人ならではの感性だと感じます。
ちょっとだけ、その思いやりの輪を広げてみませんか? というと、それはサステナビリティの実現に近づくことになると思うんです。
――思いやることはどういうことか、それはとてもよく理解できます。たしかに日本人らしい、コンセンサスになりそうですね。
ペオさん:あとは「包括的に考えるのが苦手」と言いましたが、日本人が得意な面もあるんですよ。
温泉旅行をみてください。私の父が日本に来たとき、「ぜひ温泉にいってみて」と伝えたら、「風呂なんて別にいいよ」といやがった。けれど、実際にいってみたら、大喜びでしたよ。

温泉旅行は、ただお風呂に入るだけじゃない。ゆったりと湯船につかり、景色を楽しみ、浴衣に着替えて、美味しい料理を食べて、お酒を飲んで、リラックスする。これはとても包括的な楽しみ方じゃないですか(笑)。
――なるほど、確かにそうですね(笑)。
聡子さん:温泉旅行でも、サステナビリティな社会の実現でも、大切なのは「楽しさ」や「豊かさ」を感じられることですよね。「我慢」や「貧しさ」ではなく。そうすることからSDGsのゴールは近づいてくるんだと思いますよ。
――今日、お話をうかがっても、とても豊かで、楽しい気持ちになれました。本日は素敵なお話をありがとうございました。
(構成:箱田高樹)
※ 取材時の写真を除き、お写真は株式会社ワンプラネット・カフェからお借りしました(PHOTO : One Planet Café)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
