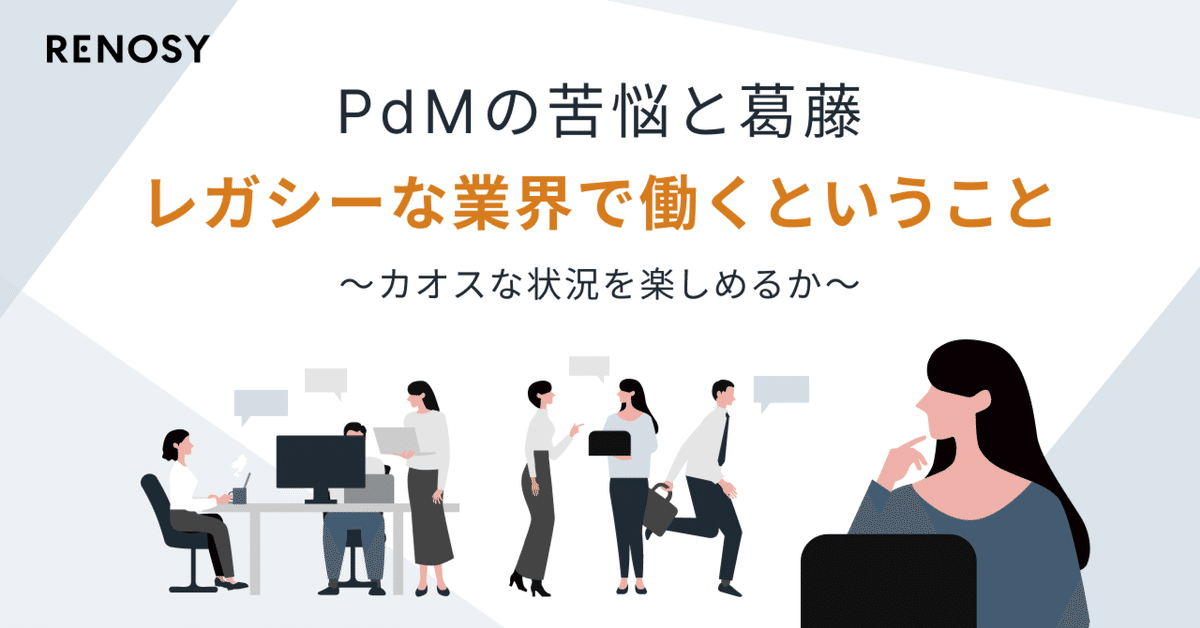
PdMの葛藤:レガシーな業界で働くということ。〜カオスな状況を楽しめるか〜
こんにちは。株式会社GA technologiesでRENOSYのプロダクトマネージャー(以下、PdM)を務める馬場(@yonyonyoko)です。
最近、近所にイケてるワインショップがオープンして毎週のように通っているのですが、まだお店の方に顔を覚えていただけておりません(笑)もう少しアイデンティティを強めたい今日この頃です。

さて、GA technologiesにジョインして3年半が経ちました。入社当時は自分がPdMで生きていくということは想像だにしておりませんでしたが、様々なバックグラウンドの方と仕事をし、時には揉みくちゃにしていただきながら何とか板に付いてきたのではないかと思っています。
前回の記事もよかったらご一読ください。
このnoteは、レガシーな業界でPdMとして働こうと考えている方、もしくはレガシーな業界で既に働いている方に向けた内容になっており、特に会社が急成長しているフェーズの中で奮闘するPdMの戯言です。「なんか面白そう」と思っていただけたら本望です。
サマリ
4,000字の長文なので、まず最初にサマると下記の課題背景+打ち手が含まれた内容になっています。興味を持っていただけたら読み進めてください!そして、同じ経験をされている、もしくは共感された場合は、X(Twitter)などでコメントをいただけたらボロ泣きします。

はじめに:プロダクト改善サイクルのスタック
GA technologiesに入社した当時は、PdMという職種で働いていたメンバーは数名程度しかおらず、マーケティングの組織にPdMの機能が内包されていました。
そんな中、3年も務めていますと会社の急激な成長スピードにケイパがフィットしない部分が出てきます。
私が担当する領域のプロダクトは不動産投資事業ですが、ビジネス側とプロダクト側の距離感があり、具体的にビジネス側に入り込んでプロダクト中心で事業成長を支えているとは言い難い状況でした。

つい半期前まではこのような状態が続き、プロダクトロードマップを引いてもなかなかワークしない状況がありました。昔ながらの不動産営業文化も残る企業ですので、最後は営業力に頼り、マンパワーで何とか目標を達成していた状況でした。現場のコミット力にはいつも驚かされますが(笑)
それゆえ、最後は営業力に依存する傾向があり、目の前の数字達成がどうしても優先になっていました。「人が頑張れば何とか達成できる」という状態が作れていたからです。
一方でプロダクト視点で見ると、非効率な業務は削減し、本来リソースを集中するべきものに注力できる状況をプロダクトの力で創出するためには、一定の開発投資期間が必要なわけです。
このような背景から、ビジネス側とピースが合わないことが多く、本来1事業では同じベクトルを向くべきであろうに、プロダクト側とビジネス側での温度差をすごく感じていました。
そんな時に出会ったnoteです。
プロダクトロードマップを作っても作る工数だけが発生していたという悩みを抱えていたときに、救っていただいたnoteです。このnoteがきっかけでプロダクトの枠組みを超えた検討ができる状態になりました。
プロダクト改善のボトルネックは何だったか?
プロダクトとビジネス側の両軸で、事業計画が検討されていない
弊社では、現行法上プロダクト完結のユーザー体験はなく、必ず購入または売却までのプロセスに人が介在する必要があります。
それはビジネスサイドとプロダクトサイド、それぞれ把握しているはずなのですが、なぜ連携が取れてこなかったのでしょうか。
これまで”丁寧なすり合わせをしてこなかった”が要因の1つでは?と思っています。
やめたこと: プロダクト主体で考えることをやめた
弊社はプロダクト単体でビジネスが回っているわけではありません。
取引先のパートナー様、実務の業務プロセス(煩雑かつ利害関係者が多い)があって、はじめてお客さまへの商品提供ができます。つまり、「プロダクト本意で動いても上手くいくはずはない」ということに気づきました。
プロダクト主導で事業ロードマップを立てることにした
半年前までが上記の状態だった上、さらに追い討ちをかけるように「プロダクトロードマップを作ろう」という動きがありました。また犬の道を歩んでしまうことになるのか?と、どうしてもモチベーションが上がりきらず、次の半年をどう過ごそうか考えていました。(今だから言えますが…!)
そして、同時期にプロダクトとマーケティング組織が分かれ、チームやメンバーもリフレッシュされました。そのタイミングで課題感を上長にぶつけてみました。どうやら同じことを思われていたようです。
ニーズがマッチしたなら、やるしかねィ!
事業計画の進め方:マッキンゼー「問題解決の7step」になぞって実践。
私が担当する領域は、投資事業の中の仕入れ領域です。販売、管理といった全領域に手を付けようとするとさすがにPdMの領域を大きく超え、足元で動いているプロジェクトが動かなくなってしまうので(笑)仕入れにスコープを置いて実践しました。
なお、以下の記事を参考にしました。戦略コンサルほど短納期コミットはできませんが、前段の部分の整理が重要なので、部分的ではありながらも同じような動きをしていると思います。
1.問題を定義する
2.問題を分解する
3.優先度を決める
4. 作業計画を立てる
5. データの収集と分析
6. 分析結果を統合する
7. ストーリーで語る
大事なこと:①前提のすり合わせ、②信頼の構築、そして③スピード
持論ではありますし、現在実践中ですので失敗するかもしれません(笑)
結局、これまでの失敗例でいうとプロダクトサイドがよしなに動いたが結果、ビジネスサイドとの認識(重要度、優先度)の乖離が生まれていたことが足枷になっていたこともあり、進め方には十分配慮しています。
①前提のすり合わせ
最も時間をかけたのは、7stepでいう1st stepの①問題の定義です。なお、私のミッションのゴールは「事業目標に対してのギャップをどのように埋めるか」 ですので、”問題を定義する”という言葉をもう少し噛み砕くと「事業目標を達成するための前提条件は何か、その前提を踏まえると何が論点になり得るか」ということに集中していました。
前提が覆らないようにすることにフォーカスしたわけです。
例えば、以下のようなケースです。
10年後の事業目標が現状の10倍だとすると、人員も比例して10倍を目指すのか?
極論ではありますが、前提が変わると全ての計画(WHO / WHAT / HOW)が覆るためです。その状態になることを死守することだけを考えて動いてきました。
②信頼の構築
これまでビジネスサイドとプロダクトサイドがよしなに動いていた、と伝えてきました。プロジェクト単位ではもちろん連携はしますが、全体の動き方、現状どのような施策が動いていてどのようなマイルストーンが置かれているのか全くのブラックボックスでした。ビジネスサイドも同じ状況だったと思います。
弊社のメンバーはWIN-X(共に勝つ)、HEART(人としてちゃんとしよう)のスピリットを持つ方ばかりなので、以下のようなことを思っている方はほとんどいないとは思いますが、そう思われても仕方ないというか、プロダクトサイドからも大きく提案ができる機会というのもなかったのは事実でした。
事業のためにプロダクトは何ができるの?何をしてくれるの?
手段としては以下の機会しかない状況でしたので、上段の背景を共有した上で、双方のコミュニケーションの機会をいただきました。現状、週に合計3時間ほどは、以下に時間を要しています。
ビジネスサイドからのインプットの機会をいただく
前提整理の共有・すり合わせの機会をいただく
その他、現段階でプロダクトサイドが関わらない施策についても全て把握しにいきました。プロダクト起点で問題解決ができる可能性があるためです。
一見非効率に見えると思いますが、もっともレガシーな業界はリアルコミュニケーション文化を大切にされるので、信頼構築のスピードもぐんと上がりました。その実感として上がったものは以下です。
(1)情報共有
- わざわざ「この件の状況って…」など、ヒアリングしないと出てこなかった情報が、能動的に共有いただけるようになった
(2)ベクトルの一致
- あっちもこっちも頑張るという状況から、ここが重要だよね、など注力ポイントが分かってきた
③スピード
事業目標の達成のために、すり合わせの時間は丁寧に、何度も会議を重ねて絶対に覆したくないこと、重要なことはキーワードを絞って反復共有しています。
みなさん忙しいです。それぞれミッションを持っていて思考していることも多方面に及ぶためです。ひいては事業計画自体は目下すぐに成果が出ることを推進しているわけではありません。”短期で成果が出ること全部頑張る”の精神が根底にあるところからの意識の脱却も行わなければなりません。
レガシーな業界でPdMとして働くということ
骨が折れます(笑)度々カオスな状況が生まれ「なぜそうなる?笑」というようなことも日常茶飯事です。それすらも笑いながら問題解決ができる人が弊社のPdMとして活躍するのだと思います。
そしてまた、このような状況を経験したPdMは、どの業界に行っても強靭なメンタルと実行力で通用すると自信を持って断言できます。
次回、”事業ロードマップの、その後。”
あと数ヶ月で事業計画・事業ロードマップを描ききらなければなりません。それが私の今期のミッションになっています。下の図を実現するために!!

乞うご期待ですw
日々カオスな状況を楽しみたい方、カジュアルにお話してみませんか?
PdM組織も少しずつメンバーが増えてきました。全員が全員、今回執筆したnoteのようなコミットメントの仕方はしていませんので、どのようなプロダクトがあり、それぞれどのように働いているか等もお伝えできれば幸いです。
今後も事業を急拡大させていく中で、動かすヒト・モノ・カネのダイナミック性は日々ワクワクするものです。プロダクトが事業成長のドライバーになることは間違いありません。
PMM / PdMポジションそれぞれで募集しています。ぜひ一緒にこのカオスな状況を共有し、分かち合い、楽しみましょう!
では、また半期後に!
最後までお読みいただきありがとうございました!
