
夏目漱石『こころ』を読む - 日本の純文学の"北極星"的な不滅の古典
朝日新聞が発表した「この1000年『日本の文学者』読者人気投票」を見ると、夏目漱石が第1位になっている。手前味噌な臭いもするが、妥当な結果だろう。その漱石の作品ランキングを覗くと、ほぼどの番付表でも『こころ』が最高位に位置づけられている。これも異論のない順位と評価だろう。日本人なら誰でも一度は『こころ』を読んで感想文を書く課題の前に立つ。普通はそれを高校時代にやっていて、教育課程の一環として通過儀礼を受けている。ずいぶん遅い取り組みになったが、私もその宿題を提出したい。ほったらかしにしておくと健康寿命の年を迎えてしまう。3年前、太宰治の『走れメロス』の感想文を書いたことがあり、自己満足ながら佳作の記事に仕上がった。果たして、漱石の『こころ』も面白かった。予想以上に面白く、ぐいぐいと惹き込まれて最後まで一気に読み切った。

素晴らしい純文学の古典だと思うし、世評どおりの至高の名作だと実感する。何より古くない。一世紀以上前という時代の古さを感じない。現代の日本語の標準的な小説であり、教科書に載るべき文章だ。その点に感動させられる。文章がいい。小説らしい。小説とはこう書くのだと教える範型になっている。多くの青年作家がお手本にして創作の技法と要領を学んだだろう。文章表現が端正で、言葉が精確で、文学の魅力が凝縮されて香り立っている。小説の魅力とは、やはり心理描写である。登場人物の内面の動きをどこまで深く鋭く豊かに説明するか、それを読者に説得するかが小説の醍醐味だと思う。『こころ』は完璧で、「先生の『遺書』」の部分は圧巻だった。「先生」の葛藤と懊悩と懺悔、嫉妬と怯弱と奸詐、悪意と弁解と自己欺瞞。漱石の筆が読者にスリリングに迫ってきて夢中にさせる。

迸るような心理描写の展開が続き、迫真の言葉が流れて読者の心を揺らせつつ、そこに印象的な二字熟語がピシピシと入り、読者を立ち止まらせる。感情のうねりの中に没入した読者の呼吸を整えさせる。調戯、狐疑、詰責、譫言、艱苦、直覚、予覚、余習、影像、摂欲、爛酔、冷罵、驚怖、所決、、。最近の一般のテキストであまり目にすることのない二字熟語のリズム感が心地いい。漱石は漢籍の人だったなあと感じ入る。切れ味のいい二字熟語が文章の魅力を作っていて、目に入る度に爽快に感じる。物語から離れて、漢字の表現の世界に心が移る。そのページに付箋を貼り、何度も読み直し、この二字熟語をストックして自分の文章に応用・駆使できるかなと考える。その瞬間が愉しくもあり、残りの人生の時間の短さや年々衰える記憶力を思って淋しくもなる。

この作品が読みやすいと思う理由は、構成が優れているからだ。構成のバランスがいい。最初にもくじを読めば、またそうでなくても、ほとんどの読者は、この小説は「先生」が自殺する悲劇だと事前に知っている。この小説を読むことは、「先生」の自殺の物語を追いかけて結末まで辿る営みだ。クライマックスはそこにある。もくじ的には上中下と三部構成だが、物語は起承転結に組まれている。上の「先生と私」が起であり、中の「両親と私」が承であり、下の「先生の遺書」でKが登場する場面からが転であり、二人の自殺が結である。起承転結のドラマ。話の構成が明確で、いわば漢詩的だ。夏目漱石だなあと思うし、周到に入念に設計したことが窺われる。晩年の作品であり、完成度が高い。新聞連載の分量で段が区切られている点も読みやすい。ここにも才能を感じる。設計の妙がある。
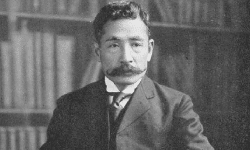
もう一つ。漱石の前半の作品群に見られるような、華麗な人文知識の散りばめというか、ユーモラスな蘊蓄の披露がない点も、この作品の特徴として感じる点だ。『こころ』は徹頭徹尾モノトーンである。モノクロの独白世界が暗鬱に進行する。『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『草枕』のような軽快でカラフルな世界がなく、漱石らしい洒脱なセンスがない。抑制的に創作されている。具体性を削ぎ落して、本質的なテーマに迫る心理描写だけに集中して筆を進めている。例えば、先生とKの大学での専攻が何かが書かれていない。主人公についても何を学んだのか、どういう学問的関心を持っていたのか触れていない。以前の漱石であれば、そこを該博な知識で縦横に描いて紹介しただろう。登場人物が肉体のない精神の塊のような姿で延々と語っている。しかし、これこそが文学らしく小説らしい世界だ。

ストーリーについて率直に疑問を上げると、不自然な点が一つある。それは、お嬢さん(妻の静)が、Kの自殺の原因について、先生の求婚と何らか因果関係があるのではないかと寸毫も疑わず、それを詮索せず意識していないという問題だ。この点は素朴に不可解であり、小説の設定として不具合だと思う。Kが突然自殺したのは、先生が奥さん(母親)に「お嬢さんを私に下さい」と告白した直後の時間である(5、6日後)。奥さんとお嬢さんの家には、二つの衝撃的な事件が同時に発生した。慶事と凶事と。その二つが何の因果関係もなく、偶然の重なりであるとは、普通の感性なら受け止めないだろう。疑いを持つはずだし、先生とKの間で何かがあったのではと直観をめぐらすのが当然だ。奥さんとお嬢さんで心当たりを推理・検討し、Kの自殺の真因が失恋にあるのではないかという目星を立てておかしくない。

奥さん(母親)は、もともと、先生を愛娘と結婚させようと考えていた。先生が下宿を求めて訪問したとき、初見で一発で依頼を承諾したのも、帝大生で印象がよかったからであり、期待していたとおりの理想の男性の出現だったからである。三人で生活するうち、奥さんの期待は確信となり、母子にとって希望的な将来方向に繋がって行った。そこへ、Kが飛び込んできて四人生活となる。が、Kの人品骨柄も悪くなかった。奥さんにとって、おそらくKは第二希望的な、いわば安牌(スペア)の存在だったに違いない。先生もKも、二人とも美貌で可憐なお嬢さんに惚れてしまう。奥さんとしては、二人が競争して娘を奪い合うことが、最も確実で安心できる展望となる。二人の男子の大学卒業が間近に迫り、早くどちらかが求婚を言い出さないかと、奥さんは焦りつつ待機していたのではないか。お嬢さんも同じだろう。

奥さん(母親)とお嬢さんの間で、そうした問題を相談し合っていてもおかしくない。「あなたはどっちが好いの?」とか。少なくとも、高等女学校の卒業を控えて、この家族の最大の関心は娘の結婚であり、できれば、気の合った下宿生二人のうちのどちらかに嫁ぐ前途が安定的に固まればいい、第一希望ならなおいい、という想定だっただろう。当然、奥さんもお嬢さんも、女性の勘で、男子二人ともお嬢さんに気がある事実は察知している。Kの純情な性格はそれを隠せない。先生の方は日常生活の挙措でシグナルを(いつ求愛してもいいように、断られないように)発信していたはずだ。結局、第一希望の方が先に求婚を切り出し、奥さんは即刻快諾した。「宣ござんす、差し上げましょう」と。待っていたときが到来し、奥さんは安堵したに違いない。しかし、であれば、当然(第二希望の)Kは失恋という事態になる。

そこから5日後に頸動脈を掻き切ったKの行動の原因が、失恋にあるという想像が奥さんとお嬢さんにできないはずがなく、思い浮かばないはずがない。ところが、小説はそこを否定していて、求婚と自殺とを切断している。最初の方で先生の妻の静(お嬢さん)にこう言わせていた。「何故その方(先生の親友K)が死んだのか、私には解らないの。先生にも恐らく解ってないでしょう。けれどもそれから先生が変わって来たと思えば、そう思われないこともないのよ」(新潮文庫 P.61-62)。この発言は、物語全体の伏線になっていて、序章の導入部だから、小説としてはこうした処理と演出になるのかもしれない。しかし、どう考えても不整合で辻褄が合わず、理解と納得に苦しむ。彼女はKとも一つ屋根で1年近く同居していたのである。まるで他人のように言っていて、自分とは全く関わりのない遠い人間のように説明している。

Kの自殺は、失恋の所為というよりも、この世で信頼できる唯一の親友である先生に残酷に裏切られたからだった。その打撃と絶望のゆえに自殺を選択したのであり、ある意味では、親友の佞奸と狡猾に対する怒りを、死を以って抗議と復讐の形にしたと言える。結果的に、先生は咎を背負って精神を苛まれる人生を送り、最後は罪滅ぼしの自殺で総括という顛末に至る。Kの復讐は果たされた。そして今度は、主人公の「私」が嘗ての先生の立場になり、先生の全てを知り、自殺の動機と真相を知りつつ、それを奥さん(先生の妻の静)に報告できないという不幸で面倒な境遇となった。先生は遺書の最後に、「私は妻には何にも知らせたくないのです。妻が生きている以上は、あなた限りに打ち明けられた私の秘密として、凡てを腹の中にしまって置いて下さい」と遺言している(P. 326)。「私」には残酷な責任と義務だろう。
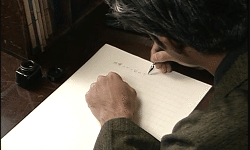
最後に、この作品は本当に薄暗くモノトーンで、これが夏目漱石の作品かと思って驚くほど、重苦しい厭世と憂愁の暗雲が覆い漂っている。書かれたのは死の2年前の1914年(大正3年)。『坊っちゃん』が書かれたのが、その8年前の1906年(明治39年)。たった8年だが、その間、漱石は胃潰瘍で5度倒れて吐血し、痔と神経衰弱に苦しむ病人となっていた。『こころ』を読んで目の前に立ち上がるのは、石川啄木の「地図の上 朝鮮国に 黒々と 墨をぬりつつ 秋風を聴く」の情景であり、その空間の暗黒と荒涼である。歌が作られたのは1910年で、その年の韓国併合を啄木は沈鬱な気分で詠んだ。同じ1910年に大逆事件が起き、幸徳秋水・管野スガら12名が冤罪で処刑された。いわゆる「冬の時代」であり、年表を確認すると、『こころ』の執筆がどういう時代環境で行われたかが頷ける。明治末から大正初。

民権が死に、国権が凶暴に張り出し、言論と精神の自由が閉ざされ、明治の革新性と溌溂さが失われた、知識人にとっては生きにくい、悲観と憔悴一色の時代だったのだろう。社会(世間)は帝国の牢獄と化していたのだ。『こころ』には時代の息苦しさが表現されている。作中、乃木希典の死が挿入されてアクセントとなっているが、果たして、漱石はあのように乃木希典の死を、当時の国家や国民と同一の心境で受け止めていたのだろうか。時代の空気に合わせた(迎合した)リップサービスだと私には映る。無論、明治の子である漱石にとって、乃木将軍は象徴的英雄であり、自己と同一化した偶像だったことは間違いない。だが、その死への感傷は、新聞が撒いて煽る帝国のプロパガンダや、それに共鳴して美化する臣民大衆のシンフォニーとは異質で別次元の中身だったのではないか。漱石は帝国に深刻な疎外感を感じていたはずだ。

最後の最後に、『こころ』の解説と批評には、必ずエゴイズムという言葉が躍っている。人間のエゴイズムを見つめた作品だとか。エゴイズムの語を入れて論じない感想文は、『こころ』の感想文として失格だろう。私たちも学校の国語でそう習った。人間は誰でもエゴイズムの弱点を持っていて、その心性を正しく認め、そこからの解脱と克己を考えないといけないのだと。そんな指導を教室で聞いた。『こころ』はその教育素材だと。果たして、半世紀経って、エゴイズムという言葉は当時と同じ意味で日本社会で使われていないように観察される。エゴイズムの対象化や批判の態度はないように見える。純粋で潔癖な理想的生き方とエゴイズムの宿痾と悪弊というような、白黒、明暗、善悪の対立軸が現代人の中に画然とあるのだろうか。ネットを見ると、株価の話題一色であり、グリードな資本主義者以外がこの世に生きている感じがしない。

どれもこれも、デフォルトで弱い者いじめを肯定している。弱者には揶揄と冷笑と差別しかない。批判精神を核とした知識と教養と問題提起には、侮辱と罵倒だけが返ってくる。エゴイズムという言葉も、畢竟、死語になっていて、現在の日本人は嘗ての生きた概念で日常会話の中で使っていない。倫理の緊張感を以って対峙する自己内の悪ではなくなっている。エゴイズムが普通の生き方で、それは正当化される表象と化している。なので、漱石の不滅の労作も、今の日本人(特に若い世代)にどう響いているか、よく見当がつかない。欲しいものは巧く手に入れるのが当然で、欺かれて自殺する奴がバカだというのが、現代の若者の正直な認識と結論だろうし、その正直な感想文にマルをつけて返したいのが、自民党と文科省に律儀な教師の対応ではないか。我利我利のネオリベ・エゴイストしかいない社会に、エゴイズムという批判語の居場所はないのだ。














この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
