
今日からスマホと距離を置く
朝起きたらスマホ、通勤の往復でもとりあえずスマホ、ご飯食べるときもスマホ、寝る前もぎりぎりまでスマホを見ているという方は必読です。
■はじめに
『スマホ脳』
どんな本→スマホが人の体に引き起こす様々な問題を丁寧に解説
読みやすさ★★★★☆(読みやすい)
新潮社 2020年出版
著者:アンデシュ・ハンセン
自分が初めてiPhoneを手にしたのが2009年。そこから常にスマホが傍らにある生活を送っているのですでに12年が経っています。もはや手放すことは不可能と言っていい状態です。
日本ではスマホの前にガラケー全盛期があり、スマホが普及するのか懐疑的な声もありました。結果としてはそのような予測は完全に外れ、今では誰もがスマホを持つ生活が当たり前になっています。電車の中でふと周囲を見回すと全員がスマホを触っているという状況も日常の光景です。
今回ご紹介する「スマホ脳」は前から話題になっていたのですがやっと読むことが出来ました。自分自身、寝る前に布団の中でスマホをさわり出すとあっという間に30分経って寝不足へ・・・と言ったことがよくあります。そういた意味でもスマホがどのような影響を人に与えているのか注目です。
■学びたい3つのポイント
①なぜ人はスマホに夢中になるのか?
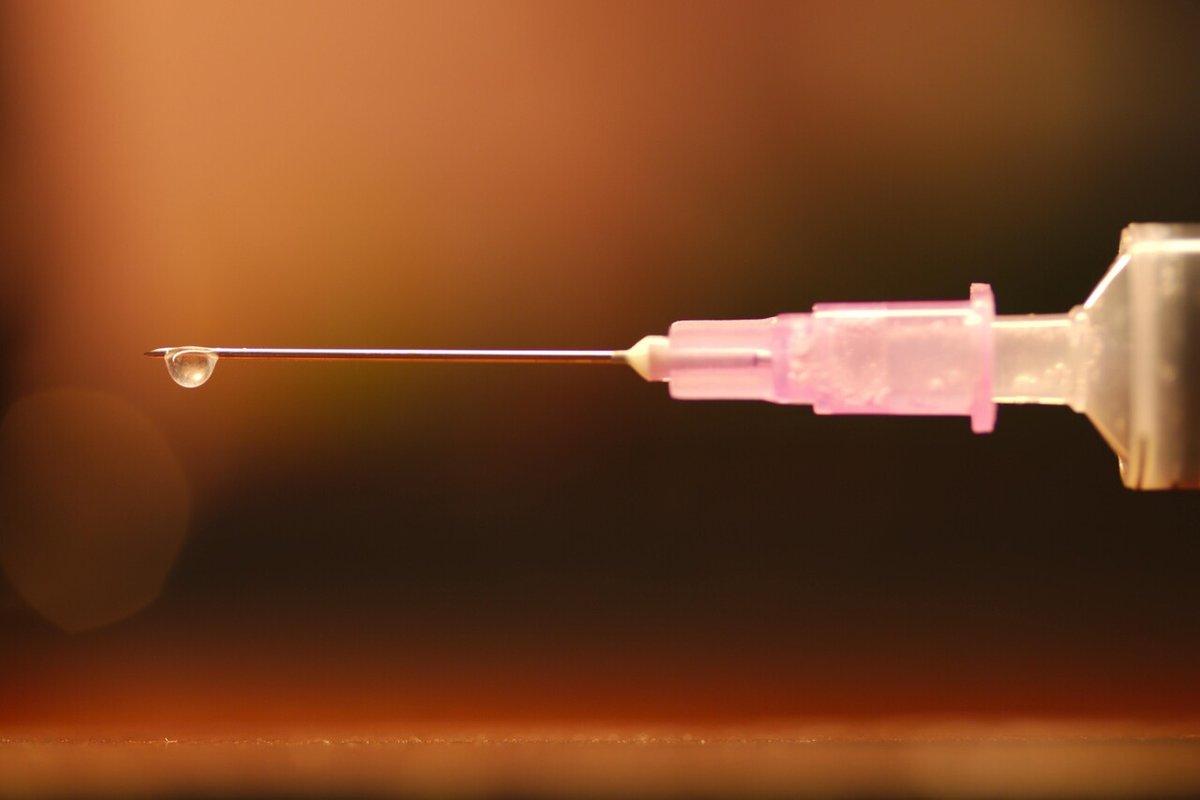
脳は基本的に昔と同じままで、新しいものへの欲求も残っている。しかし、それが単に新しい場所を見たいという以上の意味を持つようになった。それはパソコンやスマホが運んでくる。新しい知識や情報への欲求だ。パソコンやスマホのページをめくるごとに、脳がドーパミンを放出し、その結果、私たちはクリックが大好きになる(P73)
ドーパミンの役割はつまり、何が重要で何に集中を傾けるべきかを伝えることだが(中略)スマホほど巧妙に作られたものが他にあるだろうか。ちょっとした「ドーパミン注射」を1日に300回も与えてくれるなんて。スマホは毎回あなたに「こっちに集中してよ」と頼んでいるのだ(P107-108)
なぜスマホやPCでニュースサイトやSNS、アプリ記事を見ているとつい次のニュース、他のニュースを見て「だらだらネットサーフィン」をしてしまうのか。単なる現実逃避と思っていましたが、こういった行動を取ることにも理由がありました。
本書で何度も指摘されるのが、人間の「脳」は実は太古の時代からほとんど性能としては変っていないという事実です。過去の人類が生き延びるためで必要とした”新たな情報を求める行為”に対して、現代でもドーパミンが放出されます。
スマホはこの人間に脳の仕組みを利用することで、より新しい情報、より新しい情報へと我々の指をスクロールやタップに導いているのです。急ぎでもないのについスマホを開きたくなるのは「新しい情報を得られるかも=ドーパミンが放出される」と無意識でも感じていることが原因でした。
②様々な無料サービスは、あなたの時間を欲している

あなたがフェイスブックやインスタグラム、スナップチャット(訳注で日本の場合はLINEが主流との記述あり)に費やす1分1分が、企業にとっては黄金の価値を持つ。広告が売れるからだ。彼らの目的は、私たちからできるだけたくさんの時間を奪うこと(P14)
フェイスブック、スナップチャット、ツイッター各社の製品は、あなたが自由にメッセージや画像をシェアし、デジタル承認欲求を満たすプラットフォームそのものではない。「あなたの注目」こそが、彼らの製品なのだ。それを様々な広告主に転売できるよう、メッセージや画像、デジタル承認を使って注目を引く。無料で使えてラッキーと思っていたら、大間違いなのだ(P159)
なぜツイッターもLINEも無料で使えて、Yahoo!にお金を払うことも無く様々なニュースやコンテンツを見ることができるのか。私たちはもはやそんな理由を考えることも無いくらい、日々の生活で多くの無料サービスを活用しています。
民放テレビもそうですが、基本的には無料で提供されているサービスはその多くが「広告収入」によって成り立っています。ウェブ上の広告に興味を持ったことが無いという方もいるかもしれませんが、広告を掲出する企業が費用対効果を得られると評価したため、ビジネスとして成立しているのです。
各サービスは、ひとりでも多くの利用者を獲得し、その利用者に多くの時間を使ってもらうことで、より広告収入を得ることができます。ユーザー主導に見えるサービスも、原則ビジネスで行われていることを改めて理解しておくことが必要なのです。
③スマホが子どもたちに与える影響

パソコン、スマホ、タブレット端末を週に10時間以上使うティーンエイジャーがもっとも「幸せではない」と感じている。その次が6~9時間使用する若者だ。つまり4~5時間以下の若者よりも「幸せではない」と思う率が高い。そんな調子で続く(P189-190)
4000人の若年層にアンケートに答えてもらい、さらに1年後にもう一度アンケートを取った。その回答からは1回目のアンケートでスマホをよく使うと応えた人ほど、その後の1年で睡眠障害やうつ、ストレスを感じる率が高いことが読み取れた(P191)
筆者は精神科医として、精神の不調を訴える若年層が年々増えていることを危惧してきました。安易な結論を出さないためにも、各国で行われた様々な調査を見ていますが、やはりスマホが若年層に与える負の影響が多いことを示唆しています。
イギリスの調査では11~18歳の半数が夜中にもスマホをチェックしたと答えており、7割近い回答者が「学校での勉強に影響が出ている」と自覚もしていました。大人と違ってまだ脳や心の機能が発達していない若年層は、スマホの影響をより強く受けてしまっている実態が垣間見えます。
今子どもを育てている親世代は、スマホが無かった時代に、小中高を過ごしてきた方が多いと思います。自分の子どもとスマホの距離については、安易に見過ごさず、真剣に考えてみてはどうでしょうか。上で画像も見えますが、本書の帯には「スティーブ・ジョブズはわが子になぜiPadを触らせなかったのか?」と書かれています。
■まとめ
スマホと人の関係性について様々な調査(出典がないのが若干気になりますが)をもとに書かれている本です。太古から人の脳がいかに仕組みとして変っていないか、そしてその脳に対してスマホと様々なWEBサービスが巧くアプローチして来るか。
「人の体は進化し、いずれ新しい技術に対応するはずだ」という意見について、筆者は否定的な見解を持っています。生存や繁殖に関わらない限り、人間は大きくは進化しないと。私たち自身がスマホとの付き合い方を、意識的にコントロールしていかなければならないのです。
本書では終盤に、心身の不具合への対抗策として「運動」がいかに効果的かという点にページが割かれています。1週間に合計で2時間の軽い運動を行うことで非常に良い効果が得られると。スマホを手放せなくなった今だからこそ、運動を行って、負の影響を打ち消すことが大事なのかもしれません。
いつもついスマホを開いてしまう方は、是非この本を読んで一度自分の人生にどこまでスマホが必要なのかを考え直してみましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
