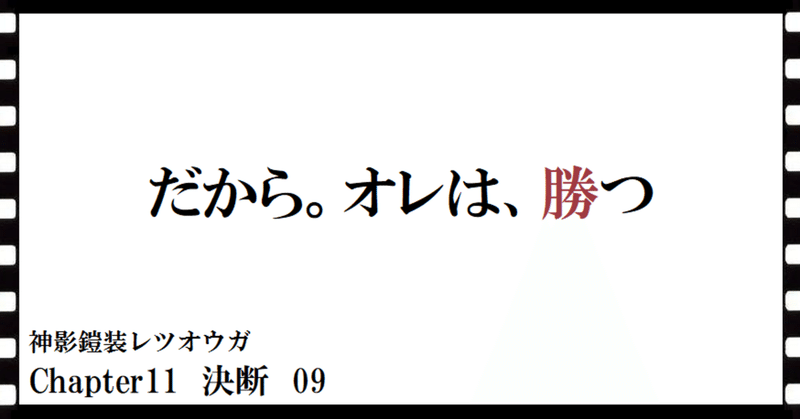
神影鎧装レツオウガ 第百十話
Chapter11 決断 09
USC――Under Ship Connection。日本語に訳するところの、地下帆船同盟。アメリカはサンフランシスコに本拠を構える、同国最大規模の魔術組織である。名前の由来は、日本語訳の通りサンフランシスコの地下に帆船が埋まっている所から来ている。
嘘でも冗談でも無い。1850年頃を中心に、その途方も無い埋め立ては行われた記録が実際にあるのだ。
ジョン・サッター氏が発見したのを皮切りに、当時のアメリカのみならず諸外国をもを揺るがした大金鉱の発見――いわゆるゴールドラッシュ。一攫千金の夢に見せられた血気盛んな者共は、あらゆる交通手段を使って山を掘りにやって来た。
徒歩で。
馬車で。
鉄道で。
そして海路で、だ。
特に海路、つまり帆船でやって来た者達の熱狂は凄まじかったようだ。当時の船乗りの仕事が、現在では考えられないレベルの危険や非常識と癒着していた事も理由の一つではあろうが……どうあれ熱狂に突き動かされるまま海を渡ってきた者共は、そのまま全員が船を下りて金を掘りに行ってしまう、という事態がままあった。
そう、全員だ。乗客のみならず、平船員、操舵手、航海長、甲板長、引いては船長に至るまで――要するに、帆船を乗り捨てる程に茹だった連中が居たのだ。
動かそうにも人手が足らず、どうにも出来ない巨大な帆船《そだいごみ》。倉庫や住居などとして使われた事もあったそうだが、それでも結構な数の船が湾岸の整備と一緒に埋め立てられてしまった。このため、近代においてもサンフランシスコでは工事の為に地面を掘り返すと、古い船が顔を出す事態がままあるのだという。
閑話休題。
さて、そこに目を付けたのが当時開拓者達と共にアメリカへ渡っていた魔術師達である。何せ表社会の者達が秘密の地下空間を、しかも合法的に作ってくれるというのだ。使わない方が嘘だろう、と魔術師達は狂喜した。
かくてUSCは産声を上げる。彼等はサンフランシスコの誰もが忘れ去った土中の船を足がかりに、地下深く深くへと根を広げた。土木開発目的の術式は、この時USCの手によって目覚ましい躍進を遂げた。何せサンフランシスコ近郊には、金の採掘を夢見る者達が絶えずひしめいていたのだから。
採掘者達が発する無形の霊力は、こと土木作業という一点において方向性を揃えていた。濾過術式が現代ほどの精度を持っていなかった当時、この性質は土木関連術式の開発に大きな手助けをしたのだ。
近年に至っては世界規模の巨大IT企業――ググるというネットスラングの元となった会社――の本社へ世界規模で流れてくる巨大霊脈をほぼ独占しており、百年単位に渡って未だ成長し続けている魔術組織なのだ。
だがそのような暴走じみた急成長の影には、やはり少なからぬ歪みが生まれるのもまた常であり。
USCが管理している最下層、その更に下。組織内の誰一人として知らないこの場所で、おもむろに剣を構える者が一人。
「……」
誰あろう、グレン・レイドウであった。
天井の照明を反射して、冷たく輝く両刃の刀身。色こそグレンの鎧装に合わせてあるが、現代的にアレンジされたその剣は、どう見ても辰巳《たつみ》が用いていたグラディウスそのものであり。
そのグラディウスを、グレンは無造作に振るう。
「しゅッ」
びょう、びょう、びょう。
刺し、斬り、払い。
軽く振るったつもりだったが、切っ先はグレンの想像以上に縦横無尽な孤を描いた。使い慣れた、いや、指先が剣になったようにすら思える一体感。微かな昂揚すら、グレンは覚えた。
だがその昂揚は、既にアイツも、ファントム4も味わっているものだ。
「……ッ」
知らず、グレンは奥歯を噛んでいた。
「新しい得物の調子はどうですか?」
そんなグレンの心情を知ってか知らずか、横合いからかけられる声が一つ。見やれば、壁を背にしてひょろ長い金髪の男が佇んでいた。
右にサラを、左にペネロペをそれぞれ侍らせた彼の名は、エドワード・サトウ。USCに潜入していたグロリアス・グローリィのエージェントであり、言わずもがなサトウの、標的《ターゲット》Sの分霊の一人であった。
このアメリカのサトウの尽力があったからこそ、グロリアス・グローリィは出島とでも言うべきこの秘密拠点を手に入れる事が出来たのだ。もっとも秘密裏かつ非合法、かつ物理的に密閉された空間であるため、出入りにはグレンのフォースアームシステムが必要不可欠なのだが。
それでも対外的に人造Rフィールドで入出を拒んでいる、ように見せかけたグロリアス・グローリィとしては、非常に貴重な補給経路の一本であった。
USCの歴史をなぞらえ、どこか船倉を思わせる造りをした広大な人工空間。ちょっとした民家なら丸ごと収まりそうなその壁際には、種々の補給物資を詰め込んだコンテナが山を成している。その内の一つに座りながら、ペネロペは足をぶらぶらさせていた。何故か体操服に身を包んでもいたが、グレンにツッコむ気力は無かった。
「良いさ。良いに決まってやがる。何せゼロツーが使ったブツなワケだからな。韋駄天術式共々、俺に使いこなせねぇハズが無ぇ」
韋駄天術式。つい先日完成したばかりの、韋駄天《アレクサンドロス》の力を引き出す五辻辰巳専用術式の名を、グレンはしれりと口にした。
確かに遺伝学上の同一人物《クローン》であるグレン・レイドウならば、問題無く使いこなす事は可能だろう。
だがまだまだ試作品の域を出ない上、ファントム・ユニットが凪守《なぎもり》へ存在を報せてすらいない代物を、何故グレンが既に使っているのか。
その答えを、サトウはにこやかに告げる。
「なるほど。霊泉同調《ミラーリング》は問題無く動いているようですね?」
「ああ。まったく便利なもんだぜ、忌々しいぐらいによ」
今サトウが言った霊力同調という単語、それが答えだ。
二年前。無貌の男《フェイスレス》に操られるまま、レツオウガが虚空領域へ設置した虚空術式。
完全な敷設こそ失敗したが、幾つかの機能は問題無く展開し、今も風葉《かざは》達がいる部屋の外で稼働を続けている。
そしてその内の一つに、辰巳《ゼロツー》とグレン《ゼロスリー》の深層意識を繋げる霊泉同調《ミラーリング》という機能があった。
虚空領域という亜空間を経由したこの同調は完全リアルタイムであり、かつ完全解放されれば人格の混濁すら引き起こすだろう強力な代物だ。
だが現状、混濁は成されていない。同調度合いそのものはかなり厳しく制限されているし、何よりグレン《ゼロスリー》側しか霊泉同調の術式を完全に搭載していないのだ。それもこれも、最終調整前に辰巳《ゼロツー》がレツオウガごと凪守へ鹵獲されてしまった為である。
故に現状、霊泉同調はグレンが辰巳の無意識の一部――強烈に印象に残った出来事や、使用術式のデータを回収するといった程度で留まっている。トルネード・ブラスターやスティンガー・ブラスターも、この霊泉同調を経由して生み出された術式なのである。
そして今、グレンは新たな術式を、韋駄天術式を霊泉同調によって手に入れており。
「では、ぼちぼち最終調整に入りましょうか。ねぇ、サラくん」
「そうですね」
サトウに促されるように、鎧装姿のサラはしずしずと歩み寄る。腰へ提げられた太刀へ、手をかけながら。
「正直、ちょっと。たまらないんですよね」
サラは笑った。
グレンは、小さく頭を振った。
「戦闘狂《スキモノ》め」
「イイじゃないですか、最初から最終調整《ソレ》が目的で私が居るんですし。それに」
仮面《バイザー》から覗くサラの唇が孤を描く。太刀の反りよりも深い曲線を描きながら、唇は謳う。
「ソレしか、無いんですから。私達には」
謳いながら、サラは太刀を抜き放つ。ゆらりと構えられた刃が、ぬらりと光る。
「……そうだな。まったくもってその通りだ」
対するグレンの表情は硬い。同じように仮面の下から覗く口元は、への字に結ばれている。
サラはそれで良いのだろう。何せ彼女はヴァルフェリアなのだから。
――ヴァルフェリア。それは北欧神話に謳われる戦乙女《ヴァルキリー》と英雄《エインフェリア》を掛け合わせた造語であり、ザイード・ギャリガンによって調整された乙女のなれの果てだ。
魔術や薬物によって記憶を漂白された彼女らは、その空いた記憶領域に英雄の情報やら術式やらをひたすら詰め込まれる。より強力になった転写術式、と言った所だろうか。
植え付けられる情報は膨大かつ強大であり、記憶の殆どを消去した上でも許容能力《キャパシティ》を逸脱する程だ。
なので、ザイード・ギャリガンの手腕がここから真価を発揮する。
記憶の漂白と同時に北欧神話系の術式を引用し、乙女《ひけんしゃ》を戦乙女《ヴァルキリー》へと強化。『英雄《エインフェリア》の魂を集める』という戦乙女の権能によって親和性が高まるため、英雄の情報に限ってではあるが、許容能力が大きく増えるのだ。
こうして乙女は英雄の情報を詰め込まれた上、能力に合わせた補助装置――サラで例えるなら能力のオンオフを切り替えるバイザー――を装着する。これで容赦無き戦闘マシンは、ヴァルフェリアは完成すると言う訳だ。
だから、サラは迷わない。ペネロペもそうだ。彼女等は主たるギャリガンの命令に従う、忠実な配下《ヴァルキリー》なのだから。
迷う理由が、なにもないのだ。
だが、グレンは違う。
「では、せっかくだからお願いしますよ、ペネロペさん」
「んぇ、あたしッスか? まぁ良ッスけど」
所在なげに揺らしていた足を止め、ペネロペは頬をかく。
「んじゃー、まぁ、よぉーい」
気怠げに腕を上げる。
「はじめー」
どうにも気の抜けた合図ではあったが、刃を交える二人には関係なかった。
「行きます」
「ああ」
無造作に、グレンがグラディウスを持ち上げる――その瞬間を縫うかのように、サラは動いた。
素早く、鋭く。英雄の知識と情報に裏打ちされた、恐るべき精度の踏み込み。鎧装の隙間を当然のように狙うその切っ先に、グレンはどうにか反応できるか出来ないか、と言った所だったろう。通常ならば。
だが今。グレンは辰巳と同様の韋駄天術式を展開しており。
仮面の下の双眸は、加速されたグレンの知覚は、サラの猛った太刀筋を易々と捉えていて。
振り下ろされる刃。
音を斬り裂くその一撃を、グレンはまざまざと視認しながら、半歩退く。
胸元の装甲で火花が散る。大腿の数ミリ先を刃が通過する。グレンの仮面の鼻先で、サラの刃がぎらと光る。
コンマ数秒の一瞬、グレンはサラの目を見た。
自分と同じく仮面に秘された双眸に、グレンは驚愕の色を見た。
「しゃッ」
下段。その仮面目がけて、グレンは刃を掬い上げる。
サラに回避を行う余裕は、無い。
かぁん。
甲高い音を立てて、サラの仮面が宙を舞う。先程以上の驚愕にまみれた素顔が、露わになる。
「――。おみごと」
熱っぽい吐息混じりに呟くサラ。それを待っていたかのように、仮面は床に落ちて来た。
バウンドし、回転しながら滑った後、壁にぶつかるサラの仮面。
多少歪んだようではあるが、切断されてはいない。どちらも霊力武装を切断出来ない訓練モードへ設定していたためだ。
「いやはや素晴らしい。韋駄天術式は問題無く馴染んでいるようですね」
ぱん、ぱん、ぱんと乾いた拍手を三つ。それから飛んだサラの仮面を拾って、サトウは壁際から歩いてくる。
「流石はゼロスリーの面目躍如、といったところですか」
にこやかな笑いを顔面に貼り付けるサトウ。その顔を、グレンは仮面越しに睨み付けた。
「……ああ。そうだな。そうだろうよ」
今ここでグラディウスをサトウのにやけ面へ叩き付けられたなら、どんなにスカッとするだろう。酷く魅力的なその妄想を、グレンは韋駄天術式と一緒に停止する。グラディウスは形を失い、霊力光となって妄想共々霧散する。
だが、消えないものもある。
怒りだ。
サトウに対して、ではない。辰巳《ゼロツー》へ向けた、グレン《ゼロスリー》自身どうにも形容できない激情だ。
グレンは霊力同調によって、辰巳の使った術式や戦闘経験、引いては日常の経験や心情の変化を知っている。
もっとも日常や心情に関してはうっすらと、といったレベルだ。虚空術式が不要と判断してフィルタリングしてしまうからだ。
だが、断片的には分かる。分かってしまう。
霧宮風葉と出会った事。歪ながらレツオウガを再現した事。ファントム5の入隊、共闘、離別。
そして、それを乗り越えた上で固めた決意。
気に入らなかった。
グレンには、その何もかもが、気に入らなかった。
「まぁ今回は模擬戦で、私も全力じゃなかったですからね? ヴァルフェリアの能力を解放してたら、どうなったか分かりませんよ?」
「ははん。絵に描いたような負け惜しみッスね」
「むっ、なによぉー」
道すがらサトウから仮面を受け取りつつ、サラはペネロペへ歩み寄ろうとする。
「だから。オレは、勝つ」
だがサラの足は、ぴたと止まった。背後。熱く、黒く、粘性を含んだ呟き。
振り向けば、グレンが己の仮面を指でなぞっていた。
ヴァルフェリアの能力を制限するサラのそれとは違って、グレンのバイザーに大した機能はない。無論視界の拡大や各種センサー等こそ搭載されてはいるが、それらは概ね普通の鎧装にも搭載されている機能ばかりだ。
では何故、グレンはそんな仮面を被っているのか。
単純な話だ。辰巳と自分が同じ顔だという事実を、認めたくないからだ。
認める訳には、いかないからだ。
「あのニセモノをツブして。オレは、ホンモノに、なる」
がりがりと。
かきむしるように己の仮面を抑えながら、一語一語を噛み締めるように、グレンは決意を吐き出す。
そのねじくれた決意を、サトウだけがにこやかに見つめていた。
【神影鎧装レツオウガ 裏話】
USCについて
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
