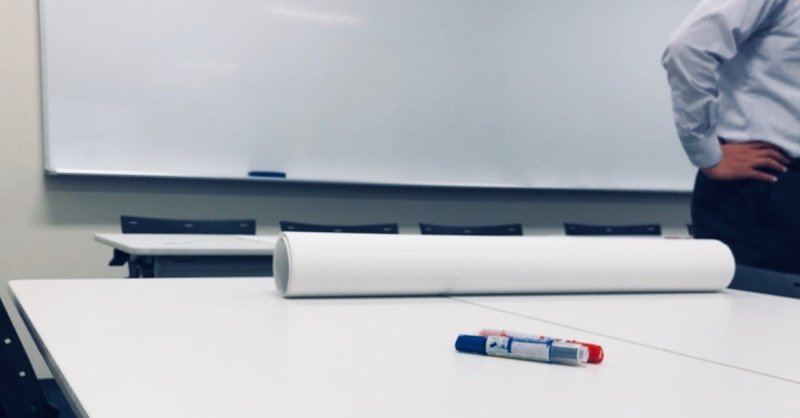
「職場はATMだ」に反論はできるのか!?
大学院の講義の中、サードプレイスのディスカッションの時間に、20代プログラマーのA君は言った。ザックリというならテーマは「あなたにとってセカンドプレイス=職場とは?」であった。
「職場はATMだ」
「仕事で自己実現とか、やりがいなどを考えていないです。サードプレイスの友達の中にいる時、楽しく過ごせることがイチバンなので、職場はお金(給料)を引き出せればいい、というか」と言葉が続いた。
よくよく聞けば彼は職場でかなり有望視されていることが分かるのだが、本人は「それに恩義は感じていますが、それだけが理由で会社に残るという選択はありません」とキッパリ。それを聞いていた40代、50代から、「せっかく働いているんだから、やりがいがないとつまらなくない?」「出世させてあげるって言っても魅力はない?」「じゃあ、給料が減ったら辞めちゃうの?」などとたくさんの質問が飛ぶが、「この人たちは何を言っているのだろう?」とA君はキョトンとしている。
「マズローで言うなら、ストレスなく、生きていくためのお金が稼げる自分自身の安全欲求が満たせれば、職場でその上の欲求を満たそうと思っていない」とキッパリ。
そうなのだ。年功序列、終身雇用がくずれてくると、ファーストプレイス(家庭)、セカンドプレイス(職場)、サード(利害関係がない自分らしくいられる場所)という考え方にも疑問がわいてくる。これからはセカンドとサードの境界が曖昧になっている働き方が求められているとも聞く。
会社はいちばん自分のコントロールが効きづらい場所なので、そこだけに「自分の居場所」や「自分のやりがい」を託すことの脆弱さは想像すれば分かる。ましてや、終身雇用は崩壊すると言われているので尚のこと。
Aくんは能力がないわけではない。やる気がないわけでもない。仕事に対する考え方が違うだけだ。これまでの常識の枠でこのような考え方に対しての判断をしまうと、せっかくの才能が埋没してしまう可能性がある。
「そういえば、子供も同じようなことを言っていた。説教しちゃったけど、説教されなきゃいけなかったのは自分だったかも」などと言いながら、「いや〜、ためになった」と管理職層の同級生たちは言葉を交わし合い、教室を後にした。
少なくても利害関係がない場所として、このようなフラットな対話が成立する社会人大学院は機能しているように思う一件だった。
今日の一冊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
