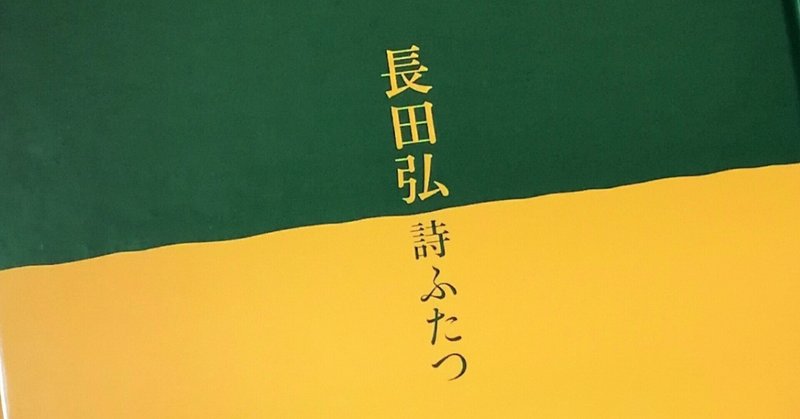
親を孤独死させないために
先日参加した勉強会での学びについて少し。
「地域のつながりがセーフティーネットになる」といった内容でした。地域づくりを木にたとえて、3つの社会資源で表して説明してくださいました。
枝・葉はフォーマルな社会資源。つまり、制度に基づくサービスのこと。
幹はインフォーマルな社会資源。地域の支え合い(自治会など)制度外で行う生活支援サービスなど。
3つ目は、根っこ。ナチュラルな資源だといいます。
ナチュラルな資源は、近所づきあいや仲間同士のつきあい。隣近所さんや、コンビニのオーナー、行きつけの喫茶店やそのほか犬の散歩で出会うお仲間などです。多くの人が当たり前にもっている資源だと思います。
しかし、何らかの理由でそれらを「当たり前」にもっていない人もいます。
タイトルに「親を孤独死させないために」と書きましたが、現代では、一人ぐらしも多く、一人で死を迎える方も多くいらっしゃることでしょう。
でも、そのすべてを「孤独死」と呼ぶものでしょうか。
「孤独」とは何でしょうか。
家族や友達のいない人?人に心を打ち明けられない人?誰かに頼れない人?弱音を吐けない人?助けを得られない人?誰も応援してくれる人がいない人?
「孤独死」とは?
一度、しっかり考えたいとは思いますが、私にはどちらもはっきりとした答えが出せません。
ただ、ナチュラルな資源がたくさんある人のことを「孤独」とは言わない気がします。たとえ一人で亡くなったとしても、誰かがすぐに発見してくれるなら、それを「孤独死」と言わない気がします。
自分の話になりますが、私の母はひとりで亡くなっていました。
最初に気づいてくれたのは、新聞配達の方でした。新聞が数日分たまっていたため、気になって管理人さんに伝えてくれました。発見されたときには死後何日かが、すぐにはわかりませんでした。その後、警察の聞き込みで複数の証言が出てきました。
「〇曜日に買い物にでかけていた」
「〇曜日にゴミ出しをしていた」
「お父さんが亡くなってから寂しそうだった」
「最近、病院に来ていないので心配していた」など。
母は病気だったため、ご近所との関係は途絶えていました。
母には友達はいなかったと思います。相談できる相手もいなかったでしょう。娘である私は月1回、儀礼的に訪問するだけでした。たしかに「孤独」だったかもしれません。
でも、何人もの人が母の存在を知っていました。気にかけてくれていました。母は地域の一員であったのですね。
母はそこに存在していた。
当時は「孤独死」させてしまった自分の責任を問いました。
母が哀れに感じました。どんな思いで亡くなったのだろうと胸が苦しくなりました。最後の挨拶ができなかったことも、最後の姿をみてあげることも、手を握りしめて見送ることができなかったことを悔いました。
でも、これらの証言を聞いて、私は少し救われたのです。
母はスーパーに行き、誰かに「こんにちは」と言葉を交わしていた。
たった一人で生きていたのではなかったと知って、本当にほっとしました。
ナチュラルな資源に助けられたのは、私ですね。
意識すれば無数にナチュラルな資源に囲まれていることに気づきます。
お互いが支え合っていることをほんの少し意識することができれば、孤独感が薄れるのではないかと思います。現実にはそんなキレイごとではないことも、自分の経験から分かっています。でも、やっぱり希望をもっています。私ができるだけ多くの人にとってのナチュラルな資源でありたいなと思います。

私の世界観を楽しんでいただけたら、サポートをお願いします。励みになります。
