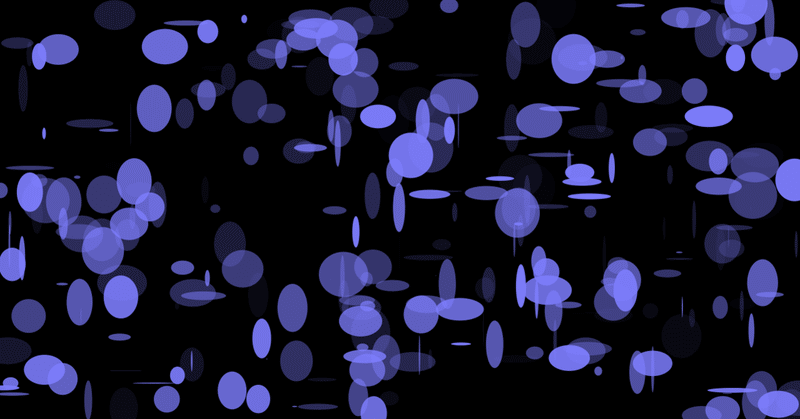
カフカの性描写(3)―『城』より
前回は、カフカ第二の長編『訴訟』で性行為が暗示されている個所についてコメントした。今回は、カフカ第三の長編である『城』における性描写を見ていく。
『城』には、主人公のKと、城の高官クラムの愛人である給仕女フリーダによる、二度の性行為が描かれている。
最初の性描写
最初の性行為は、酒場「紳士館」のカウンターの裏側でのものだ。
彼がまだ部屋を出て行かないうちに、もうフリーダは電気を消してしまい、カウンターの下のKのそばに来た。「愛しい人! 私の愛しい人!」と彼女はささやいた。しかしKにはまったく触れなかった。愛するあまり気を失ったかのように仰向けに横たわり、両腕を広げた。幸福な愛の前では時間は無限だったのだろう。彼女は歌というよりはため息をついているように、何かささやかな歌を歌った。それから、Kが静かにもの思いにふけっているので、驚いて起き上がり、子供のようにKをひっぱり始めた。「起きて、この下は息がつまるわ。」彼らは抱き合った。小さな体がKの両手の中で燃えた。彼らは我を忘れて転がった。Kは絶えず忘我から自分を救い出そうと試みたが無駄だった。数回転がったところで、クラムのドアに鈍い音を立ててぶつかった。それからこぼれたビールと床を覆っているほかのゴミの中に横たわっていた。そこで何時間も過ぎていった。一緒に息をしながら、一緒に心臓を鼓動させながら何時間も。その間Kはずっと、自分が迷っている感じ、あるいは彼以前には誰も足を踏み入れたことのない遠い異国にいる感じにとらわれていた。そこでは空気さえも故国のものとは成分が違い、あまりに違っているので窒息せざるを得ず、そのとてつもない魅惑の中では、さらに進んでいく以外、さらに迷っていく以外何もできないのだった。(『城』第3章「フリーダ」、ヨジロー訳)
「ため息をついているように」――『失踪者』においてと同じ「ため息をつく」という語が用いられている。
「何かささやかな歌を歌った」――『ある犬の探究』において探究犬が狩人犬の歌を聞くのと同じ。
「彼らは我を忘れて」――『ある犬の探究』の探究犬と狩人犬の性愛場面では、「忘我」という言葉が使われている。(「それは少なくとも、完全な忘我において我々がどれほどのものに到達することができるかを示している。そして私は完全に我を忘れていた。」)
「こぼれたビールと床を覆っているほかのゴミの中に横たわっていた」――カフカは性行為を「汚れ」と強く結びつけていた。しかし、ここではKは不潔な汚れをまったく気にしていない。
「そこで何時間も過ぎていった。一緒に息をしながら、一緒に心臓を鼓動させながら何時間も。」――美しい表現。
「そのとてつもない魅惑」――性行為がはっきりと肯定的なものとして描かれている。
伝記的に見るなら、フリーダのモデルはミレナであり、クラムのモデルはミレナの夫ポラックである。ここで描かれているのは、カフカとミレナの最初の逢い引きのことだ。二人はウィーンの森を散歩し、途中、草地で横たわって抱き合った。
小説の中では、「こぼれたビールと床を覆っているほかのゴミの中」での行為とされているが、実際には草地でのロマンチックな抱擁だ。このときが、カフカにとって人生でもっとも幸福な瞬間だったのではないか、と勝手に思っている。
Kとフリーダは転がりながら、クラムの泊まっている部屋のドアにぶつかる。クラムのモデルであるポラックは実際には空間的に離れたところにいるが、カフカの小説では同じ建物の中にいて、愛の行為の最中にそのドアにぶつかることになる。ミレナとの逢い引きで、どこかでポラックを意識するところもあったことが、このような空間的な近接となっているのだろう。カフカの物語の作り方を見るようで、おもしろいところだ。
二度目の性描写
クラムにKとの関係を伝えたフリーダは、翌日、Kとともに、「紳士館」より格の低い、居酒屋を兼ねる宿屋「橋屋」に移る。その夜、二度目の性行為がなされる。それは最初のものほど肯定的ではない。
Kにとって腹立たしいことでもあるがある意味では歓迎すべきことでもあったのは、助手たちが行ってしまったときにフリーダがすぐに彼の膝の上に乗ってきて、次のように言ったことだった。「ねえ、助手たちのどこが気に入らないの? 彼らには何も秘密にする必要はないわ。忠実だもの。」「忠実ねえ」とKは言った。「始終僕を見張っている。意味もないことだが、嫌悪を覚える。」「わかる気がするわ」と彼女は言って、彼の首に両手を掛け、もっと何かを言おうとした。しかし、それ以上話せなかった。なぜなら椅子がベッドのすぐ横にあったので、二人はそちらによろめいて、そのままベッドに倒れ込んだからだった。二人はそこに横たわっていたが、前の夜のように夢中になってというわけではなかった。彼女は何かを探し求め、彼も何かを探し求めていた。腹を立てながら、渋面を作りながら。互いに相手の胸の中に頭を押し込みながら互いを探し求めていた。互いに抱き合っても、互いに身をぶつけあっても、二人とも探し求めるという義務を忘れることなく、思い出していた。犬が絶望して地面を引っ掻くように、彼らは互いの体を引っ掻いた。どうしようもなく失望しつつ、なおも最後の幸福を得ようとして、ときおり互いの舌が相手の顔をペロリと舐めた。やがて疲れ果てて彼らは静かになり、感謝し合った。それから女中たちが部屋に上がって来た。「まあ、なんて格好かしら」と一人が言い、かわいそうに思って二人にシーツをかけてやった。(『城』第4章「橋屋のおかみとの最初の対話」、ヨジロー訳)
「前の夜のように夢中になってというわけではなかった」――Kとフリーダとの二度目の性行為にはすでに影が差している。
「彼女は何かを探し求め、彼も何かを探し求めていた」――互いに相手から大事なもの、つまり愛を必死になって引き出そうとするが、得られないままにもがいている。
「犬が絶望して地面を引っ掻くように」――ここでは性行為が犬同士の絡み合いにたとえられている。「犬」はカフカにおいては否定的な意味合いが強い。しかし、ここで犬にたとえられたことが、『ある犬の探究』における探究犬と狩人犬の愛の交わりへとつながっていく。
「なおも最後の幸福を得ようとして」――二人は努力するが、結局求めていた幸福は得られないまま。
「ときおり互いの舌が相手の顔をペロリと舐めた」――カフカ独特のユーモア。ユーモアでごまかそうとしているが、「彼女は何かを探し求め」からここまでは、せつない描写となっている。
伝記的に見るなら、背景となっているのは、ウィーンでの逢い引きから一ヶ月半後の、グミュントにおけるカフカとミレナの二度目の出会いである。カフカは最初の出会いと同じものを期待したが、ミレナの心はすでに後退しつつあり、二人の間には微妙なわだかまりが残ったままになった。その後、二人はしだいに遠ざかっていくことになる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
