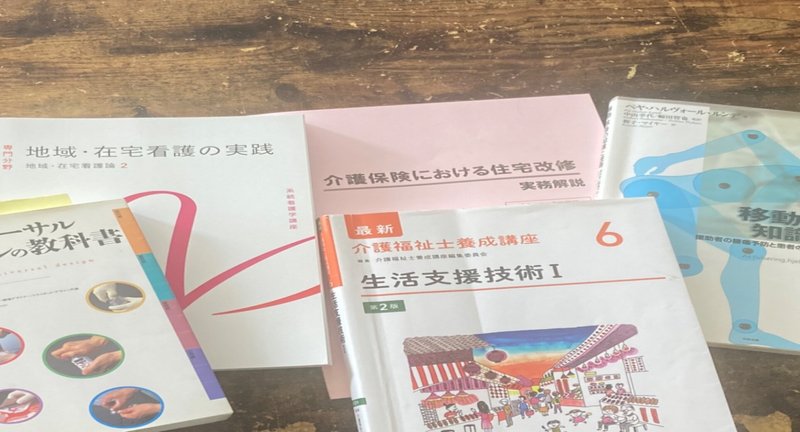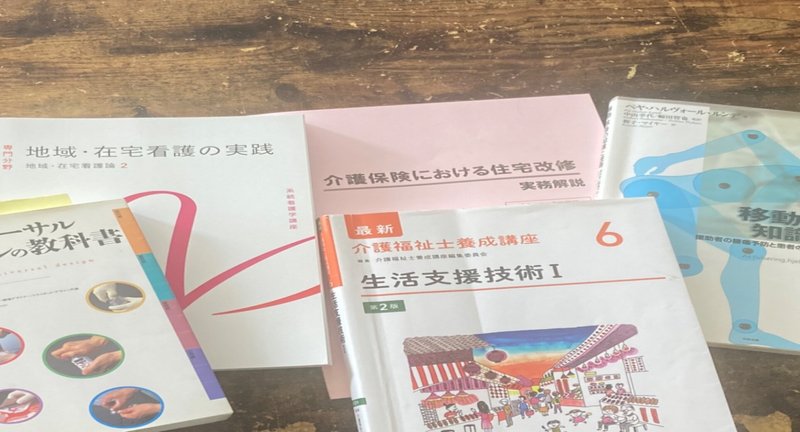車いすのドメスティック進化 〜6輪車いすの話
かつて自分がいた大学に、車いすの動線やら空間やら何やらを研究テーマにしている先生がいらっしゃった。
だがこの業界にあまり興味がなかった自分は、当時は華麗にスルーして劇場の研究などをしている先生のゼミに入ったのだった。
でもその先生方の研究成果は、車いすで生活するための標準的な寸法などに生かされ、何らかの基準として、高齢・障害者の住居基準や現在のバリアフリー法などに記されている、はずである。
そしてその結果として、日本の一般的な木造住宅の廊下は車いすを使うには狭いという建築