
離床の夢、そして現実 ~ある介護ロボットの始まりから終わりまで
リショーネ、というベッドと車いすの変形ロボのような製品を、皆様はご存知だろうか。パナソニックさんが文字通り社運をかけて開発した、介護ロボットの主力製品である。
ベッドが縦に2つ割になり、その片側がチルトリクライニング車いすになるというものだ。要は、ベッドの上で横水平移動するだけで、移乗せずとも通常のベッドの背上げ脚上げと同じ動作で、車いすに乗ったことになり室内移動ができる。移乗負担ゼロですね、これはいい。
そんなムードの、ちょうど10年前に掲載された記事が、日経のサイトに残っていた。
地味が示す本気
日本の大手メーカーが考えられる技術をすべて盛り込み、介護現場を技術力をアピールするショールームにする時代は終わった。リショーネにロボットの面影はもはやない。地味な介護機器だ。それはパナソニックの本気度を示す。
介護現場は外国人に頼らないと回らない時代が目の前にある。プロジェクトリーダーの河上氏はある介護事業者から「介護する人がいなくなる問題意識を持ってほしい。1週間のうち5日をロボット、1日外国人、日曜日だけ日本人が介護する時代が来る」と言われた。
ベッドから車いすに移すロボットは、いくつもの方式が提案・開発されている。パナソニックに続く挑戦は大歓迎だ。
この頃は、介護ロボットに対する期待感も膨らんでいた。安倍政権のときに、補助金の大盤振る舞いも始まった記憶がある(調べたらH25、2013年でした)。このリショーネの地味な見た目が、その実用化の象徴に見えたのも不思議はない。
そして、現在のリショーネのウェブサイトを見てみよう。
あら、2022年4月に生産終了である。
2006年から10年かけて、ニーズを把握し、問題点を潰してようやく実用の域に達したのに、製品として生きられたのは6年(+旧バージョン2年)だった。新規需要が一段落して、その後が続かなかったのだろうね。
開発ヒストリー、紆余曲折がサラッと書いてありますが、その中でも無数の課題発見と解決のPDCAサイクルがあったのではと思われます。
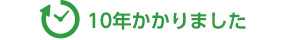
でも、これは失敗例として笑うべきではない、むしろ開発中止にもならず、走りきったという意味では成功例である。我々はその知見を余すことなく受け取って、活かすべきである。
ということで、当時の諸々のサイトが残っているうちに学びを得たい。
2017.08.01 UP、改良版たるリショーネPlus発売後の苦闘記から。
しかし、マットレスを2分割にするというアイデアにもまた問題があった。
褥瘡の恐れがある高齢者にとっては、シーツの折り目、しわのひとつでも大きな影響が出る。寝ている真ん中でマットレスを割るという大胆な発想は、現場の介護職からすればあり得ないことだった。
「ここが、われわれにとってはチャレンジングな部分でした。クリアしなければ、この商品は成り立たない。現場の介護職の方にも納得していただけるよう、筑波大学病院の褥瘡の専門家にアドバイスを受けながら、問題がないというエビデンスをしっかりととって開発を進めていきました」
厚さ10cm、3層から成る体圧分散ウレタンマットレスは、特に分割部分の滑らかさに配慮。曲面構造を採用し、体圧がかかることで分割部分がぴったりとくっつき、段差は生じない。体圧分散性も、市販の体圧分散ウレタンマットレスと遜色ないレベルを実現した。
やはり、この機械の一番問題だと思われたのはココか。確かに。
そして、そのためのマットレスを開発してクリアした。市販の体圧分散マットレスと遜色ないレベルの。ここ、覚えておいてください。
よくある質問
【真ん中の割れ目は気にならない?】
褥瘡予防の柔らかいマットレスなので、適度に沈み込んで隙間が埋まる構造になっています。隙間はほとんど感じられません。
リショーネの場合、その分割線による問題を解決するための選択の結果、ソフトマットレス専用となっている。なので、自分で寝返りが出来る能力のある人などは、沈み込みのためにそれがやりにくくなる。
そしてそれは、車いすモードの時の座面に必要な硬さとも、微妙な不適合を起こしていたのではないか。柔らかい座面では、座り直しも自力でやりにくいのだ。フットサポート部分が固くないマットレスであることも、脚での踏ん張りが効かないはずなので、その方向で作用したと思う。
また、床ずれができてしまうようなADLの人だと、エアマットレスなどの床ずれ防止用具を利用する人も多い。夜間の体位変換などを自動でやってくれるスグレモノもあるしね。
でもリショーネの専用マットレスにはその機能はないし、そもそもマットレスや床ずれ防止用具を利用者のニーズに合わせて選定することも出来ない。専用マットレス一本槍である。
つまりこの製品の対象となる利用者像は、その設計のコアであるベッド分割線がもたらす問題への対策がもたらした結果として、ADL低めだけど床ずれが容易くできるほどでない方、という狭い範囲に限定されてしまう、ということになる。
このあたりからどうやら脱線が始まっていたのだね。
また、導入事例の画像を見ると、シーツを使っておらず、マットレスに直に利用者さんは寝ているようだ。いちおう専用ボックスシーツは存在するらしいのだけれど、使いたい場合はそれぞれ両側にいれるのだろうね。でもそうするとベッドメイクの手間、2倍になっているように思える。
結局、移乗が簡単になるメリットと、その形態が生み出すデメリットの天秤が、メーカーの開発者側には介護者側目線で正確に見えていなかったように思えるし、利用者像を狭く限定してしまったことが、数が出ない理由になってしまう、量産メーカーとしてはつらい状況になっていたのではないか。
そして何より、その介助者のさらに先にいる、利用者さんのニーズに合わせるところまで、開発研究が届かなかったのだろうな(マットレスの選択とか)ということもなんとなく見えてくるのだった。
実は、それをメーカーの方もよく認識していたことを窺わせる記事がある。まさにそのリショーネの話を取り上げられている後半は、有料なので読めていないのが残念ですが。
なぜあえて「こだわり過ぎるな」と注意しなければならないのか。それは、ロボットに「魔力」があるからである。しかも、かなり強い魔力だ。気付かぬうちに、ロボットで事業を変革するはずが、ロボットを開発すること自体が目的になってしまうのだ。
ユーザーからすれば、ロボットが欲しいわけではない。何か困りごとがあり、それを解決したいわけだ。解決できるのであれば、必ずしもロボットである必要はない。当たり前だが、ロボットよりも、安く、簡単に、効果的に課題が解決できる手段があれば、ロボットは不要だ。
この当たり前は、ロボットの魔力により、いとも簡単に忘れ去られてしまう。ある意味では、ロボットの「魅力」とも呼べる。しかし、魅力的であるが故に、その魅力は時に魔力となってしまう。
パナ社のロボ開発責任者の方の言だけに重みがあります。ロボットの魔力。
リショーネの場合のライバルは、やはりオーソドックスな移乗である、既存のベッドと車いす+リフト、もしくはストレッチャーとスライディングシートのセットだったのだろう。
リショーネより安いベッドで、適切なマットレスを選んでリフト移乗をするほうが、その移乗に時間は掛かるけど、リショーネが生み出す上記の課題からは自由でいられる。結局、そこに勝てなかったということかな。
誰かの支援、ケアに携わるひとでなくても、自分の行動は何を目指しているものか、日常の多忙の中で、その目的は忘れられてしまいがちなのだ。
自分は介護福祉士の学校で、転倒予防のための最も合理的な対策について生徒さんに質問することがある。
これ、正解は「ベッドに固定する」になる。なぜなら拘束や投薬などで、転倒する側の自由を奪えば、確率100%で転倒事故を防げるからだ。だが、現在では違法になる、身体拘束そのものだから。
この問いの意味は、目的の設定を間違ったときの怖さを感じてもらうことにある。介護の目的は転ばないことでなく、利用者さんの、そして副次的にその周囲の人々のQOLの最大化であるからだ。そのことを常に忘れてはいけない。
前回のAIスーツケース話の裏テーマもこれだったのですが、我々はえてしてQOLの最大化という大目標を忘れ、それより下のレイヤーで手段と目的をすり替えてしまうのです。これが日本人の特性とは自分は思わないが、後戻りや失敗を恐れる組織が持っている特性とは言えそう。
これ、どのジャンルで生きている皆様にとっても何らかの教訓がある話なのではと思います。この記録が、何らかのお役に立つことを願って。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
