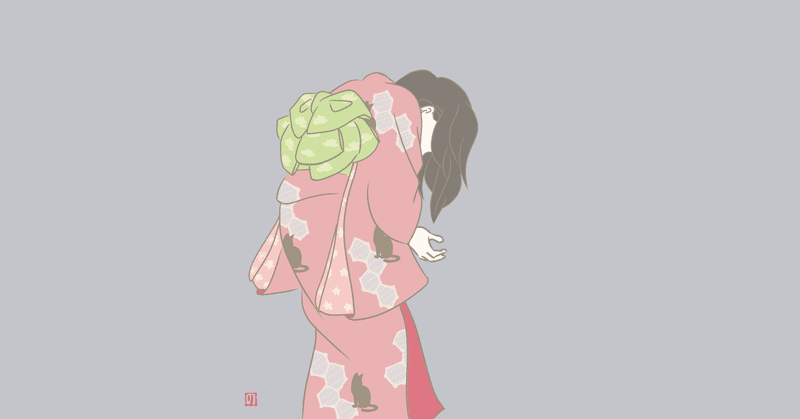
自分が小さくなったり大きくなったり、
どこまでを自己として認識しているのか時々よくわからなくなる。
のべつまくなし疑問に感じているわけではなく、普段生活しているぶんには、自分の肉体を「自分」だと自然に定義していると思う。
ところが例えば、交感神経や副交感神経といった自律神経は、鼓動や呼吸、腸の運動、その他内蔵システムを「勝手に」制御している。
中枢神経とは関係なく、文字通り自律的に彼らは働いていて、意識して鼓動のテンポや、胃腸の動きを変えることはできない。
腸にいたっては、彼ら独自の神経ネットワークを持っている。
脳や脊髄、自律神経からの指令がなくとも腸管の内容物を感知し、もっと蠕動運動を激しくするために筋肉に指示したり、もっと栄養を取り込むために血管を広げたりしている。
自分の意識に上るのは、彼らが通常とは異なる状態に陥ったとき、心臓がバクバクしたときや、お腹がキュルキュルするときに限られる。
彼らも一応、情報は上げてくれるらしい。
でもこちらから直接、何かを要請する手段はない。
自分の意識が、自己を自己であると感じている場所だとしたら、体内と自己は、思ったより希薄な関係しか結べていないようにも思える。
逆に、体の外はどうかというと、切られた爪や抜けた髪の毛は、自己の一部だろうか、あるいは単なる有機物だろうか。
この疑問は、子供の頃でもふと浮かんでくるものであるし、多くの人が覚える類のものであるらしい。
もっともらしい答えは、自分の意識が自分であると感じているのは、システムとしての自分であるから、そこから外れた爪や髪の毛は外部のもの、よくいっても「自分だったもの」でしかない。
よく引き合いに出すのは、自転車から外れたタイヤは自転車の一部ではあったけどもう自転車とは呼ばない、という例だ。
どうやら人間は、物質をそのまま見ることができないようで、ある特定の物質の組み合わせを「自転車」という概念でくくって認識している。
概念あるいはシステムという言い方でもいいけれど、とにかく、そういう機能や構成する物質の集合体としてモノを認識している。
自己もそうで、自分の精神やら肉体やらの総体をぼんやりと自分だと認識している。
おそらくわたしは、近代以降の「自我」の概念を刷り込まれているので、自分と他人の区別を明確につけているはずだ。
しかし、何かの折にふれ、自分は人類という大きな生命システムの部品にすぎないのではないかと感じることがある。
そういうときはだいたい疲れていて、心の奥に丁寧にしまい込んだはずの黒歴史的厨二病が顔を出しているだけなので、何も考えずに寝てしまうか、それができないときは、そっとお引取り願っている。
生物学の中には広範な領域が存在しており、人間を含む多細胞生物だけではなく、当然、細菌や酵母といった単細胞生物の研究をしている人たちがたくさんいる。
個体同士の情報交換について興味を持った研究者の一部は、哺乳類や昆虫、魚類ではなく、単細胞生物を研究対象にしている。
大腸菌や酵母たちも盛んにいろいろな物質を分泌したり取り込んだりして、「会話」を交わす。
数が増えすぎたときには増殖速度を抑えるための物質を分泌し、過増殖による死滅を回避したりと、彼らは彼らのやり方で集団の秩序を保っているらしい。
あるいは、異なる種類の細菌のコロニーが接触すると生存をかけた激しい戦闘が始まるが、前線で瀕死になった細菌は、相手に対する毒素をばらまきながら自殺する。
進化論的に考えると、自爆機能を持った細菌種のほうが、細菌集団として生存競争を勝ち抜きやすいのだろう。
もっとキャッチーな例としては粘菌がよく知られている。
日本では特に南方熊楠の名前とともに知っている人が多いと思う。
栄養が足りなくなると、普段はばらばらに生活していた粘菌たちが集合しひとつの個体のように動き回る。
集合したり、協働して運動するための情報を細胞間で交換するためのシステムは、生命現象の中でも一際、エレガントだ。
一つ一つの個体からなる集団が、全体でひとつの生命体のように見える現象は、生物学の中ではよく見られる。
だから人間集団を一つの生命と考えるのもまるきり妄想というわけではない。
物質的につながっている範囲として考えるなのならば、自分の肉体が占めている領域を自己と判断するのが妥当だけれど、情報を交換し協働的に機能する一つのシステムを「個」として考えるのなら、人類全体とは言わなくとも、ある人間集団を一つの自己として認識することも可能かもしれない。
先程、近代以降の自我の概念、と書いたが、大昔の人間は自己についてどんな感覚を持っていたのだろうか。
今ほど、自分と他人をはっきりと区別していたのだろうか。
随分と前に読んだエッセイかなにかに、香港の話が書いてあった。
筆者は野外で絵を描いていて、ふと振り返るとほとんどぶつかりそうなくらい近くに男性が立っていた。
筆者の絵を見ていたそうだ。
その例にかぎらず、とにかく物理的な距離感が近くて驚かされる、とそのエッセイには書かれていた。
プライバシーやパーソナルスペースと、自己の認識範囲の問題は同じではないから、その当時の香港人の認識する自己がわたしと大きく違うとは言えない。
けれどももっとずっと昔の、まだ人類全体に、素朴な意味でも私有財産の概念がなかったくらいの昔に生きていた人たちは、自己と非自己の境界線をどのくらい明瞭に引いていたのだろうかと、ふと考えてしまう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
