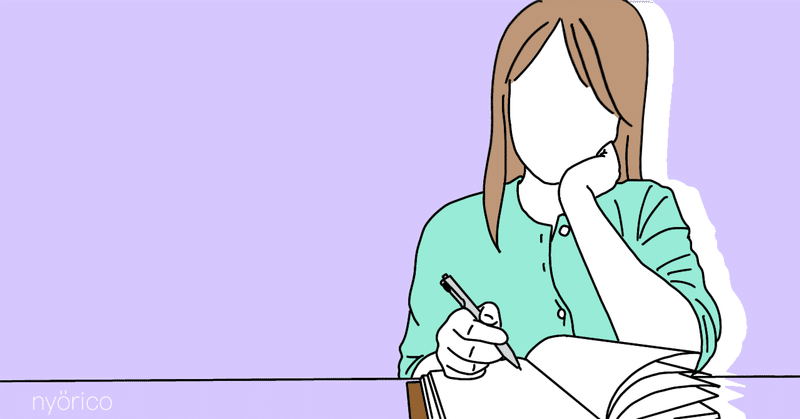
「ハッピィ・バースデイ」第3話(全10話)
私が乗ってから三つ目の駅で、電車が止まった。準急の通過待ち。何だかえらく長い時間、待たされている気がする。まあ、そんなに急いでないからいいけどね。暖房が心地よく、私は大きなあくびをした。一年間、付き合って聡志の嫌な部分が目立ってきた。結局、ワインを飲みに行ったり、近所の居酒屋に行ったりはするけれど、休みの日は、だいたいゲーム。記念日もクリスマスも正月も、サプライズもなし。靴下は脱がない。ご飯は残す。子どもは嫌い。家ではほとんどしゃべらないのに、母親とは長電話できるってどういうこと? 自分に関わる他人の欠点は、いくつでも挙げられる。不思議だよね、自分のことを一つでも言われたら、すぐに言い訳するのに。
準急が通過する。上り電車も少しはすいてきたようだ。私は特に見るともなく雑誌を広げ、過ぎていく景色を眺めている。耳にはイヤホン。流れてくるアプリからのヒットメドレー。好きなアーティストの音楽に耳を傾けながら、視線を雑誌に移す。興味ない記事なら、目をつぶる。好き放題の時間。やりたいように過ごす。めんどくさいことは嫌い。それが、私の主義。聡志との将来を考えるのは、めんどくさい。スマホを開き、ディスプレイの日付を眺める。
明日で私は三十歳になる。
先月、私の出した結論は、やりたいようにやってみる。そろそろ付き合う人との結婚も考えなくてはならない年齢にきているのに、考えられない人といつまでも一緒にいてもしかたがない。でも、いつまでもだらだらとカラダの関係を続けてしまっている。ホントはそんなのダメだってわかってるんだけど、何でこんなになっちゃってるんだろ。スマホのメッセージを確認した。昨日の夜の聡志と私のやりとり。
聡志「今日は暇?」
私「何で?」
聡志「店長からワインもらったから」
私「じゃあ、暇」
ため息をつき、スマホをカバンに押し込む。……ふう。我ながら情けない。早く本命の彼氏を見つけないと、「じゃあ、暇」の人生になっちゃうよ。
家に戻って、横に線の入ったスカートから、グレーのタイトスカートに履き替える。もう横線が入ったものは、今日は履きたくない。クローゼットを開けて、鏡を見ながら、改めて服装チェック。カーディガンのボタンが取れていないか。しみがついていないか。小学生たちは、大人のチェックに余念がない。スカートの横に線が入ってたら、その日一日いい笑いものだ。正面も、横もチェックオッケー。さて、では今日も適当に一日を過ごしましょう。
昼の一時。いつもより早めに、学習塾に着いた。首都圏にいくつかの教室があり、ここは社員五名。全部の教室を合わせると、社員は五十人ほど。大手の塾の足元にも及ばないが、ネットの口コミでも評価が上々になってきている。朝は苦手だし、夜は目が冴えるので、この勤務時間帯は私にもってこいだ。生徒が着くのは、学校が終わってからだから、五時半までは予習の時間。席について、今日の授業の教材に目を通す。六年生の算数一コマと国語一コマ。どちらも何回かやったことのある教材だ。よし。授業準備終了。私は答えが丸写ししてある問題集を閉じた。教室掃除も二十数個の無機質な机を縦横揃えるだけなので、大して時間はかからない。生徒が来てから雑談しながらできる作業だ。まだこの時間は教室長しか来ていない。しかもどうやら銀行へ行く準備をしているようだ。では、生徒が来るまでの間は、パソコンを立ち上げてネットサーフィン。「お気に入り」には、テレビ番組のホームページや友達のブログ。チェックするだけであっという間に時間が経ってしまう。私は左手にコーヒーカップを持ち、右手にマウスを握った。今日は腰を据えてのネットサーフィンができる。
もともとは小学校の先生になりたかった。でも教育実習の時に感じた「めんどくささ」は半端なかった。物がなくなったら学級会。泣いている生徒がいたら話を聞き、保護者に連絡。そして、生意気な生徒相手にわからせる「人という字は……」。一連の教育活動を覗き見て、それをやり切ることが自分にはできないと感じた。
そこで「ハートよりもテクニック」と塾講師を選んだ。私にとって勉強は簡単だった。問題には必ず答えがある。それに加えてテクニックという近道さえ身につければあっという間にゴールできる。まあ、私には彼らの前に立つほどの責任感も情熱もなかったんだよ、きっと。
恋愛だって、愛情よりも、相手をどう喜ばせるか。百万回の「愛してる」より、一つのプレゼントですよ。
「誕生日」
「え?」
ネットサーフィンに夢中になりすぎて、思考がはるか沖まで流されたとき、ふいに銀行から帰ってきた教室長から声をかけられた。私は溺れたような手つきで、お笑い番組のホームページを開いたパソコンを閉じて、いつの間にか私の席のそばに立っていた彼に、視線を移した。三つ年上なのだが、早くに結婚し、若くして教室長を任された彼は、日ごろの仕事漬けの不健康な生活で、サーフィンどころか、海水パンツも履けないような情けない体型になっている。しかし、私と違い責任感も情熱もあり、子ども達からは「ブー太郎先生」と親しみをもたれている愛すべきキャラクターだ。年も近く、意見もよく合い、信頼をされているのは感じる。
「誕生日、明日だよね」
「さすが教室長。よく知ってましたね」
「そりゃ、知ってるよ! 2月は遠藤さんと、牧原くん」
「……」
「あのね。生徒と娘のデータくらいは、全部この頭脳とお腹に、インプットされてるのよ」
彼は右手をお腹においてぶるんと揺らし、体全体を震わせた。塾のロゴが入った電子辞書が机の上に置かれる。生き残りのため、誕生日やイベントのプレゼントは手厚い。てっきり私の誕生日を知ってのサプライズかと、一瞬でも期待をしてしまった自分にも、得意満面の顔で自分の席に戻る教室長にも腹が立ち、私は机の上に置かれた電子辞書を睨んだ。何か、悔しい。そうだ。せっかく三十歳になるんだから、プレゼント代わりに反応を楽しませてもらおうっと。私はコロコロの付いたイスに座ったまま、彼の後を追った。
「あ、もう一人いました。誕生日」
「え、マジ?」
目の前で、振り返った教室長のお腹がぶるんと横に揺れた。同じくらい大きく、私は縦に首を振った。教室長は、冬なのに汗をかきながら私に聞いた。
「誰?」
「実は、私」
「……マジ?」
「マジ」
あごを突き出し、満面の笑みで教室長を見て、親指で自分を指す。ストップモーション。しばしの沈黙。さあ、教室長として、一人の男として、ここはどうでるの?
教室長は、ゆっくりとおでこに手の平を当てた。頭の中にあるコンピューターを起動させるときの彼の癖だ。さあ! そのおでこから、何が出るかな?
「ああ、二十二人だっけ? 今のクラス」
「はい……」
「谷村先生入れて二十三人」
「そうですけど」
おでこから手が離れ、教室長の表情が見る見る明るくなっていく。何か思い出したんだろう。急に大きな声になって、彼が答えた。
「いやあ、二十三人いたら同じ誕生日の人がいる確率って五十パーセントなんだって。すごいな、一組いたね、谷村先生のクラス」
「……」
私は、おでこに手の平を当てた。
「ちなみに四十一人いたら同じ誕生日の人がいる確率は九十パーセントになるんだって。知ってた?」
「いえ」
「使っていいよ。この雑学ネタ」
「……ありがとうございます」
「いいよ。谷村先生への誕生日プレゼント」
親指を立て、微笑んで去っていく教室長。コロコロのイスに座ったまま、とぼとぼと席に戻る私。何か疲れた。
第4話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
